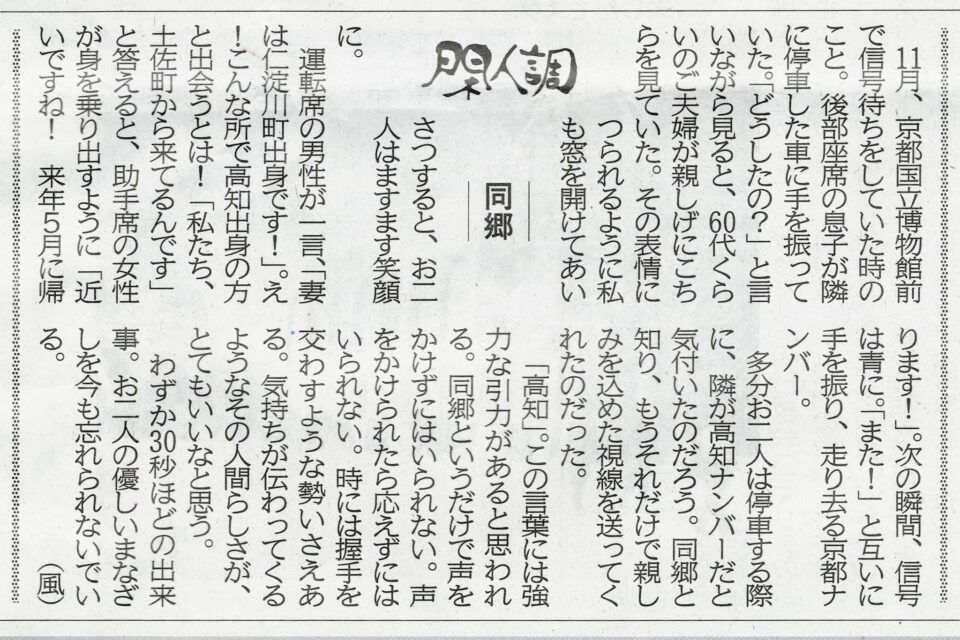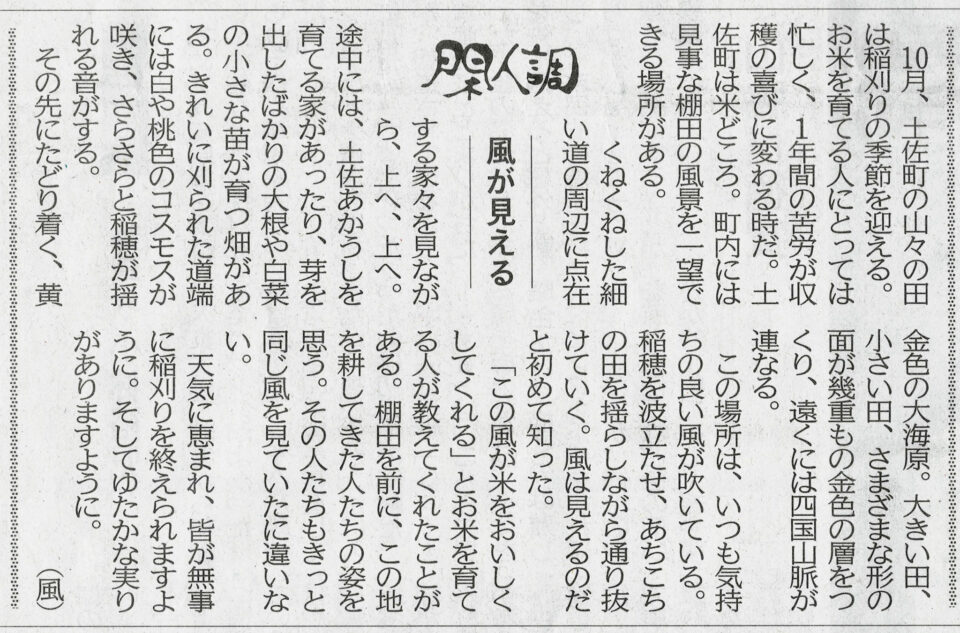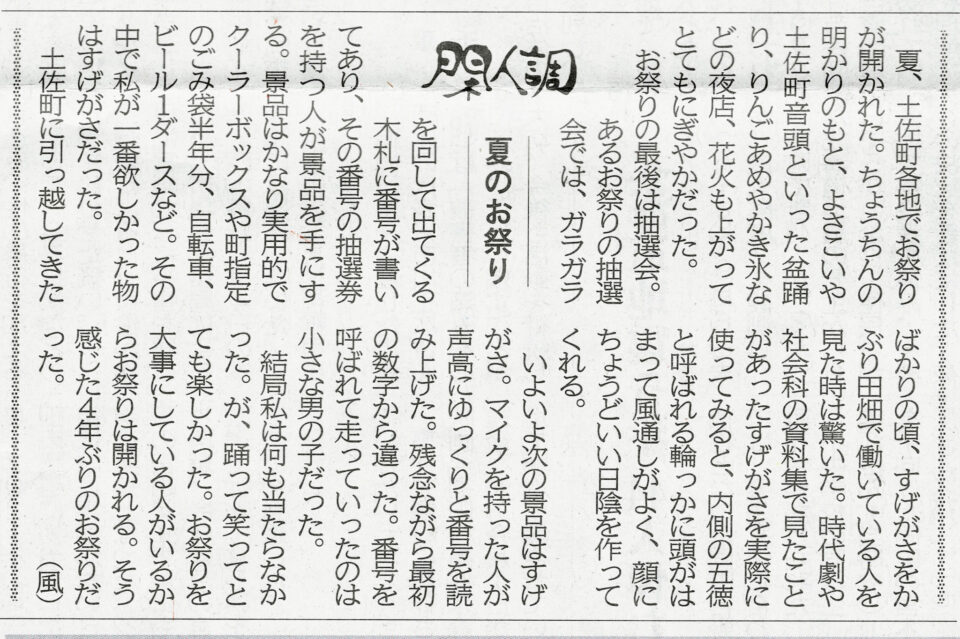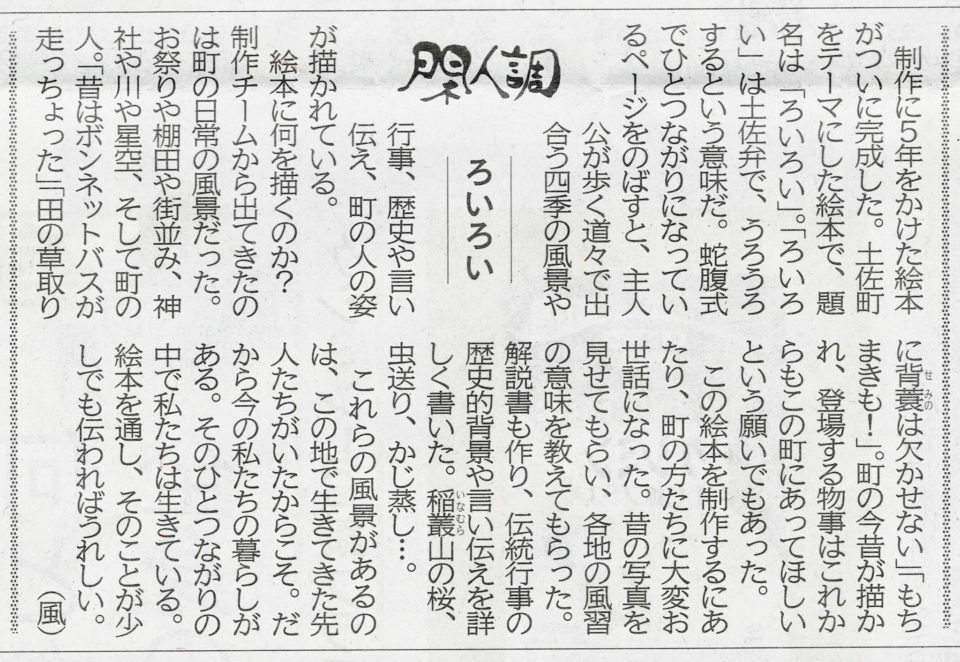伊勢喜さんはよく笑った。つられて私も笑った。
伊勢喜さんはぜんまいの帽子を退けるのがあまりにも速いので「速い!追いつけない」と言うと「追いつきや!」と笑い飛ばす。ちょっとしたことは軽やかに飛び越えられるような気持ちになる。伊勢喜さんはそんな笑顔の持ち主だった。
一緒に作業をしながらふと見上げると、満開の八重桜の花びらがはらはらと地面へ降りていった。あたりはとても静かで、桜の木の下に干されたぜんまいに花びらは重なっていくのだった。
帰り際、伊勢喜さんは私の手を包むように握って、言った。
「ありがとう。また来年も一緒にぜんまいの仕事、しましょうね」
その手のあまりの温かさに、私は涙がこぼれたのだった。

次の年、私はその約束を守らなかった。日々の出来事に追われて、私は伊勢喜さんのぜんまい山へ行かなかった。行けなかったのではなく行かなかったと言わないといけない。忙しさは理由にならない。気になりながらあれこれしているうちに、ぜんまいの季節は終わってしまった。
伊勢喜さんごめんなさい。
そう思いながら伝えもせず、会う機会もつくらなかった。
それからさらに一年が過ぎ、またぜんまいの季節を迎えた。約束を守らなかったことへの後ろめたさが何度も頭をよぎった。栗ノ木の道を走っていた時、自分の内側の何かが背中を押した。
今日行かなければ。

栗ノ木へ向かう道沿いを流れる川は2年前と同じように流れ、山道沿いの八重桜は2年前よりもぐんと大きくなっていた。それだけの時間が経ったのだ。それだけの時間をあけてしまった。
伊勢喜さんはいるだろうか。会って何と言ったらいいのだろうか。その答えが思い浮かばないうちに、一面に広がるゼンマイ畑が見えてきた。煙突からは煙が上がっている。2年前と同じ風景に入っていくことが不安だった。
伊勢喜さんはいるだろうか。会えたら、昨年来れなくてすみません、と言うんだ。そう心に決めて、煙の方へと向かった。
何人かの人が忙しそうに働いていた。伊勢喜さんを探す。あの人も、あの人も違う。探しても伊勢喜さんの顔は、そこになかった。
伊勢喜さんの娘さんがいたので聞いた。
「伊勢喜さんはいますか?」
娘さんは言った。
「お母さんはめったにここには来なくなった。体がしんどくなってね」
週に何日かは出かけたりしているものの、伊勢喜さんは体調が良くない日が多くなり家にいることが増え、酸素の吸入器をつけている時もあるという。

その日、娘さんを手伝いながら繰り返し考えた。
去年、私はなぜ行かなかったのだろう。
むしろに干されたぜんまいの間を行ったり来たりする伊勢喜さんの姿があるはずだった。ぜんまいを茹でる釜から上がる煙も、茹で上がったぜんまいの香りも何ら変わらずそこにあるのに、伊勢喜さんはいなかった。
私はどこかで、また次があると思っていた。でも行きたい時に行かないと、伝えたい時に伝えないと、その時がまた来るとは限らない。その時は待ってはくれない。たとえ小さくとも自分の内からの声に耳を傾け、次の一歩を踏み出したいと思う。
これからまた春が来る。
伊勢喜さんはどうしているだろうか。
会いに行って、ごめんなさいとちゃんと謝りたいと思う。
そしてまた四月の晴れた日に、一緒にぜんまいの仕事をすることができたならこんなにうれしいことはない。