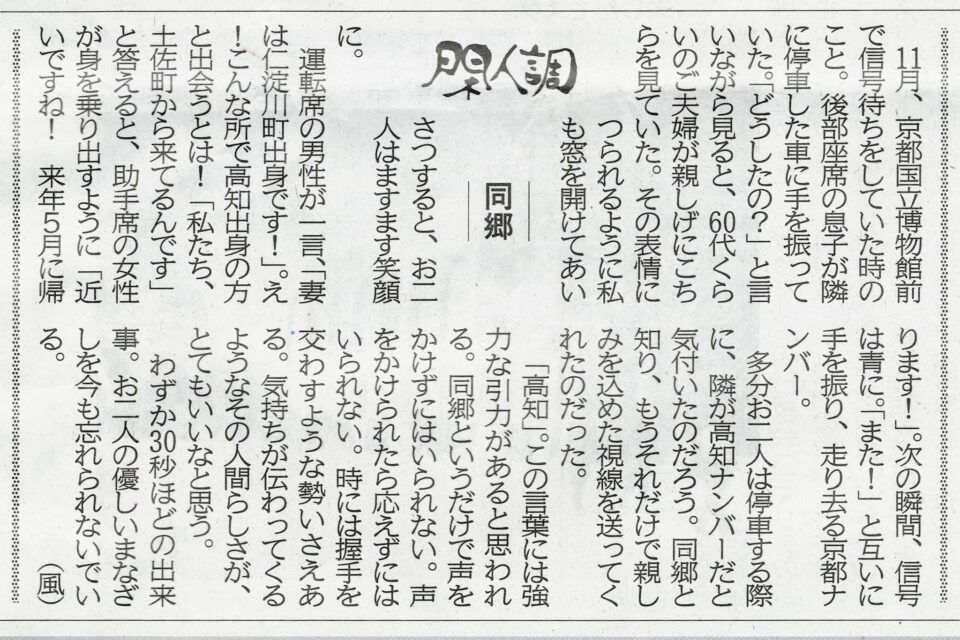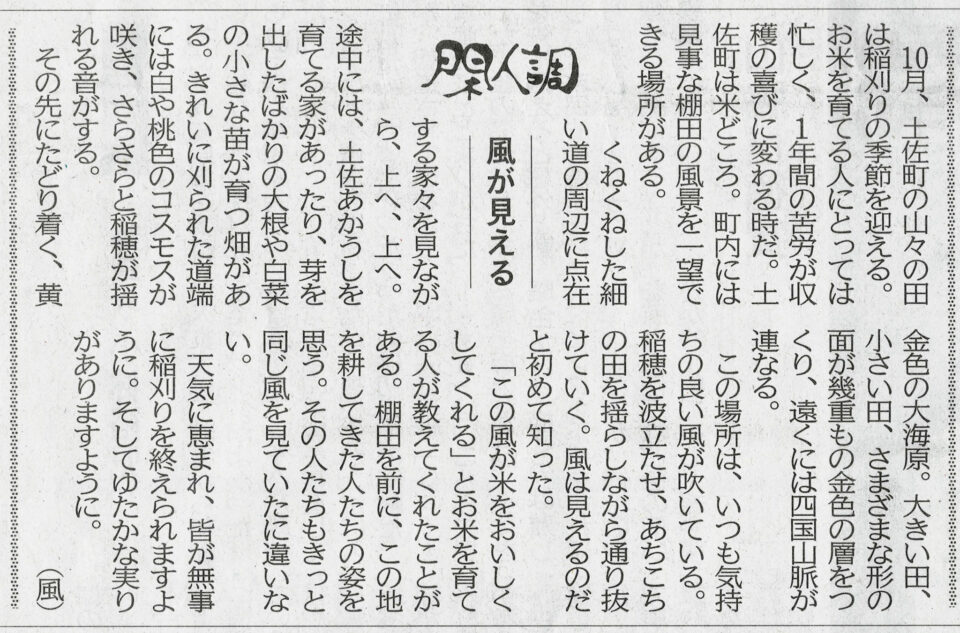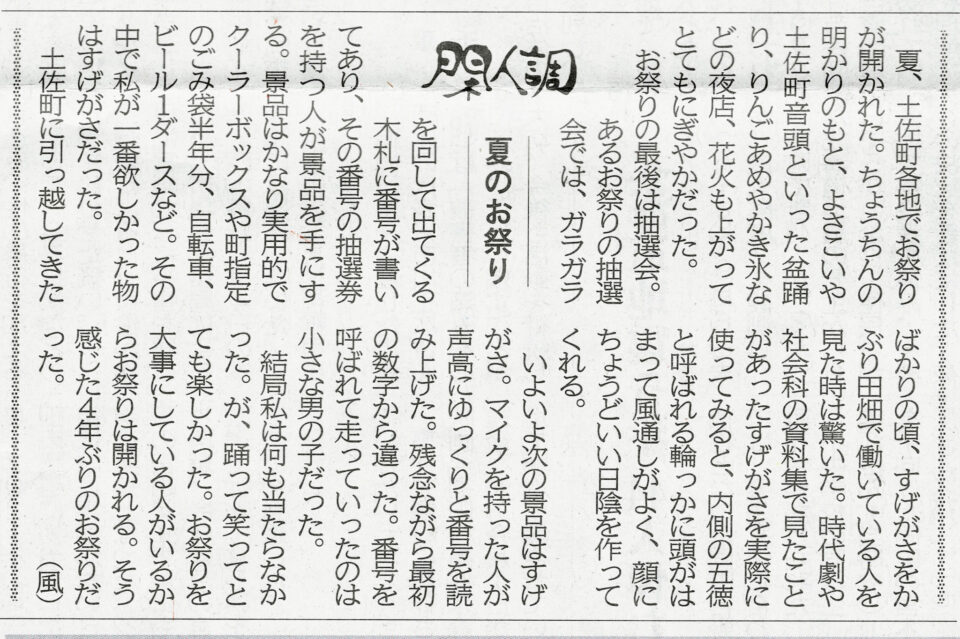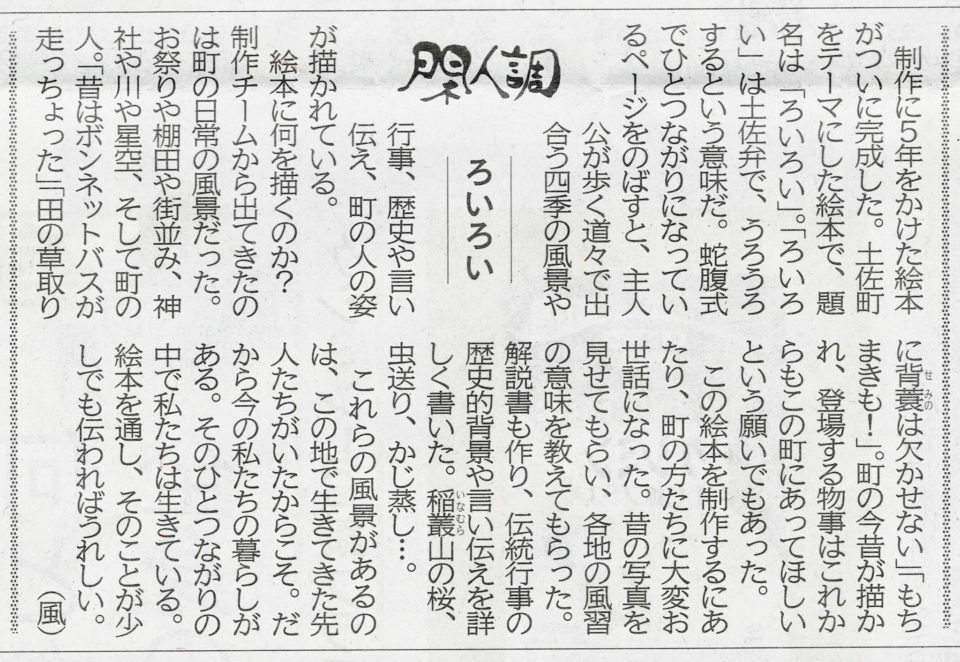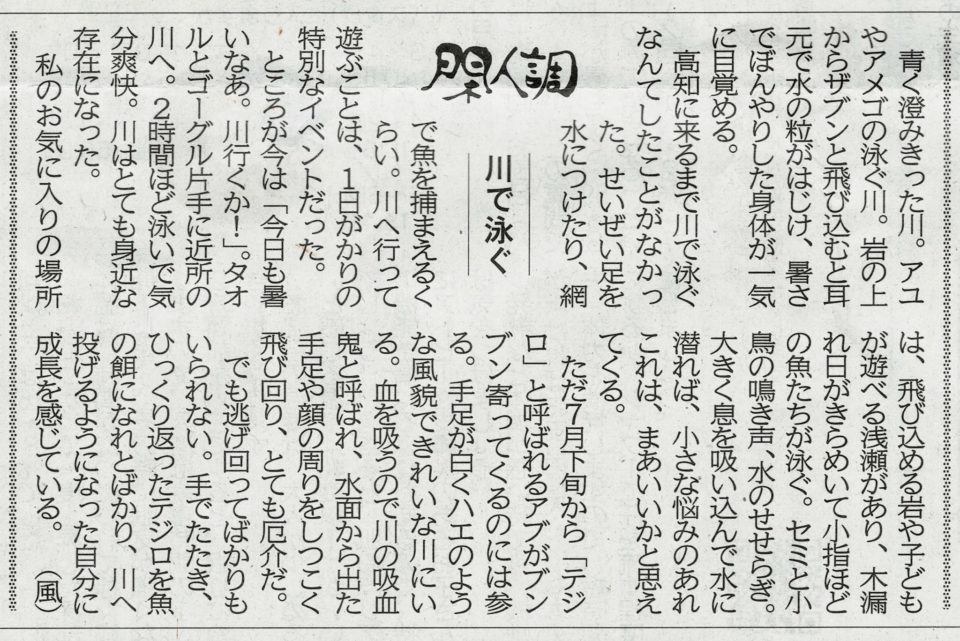(「この山に暮らす 3 」)
話していると雨が降ってきた。
濡れるから上へいきましょう、と声をかけると佐登美さんはうなずいて、一緒にもと来た道を歩いて戻った。
坂道を上がり切って、ありがとうございました、と言いながら佐登美さんの方を振り向くと、佐登美さんは「土佐町のために頑張って仕事をしてください。お願いします。」と友人の目をしっかりと見つめて、頭を下げた。
そして次はこちらに向き直り、私の目を見て「鳥山さんも一緒です。がんばってください。」と頭をさげたのだった。
その時の気持ちをなんと表したらいいだろう。
私は驚きと震えるような気持ちで「はい」と頭を深く深く下げ、胸の奥底からこみあげてくるものを抑えることしかできなかった。
この時の佐登美さんのまなざしや佇まいは、今も目の奥に焼きついている。
きっとこれからずっとずっとずっと、私の根本を支え続けるだろう佐登美さんの姿だった。
決して忘れない。
決して裏切れない。
そう思った。
「また寄ってくださいよ。」
佐登美さんは近くにある水場で腰をかがめて手を洗い、そのあと私たちの方を向き、手を振って見送ってくれた。
車が動き出して、それまでバックミラーに映っていた佐登美さんの姿が見えなくなった。
涙がこみあげた。
いつまで元気でいられるのかわからないのに、こんなに山奥でふたりで暮らし続ける。
一週間に一度しか町におりない、ふたりだけの暮らし。
家を訪れるのは郵便屋さんと猿と、いのししだけ。
もういつお迎えがきてもいいし、早く来てもらいたいと言っていた。
あきらめたような表情でそう話す姿を見ているのは、切なかった。
でもおふたりは、種をまく。
かやを刈り、畑に敷く。
来年の薪をつくる。
今日より先のことの準備をする。
ひとつ、ひとつ。
今まで積み重ねてきた道のりのうえに、今日もまたひとつ。
また明日目が覚めたら、同じようにその日のするべきことをふたりで静かに積み重ねるのだろう。
そのように一日を、ひと月を、一年をつくってきたのだろう。
もっというとこれまでの人生という道のりをつくってきたのだろうということを考えると、毎日ちいさな積み重ねをしていくことが、人が生きるということそのものなのかもしれない。
私が歳をとった時、和田さんのように、毎日の仕事をこつこつと積み重ねていけるだろうか。

失礼な言い方かもしれないが、和田さんのような暮らしをしている方は土佐町にも日本中にも世界中にもたくさんいて、でもそういう方たちは一見目立たなくて、見ようとしなければ気づこうとしなければ、そのまま知らないまま通り過ぎてしまう。
でも実は、和田さんのような方たちが地域や町、日本という国や世界を今までずっと支え続けてきたのだと私は思う。
自分の場所で自分のやるべきことをこつこつと静かに積み重ねる。
その方たちの存在が本当に尊く、決して忘れたくないと思うし、私もそういう存在でありたいと思う。
遠くから和田さんのお家を見つめる。
あの場所で、おふたりが暮らしている。
「私は山の方が好きなのよ。」
その言葉に込められているのは、ただここにいたいということだけではない、おふたりのひとつの覚悟のようなものであり、誇りでもあるのかもしれないと後から気づいた。
でももしかしたらそんなに気負わずに、今していることを明日もする、と、ずっと昔から引き継がれてきたことを当たり前のようにしているのかもしれない。
また和田さんに会いに行こう。
そして、出会えてほんとうによかったと思っています、と何度でも伝えたいと思う。