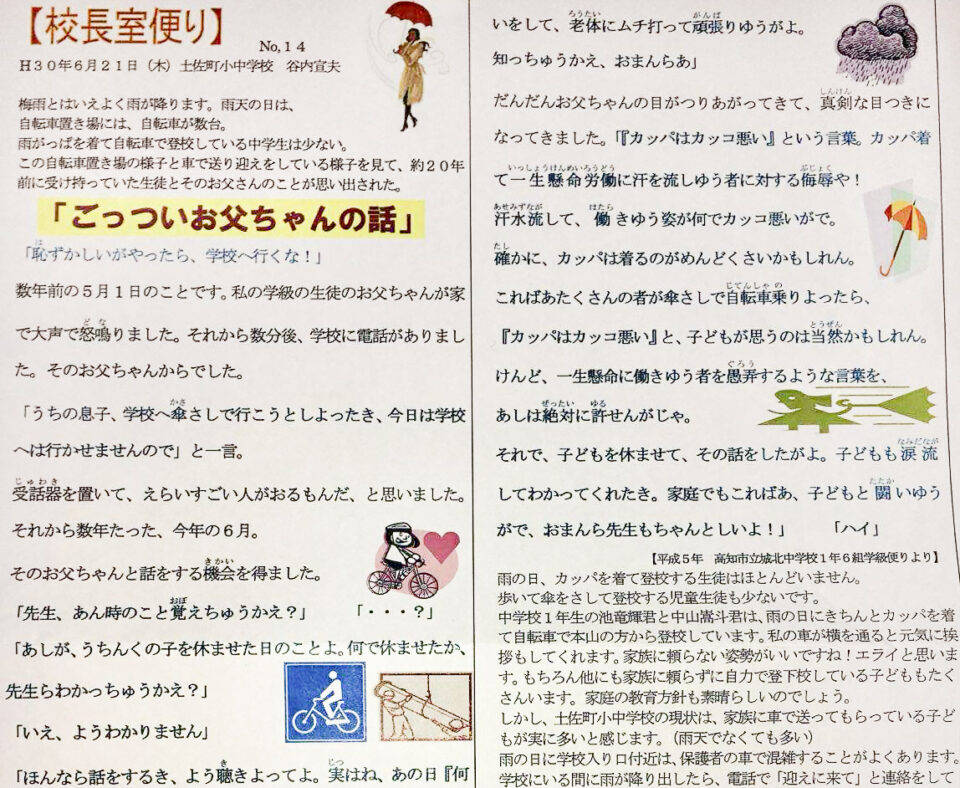他にも驚かされたことはたくさんある。僕が土佐町の「地域おこし協力隊」に着任し、その週の金曜日に、役場の人たちが僕の歓迎会を開いてくれた。愉快な会の後、2次会は土佐町における「ザ・2次会」の場所とも言えるスナック『なんてん』だった。
支払いはどうなっているのだろう、と気になっていたら、「あとで」と同僚に言われた。店を出る時にも聞いたらまた、「あとで」と言われた。
ようやくその意味が理解できたのは週明けになってからだった。月曜日、職場で集金の封筒が回って来たのだ。途中で帰る人もいるから、ということだろう。いちいち勘定するよりもよっぽど合理的だ。それにしても、2000円飲み放題歌い放題はいくらなんでも安過ぎだし、何よりも信頼関係があって初めて成り立つシステムだ。土佐町おそるべし!
僕の友人家族がニューヨークから移住してきた時、その娘は、「なんでいつも同じタクシーの運転手さんなの⁇」と驚いていた。そりゃそうだ。だってニューヨークのような大都会では、同じタクシーの運転手と巡り会う確率なんて奇跡に近いのだから。
それは宅配も同じだ。土佐町に移住して数ヶ月もすれば、宅配の人とも顔見知りになる。なにせ、荷物を持って来てくれるのはいつも同じ人なのだから。みんながそれぞれ、決められた仕事を一人もしくは少人数で担って、このコミュニティーが成り立っている。ごみ収集の人も、新聞配達の人も、スーパーのレジを打つ人も、プロパンガスを換えに来てくれる人も、ガソリンを入れてくれる人も。
そんな田舎の宅配事情が、これまた面白い。最初のうちは僕の不在時には不在票が置いてあったものの、慣れてくると、不在時にはこんな電話がかかってくるようになった。
最初は、
「ああ、鈴木さん?いらっしゃらないようなんで、玄関の中に置いちょってかまんですか?」
だったのが、そのうち
「おらんかったき、サインして置いちょきました!」
に変わり、1年も経てば電話すらなくなり、帰って来たら玄関の中に荷物が届けられるようになった。勝手にサインして置いといてくれるのだ。なんて便利なんだろう。都会では、宅配ボックス付きの家やマンションが人気だというが、田舎ではそんなものにお金を払う必要すらない。信頼関係ほど効率の良いものなど、あるわけがないのだ。
土佐町では、運転している時ですら、人とのつながりを感じられる。土佐町を突き抜ける国道439号線は、土佐町のメインロードだ。そのメインロードすら、片側一車線しかない。だから皆、運転中には対向車の運転席を必ずと言っていいほど見る。そして、知り合いに気づくと手を振るのだ。そんなこと知るよしもない僕は、最初の頃は「こっちが手振りゆうのにどいて無視するん?」などと言われたものだ。
僕が大好きなのは、子どもたちの登下校時に国道を運転することだ。運転席を見るのは、道を歩いていたり自転車をこいでいたりする子どもも同じ。前にも書いたように、土佐町には学校が一つしかない。そして、学校に行くには国道を通って行くしかない。学校に行く途中、子どもたちは誰の車が来たのかと運転手をチェックする。知り合いの車が来ると、子どもたちは手を振ってくれる。下校時には、重いランドセルを背負った子たちにヒッチハイクされることだってある。土佐町で過ごす時間の経過と共に、手を振る回数も増えていることが、なんとも心地よい。
そんなんだから、土佐町で育つ子どもたちは、とっても無垢で、子どもらしい。そして、僕が娘たちにかける言葉は、ニューヨーク時代とは真逆だ。
「知らない人でもちゃんと挨拶するんだよ。」
「人が何かくれる時はありがたく受け取りなさい。」
「誰かにご馳走してもらったり、車に乗せてもらったりしたら、お礼をしたいから必ず教えてね。」
子どもたちの素直な心と、人を信じる力を、大事にだいじに育てたい。そして、日本どこでも、親が安心してそのような子育てをできる社会をつくらねば、と心から思う。
(雑誌『教育』2019年6月号より再掲載)
(おわり)