
フランスの哲学者、ミシェル・フーコーにとって大事なのは、新自由主義政策の何が悪いかではなく、なぜその影響が私たちの生活や価値観をここまで支配するようになったかである。このような甚大な変化を、私たちはなぜ受け入れてしまったのか?
そう考えると、この社会を構成する私たちが、新自由主義の価値観と条件を受け入れ、それに従って自分たちの行動を統制してきたことがわかる。新自由主義の「小さな政府」は、知らず知らずにその価値観を内在化し、その要求に応えることで、私たち一人ひとりが歯車となって積極的に支えてきたのだ。
千葉市民花火大会に話を戻そう。行政が私たちに提示する議論の枠組みは、「傍聴する大会経費をどう賄うのか?」だ。しかし、大会の発端は、戦後、復興に明け暮れる市民の憩いとして行政が準備した行事だった。そもそも採算が取れるようなイベントではなかったということだ。
文化人類学者の松村圭一郎は言う。この社会は「わたし」の集まりによって構築されていることに気づくことにこそ希望がある、と。「わたし」たちが社会を構築しているなら、それをつくり直すことも可能だから。
(全人教広報誌『であい』2025年8月号より再掲載)
(おわり)









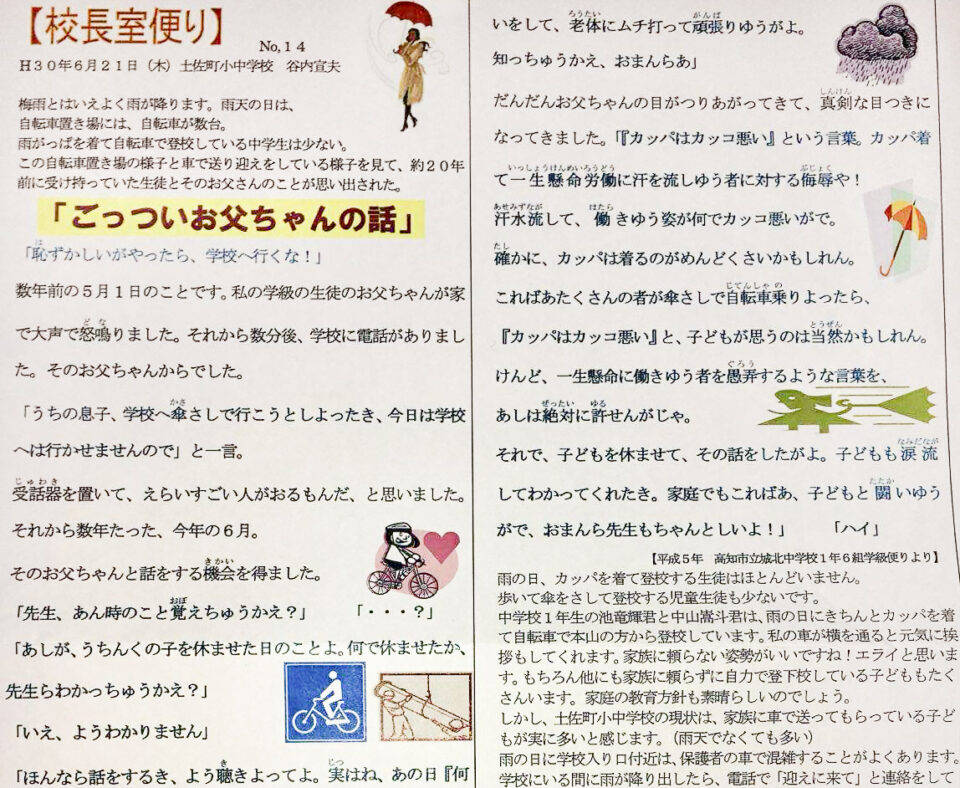
権力は、人の行動・思考・価値観へしみ込むことで実現する。
制度に従っているようでいて、
実は私たち自身が、その制度を
続ける主体になっている。
人々は、貧困は本人の責任で、
失業は努力不足で、自己投資しないと負け、という、仕事=生存
という考えを自ら採用し、生きることになる。
つまり、制度に支配されているのではなく制度を支える主体そのものに自らなっている。
フーコーの言う生政治ですね。
そしてその幻想から目覚めるには…を日々考えています。
Janeさん、コメントありがとうございます。
その通りだと思います。「その幻想から目覚めるには…」を考えると、やはり文化人類学者の松村圭一郎さんが言うように、この社会は「わたし」の集まりでできていると気づくことにこそ希望があるのだと思います。そこら辺については、『崩壊する日本の公教育』の終章、「遊びのないところから新しい世界は生まれない」に詳しく書いているので、もしよかったらまたご意見お聞かせください! 大裕