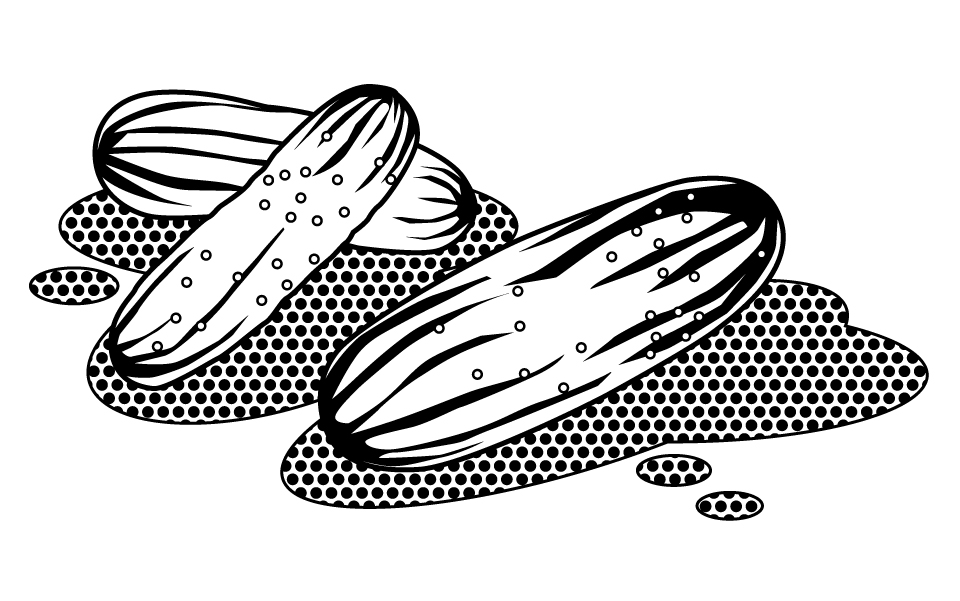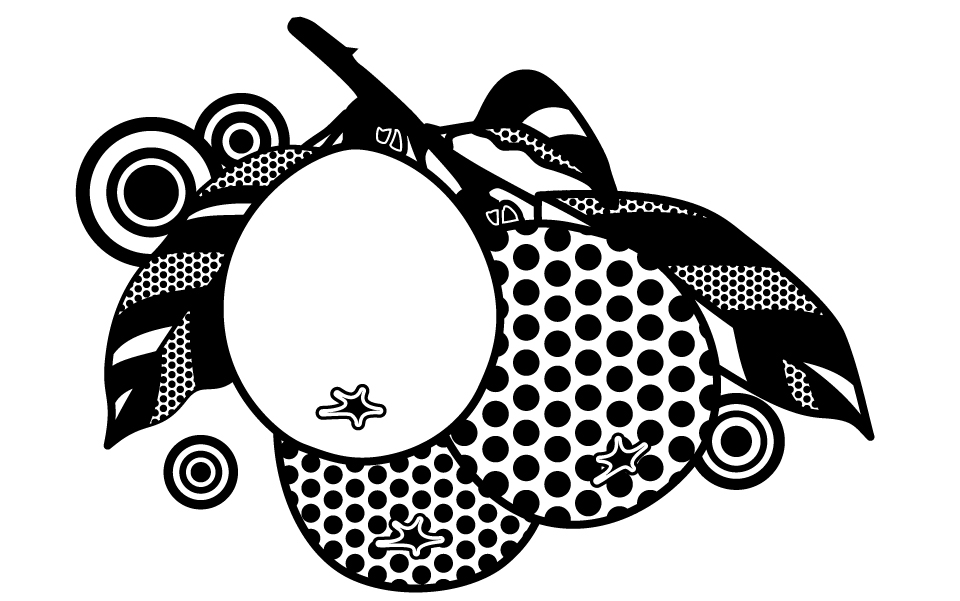(後編はこちら)
9月の中頃、近所の上田覚さんから電話がかかってきた。
「スイカ、まだあるんやけど。だいぶ割れちゅうのもあるけんど、よかったら取りに来や~」。
おじいちゃんはこの前した約束を覚えてくれていた。
おじいちゃんの家へ行き、おじいちゃんの運転する軽トラックに乗って畑へ向かう。今日は房子さんも乗っている。
この前スイカを取りに行ったのは2週間ほど前。セミが鳴いていて、空気がむん、としていた。
でも今日は違った。畑へ向かう一本道の両脇には紅い彼岸花が咲き、田んぼは黄金色になりつつあった。頬にあたる風もひんやりと涼しい。いつのまにかもう、すっかり秋になっていた。
畑にはスイカが2つあった。私たちが取れるようにわざわざ畑に残しておいてくれたことがわかった。少し前までスイカがごろごろ転がっていた畑の土は柔らかくしっとりと濡れ、畑の一角にはさっきまで耕していた、というように鍬が土の中に刺さったままになっていた。
「今日は暑かったけ、ここまでにしとこ、って思って。明日の朝の涼しいうちに、たたこう(耕そう)と思いゆう。」と房子さん。
次は何を植えるのかと聞くと「白菜じゃね。白菜の苗が大きくなってるの、見たろ?」。
苗は作業場の軒下に並べられている。黒いポットに種をまき、ある程度大きくなってから畑に植え替える。前にスイカをとらせてもらった時にはまだ小さかったその苗は、今ではもうずいぶん大きくなっていた。近くにいつもじょうろが置かれているから、夕方におじいちゃんかおばあちゃんが忘れずに水をやっているのだろう。
スイカはずっしりと重かった。
2つのスイカを抱えて、来た道を戻る。
「あっ、この畑、さっき、大根やらかぶやらを蒔いたんよ。」
おばあちゃんが指さした畑の土のうえには、茶色の細かい枝のようなものがまかれている。「これはわら。雨が降ると土が跳ねるき、細かく切って土の上にまいとくと種を守ってくれる。」

数日後に畑を訪れた時には、もう芽が出ていた。
大根やかぶの種が大きくなって、もうひとりでやっていけるとなった時、そのわらは役目を終え土に還り、また次のいのちを育てるための準備をする。
おじいちゃんがいつもしいたけやなめこを育てている森の手前で「びわの木、いるかね?」と言った。
この場所の杉を全部切ることになったそうだ。薄暗く湿り気があって、しいたけやなめこのコマを打ち込んだ原木を置いておく場所。
今まで何度も美味しいきのこたちをとらせてもらったことがあった。その森の脇にびわが生えていてその木がほしかったら持っていきなさい、ということだった。

そのびわの木から出ている枝の元には黄色のテープがまかれていた。
「去年自分が継ぎ木したんよ。大きいがを継いだが。おいしいびわの枝を切って、ここにテープで巻き付けてね。うまくいけば来年か再来年、実をつける」。
おじいちゃんは杖をつきながら話してくれた。
「これは『ひとりばえ』じゃ。鳥が食べた種がおちたんじゃろう。」
鳥たちがどこかで食べたびわの実の種が落ち、偶然ここに芽をだした。
この山だけでも人知れず育つ木はたくさんあるだろうに、この木はおじいちゃんに見つけてもらって見守られてきっと幸せだったと思う。
「うちには何本もびわの木があるけ、よかったら持っていきなさいや。」
おじいちゃんはそう言って笑うのだった。

帰り道、軽トラックの荷台に乗って帰った。荷台で風に吹かれているおばあちゃんの背中の向こうには、秋があった。この風景を見つめてきた人が今までもたくさんいただろうし、私もそのうちのひとりなのだという実感が胸の奥にぐっと迫ってくるようだった。
おじいちゃんからもらったすいかは、赤色だった。とてもとても甘かった。
これが今年最後のスイカになるだろう。