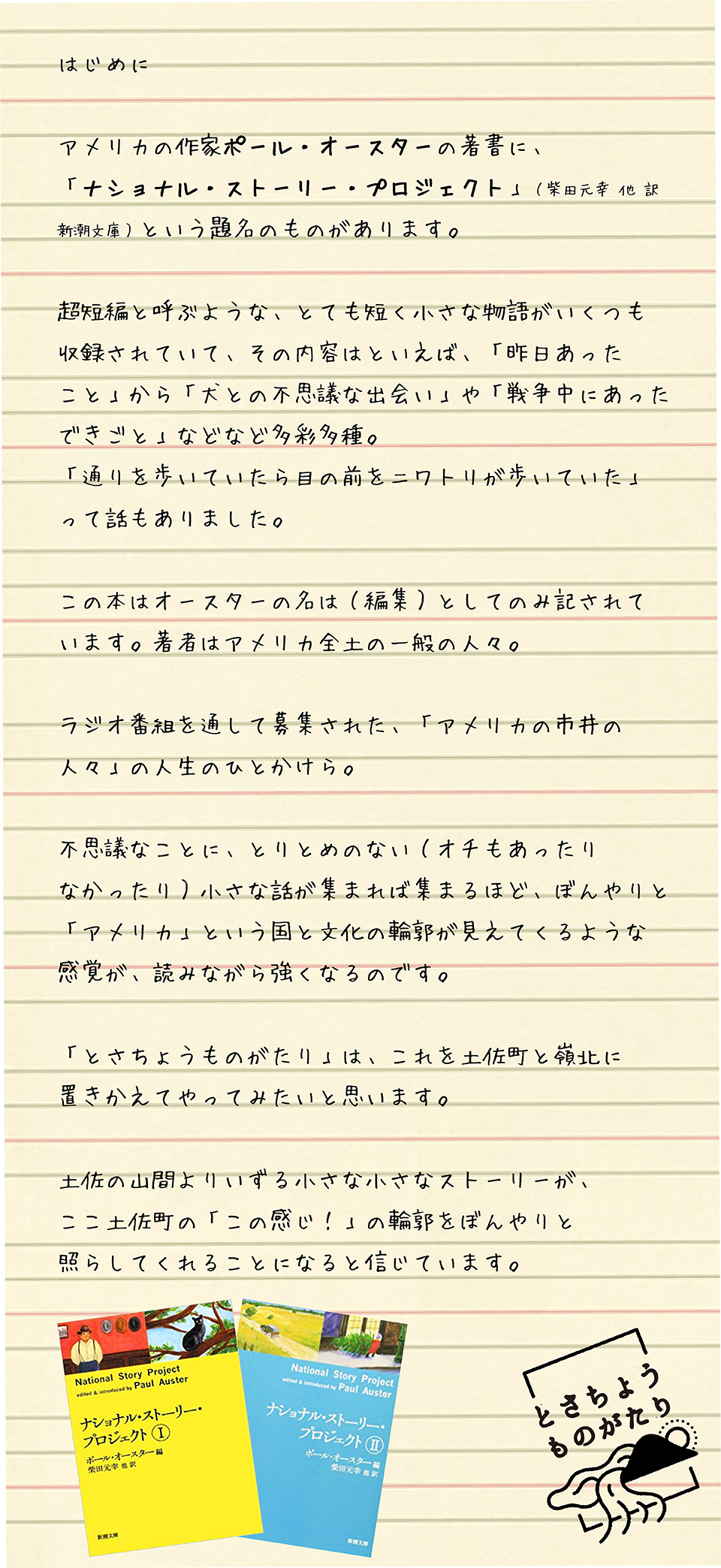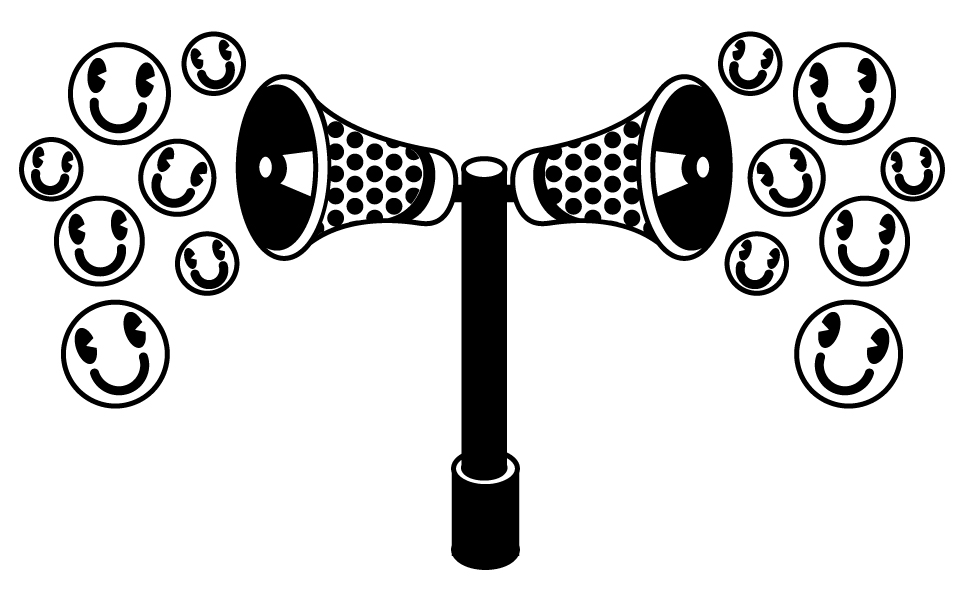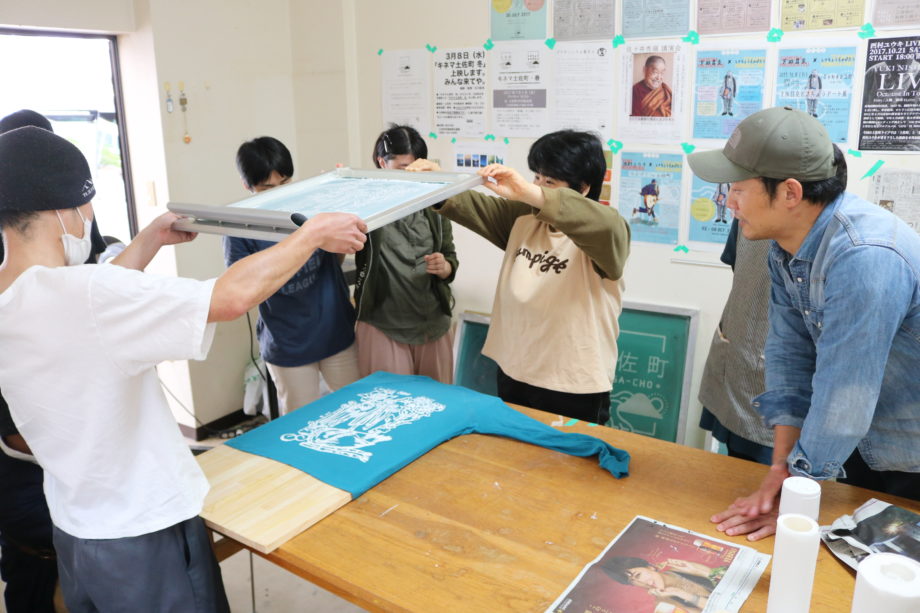土佐町相川地区。美しい棚田が広がり「相川米」という名のついた美味しいお米の生産地です。
夕方になると、水を張った田んぼは向かいの山々の輪郭や夕焼け空を鏡のように映し出し、その時を待っていたかのように、あっちからこっちからカエルが大合唱を始めます。「これは土佐町の第九やね」と言った人がいましたが、なんとも上手くその時の様子を言い表していると思います。
こんな風景を土佐町の毎日のなかに見ることができるのは、田んぼを守り続けている人たちがいるからです。
今年も田んぼの準備が始まっています。3月下旬ごろから、土佐町の田んぼに「畦(あぜ)」が付きます。
今は機械で畦をつける人が多いですが、昔は又鍬と平鍬を使い、田んぼの周りをぐるりと一周、人が畦を付けていました。
必要最低限の機械と人の力でお米を作っている人は、一年間の田んぼの仕事の中で「畦付けが一番しんどい」と言います。
土佐町相川地区高須の沢田清敏さんが「これから畦を付けるき」と言うので、その様子を見せてもらいました。
清敏さんは麦わら帽子をかぶり、三又鍬を肩に担って、ずぶずぶと田んぼに入っていきます。
清敏さんの田んぼはすでに機械で畦が付けられていますが、機械が大きいのでどうしても「手の届かないところ」が出てきます。その部分を人の力で付けるのです。
「昔は田んぼに水を溜める前に畦を「かいで」た。平鍬でかいで、かいだら水を貯める。昔は畦付け機なんかなかったきね、田んぼの縁周り、ぜーんぶ平鍬で、かがないかんかった。」

これが「平鍬」
「かいだ土を練って、練ったものを又鍬で畦を付ける。ほいで、この上をもう一回、平鍬で、左官屋さんがするみたいに、すーーーっ、と平くするがよ。今はそういうことはせんなったけど。
そこの角なんかはどうしても機械で付けれんろ。付けれんところは手で付けるがよ。」

「でも今日は平鍬でまでようせん。そこまでしよったら大変! 見えは悪いけんどね。ようは、もぐらが穴を開けて水を漏らさんために畦を塗るがやきよね。」
清敏さんの田んぼは、一部コンクリートになっているところがあります。
「コンクリートのところも機械で(畦を)付けれるけんど、コンクリートの縁まで機械がぴったりいかんき、縁周りの畦の幅がひろうなるわけよ。もったいないわね。やき、コンクリートのところは手で畦を付ける。しんどいけんど、その分苗が植えれる。一株でも多く植えれるように。楽をしようと思ったらこんなことせんでも構わんけんど。」
その言葉には、清敏さんの姿勢が現れているような気がします。
 コンクリートの縁にも畦を付けていく
コンクリートの縁にも畦を付けていく
「畦を付けるろ、田植えの一週間くらい前に肥料を振って、もう一回代掻きをするがよ。叩いたら(意味:耕したら)土がどうしてもやりこい。土を落ち着かすがよ。
あんまりドロドロのところを植えたら、どうしても植えた時に「かやる」。苗が立たなあね。一週間ばあ置いちゃったら土も落ち着くし、水の中で土が固くなってくる。」
 「ほんなら帰って、自分くのやってみて!」 そう言って清敏さんは笑った。
「ほんなら帰って、自分くのやってみて!」 そう言って清敏さんは笑った。
「畦をつける時は、雨が振って4〜5日ばあ経ってから。もうそろそろ畦をつけないかんというても、あんまり天気が続いて土そのものがカラカラやったら山ができん。ある程度水分を持たしたら山ができるろ。そういう感じよ。
みんな天気予報を見ながら段取りを考えゆう。雨が振ったら『4〜5日後に畦つけるぞ』と思うちゅう。
ちょうどいい土の状態を見て『明日やろう』って決めるがよ。」
清敏さんに聞きました。
「畦を付ける頃、もし雨が降らんかったらどうするんですか?」
清敏さんは、少し考えて答えてくれました。
「春先、桜の花が咲く時分いうたら、いつでも毎年よう雨が降らあ。今年は桜の花が咲いた時分、うんと天気が続くのは続いたけんど。大体普段は一週間に一回は降るもんよ。」
清敏さんの言葉には迷いがありませんでした。
まっこと自然はうまいことできているなあ!と思います。
「田んぼに足音を聞かせてあげなさい。」と近所のおばあちゃんが話してくれたことがあります。
それがお米を育てる一番の秘訣だ、と。
土佐町の先人たちが引き継いできた田んぼに、今年も足跡が重ねられていきます。
又鍬で畦を付ける沢田清敏さん
機械で畦を付ける 協力:澤田光明さん