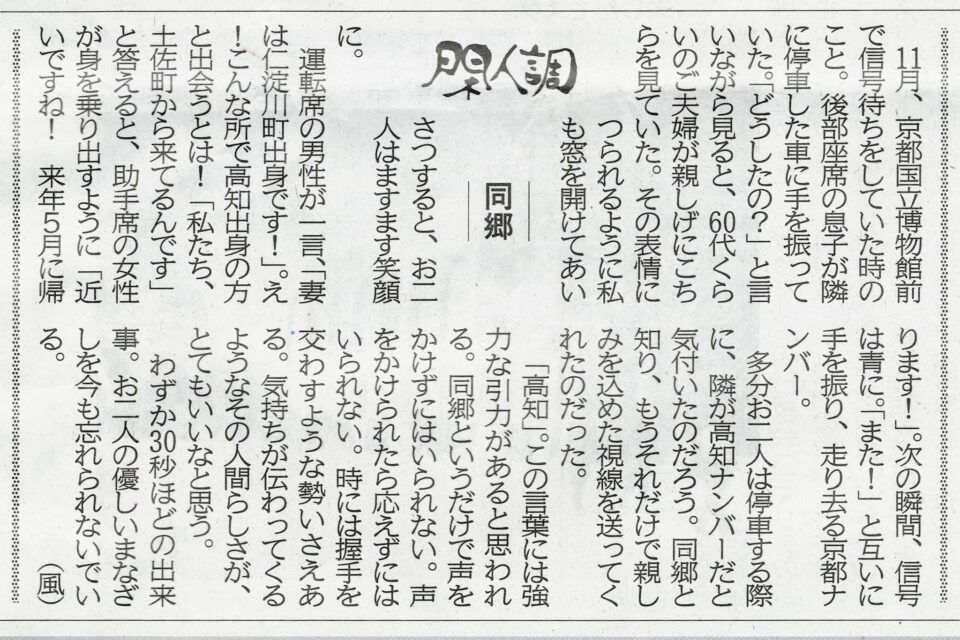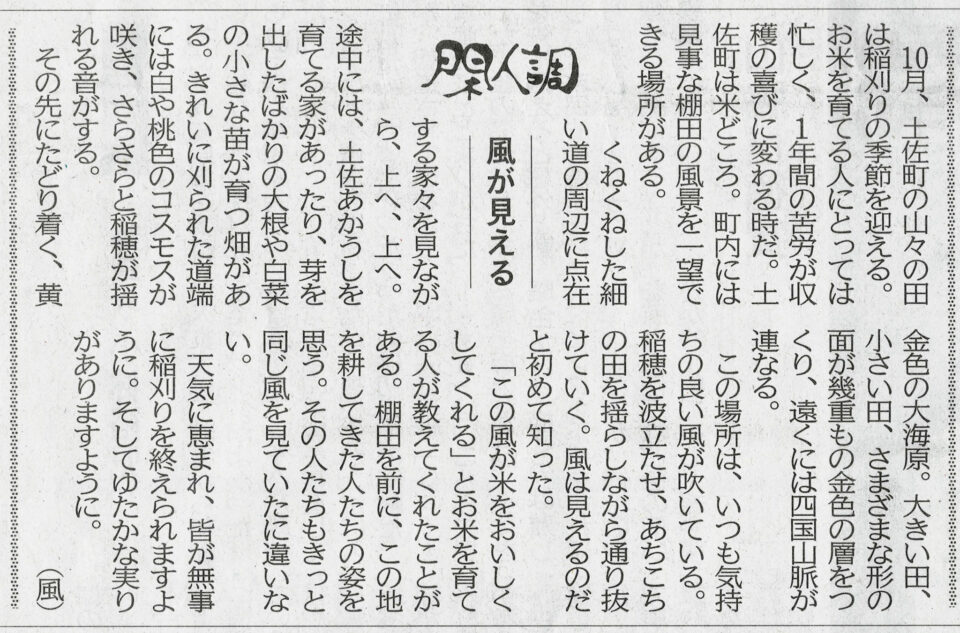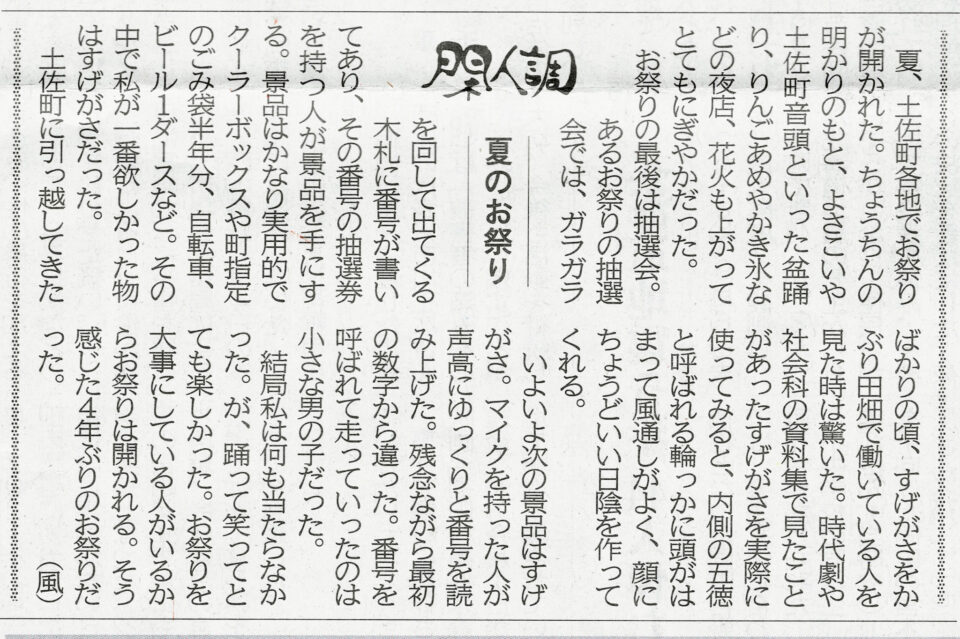写真後列左から:筒井浩司さん・澤田明久さん・森岡拓実さん
写真前列左から:池添篤さん・大石淳一さん・山中晴介さん・小笠原啓介さん
以前、自衛隊員として仕事していたという大石淳一さん。
池添さんと知り合い「30歳になって年齢的にもう転職はできん。“いい加減にちゃんとせえよ”と喝を入れられ、“よっしゃ、頑張るわ”と大工を続けてきた」と言います。
今回のベンチの製作は、 “げっちゃん(池添さん)”に誘われて、ちょうど予定が空いてたから。やっぱり助け合いよ。情が違うけ。こんまい(狭い)中でやるには 困っちょったら助け合わんと。それが田舎やけ
今回のベンチの作業は、冗談も言いながらの余裕がある仕事で、和気藹々にできたとのこと。そして、その仕上がりは完璧。
やるべきことはやり、真剣にやりゆう中にここはかまん(かまわない)という時がある。現場は楽しくなかったらいかん。俺はそういう考えやけ

大石淳一さん
町のあちこちにベンチを届けると「これはいい木を使ってるにゃあ」「しっかりよくできちゅう」と何人もの町の方たちが声をかけてくれました。そう言ってくれたのは、木に関わる仕事をしている方や町の職人さんたち。長年プロとしてやってきた方がかけてくれたその言葉の数々に、このベンチはとてもよいものなのだとあらためて実感しました。
でもきっと、このベンチを作ってくれた職人さんたちは「よいものであるのは当たり前だ」と思っているでしょう。助け合いながら、仕事への覚悟を貫く職人さんたちの魂ある姿に、ただただ頭がさがる思いです。
嶺北高校卒業後、2年間専門学校へ通い、20歳で大工として家を継いだ小笠原啓介さん。「最近やっと、大工になってよかったと思えるようになった。ありがとうと感謝できるようになった」と話します。

左:池添篤さん 右:小笠原啓介さん
小笠原さんは現在40歳。家業である大工を継ぐかどうかの選択を自らした訳ではなく、“継ぎなさい”と言われた訳でもなく、ただ自分がどうしたいのかがわからなかった。自分の意見を言える人間ではなかったと言う小笠原さん。それでも大工を続けてきたのは、なぜでしょうか?
なんやろね?…負けたくないというところができたのだと思う。それは、カンナ。最近、やっと親方に認めてもろうた。それまでは親方がしていたところを “お前削ってみろや”と言われた。カンナで削ることは大工としては一生もの。
カンナで削ることだけは誰にも負けたくない。小笠原さんはその一心で、いつ仕事が来てもいいように常にカンナを研いでおき、誰にも負けない刃を作っていたとのこと。カンナは小笠原さんにとって、大工として生き抜くためのいわば武器だったのです。
柔らかい表面削っていて急に硬くなる時がある。それをいかに削るか。そういう時は秘密がある。それはやった人しかわからん。カンナがあって歯があって、引っ張ったら吸い付く感じ。切れてることが伝わってくる。カンナは手工具なので、伝わってくるものは自分にしかわからない。それは機械にはできないこと。手でやるしかない。
それを誰がやる?それは俺がやる。ほんと、そこだけ。カンナだけは負けたくない。ここだけは譲れない
お互いの良さを認め、日々「あいつには負けん」と切磋琢磨する職人の世界。ふと頭をもたげてくる自分への楽観を振り払うように、目の前の仕事にひたむきに向き合ってきた人だけが持てる眼があるのではないでしょうか。
自分がやってきたことに対して、今やっと感謝できるようになった。今回のベンチも、色々な人と仕事できたのが嬉しくてね。こんなの初めてやった。それはみんなのおかげ。前だったら、言いたいけど言えんことやった
目を少し赤くしながら、小笠原さんは最後に話してくれました。
人間は木がないと生きていけない。森林があるということは、二酸化炭素を酸素に変えてくれるということ。素晴らしいんで木は。それは昔からの根本的なことで、木があってこそ人間の暮らしがある。暮らしには家が必要で、家を建てる人が必要で、暮らしはそういうことかなと思う。人はいつか死ぬ
日々の感謝を言えることが一番大事やなと思うし、感謝してるからこそ言える。循環してるんやなあと思う
町のあちらこちらに置かれたベンチはこれからきっと町の一部になっていくことでしょう。
山があり、技術ある職人さんたちがいるこの地だからこそベンチを作ることができました。
嶺北の木を使い、土佐町の職人さんが作ってくれたベンチを土佐町の人が使う。このひとつの循環が、町の人たちを繋ぐようなかたちになればとても嬉しく思います。