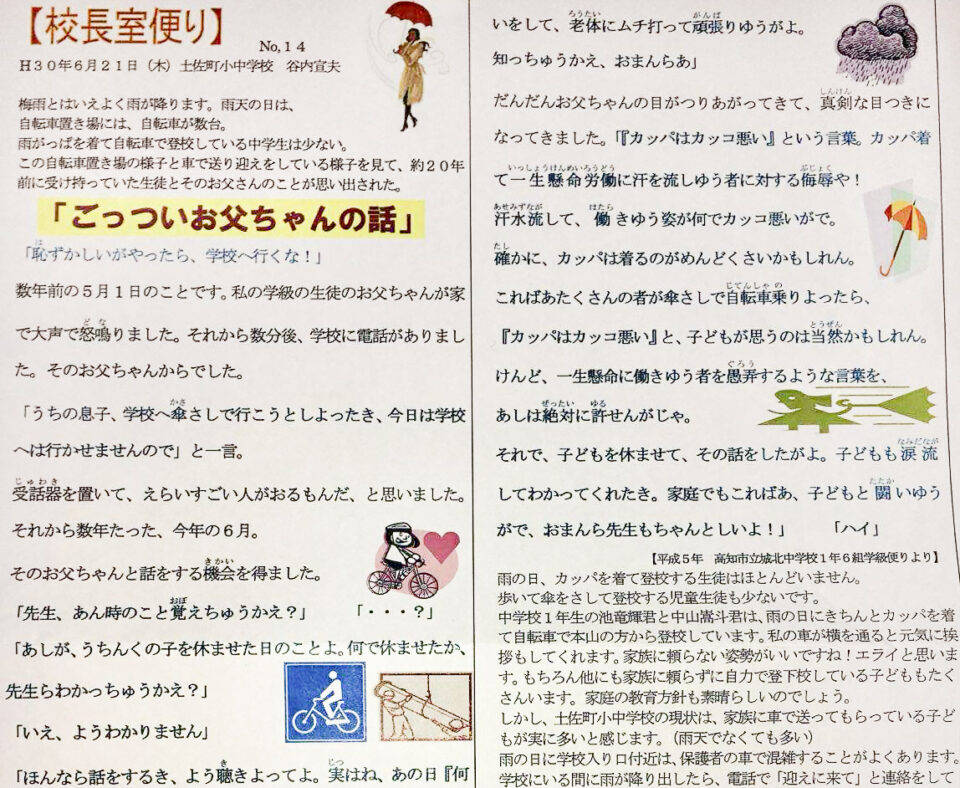それでは、新自由主義の競争的な格差社会を根底で支える自己責任論は、どのようにして社会に浸透していったのだろうか。その答えを国内だけに求めても、到底理解することはできない。「自由と平等の国」であるはずのアメリカでは、勝者に優しく弱者に厳しいトランプ大統領が誕生した。少し時間を遡ってその背景を考えてみたい。
1950〜60年代は、公民権運動がアメリカを席巻し、多様性や黒人の人権が焦点になり、国民の権利を重視する左派が躍進した時代だった。そこから右派の猛烈な巻き返しが始まった。右派は、有名大学の中にシンクタンクを次々とつくり、右派の価値観を継承する若い学者を育成し、シンクタンク内につくったメディアを通して彼らの主張を拡散した。右派は、議論の枠組みを設定する「フレーミング」を駆使し、あらゆる論点をねじ曲げて、自分たちに都合のよい議論の枠組みを設定するようになった。
例えば福祉国家は、「大きな政府」と描き「税金の無駄遣いだ」と批判し、福祉政策を縮小。鉄道や電力などの公共事業は、選択肢を増やす「自由化」が必要だと言って民営化を実現。生活保護も「依存の文化」をつくると批判し縮小した。これらに共通しているのは、「公の責任」から「自己責任」、「平等と包摂」から「競争と排除」への転換だ。
背景にあるのは、「厳しくても努力が報われる平等な競争社会」という保守の世界観だ。そのレンズで見れば、貧困は個人の努力不足であり、施しを与えることはその者を甘やかすことになる。逆に、裕福な者は努力者であり、恩恵を受けて当然となる。だから低所得者に対する生活保護の削減や奨学金の廃止を行う一方で、富裕層への寛大な税金控除という、社会の構造的な不平等を再生産する白人至上主義の歪んだ政策が展開されるのだ。
教育も例外ではない。2002年のアメリカ連邦政府による「落ちこぼれ防止法」は、富裕層と貧困層の「教育機会の格差」を、国家が貧しい地域に投資責任を果たすことで解消するというそれまでの方針を、富裕層と貧困層の「学習到達度の格差」を教育現場の結果責任で解消する方針へと舵を切った。
学力標準テストと結果責任という二本の軸がインストールされると、各学校が自らの生存を賭けて生徒を奪い合う「市場型学校選択制」が始まった。テストの点数に基づく画一的な評価の下で学校は序列化され、公立小学校や中学校でも「あたり」と「はずれ」があることが正当化された。「底辺校」は容赦なくつぶされた。ちまたでは、子どものために熱心に学校を選び、入学させるのが「良い親」と言われるようになった。一方、日々の生活に必死で、仕事を休んで学校説明会などに行くゆとりのない保護者の子どもたちには、廃校寸前の、誰にも選ばれなかった学校があてがわれた。行く先々で学校が廃校になり、たらい回しにされる子どもたちも少なくなかった。
(全人教広報誌『であい』2025年8月号より再掲載)
(つづく)