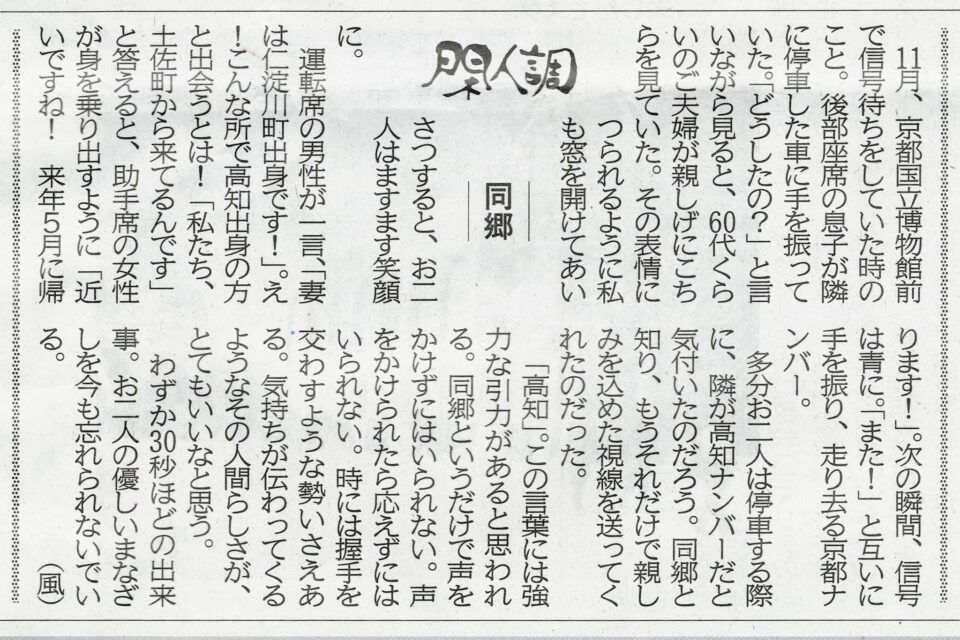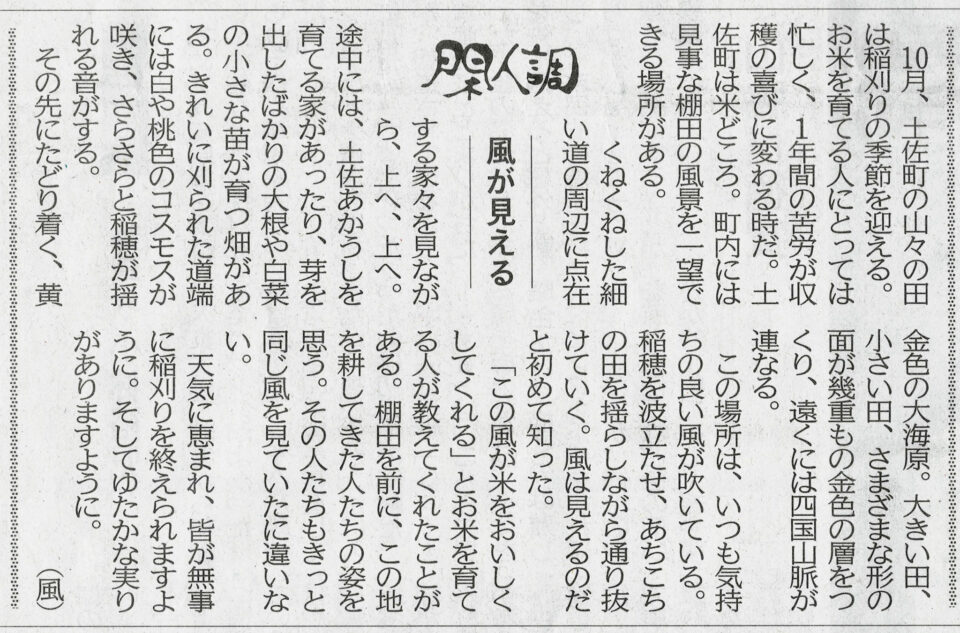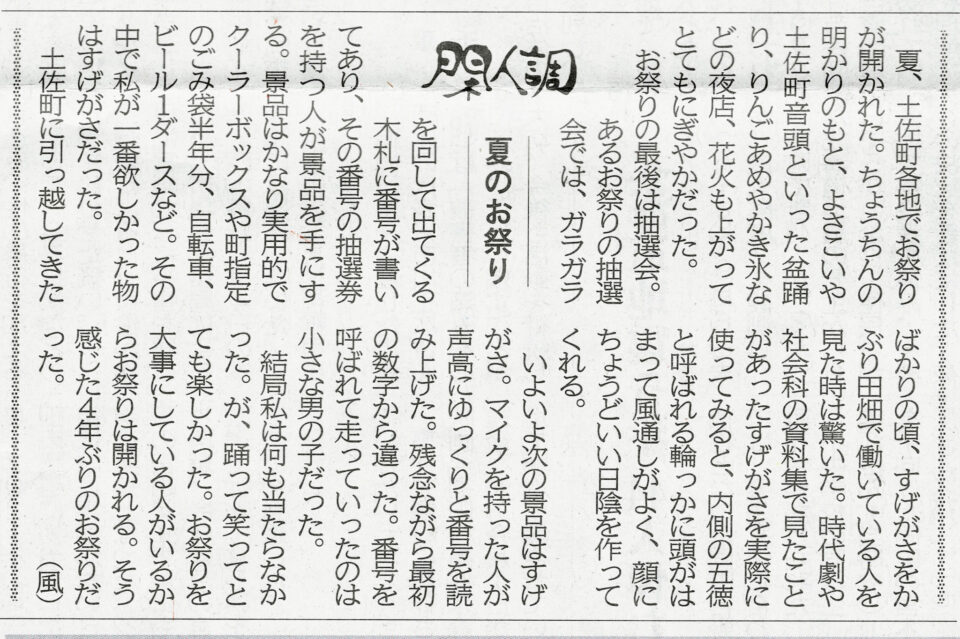土佐町には「和田」という名の地区がある。標高500~600メートル。さめうらダムの近く、山がちで、和田の人たちは急な斜面に田畑を作って暮らしている。山道に沿って薪が蓄えられ、菜の花や水仙が咲く。そういった道端の風景は、深い山の中にも人の営みがあることを教えてくれる。
和田地区に、美味しいこんにゃくを作る人がいる。その人は和田潔子さん。潔子さんの作るこんにゃくは、そのまま薄く切って刺身にしたり、煮物にしても味がよくしみるので、わざわざ家まで買いに来る人もいるそうだ。

和田潔子さん
潔子さんのこんにゃく作りは、毎年11月から3月ごろまで。秋の取り入れが終わってから作り始め、ゼンマイやいたどりなど山菜の仕事が始まる前に終える。潔子さんは先代のおしゅうとめさんから作り方を習い、10年以上こんにゃくを作り続けている。

こんにゃく芋
これがこんにゃくの材料、こんにゃく芋。芋の収穫は10月。収穫したあと、2週間から20日ほど日に干すと水分が抜けて、しびにくくなる(腐りにくくなる)。

こんにゃく芋を釜に入れ、丸ごと3時間以上煮て、皮を剥ぐ。
「そのままだと痛い(熱い)け、水につけて剥ぐんよ」
手のひらにも指先にも、さつまいもを蒸したようなこんにゃくの香りが残る。

茹でたての芋の皮は、ぬるぬると、つるりと剥ける

すぐに使わないものは冷凍して保存しておく

芋とぬるま湯をミキサーにかけることで、キメの細かいこんにゃくができる

とろとろのこんにゃく芋を固まらせる役割を担うのは、この茶色の液体、灰汁。燃えた木の灰を水とまぜ、布で濾したもの。潔子さんのこんにゃくには灰汁も加える。浅木(広葉樹の雑木)である樫の木を燃やした灰で作っているそうだ。
「樫の木だと、ええ灰がとれる」
同じ灰でも樫の灰は重く、杉やヒノキの灰は軽い。杉やヒノキの灰汁でこんにゃくを作っても上手く固まらないという。
なんという不思議、自然の神秘。

「こんにゃくは火をたくさん焚くから、木がいくらあっても足りんよ」
こんにゃくを茹でるお湯を沸かすため、大釜の下にある焚口からせっせと薪をくべる。
木はいつも自分の暮らす山にある。こんにゃく作りは、そこに山があるから成り立っている。

灰汁を混ぜると、たちまちこんにゃくの香りが辺りに広がった。灰汁だけだと足りないので炭酸ナトリウムも加え、手で大きくぐるぐると混ぜると、すぐに固まってくる。
「この時が一番大変」と潔子さん。

固まったこんにゃくを隙間なく掬い取るようにお椀に入れ、手に取り、丸める。
傍らで、釜の湯がふつふついう音が聞こえる。薪がパチパチとはぜる。お湯がぽんぽん沸き出したら、こんにゃくを入れていく。

湯に入れる前、ひとつずつ手のひらの中で丁寧にかたちを整える潔子さん。まるで話をしながら、「いってらっしゃい」と送り出しているかのよう。丸めながら茹でていくので、後から茹でるものと時間差ができてしまう。そのため、先に茹で始めた方は一旦もろぶたにあげておく。

「こんにゃく同士が肩寄せ合って、煮えますよ」
潔子さんはそう言いながら、大きな木のしゃもじで釜の中をそっと回す。こんにゃくを茹でるのはだいたい30分ほど。
もういい頃合いだという時、「こんにゃくが音を鳴らす」という。
「ほら、音がする」
潔子さんからしゃもじを受け取り、こんにゃくを回すと、釜底から低く唸るような気配が。それは、台風の日に雨戸を閉め切った家の中で聞く、もうすぐ過ぎ去るだろう外を吹き荒れる風の音に似ていた。

茹で上がったこんにゃくをもろぶたへあげる。木製のもろぶたは、こんにゃくの水分をちょうどよく逃がしてくれる。掬い上げる網は、おばあちゃんの手作り。

潔子さんは出来立てのこんにゃくを手でちぎり、ニンニクを漬け込んだ味醂醤油をつけて食べさせてくれた。その美味しさは、もう、のけぞるほど!もうひとつ、もうひとつ、と手を伸ばすうち、いくつもあったこんにゃくを私はすっかり平らげてしまった。
「これは作っている人じゃないと食べれん。作ってる人の醍醐味!」と潔子さん。
この状態でゆっくりと冷まし、次の日に産直市に持っていって販売するそうだ。

潔子さんの家の前に広がる山がち
もし、対岸の山から潔子さんの家を見たら、火を焚く煙が日々たなびくのがわかるだろうか。
山の道々の田んぼや畑、誰かが植えただろう並ぶ広葉樹。濡れないようトタンで屋根をし、丁寧に積み上げられた薪。そして火を焚く煙は、そこに人の暮らしがあるという証。山の人たちは、身の回りのものを工夫して使い、自らの暮らしを切り拓いてきたのだ。
潔子さんは、お土産に出来立てのこんにゃくを持たせてくれた。袋に入れられたこんにゃくはずっしりと重く、ほかほかと温かかった。