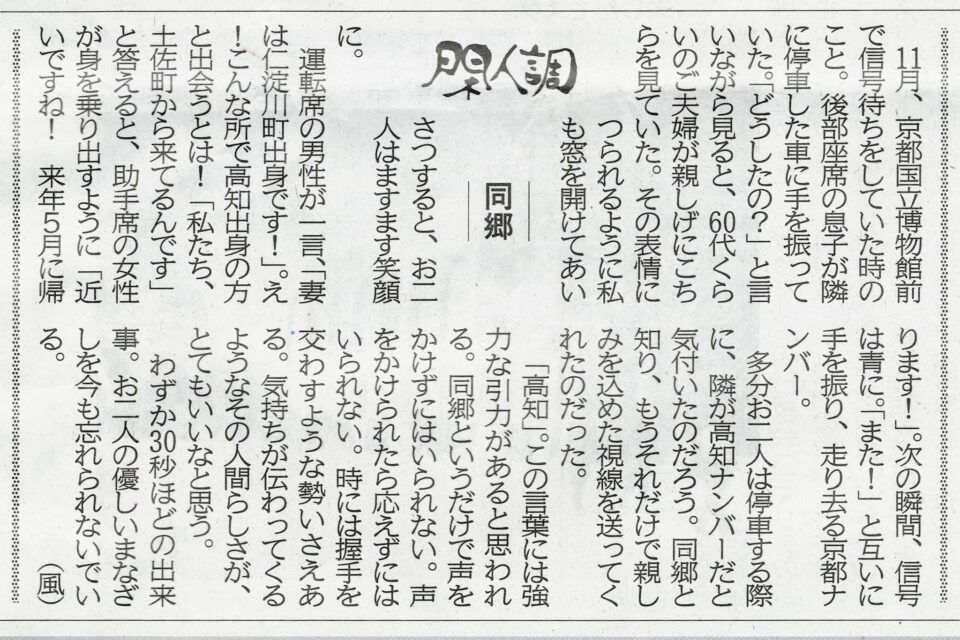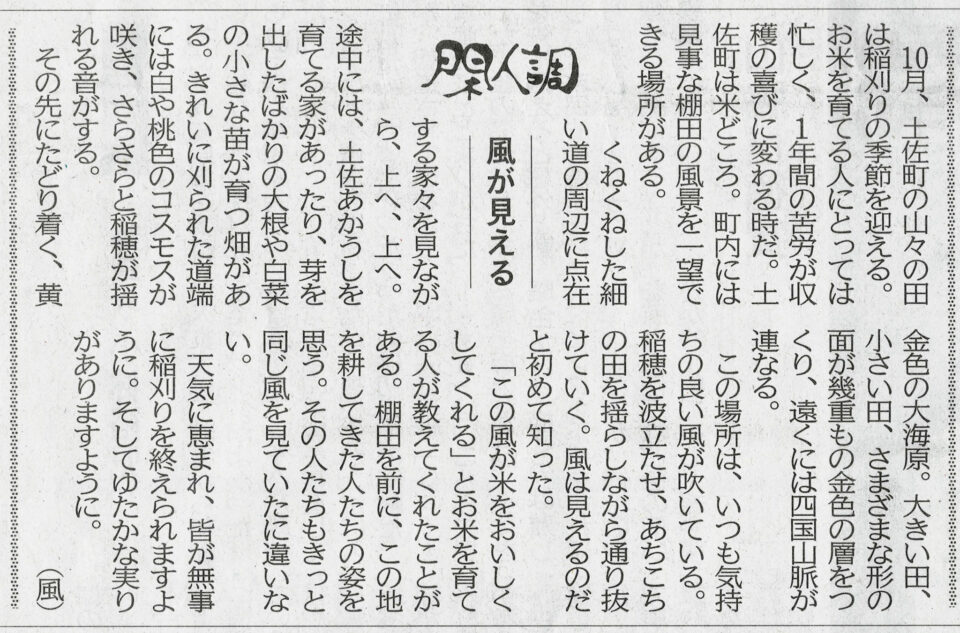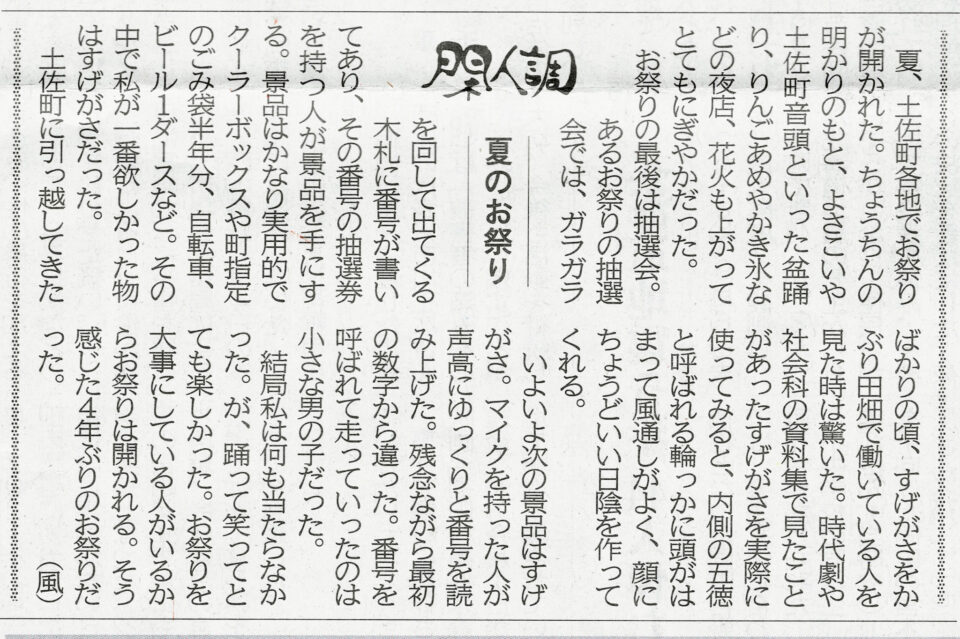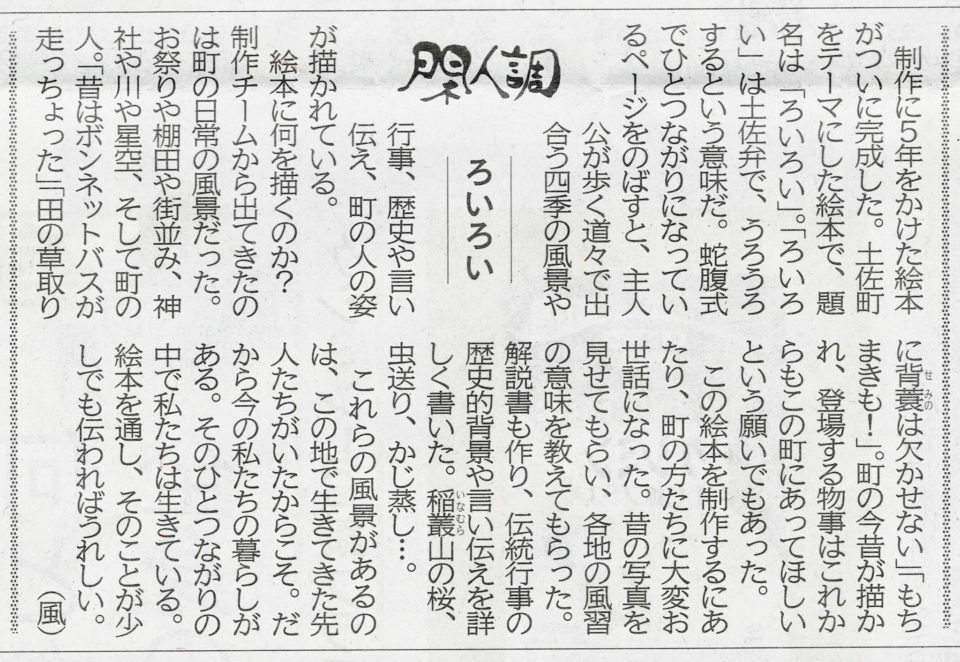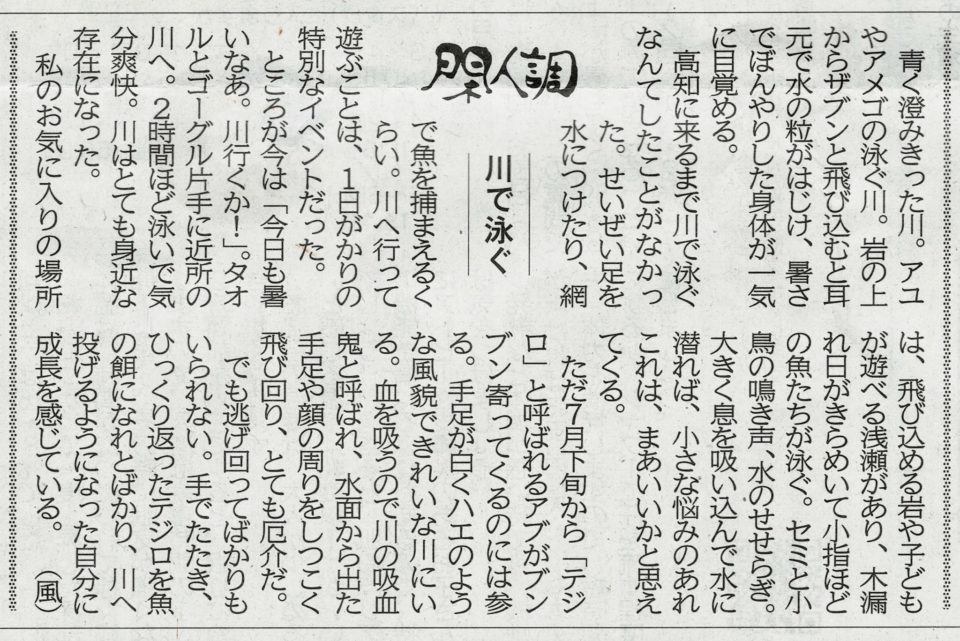(「この山に暮らす 2」)
和田さんが毎日使う水は山水で、家の裏のどんぐりの林のなかをだいぶ登ったところに水の取り口があるそうだ。
昨年、山を登って水の取り口へ行く途中、佐登美さんは山の斜面を転げ落ちてしまったのだという。デイサービスの日まで何日か痛みを我慢し、やっと診てもらって、幸い骨が折れていることはなかったそうだ。
こんなこともありうるのが、山で暮らすということなのだと思う。

佐登美さんは出会ったばかりの頃、多分私のことをちょっと警戒していたのだと思う。でも電話ではないやりとりをするために何度も何度も通ううち、やっと笑顔を見せてくれるようになったのはつい最近のことだ。
背中は曲がってはいるが足取りはしっかりしていて、いつも地下足袋や長靴を履いている。
行くとたいてい家の前の斜面にある畑でカヤを刈ったり仕事をしていて、上から私が大きな声で挨拶すると、働く手を止めてこちらを振り返り、ああ、という感じで、今までしていた仕事をしずかに中断して私がいるところまで上がってきてくれるのだ。
この日、話している途中に「え?今のは土佐弁ですか?」と私が聞き返した言葉がいくつかあったが、それは芙美子さんに言わせると『お父さんが勝手に作った言葉』なんだという。みんなで笑った。
そうやっておもしろい言葉を言って、私たちがその意味に気づくかなと待っている目はちょっとしたユーモアと親しみを込めたものだった。
芙美子さんがりゅうきゅうが生えている畑の斜面をしっかりとした足取りでおり、鎌でざくっ、ざくっと根元を切り、上の葉を落として茎の部分を手渡してくれた。
なんてよく切れる鎌。佐登美さんが研いでくれているのだそうだ。
大人の腕くらいある太い茎のりゅうきゅうのうちの一本は、お願いして葉を残しておいてもらった。そのりゅうきゅうは私の背丈よりも大きくて、持って立つとまるで傘をさしたトトロのようで、この時もみんなで笑った。
佐登美さんは70代の時、がんになったのだという。
「あの時死ねばよかった。」
「生きていても仕方ないことよ。」
佐登美さんは、背中を曲げながらまっすぐに立ち、私の目を見てそう言った。
その目を見たら、なんと答えたらいいのかわからなかった。
何も言えなかった。
帰り際、佐登美さんはこの日一緒に訪ねた私の友人がカメラマンということを知って「あの柚子の木がとてもきれいに見えるところがある。よかったら案内するけんど。」と言った。
最初は友人にそう言ったけれど彼の返事は曖昧なものだったらしく、私にもう一度同じことを話してくれたのだ。
佐登美さんの後について畑におりる。
道をもう少し下って行ったところで佐登美さんは立ち止まった。
そして、ここがそうだ、というように私たちの方を向いた。

佐登美さんが立つその場所までおり、そこから母屋の方を眺めると、少し遠くに見える母屋の下にある柚子の木が、まるで黄色の灯りをともしているようにそこにたっているのが見えた。
わぁ、と思わず声が出た。
佐登美さんが教えてくれた場所から見える風景はまるで、おふたりの今までのながいながい道のりや生きざまを描いた一枚の絵のようだった。
目の前にはお茶の木があり、手前の斜面にはもう何十年も、もしかしたら何百年も耕し続けた畑があり、その上に佐登美さんと芙美子さんが暮らす家が見えた。
おふたりはここで暮らしているという実感が、ずしんとわいた。
そして、この場所で暮らしてきたというこれまでの歴史がじわじわとみえてくるようだった。
芙美子さんがこの場所へお嫁に来たこと。
この場所でこどもを産んだこと。
こどもたちは毎日歩いて山々を越えて学校へ行き、また同じ道を帰ってきて、今日あったことを佐登美さんと芙美子さんに話しただろうこと。
こどもたちは高校へ行くために町へ出て、山へは戻ってこなかったこと。
それからはふたりだけでずっと暮らしてきたこと。

佐登美さんが、この場所から写真を撮ったらいいと言ったのは、それはもしかしたら、自分たちがこの場所で生きてきたという証を心のどこかで見せたかったのかもしれないし、自分が毎日見ていて美しいと思う風景を教えたいと思ったのかもしれない。
どんな思いであっても、案内するけんど、と言ってくれた佐登美さんの気持ちに心打たれた。
(「この山に暮らす 4」へ続く)