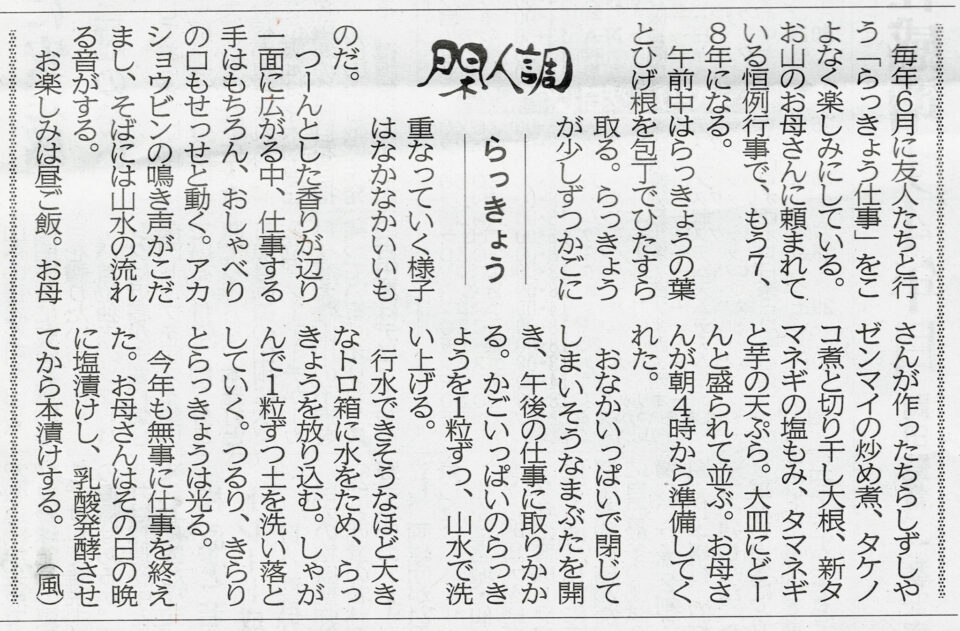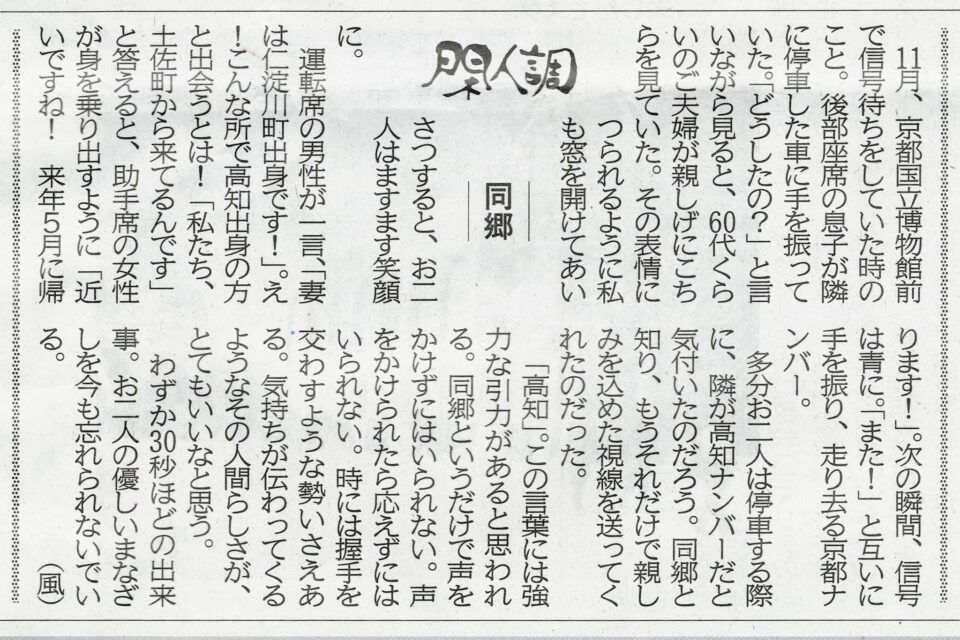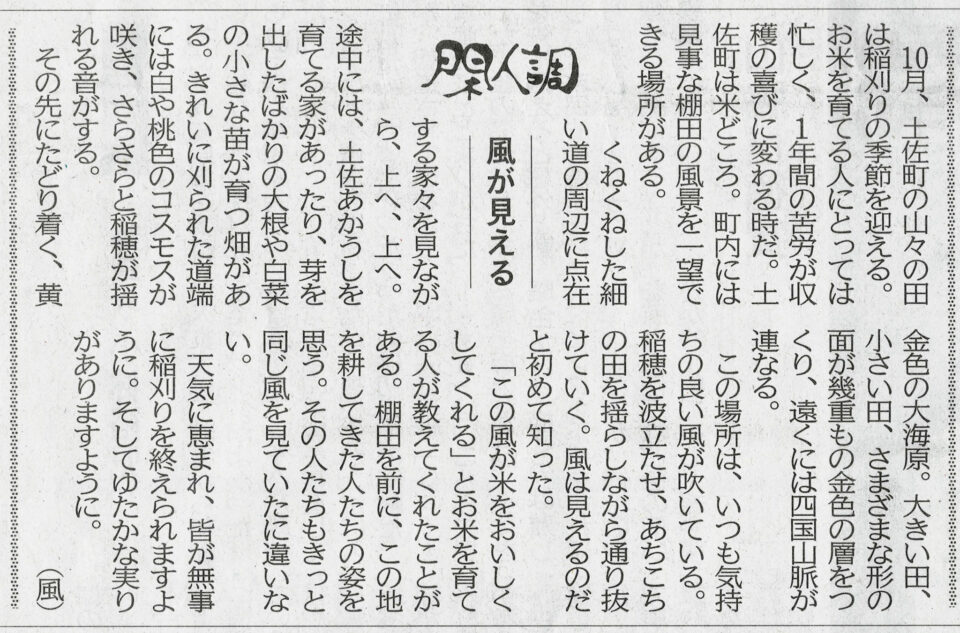麹が完成するまでの3日間は、麹の存在を常に心に置きながら過ごすことになる。
麹づくりは温度管理がとても大切。計美さんの作り方は、この時は布団が何枚と決まっているわけではなく、麹の温度によって着せる布団の枚数を増やしたり減らしたり、その日の気温によって部屋にストーブを焚いたりと、その日の空模様や気温、麹の様子と相談しながら臨機応変にお世話をする。
まるで生まれたばかりの赤ちゃんを育てるみたいに。

床に広げた白い布の上に蒸しあがったお米をひろげ、麹菌をまぶす。熱が逃げないように布の端も丁寧に折り入れてお米を包み、新聞紙をかけ、最後に布団をかける。
「昔ながらの綿の布団がいちばんいいのよ。お布団を着せてやるの。」と計美さん。

布団の上から手をあてるとお米からの熱がぽかぽかと伝わってきて、冷たくなっていた手のひらが、まんなかからじんわりとあたたまっていく。
お布団をかける、のではない。お布団を「着せる」。そのほかほかした暖かさのなかで麹菌が働く。「着せる」という言葉に、麹への思いが込められているような気がする。「もう1枚かけちょこうね」と布団を着せる計美さんの顔は、お母さんの顔だった。
ぽんぽん、とお布団をたたいて「これでよし、と」。その計美さんの顔を見て、私もほっとしたような気持ちになる。
「こういう昔ながらのやりかたが、私にはいちばんえいのよ。今は麹室で温度管理してくれるものもあるけど、また香りが違うきね。」と計美さん。
できあがった麹は家中を甘い香りでいっぱいにして、くらくらするくらいだった。
手間も時間も労力もかかる麹づくりを計美さんは、もう30年もやってきた。昔は近所の人と一緒にやっていたけれど一人減り二人減り、最後は計美さんひとりになった。ひとりになっても毎年の仕事として、こつこつとやり続けてきたその思いはどんなものだったのだろう。
「これが私の一年の、この季節のしごとなのよ」と計美さん。
ひとつ仕事をやり終えたという満足感と、ほっとした気持ちがまじったような感慨深い表情だった。

こつこつと自分のできることを自分の場所で続けることが、ひとつの文化を引き継ぐということでもあるのかもしれない。ひとつの文化が誰かへと引き継がれていくなかで、それぞれの人が工夫してきたことや思いは、少しずつかたちを変えながら次の人へとバトンタッチされていく。
その根底に流れているだろう普遍的な何かは変わらずにそこにあって、それがあるからこそ引き継いでいこう、続けようという思いが生まれるような気がする。
麹づくりの時に心が何より動かされたのは、麹を作る部屋へ行く途中にあるこたつの上に書きかけの年賀状が置かれていたことだ。こたつの上には今年の年賀状の束も置かれていて、きっとそれを見ながら来年の年賀状を書いていたのだろうということがわかった。
あ、あのこともやっておかなくては、とやるべきことを急に思い出して席を立ったのか、ふたが開いたままのペンも置かれていた。夜、計美さんがその場所に座って、どんなに忙しくても、どんなに疲れていても、どんなに眠たくても年賀状の宛先を眺め、その人のことを心に浮かべながら年賀状を書いている姿が目に見えるようだった。蒸したお米を部屋へ運び入れながら、その計美さんの背中が思い浮かんで、胸がいっぱいになった。
私にとってのお山のお母さん、和田計美さん。
今日もあの山の向こうのあの家にいて、くるくるといそがしく、誰かのことを思いながら働いていることだろう。私にはその姿がありありと思い浮かぶ。目の前にいるかのように計美さんが働く姿を思い描けるということは、私はこの地で暮らしている、という深い実感につながっている。
いつも計美さんは「またいつでもあがってきなさいよ」と言いながら見送ってくれる。「はい、また来ます」という気持ちでいっぱいになりながら、お山のお母さんからの贈り物をいただいて私は私の場所へ帰る。
人をしあわせにするしごとや人の心に届くしごとは、大切な誰かの顔を思い描き、自分のするべきことを毎日こつこつと真摯に積みあげる人がつくることができるのかもしれない。
計美さん、また季節のしごとを学ばせてください。めぐりめぐっていく季節の手しごとを引き継ぎ、そして、計美さんのような心意気も身につけて、私もいつか誰かにとってのお山のお母さんになりたい。