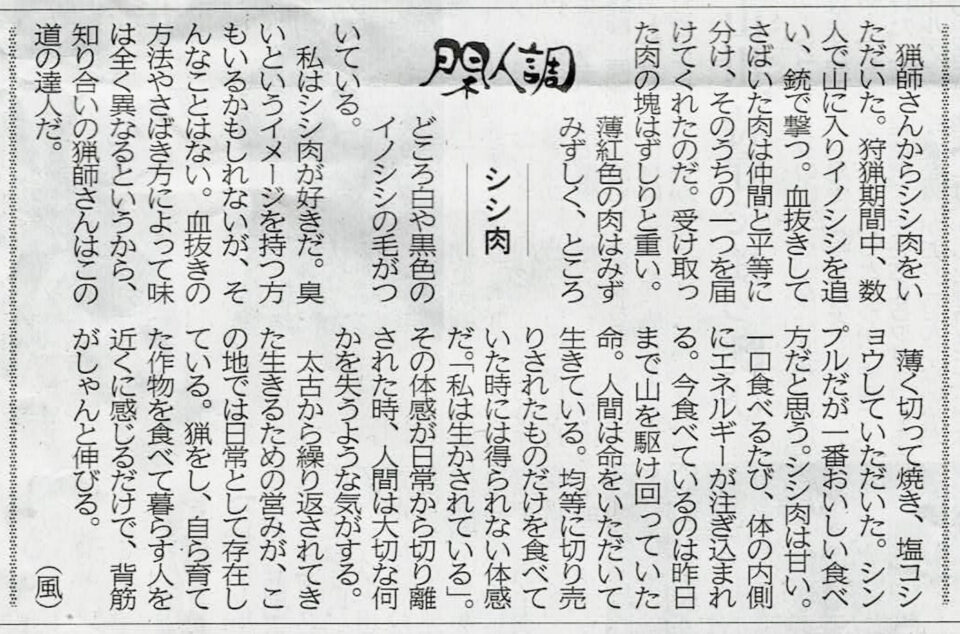猟師さんから猪の肉と骨をもらった。鉄砲で撃ち、捌いたもので、受け取った白いビニール袋は血が透け、骨がはみ出していた。
肉は瑞々しく、太い茶色の毛が何本かついていた。毛を指でつまむとゴワッとしている。この肉の塊は、つい先ほどまで山を駆け回っていた猪。その足音が聞こえるような気がした。
私は時々、無性に猪の肉を食べたくなる。牛でも豚でも鶏でもない、山で生まれ、山で育った猪の肉である。猪の肉は臭いというイメージをお持ちの方も多いかもしれない。が、そんなことはない。捕えてからいかに素早く、いかに巧みに血抜きをするか。肉の味はそれにかかっているという。
「あの山に猪がいる」
猟師さんはその情報を元に、山で犬を放す。
猪は昼間は寝ている。犬はその嗅覚で寝ている猪を見つけ、吠えて猪を追い立てる。
山にはいくつもの獣道がある。猪は逃げる時、どの道を通るのか?狙いをつけ、2~3人の猟師さんがそれぞれの場所で待ち構える。
猪が来たら、撃つ。
猪が死んだら、
「首元から心臓へ向けて、ナイフで刺すがよ」
そうやって血抜きするのだ。
捕えた猪は、猟をした人で分ける。私はそのお裾分けをいただいたのだ。
熱したフライパンにうっすらと油をひき、両面を焼いて塩胡椒で食べた。体温がじわじわと上がっていく。別の生命体が身体に入ってきたのを感じる。命をいただいたのだ、と思う。

「骨からは良いだしが出るよ」
そう聞いて、台所にある一番大きな鍋を用意した。が、骨は鍋から飛び出した。向きを変えようがひっくり返そうが、どうしても鍋に収まらず、はみ出してしまう。命には枠も規格もないのだ。
肋骨は滑らかな曲線を描き、紅く透き通っていた。脚は編み込まれた綱のようで、曲げようにもびくともしない。包丁で切り込みを入れて折ろうとしたが歯が立たない。
もうそのまま煮ることにした。水から煮て、アクをすくう。骨についていた肉は、ほろほろと崩れる。次の日、鍋の表面には白い脂の層ができていた。火を入れると脂は溶け、そこへ大根や白菜、里芋やえのきを加え、麦味噌を加えていただいた。冷えた身体に血が通う。その実感を味わいたいがために、私は何杯もおかわりをした。
「シシ汁を作って、食べるわね。残ったらうどんやラーメンを入れて食べてみ。一味違うわ」
捕えた命は余すことなくいただく、それがいただく者としての礼儀。
猟師さんの姿が、そう言っていた。