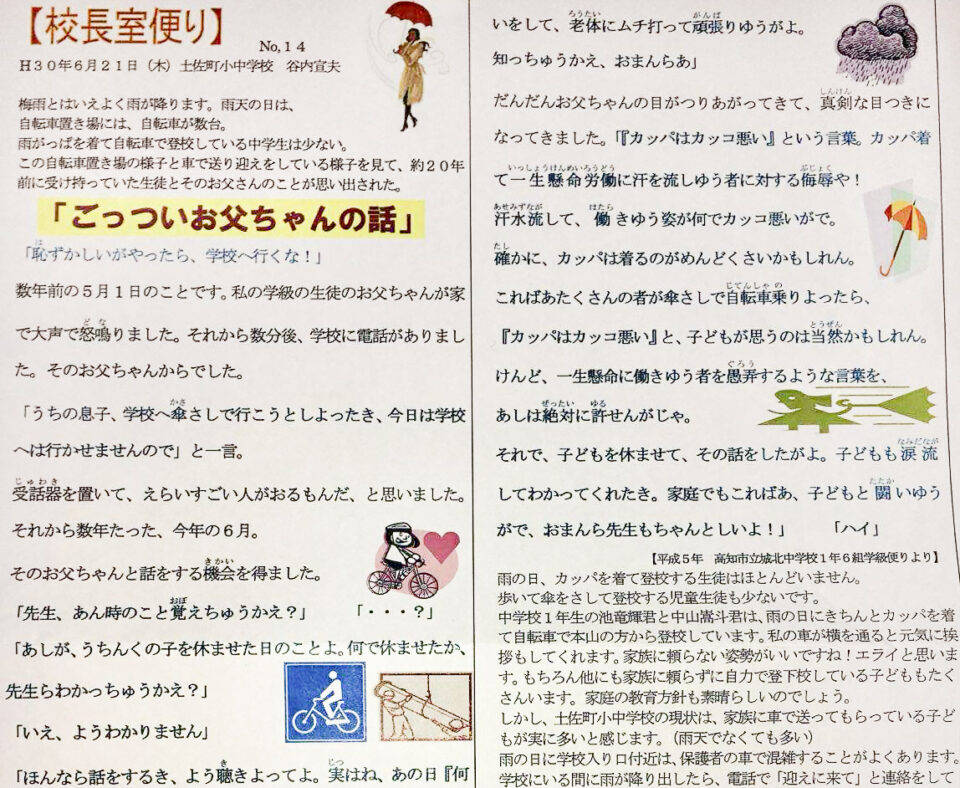私たちの社会は、いつからこんなにも競争的で、不寛容で、息苦しくなってしまったのだろう。お金を出せば何でも買うことができ、経済格差がどんどん露骨になり、金持ちが幅をきかせる世の中だ。みんなのものであった、もしくは誰のものでもなかった物や、行事や、空間が、囲い込まれ、商品化され、お金を払えない人たちが排除されていく。
2016年に出版した『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』(岩波書店)の「はじめに」で、私は当時日本の都市部で始まっていた花火大会の有料化に対する危機感を綴っている。地元の千葉市民花火大会では、かつて早い者勝ちだった浜辺の特等席がA席、B席、C席、シーサイド席と売られ、「市民」であった人々が「消費者」となって、自分の財布と相談しながら当然のようにチケットを買い求めている姿に、私は衝撃を受けた。もちろん、お金がない人、払う気持ちがない人は、遠くから小さな花火を見るしかない。
あれから8年。昨年出版した『崩壊する日本の公教育』(集英社新書)の「はじめに」で、私は同じ問題を取り上げた。花火大会有料化の流れは、とどまるどころか加速している。前述の千葉市民花火大会では、行政がチケットを持っていない人は来場しないようにと呼びかけ、びわ湖大花火大会では、高さ4メートルの「目隠しフェンス」が設置された。行政が、昔はみんなの権利であった行事を商品化し、財力によって市民を公然と序列化し、排除までし始めたのだ。
花火大会当日。フェンスの外には人だかりができていた。背の高い大人は、両手を伸ばして上の隙間にスマホを掲げ、背の届かない子どもたちは、フェンスの下の方の隙間に顔をくっつけて覗いていた。開催に反対した自治連合会の会長は、テレビの取材に対してこう言った。「このかべが、人々の気持ちを変えてしまう。」
フェンスにしがみついていた大人たちは思っただろう。「自分にお金さえあれば…。いつかあのエグゼクティブシートに座ってやる。」背の届かなかった子どもたちも思っただろう。「大人になったら自分も絶対この壁の向こう側で花火を見るんだ。」そうして新自由主義の「モノ・カネ」の価値観は、私たちの心の奥底に入り込み、自己責任論を飲みこませ、知らず知らずに一人ひとりを新自由主義の歯車へと変えてしまうのだ。
(全人教広報誌『であい』2025年8月号より再掲載)
(つづく)