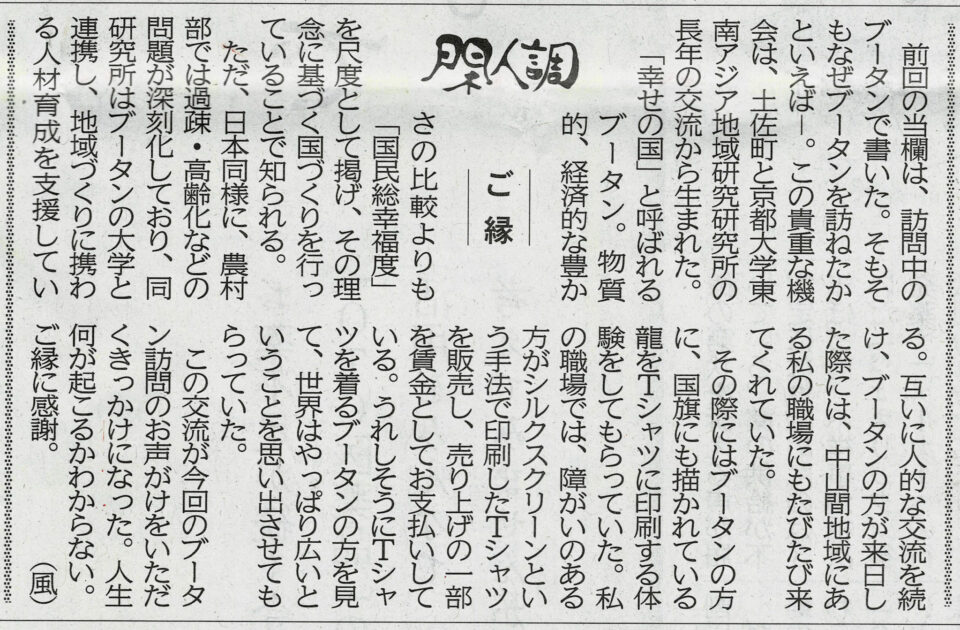どんぐりのシルクスクリーン印刷
土佐町の夏。
7月の南川百万遍祭りをはじめに、中島、相川、地蔵寺、石原と各地域ごとのお祭りが続きます。
土佐町の祭りの最後をしめるのは「野中祭」。
野中祭実行委員会から「野中祭のハッピを作ってほしい」というご注文をいただき、「とさちょうものがたり」×「どんぐり」、野中祭のハッピを作りました!

子ども用のハッピは白インクでプリントしました。
土佐町のロゴと祭りに欠かせない鳴子の入ったデザインです。地域の方とああでもない、こうでもない、と相談しながらデザインを決めました。
ハッピ制作で難しいのは、前側の衿(黒い部分)へのプリント。でもその問題は、以前「土佐町のハッピ」を作った時に解決済み!

前側の衿 右に「土佐町」、左に「野中祭」
(写真ではもう文字がプリントされていますが)文字をバランスよく決まった位置にプリントするためには、版を置く場所を固定することが必要です。
どんぐりのみなさんが考えたのは、衿の上部にダンボールをのせ、ダンボール上辺と版の上辺が合うように版を置く方法。

版の上下に貼られた青いテープに描かれている黒い線を、衿の真ん中に合わせます。衿の幅は狭いので、慎重に版を置きます。

プリントした文字の位置、インクの量などを確認します。
こんな風にして一枚ずつ制作していき、大人用30枚、子ども用20枚、計50枚を制作しました。
そして迎えた8月18日。野中祭の夜。

どんぐりが印刷したはっぴを着て踊る
ちょうちんの灯りのもと、大人も子どもも赤いハッピを着て踊っている姿を見ていたら、このハッピが出来上がるまでに試行錯誤したことや色々あった出来事がいくつもいくつも頭の中をめぐり、やっぱりグッとくるものがありました。

鳴子を使わないで踊るときは、こんな風に、腰に巻いた帯に鳴子をさしておきます。

苦労した衿の文字も、着てみるとこんな風にきれいに合わさっています。
このハッピを作ったひとりであるどんぐりのきほさんも、その風景は「何だかとてもうれしかった」と話していました。
作ったものが誰かの元へと届くということは、作る人と受け取る人の思いが重なるようなことなんじゃないかな、と思いました。
地域の方が「どんぐりさんに作ってほしい」と、注文してくださったことがとてもうれしかったです。ありがとうございます。
また来年もその次の年もやってくる夏の野中祭。
このハッピを着ている人たちがいる風景をみるたびに、きっとこの初お披露目の日のことを私たちは思い出すでしょう。