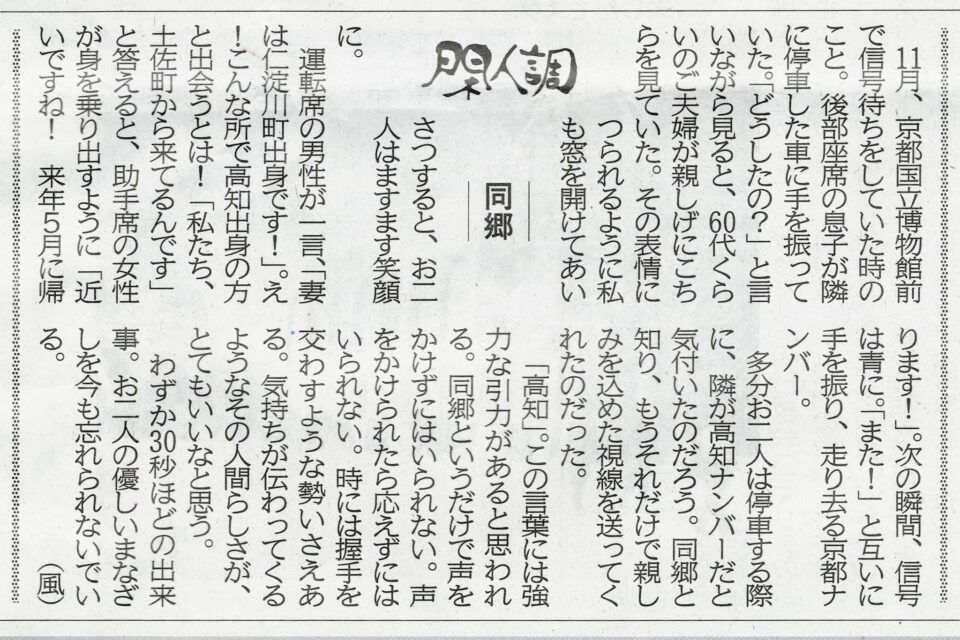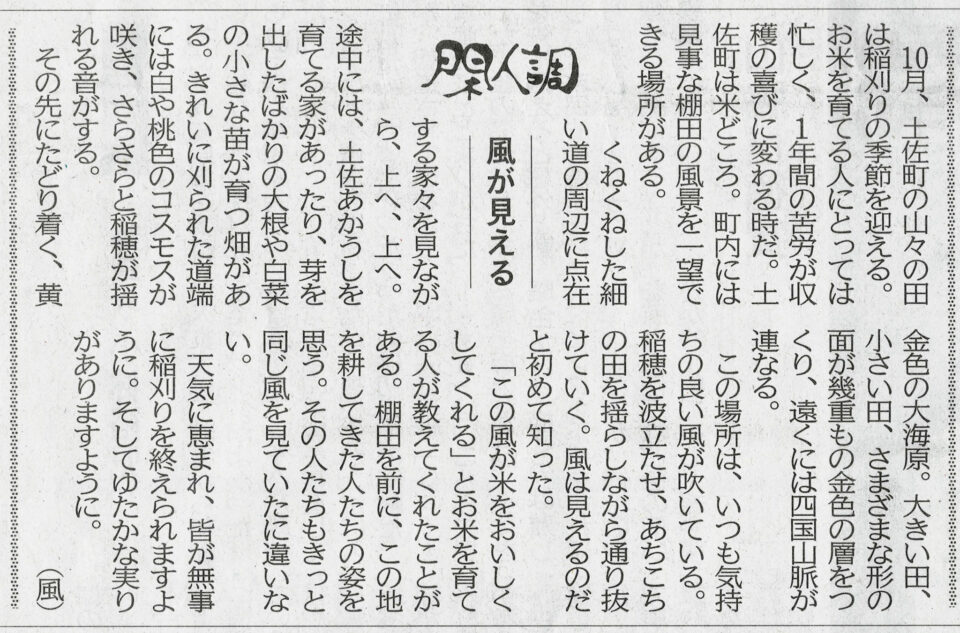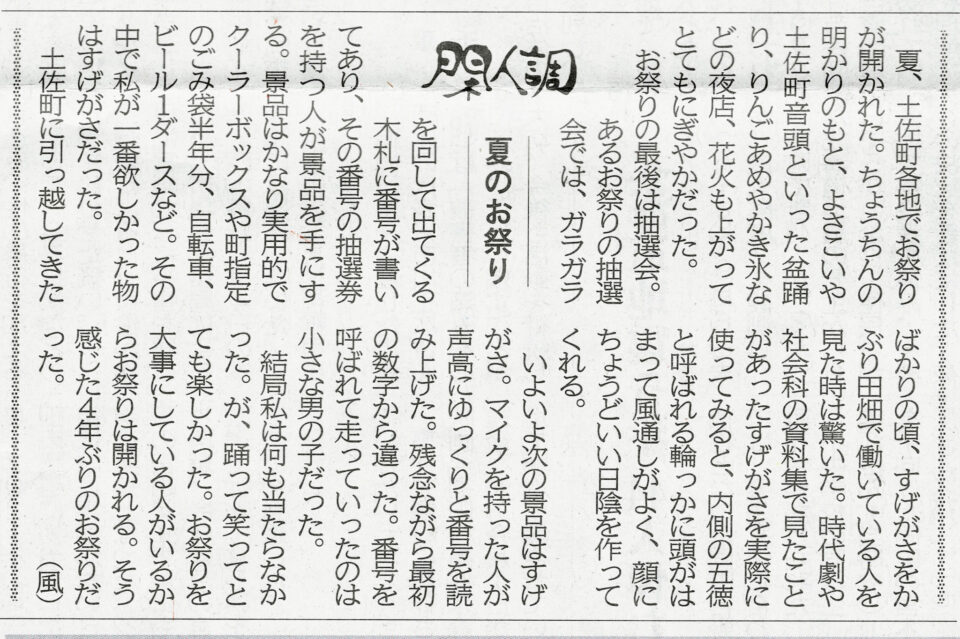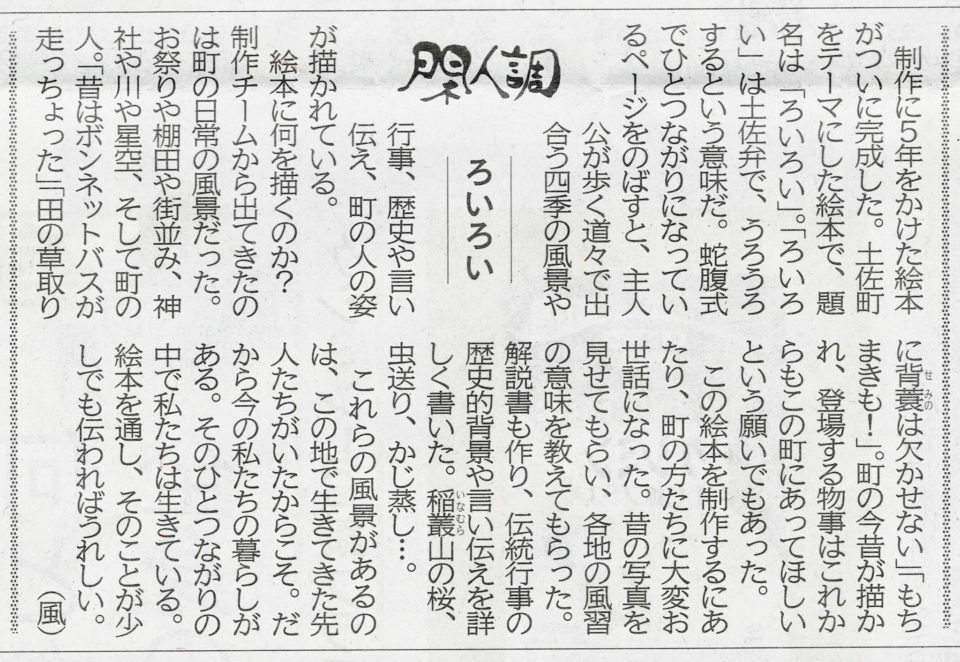寒い冬を越え、枯れた草々の中に芽生えた小さな緑に気づくようになると、土佐町の山々では山菜が顔を出し始める。土佐町は日本で指折りのぜんまいの産地のひとつ。茶色のむくむくとした柔らかい毛を身にまとい、くるりとした頭をゆっくりと持ち上げてあっという間に背筋をピンと伸ばすぜんまいは、この地にようやく春が来たことを告げる。

2年前のこの日、私は伊勢喜さんと一緒にぜんまいをゆであげ、むしろの上にぜんまいを広げる作業をした。
初めて会った長野伊勢喜さんは、昨日も会っていたかのような笑顔で話をしてくれた。
伊勢喜さんは大正14年生まれ、この時92歳。笑った顔がとにかく可愛らしい人だった。小柄な体にしては伊勢喜さんの手は厚くゴツゴツとしていて、それは何十年も仕事を積み重ねて来た人の手だった。
体はあちこちに動き、さっきまでぜんまいを揉んでいたのに、次は干したぜんまいの色が変わったのを見計らってひっくり返している。そして、乾かしてカラカラになったぜんまいの固いところをひねっては手でちぎる。仕事をしている間はとにかくぼんやりとする隙間などはなく、あっちへ行ったりこっちへ行ったり見て回り、必要なところで必要なことをし、ひとつひとつの仕事を確実に重ねていった。不思議ことに、せっせと仕事をしながらも伊勢喜さんはゆったりとした空気を身に纏っているのだった。
「私はね、この家で生まれて小学校6年までしか学校へ行ってないけ。兄弟が大勢おって手がかかるけ、仕事せないかんということでそれからずっとお百姓。二年だけ挺身隊に行ったのよ。学校も出てないけ、どうせお嫁にいけんろうと思ってた」
伊勢喜さんのお子さんたちはこの場所から高校へ自転車で通ったそうだ。土の舗装されていない道で、まともに自転車に乗れるようなところはなかったという。
「牛を引いたり、田んぼをすいたり、人並みの人間じゃないわ。社会を知らんのよ」

山の斜面一面のぜんまいは全部伊勢喜さんが植えたのだそうだ。山に生えていたゼンマイを株ごと掘り起こし、大きな袋にいくつも入れて山から降りる。その重さ40キロ。それを何度も繰り返しては植え、この一面のぜんまい畑をつくった。
「ぜんまいで収入を作ろうと思って植えたのよ。でも歳がいったらいかん、ようせんけ」
座り込んでぜんまいの帽子をせっせと手で退けながら、伊勢喜さんは少し下を向いた。
「帽子を退けたら茹でて、干して、真っ赤になったら機械でもんで、また干して。そしたらきれいにに真っ赤になる。やっぱり経験してこそ。こうしたらこうなる、とか、えいぜんまいになる、とか研究しながらせないかんのよ」

茹で上がったぜんまいはつやつやと深い黄緑色に光り、あたり一面がぜんまいの香りで満ちる。私はこの香りが大好きで伊勢喜さんへ伝えると「匂いなんてするかね?私らはもう慣れたけね」と言うのだった。
それを太陽の光の元へ干すと赤くなる。なんとも不思議な自然の仕組み。山の暮らしには人間の考えなど及ばない営みが日々繰り返されている。
「茹で方がまずかったらぜんまいが黒うなる」、「干して赤くなってから揉まないと色が変になる」、そして「この作業をするのにいい期日というものがある」そうだ。
経験に裏付けされた知恵を山の人たちはその手の中に持っている。
(「四月の晴れた日に その3」に続く)