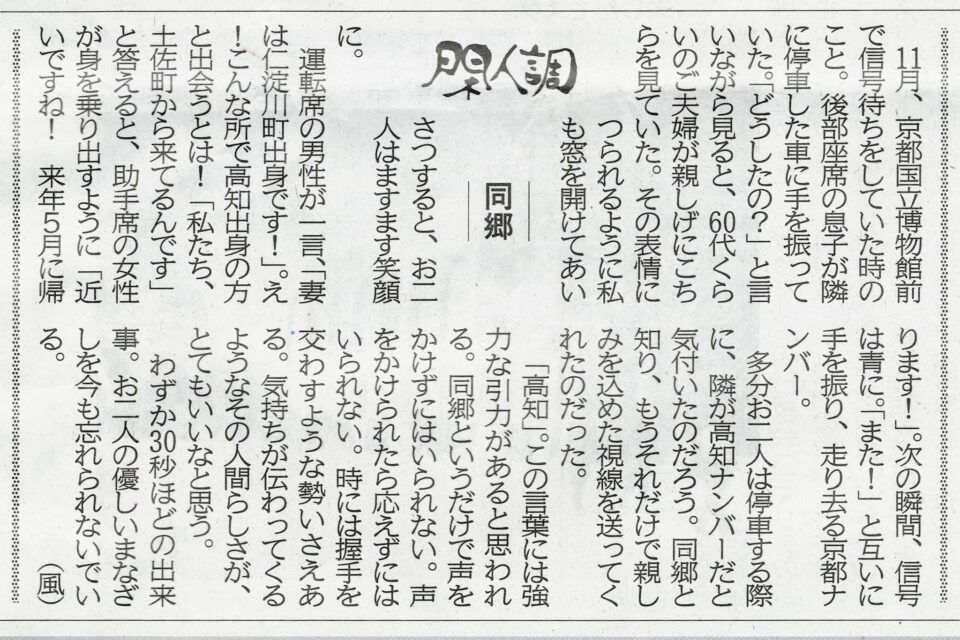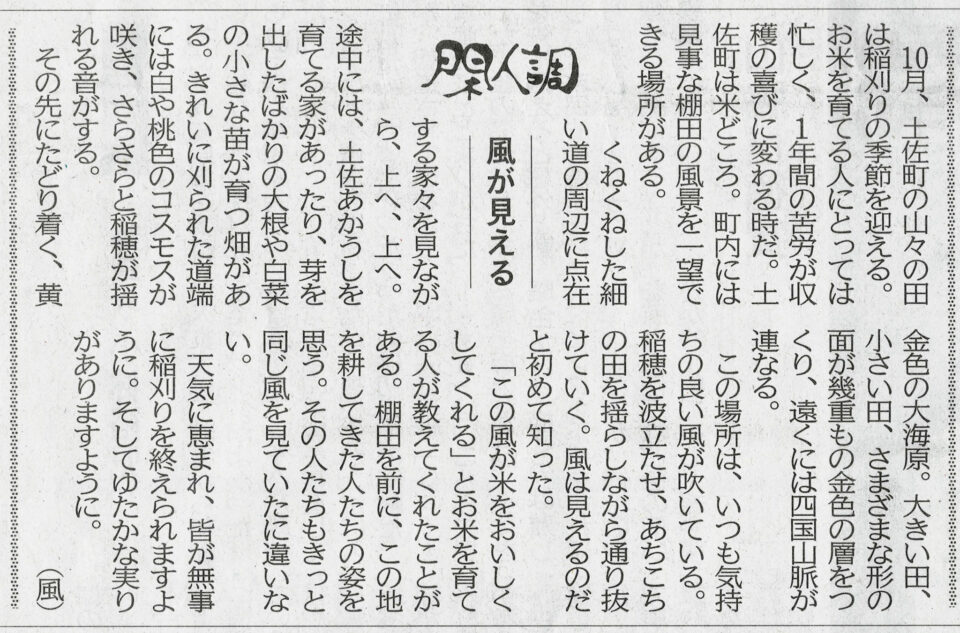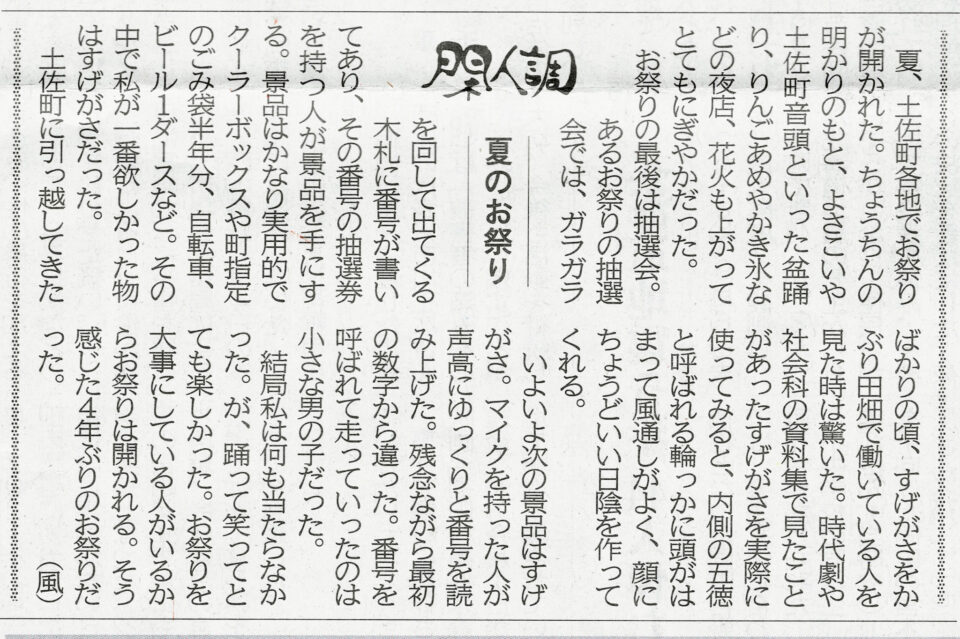(前編)

母屋の横にある大釜から煙が上がり、火が「ごんごん」燃えていた。
摘んできたお茶の葉を大釜で煎る。
「火はよう燃えてなけりゃいかん。荒火でパチパチパチパチッと煎って、それから揉むときれいに青うなる。」
栄己さんはそう言いながら、大きな木べらで上下を返していく。
あたりは香ばしいお茶の香りでいっぱいに。
「この茎がしんなりせんとね。葉だけしんなりしたんでは、乾いた時にお茶が青うにきれいな色にならん。」
パチパチパチパチ
パチパチパチパチ
「焦げたがはね、揉んだら(ざるの)網目の下に落ちるきね。。ほんで、青い葉っぱだけが残る。」

栄己さんは木べらをうちわに持ち替え「ちょうどいい」状態になったお茶の葉をカゴへうつす。それを息子さんの連れ合いさんが干す。

「これは天日で昔からやりよるやり方。昔からこうやってこしらえてたんですよ。こればあ天気がよかったらええ色に仕上がります。」
「私もだいぶベテランさんになったけ(笑)。ここにお嫁に来てから70年ばあになる。毎年毎年、この仕事を続けて今年70回目。まだこればあのことじゃったらお手伝いはできるけ、がんばっちょります。」
栄己さんはそう言って笑うのだった。
お茶は2回揉むのだそうだ。
1回目は息子さんが汗をかきかき揉んでいて、私の摘んだお茶もせっせともんでくれた。それを一度干し、まだ水分が残っているという時を見計らってもう一度揉む。

「力入れてもんでね。まろう(丸く)なるように。自分で揉んでこしらえたんですよ、って持っていかんといかんよ。帰る際まで干しちょいたらえいわ。お母さんがこれをこしらえたんじゃ、と子どもたちに持って帰ってあげなさい。」
「いい香り!」と言うと、「そうでしょう?霧がさすと、やっぱり匂いも美味しさがちがうのよ。」

「これは楽しみにやってみなさいや。」
手渡してくれたのは一掴みほどのお茶の葉。天ぷらにすると美味しいと教えてくれた。その日の夜、天ぷらにしていただくと、じんわりとお茶の味がしてとても美味しかった。
栄己さんは、今朝沸かしたというお茶を飲ませてくれた。
「山からの清水で冷やしたら色が変わらんの。はように冷えたら黄色うてきれいでね、美味しい。さあ、飲みなさい!」

ふと気づくと、山からの水が流れ込んでいるおけに瓶がつけてある。
聞いてみると「柚子をつけちゃあるぞね。清水は地の底から湧いて来る水でしょう?温度が変わらんのでしょうね、冷蔵庫の代わり。夏は手をつけちょっくと寒いようになるぞね。冬はあったこうてね。こうやってたら腐らない。」
「絞ったゆずの皮の油が持ち上がって固まっちゅうきね。柚子を絞ったら、つっと散るろう?あれが油。一回ガーゼでこして小分けにして冷蔵庫に入れちょいたらえい。」
「水炊きをしてこれをかけて食べても美味しい。あそこに木が見えるろう?柚子もね、昔から実生えで生えた木が美味しい。」
この場所で身につけてきた知恵や日々重ねてきた思い…。栄己さんの「70年間」が、栄己さん自身の深い深い引き出しにしまわれている。
栄己さんは、話したいことをその手に握りしめている。
栄己さんは次々と溢れ出してくるなにかを私の前に差し出しているようだった。
「タケノコ食べるかね?ちょうどタケノコを茹でたががここにあるのよね。ここへさらしゆうのがあるけ、おかずに持って行きなさいや。」

「このタケノコは四時間と言わんと炊いてあるよ。あの大きな釜でコトコトコトコト煮て、朝まで煮込んでおいちょいたりするんじゃけ。お鍋で炊いちょいて朝晩温めないかんし、めんどいけど炊いちょいたら結構おかずになる。味噌和えにしたりタケノコご飯にしたりね。」
そう話しながらせっせと袋につめてくれる。もう十分です、と伝えても、もう少しもう少しと入れ続けてくれるのだった。
「なんちゃあおかずもないけんど、ご飯を食べて帰りなさいや。」
もうすっかりお昼ごはんの時間だった。けれどもこの日はもう帰らないといけなかった。そう伝えると一瞬残念そうな顔をし、でもすぐに気を取り直したように言った。
「まあまた上がって来なさいや。もう少ししたらアイリスがいっぱい咲いちゅう。春は花見ができるばあ順々に桜が咲いてね。思い出したら上がって来てください。」
お茶や柚子酢、タケノコ、下の畑から採ったウド…。抱えきれないほどのお土産をいただいた。
帰る時、栄己さんは下の道路まで一緒におりてきてくれた。
車にお土産をつみ、挨拶しようとすると栄己さんが口を開いた。
「あの息子の他にもお姉ちゃんがいてね。あともう一人、私には3人子どもがいたんやけど…。長い人生には色々あるもんね…。」
私はただ頷きながら、栄己さんの話に耳を傾けることしかできなかった。
山からの風がすぐそばの森の木々を静かに揺らした。
私はその場所に栄己さんとふたり、立っていた。
栄己さんと出会い、今一緒にここにいる、という当たりまえのような事実をその時はじめて自覚した。
「また上がってきなさいや!」
栄己さんは私の目を見ながら笑って言った。
車が見えなくなるまで手を振ってくれた栄己さん。
あの山の、あの場所で、今日も栄己さんの暮らしを重ねている。
「また上がってきますね。」
私はそう約束した。
私はまた栄己さんに会いに行く。