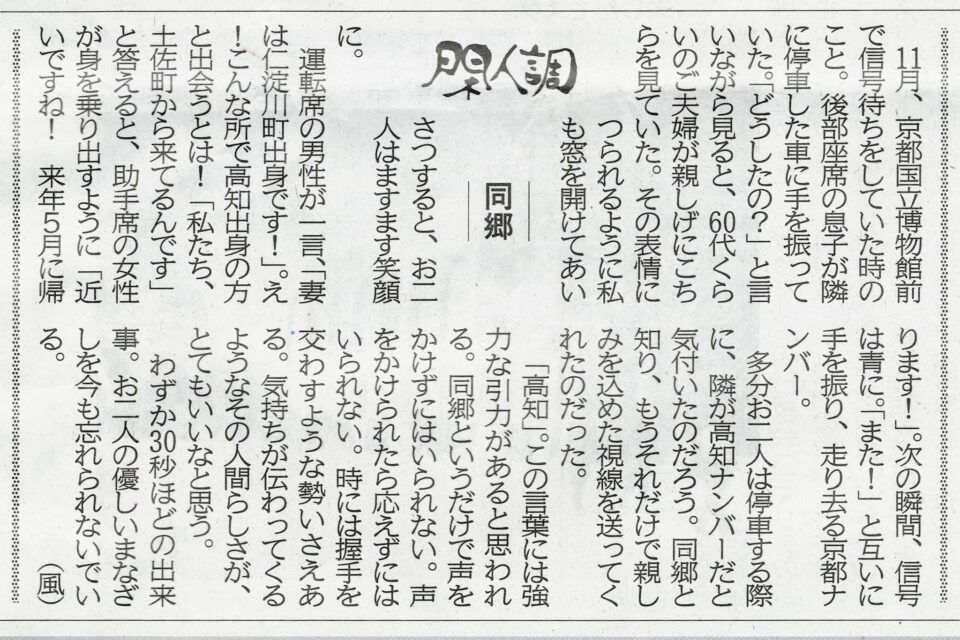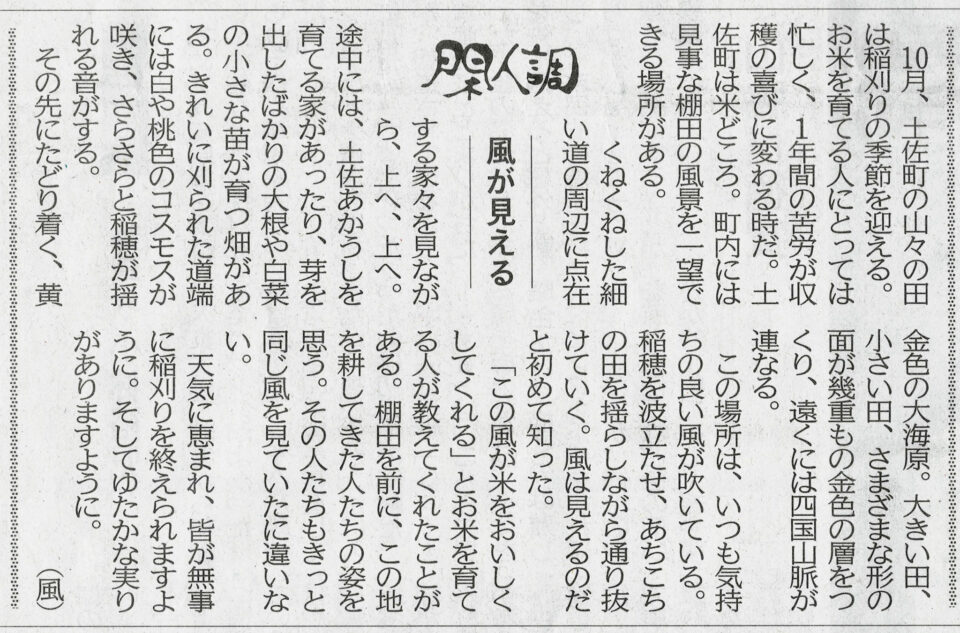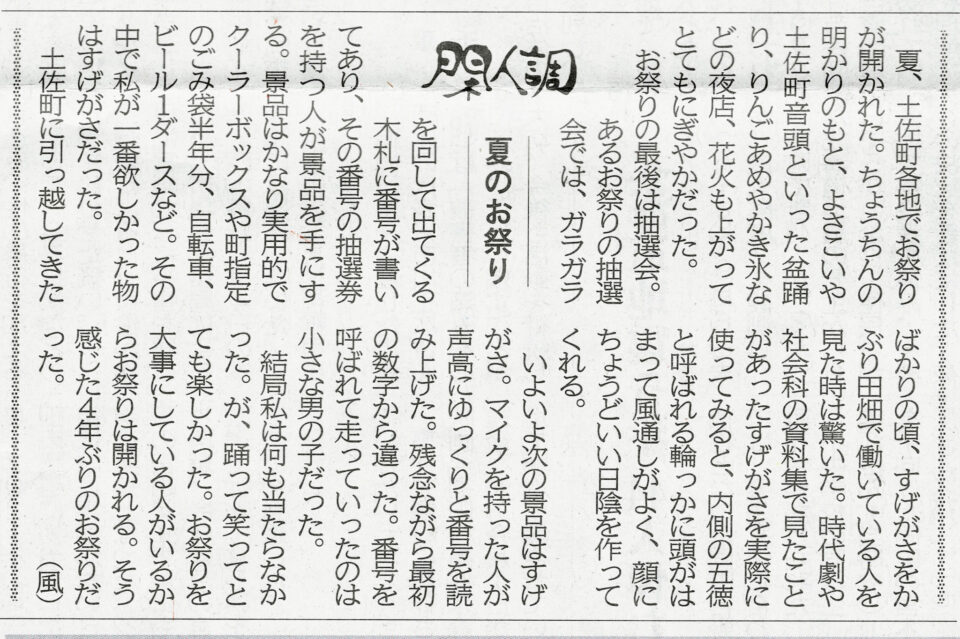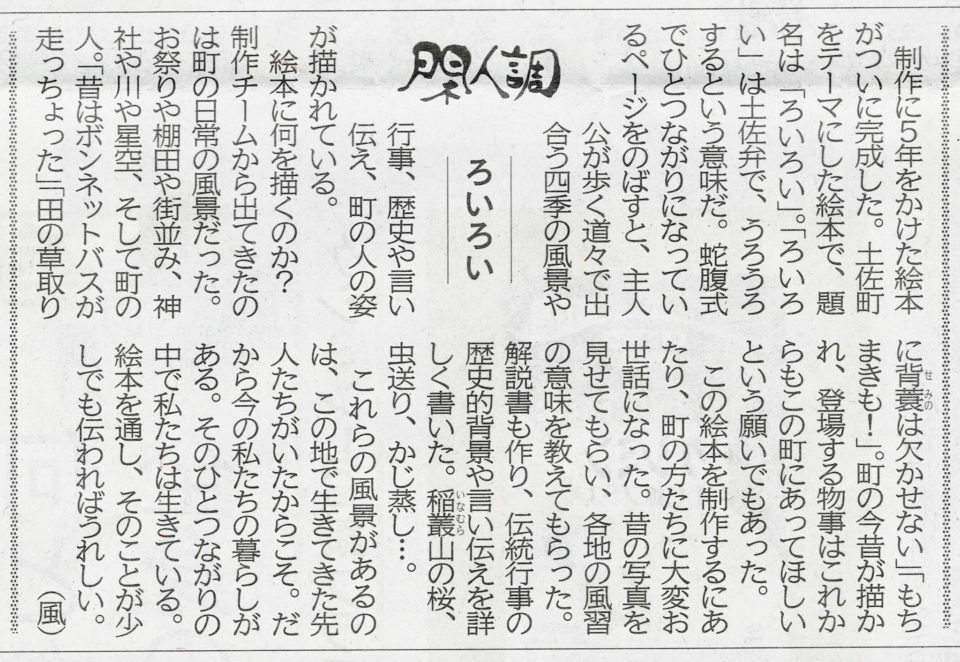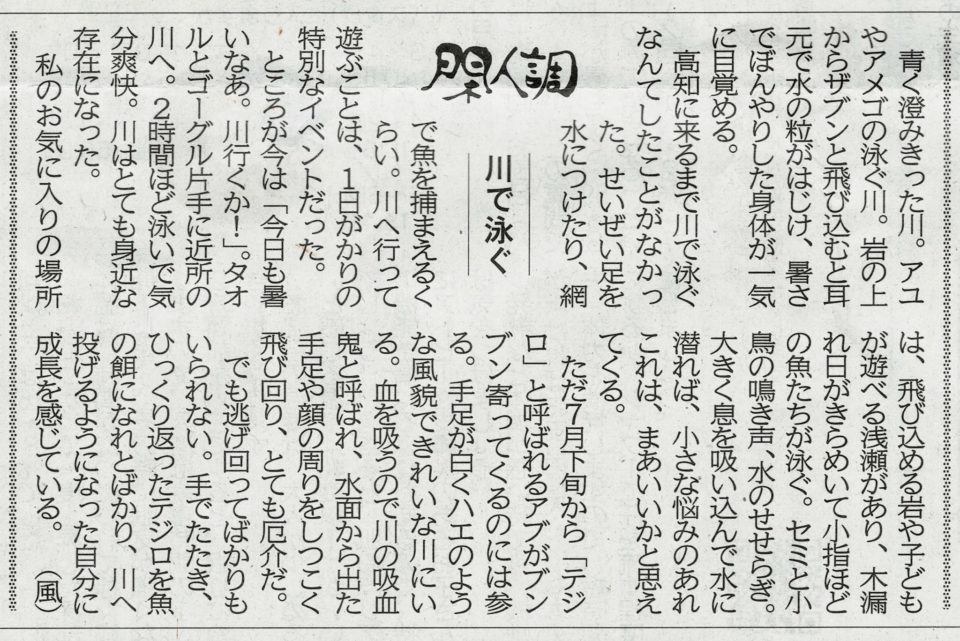薄紅色だった空は刻一刻と色を変えていく。
棚田を目の前に眺めながら友人と話をしているうちに、山の向こうへと太陽が沈んでいった。
墨で色をつけたような山々と、その上にいつのまにかぼんやりと黄金色になっていた空の層を挟み、上空の藍色の空では一番星が輝く。
隣に座っている友人の表情がかろうじてわかる。もうそのくらい、夜を迎えつつある。
向かいの山道を通る車のライトが時々ぴかぴかと光るのが見える。
不思議と目の前に見えている水の張った田んぼは銀色のまま、鏡のように光っている。昼間浴びた光を水の中に蓄えているのだろうか。
山と空が色を変えてゆく夕方と夜の間、人は家にあかりを灯し始める。
ぽつん
ぽつん
ぽつん
山の家にひとつ、またひとつとあかりが灯っていく。
あのあかりのしたに、人の暮らしがある。
私が暮らしている土佐町の相川地区。
私にとって大切なかけがえのない人が住んでいる。

上田覚さん、房子さん。
覚さん82歳。房子さん83歳。私が生きた年月の倍以上を生きている。親しみを込めて上田のおじいちゃん、おばあちゃんと呼んでいる。
おふたりが土佐町のこの場所にいてくれたからこそ、私にとって土佐町での暮らしが真の意味でゆたかでかけがえのないものになっている。
私の家と覚さんと房子さんの家は、直線でいったら200mくらい離れていてちょうど向かい合うように建っている。お互いの家が見えるから、覚さんの軽トラックがとまっているなあ、とか、小屋の軒下に玉ねぎがぶら下がっているからもう収穫が終わったんやなあと毎日何かしら気づくことがある。
多分それはおふたりも一緒で、きっと我が家の方を見ながら、どうしているかなと思ってくれているだろう。

覚さんと房子さんは、田んぼではお米を、畑では季節の野菜を育て、庭にはびわやいちぢく、梅や柚子、栗や梨、柿の木を植えている。
山からはきれいな湧き水が流れてくる。今はもう飲み水としては使っていないそうだが、鯉がいる池にたえまなく流し、収穫した野菜を洗ったりする。房子さん曰く「じびじびと」湧いている水は、冬は湯気が上がるほど温かく、夏は冷たいのだそうだ。「どうしてでしょうね?」と聞いたら「ん?昔からそうよ。」と房子さん。理由なんてきっとないのだろう。自然は全くうまくできている。
外には手作りのかまどがあって、春はたけのこ、秋はさつまいもを茹でる。薪は覚さんが斧で割り、よく乾くようにきれいに積み上げてある。薪は何年分あるだろうと思うくらいたくさんあるけれど、覚さんはいつも秋になると来年の薪を作り始め、その傍で小さな火を炊き木の皮を燃やす。おふたりの田んぼの脇から煙が上がっているのが見えると、覚さんがあそこで仕事をしているんだなとわかる。
家の横にある小屋にはだるまストーブが据え付けてあって、小屋の煙突から煙が上がり始めると「今年もまた冬がやって来たのだ」という実感を運んでくる。そのストーブにあたりにおふたりの友達がやって来て、井戸端会議をしながらしし汁を炊いたりお芋を焼いている。
「食べや」と差し出してくれたお芋を半分にわってみると中は黄金色。ほかほかとあがるゆげまでが美味しそうに見えて、今まで私は一体何本のさつまいもをお腹に収めただろう。