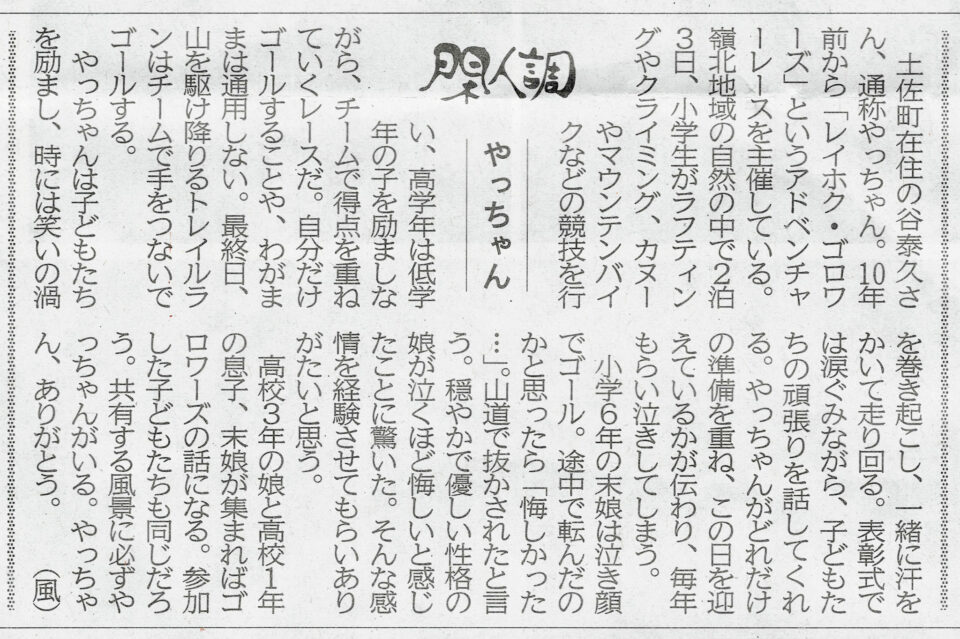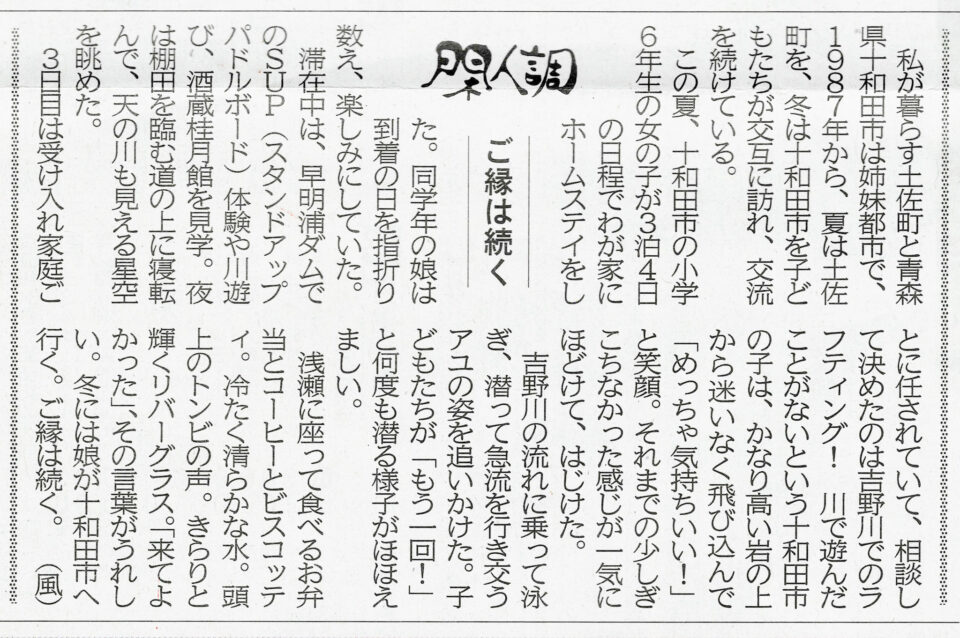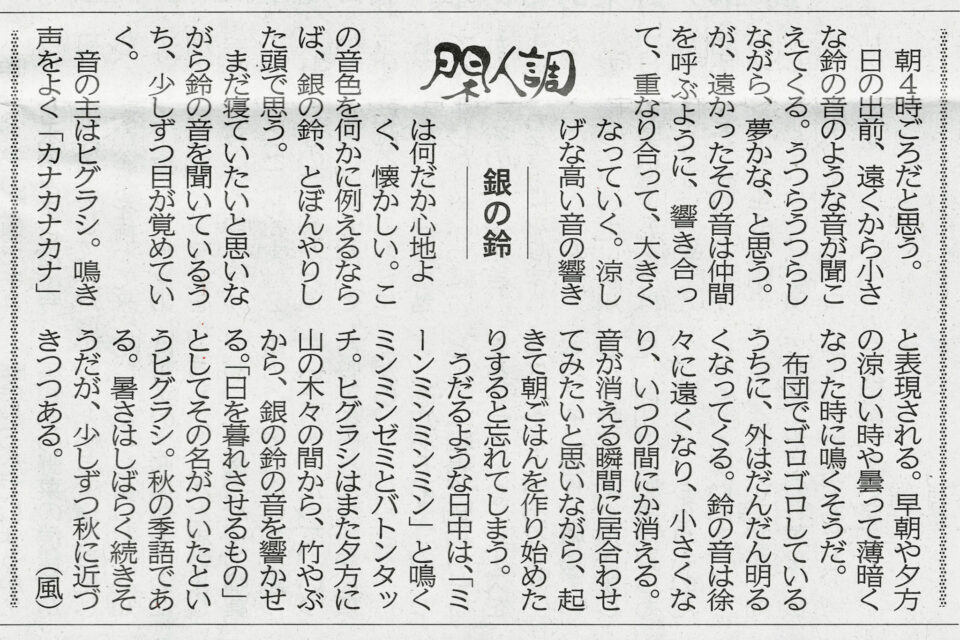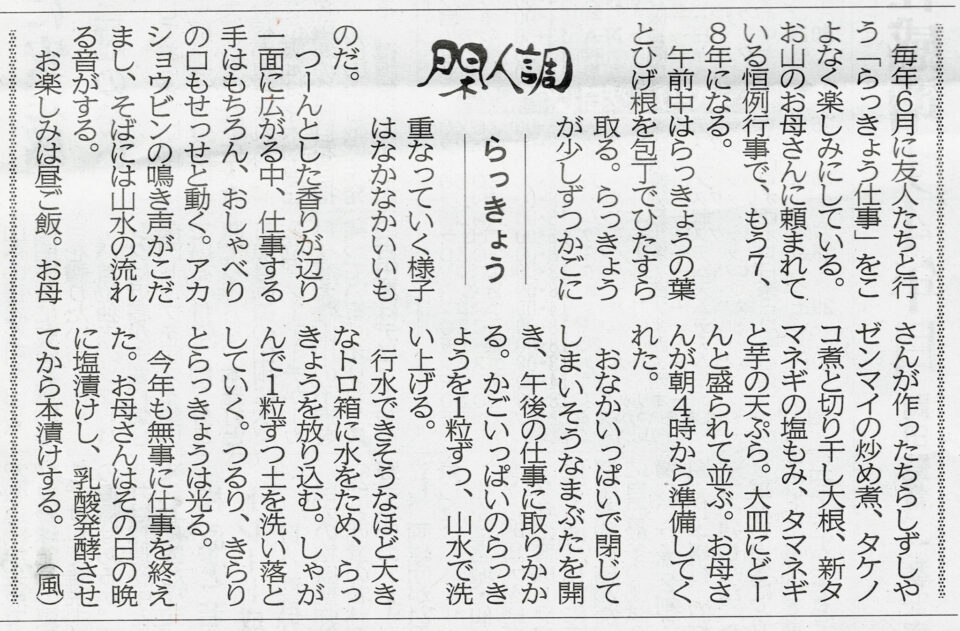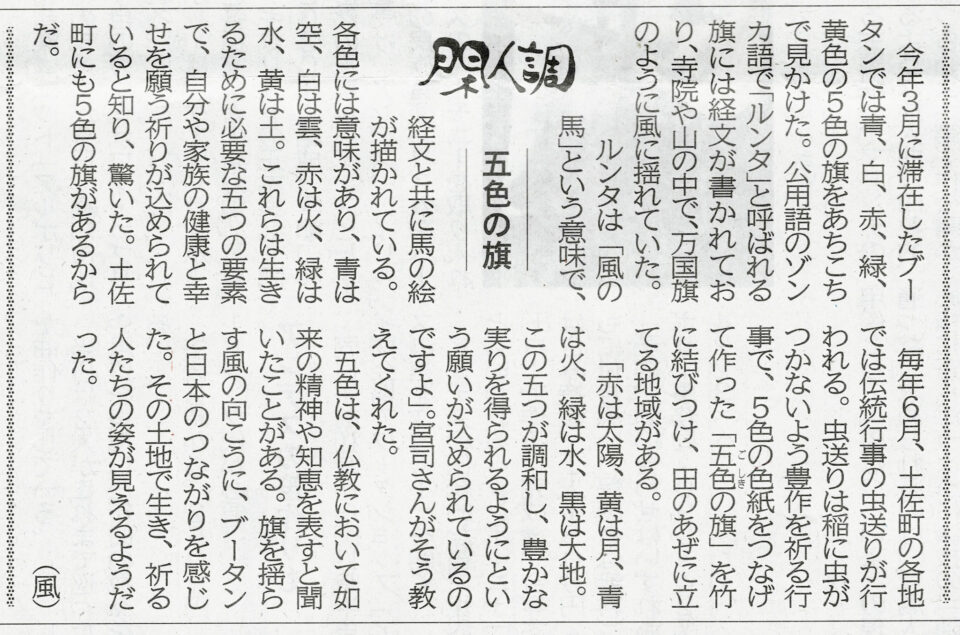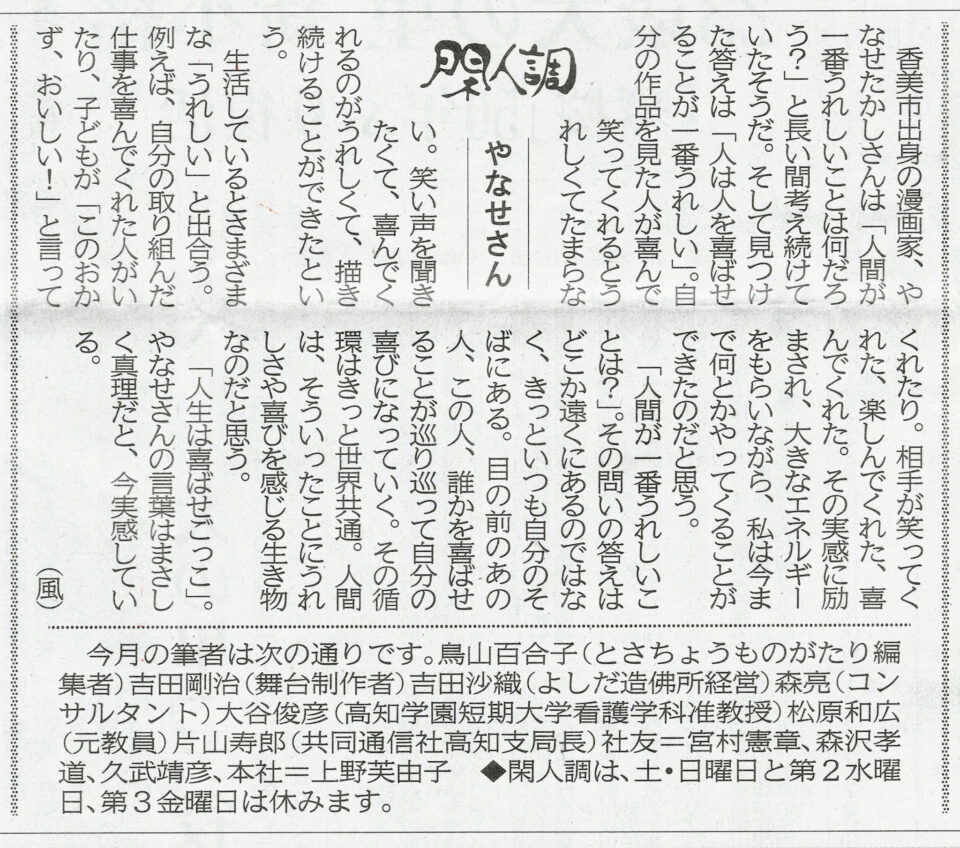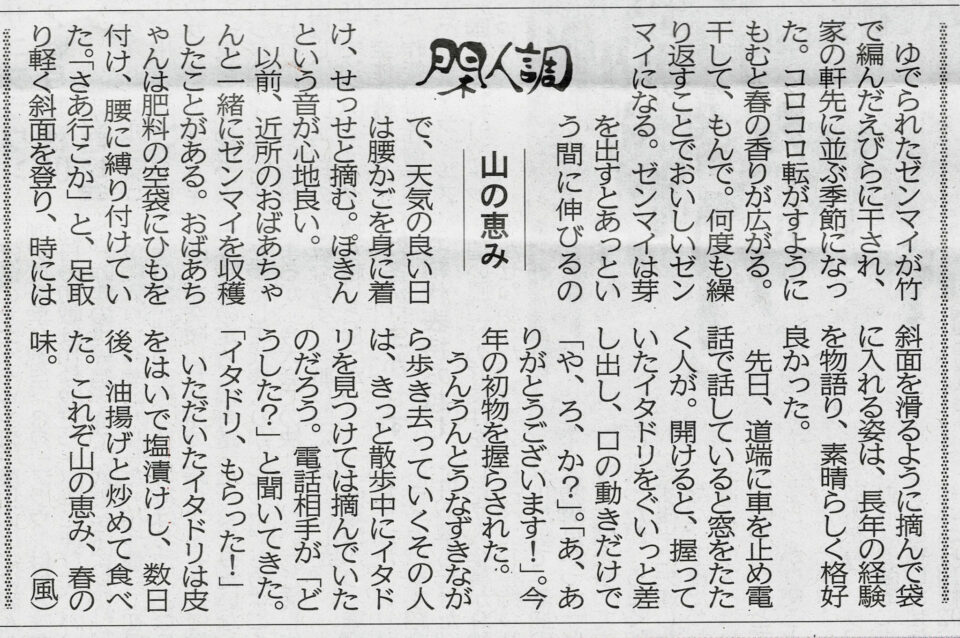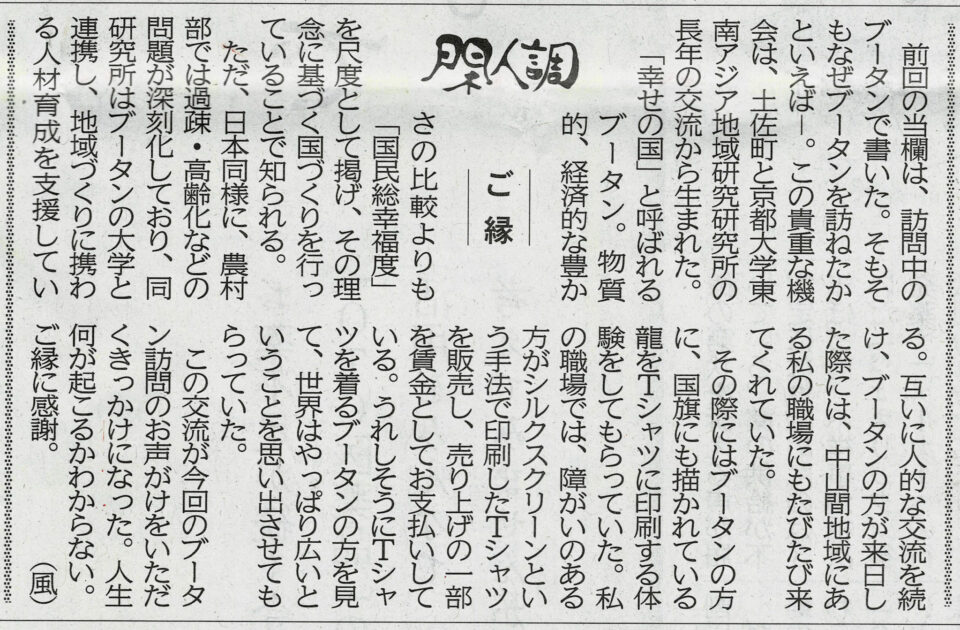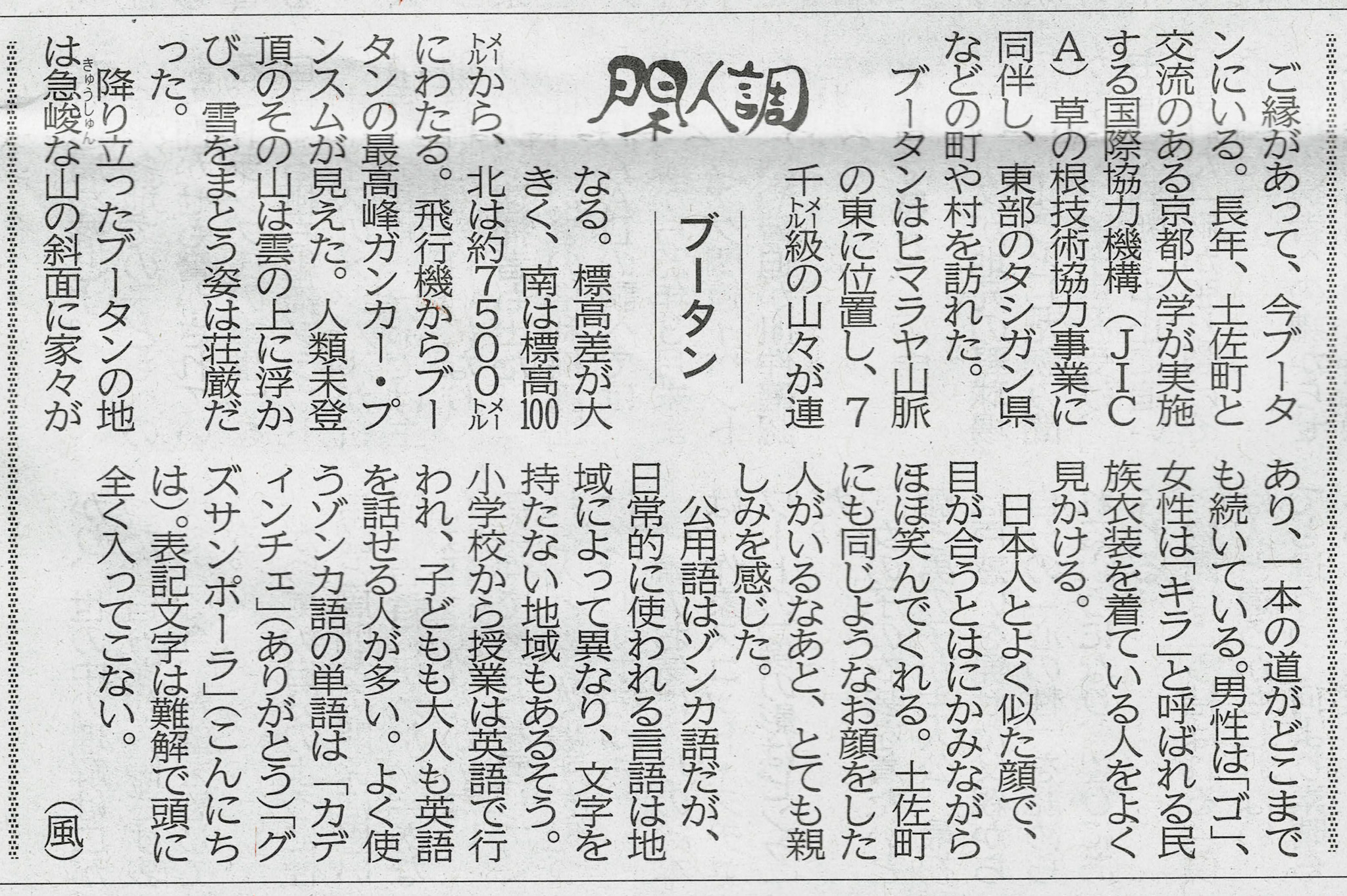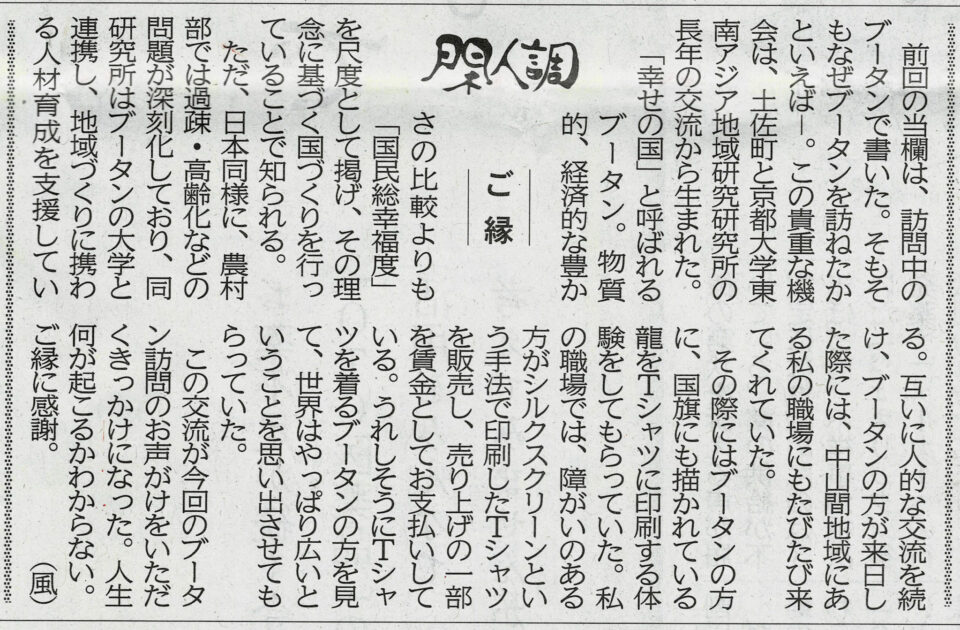
とさちょうものがたり編集部の鳥山が、2023年春より、高知新聞の「閑人調」というコラムに寄稿させていただいています。
このコラムには数人の執筆者がおり、月曜日から土曜日まで毎日掲載。月初めにその月の執筆者の氏名が掲載され、コラム自体には執筆者のペンネームが文章の最後に記されます。
鳥山のペンネームは「風」。月に2回ほど掲載されます。
ご縁
前回の当欄は、訪問中のブータンで書いた。そもそもなぜブータンを訪ねたかといえばー。
この貴重な機会は、土佐町と京都大学東南アジア地域研究研究所の長年の交流から生まれた。
「幸せの国」と呼ばれるブータン。物質的、経済的な豊かさの比較よりも「国民総幸福度」を尺度として掲げ、その理念に基づく国づくりを行なっていることで知られる。
ただ、日本同様に、農村部では過疎・高齢化などの問題が深刻化しており、同研究所はブータンの大学と連携し、地域づくりに携わる人材育成を支援している。互いに人的な交流を続け、ブータンの方が来日した際には、中山間地域にある私の職場にもたびたび来てくれていた。その際にはブータンの方に、国旗にも描かれている龍をTシャツに印刷する体験をしてもらっていた。
私の職場では、障害のある方がシルクスクリーンという手法で印刷したTシャツを販売し、売り上げの一部を賃金としてお支払いしている。うれしそうにTシャツを着るブータンの方を見て、世界はやっぱり広いということを思い出させてもらっていた。
この交流が今回のブータン訪問のお声がけをいただくきっかけになった。人生何が起こるかわからない。ご縁に感謝。
(風)
2024年3月29日の高知新聞に掲載されたコラム「閑人調」です。
前回に引き続き、ブータンについて。今回は、ブータンに行くことになったきっかけを書きました。
3月1日〜12日のブータン滞在中、以前土佐町でお会いした方に何人も再会しました。保健省の役人さんや大学の先生、京都大学が主催するJICA(国際協力機構)草の根技術協力事業に関わる現地の職員さん…。日本滞在中に編集部に来てくれて、シルクスクリーン体験をしてくれた人たちです。「また会えてうれしい!」と握手を交わせることは、本当に素晴らしいことです。
「(シルクスクリーンで印刷した)龍のTシャツ、今も着てるよ!」と話してくれる人も。
滞在中、私にもっと語学力があれば…と思うことも多々あり、英語は勉強し続けるべきと痛感しました。
ブータンの方が初めて土佐町に来たのは2011年だったと聞いています。土佐町とブータンのつながりが生まれたきっかけなどなど、ブータン滞在記として、これから書いていこうと思っています。
*前回の「閑人調」はこちら
高知新聞 閑人調 17
*国民総幸福度(GNH)による国の運営を進めているブータン。2019年、土佐町で幸福度調査を行うにあたり、ブータンの現状を学ぶため、とさちょうものがたり編集長の石川がブータンを訪れています。
【番外編】ブータン・GNHレポート No.5