
しゃんしゃんいね
【意味】さっさと帰りなさい
例文:熊猫(パンダ)が熊を「しゃんしゃんいね!」と追い払いゆう。
意味:パンダが熊を「さっさと帰りなさい!」と追っ払っている。
著者名
記事タイトル
掲載開始日
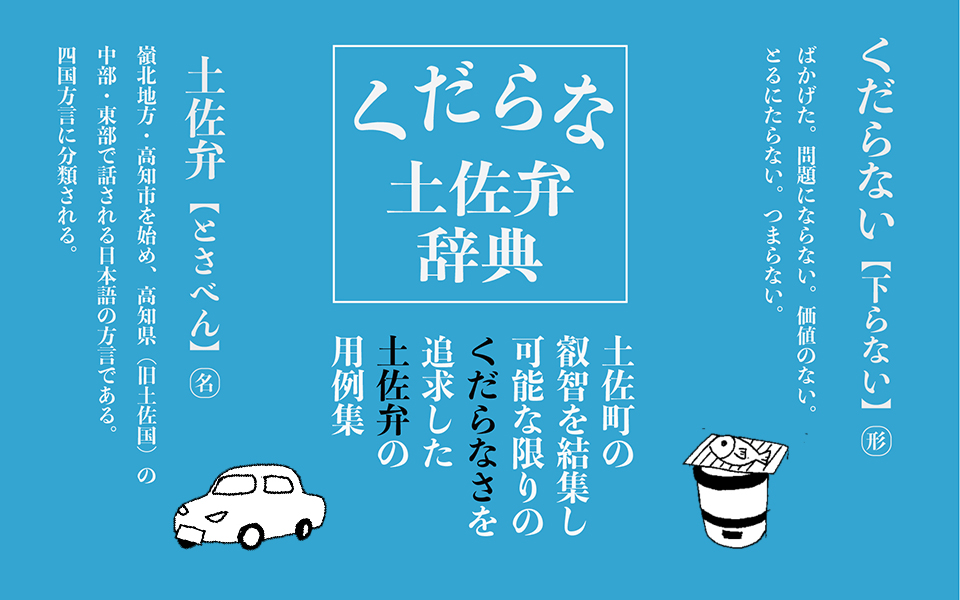
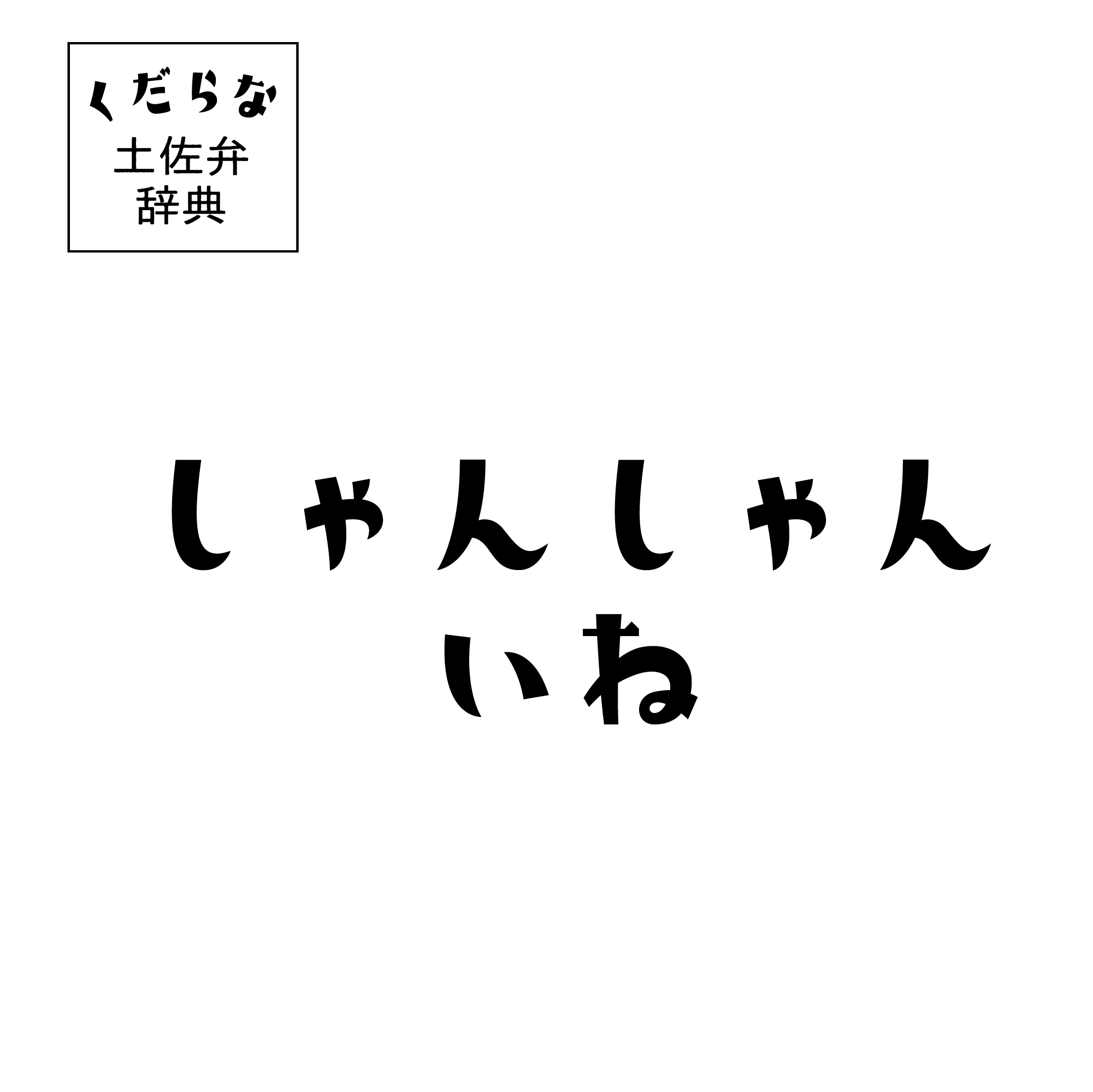


私はカカヤンに似て背が低かったので、学校では前から二番目でしたが、元気で子守やお使いと走り回っていました。
でも学校に行くようになってから、時々喉が痛くなって、左の耳の後が少し腫れて痛くなり、カカヤンに「アンマコウ」を、貼ってもらいました。
学校では皆におこつられ(からかわれ)たが、三日位で治って、「アンマコウ」は、はいだ跡が黒く残って又々笑われました。
服む薬があったら笑われんのにと思っていたら、オトッチャンが石山の粘土で小さな壺を作ってきて、梅干しを五つ位入れて、囲炉裏の隅で焼いて、梅を黒焦げにして粉にして「服んだら、治る。扁桃腺ぢゃけ」。
その通りにしたら本当に良くなりました。誰かに聞いたんだと思いました。
それからも時々痛くて、黒い苦い薬を飲んで治りました。「アンマコウ」もいらなくなりました。
昔の人の知恵ですネ。現在と違って、知恵と経験だと思います。現在もセンブリ、オオバコ、切り傷にはヨモギの汁とか、お世話になりました。


マメ科ネムノキ属の高木です。
大きくなると独特の枝ぶりになって夏にはもってこいの緑陰を作ります。
「この木なんの木 気になる木 名前も知らない 木ですから ~」
こんな歌詞が流れ、大きな傘のような枝を広げた木が出てくるテレビのCMを見たことはありませんか。ハワイ・オアフ島の公園にあるモンキーポッド(別名アメリカネムノキ)という木です。20年ほど前に実物を見たことがあるのですが、樹高は20mを超え、幅が40mほどもある大樹です。ネムノキとは比較にならない大きさですが、同じネムノキ属で花や葉は見間違うほど似ています。
ネムノキは落葉樹で日本をはじめ中国大陸や東南アジアに分布し、モンキーポッドは熱帯アメリカ原産の常緑樹です。

ネムノキは河原にも山地にも生え、夏になると枝先にピンクの花を咲かせます。
夕方咲いて、あくる日の昼には傷(いた)んでしまう一日花だということなのですが、昼間の暑い日差しの中でも花が見られないようなことはありません。
一つの花序に30~40個もの花が付き、その内の数個は常に咲いているような感じでふわふわしたオシベが目立ちます。

深い緑をバックにすると紅色がさらに濃く、鮮やかです。

ネムノキの葉は鳥の羽根のような形をしています。
この写真の中央にある葉は小葉が1片欠けていますが、10対の小葉をもつネムノキです。これで1枚です。2回偶数羽状複葉と呼びます。
「複葉(ふくよう)」はサクラやアジサイのような単葉とは異なる、「羽状(うじょう)」は鳥の羽根のような、「偶数(ぐうすう)」は最頂部の小葉が対になっている、「2回」は小葉もそれぞれの再頂部が対になっているということを表します。

葉は、暗くなると左右の小葉がくっついて両手のひらを閉じたようになります。その姿からネムノキは夜になると眠る木で、「眠りの木」が転じてネムノキという名前になったと云われます。
昼間は葉を広げて光合成を行い、夜間は葉を閉じて水分の蒸発を抑えるようですが、昼でも強烈な高温や直射日光に晒されるときには葉を閉じてしまいます。
採集した葉を花瓶に挿して暗い場所へ置いてみたところ、あっという間に葉を閉じました。樹上のままなら葉は垂れ、小葉同士もくっついてしまう様です。
ネムノキの中国植物名は合歓(ごうかん)。これは夜になると左右の小葉が重なり合って閉じるので、歓びが合わされるのでめでたい木という意味です。中国では夫婦円満の象徴とされているそうです。日本では漢字で合歓木と書き、「こうかぎ」と読んだりもします。

ネムノキの樹下には花がたくさん落ちます。
林内や草地ではほとんど気が付きませんが、道路の上に樹冠がある様な場所では面白い光景が見られます。
土佐町地蔵寺から和田に向かう奥山の道路のアスファルト舗装の上にネムノキの花が散らばっていました。結実が心配されるほどの数ですが、不思議なことに、豆果は秋になるとちゃんとぶら下がります。
実際のところは分からないのですが、「結実数を自ら調整しているかもしれない」という説があります。


朝から雨が降ったり止んだりが続き、いつもより少し涼しく感じられた日のことだった。
7月中旬、稲が青々と育つ田の中で黙々と仕事をしている人がいた。つばの広い帽子をかぶり、手袋とアームカーバーを身につけ、長袖長ズボンを履き、足元は長靴。手にくわを持ち、背中には背みのをつけていた。
青い稲の中を潜るように、這うように、頭を低くしながら少しずつ移動している。しばらくその体勢は続き、やっと体を起こした時、お腹のところに草の束を抱えているのが見えた。そして長靴の足元を持ち上げるように、一歩ずつ、一歩ずつ、田の端まで歩いて行き、どさっと束を投げた。そして、またゆっくりと、さっき手を止めた場所まで戻っていく。畦にはいくつもの束が投げ置かれていた。
稲の高さは約50センチくらい。よくよく見ると、稲とは別の、同じくらいの背丈の草がところどころに生えていた。この草を抜くために、稲の海に潜りながら広い田の泥の中を移動していたのだ。泥は重い。ずしりとした一歩がいつまでも続くような、とてもしんどい作業だ。沈めた顔には稲の葉の先が当たり、相当ちくちくすると思う。
こうやって人は稲を育て、お米を作り続けてきた。何百年も前から続けられてきた営みの一片を垣間見た思いだった。
これは夕方5時くらいのこと。暑くうだるような日が続く中、この人は少しでも涼しい時を選んで仕事をしているのだろうなと思った。
お米づくりは植えて終わりではない。草取りや日々の水の管理、台風が来れば気を揉み、危険を承知で田は大丈夫かと見にいく人がいる。目配り気配りの積み重ねがあってこそ、お米は成長する。
私は自分でお米を作る知識も経験もない。育てる人の姿を近くでただ見ているだけで偉そうなことは言えないのだが、今、マイクを持って声高に叫んでいる政治家の人たちに、お米を作っている方々の姿を少しでも知ってほしいと思う。真夏の夕方に腰をかがめ、田の草を一本ずつ抜き取っている人がいること。常に田の様子に気を配り、その時必要な仕事を熟知し、行動している人たちがいるからこそ、秋にお米が収穫できる。その過程にどれだけの汗が流されているか。そのことを少しでもいいからどうか分かってほしい。そう切に願う。

「山岳紀行」とは名ばかりになっているこの連載。今回も散歩道の紹介です。
散歩道といっても、川の散歩。7月のある日曜日、あまりにも暑いので、近くにある地蔵寺川で涼むべく行ってきました。
今回の場所はこちら。
国道439号沿い、森地区ヘリポートが目印です。

奥がヘリポート。ヘリポートの横を降りれるように道があります。

降りていくと先に川が見えます

この場所は川まで降りやすいのが特徴です

先客の家族が川遊びをしていました

川の水はこんな感じ。土佐町の年配の方々は、「昔の方が水がきれいやった」と口を揃えて言いますが、それでもこの透明度はすごいと個人的には思います。
この季節、水温も「ちょっと冷たい」くらいで本当に気持ちいい。

水の中はこんな感じ。

石の上に載っているのはうちの犬です。まだ水を怖がるので、川に連れてきて水に浸けても、一目散に岩場に避難します。
夏の川水の気持ちよさをいつか理解できる日が来るのでしょうか。
土佐町はこういった場所があちこちに存在するので、暑い日に体がオーバーヒートしていると感じたら、いったん仕事を脇に置いて川に飛び込んでくる、なんてこともふつうにできます。
私は千葉県育ちですが、時代のせいもあり川で泳ぐなんてことが考えられないくらい、近所の川は汚染されていました。
夏になる→暑くなる→川で泳ぐ→涼しい という自然なことが自然にできるという環境が、ことさら豊かに感じます。

図書館司書としてかれこれ25年ほど働いてきた。司書こそ天職だと思っているが、この職に至るまでには公務員、タウン誌の編集者、映画館のもぎりなど様々な仕事についてきた。その中で7年ほど経験した作家秘書は、ちょっと珍しい職歴かもしれない。
作家氷室冴子さんとは、講演会講師として高知にお招きしたことがきっかけで親しくなった。ある日「ファンレターのあて名書きのアルバイトをしない?」と持ち掛けられ、高知にいても間に合う仕事を手伝うようになった。ほどなくして出版社からの原稿やインタビュー依頼の返答、スケジュール調整もアルバイト業務に含まれるようになり、気がつけば“遠隔地秘書”に格上げ(?)されていた。
遠隔地秘書時代のメインの仕事はなんといっても、高知を舞台とした青春小説「海がきこえる」に関わるものだった。月刊誌に連載するにあたっての下準備やロケハンの同行。連載が始まれば標準語で話す主人公たちの会話を土佐弁に変換して送り返した。まだパソコンやメールは普及しておらず、FAXで送信されてくる原稿を正座して待っていたのは懐かしい思い出だ。

「海がきこえる」を書き始める時、この作品では主人公たちの思いを具体的な言葉ではなく、情景を積み上げていくことで表現してみようと思っているんだ、と言っていた氷室さん。人気作家としての実績に甘んじず、作品ごとにクリアするテーマを自分に課し、表現の幅を広げ、多様な文体を獲得しようと挑戦する姿に「ああ、この人は本当に作家なのだ」と思ったことだった。
約2年にわたって連載された物語が単行本としてまとめられる頃には、上京して身近に仕事をするようになっていた。小説『海がきこえる』は幅広い層から支持を得たこと、また担当編集者の尽力もあり、テレビアニメーションやドラマ化された。そのテレビアニメーション版がこの夏、32年ぶりに全国でリバイバル上映されることになった。テレビアニメーションは氷室さんや編集者たちと一緒に見たのだが、その時はあれこれほか事に気を取られ、作品をゆっくり楽しむ余裕はなかった。今回は何のしがらみもなく鑑賞したのだが、作品世界に浸って楽しむ余裕は、やはりなかった。高知の風景をバックに話す拓や里伽子の声を聴きながら、氷室さんのことが次から次へと思い出された。どうしてここに氷室さんがいないのだろう、いないなんて間違っている、とそんなことを思っているうちに上映が終わっていた。
亡くなってから17年も経てば氷室さんの小説は書店の店頭には並ばず、図書館では書庫にしまわれているかもしれない。けれども氷室冴子の小説はどの時代の人が読んでも腑に落ち納得する、普遍的な世界を描き出しており、決して古びることのない作品だと思う。今回のリバイバル上映がきっかけとなり、氷室冴子の小説やエッセイを手に取る読者が増えることを願ってやまない。