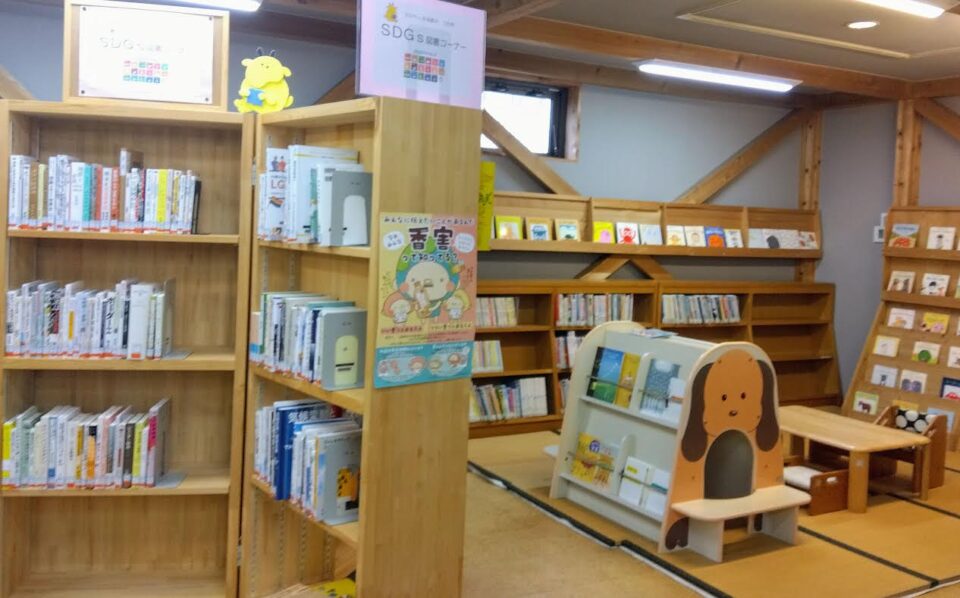アカネ科ヘクソカヅラ属。
暑い時期が大好きなつる性の多年草です。ほかの樹や草やフェンスなどに絡まって長く伸び、8月の灼けつくような日差しの下でも元気よく花を咲かせています。
それにしても、屁糞葛・屁臭葛とは…
何とも可哀そうな和名が付けられたものです。
花実や茎葉を切ると悪臭を放つことに由来しています。
奈良時代にはクソカズラ(屎葛)と呼ばれ、万葉集にも登場しているそうです。
英名はスカンク・ヴァイン(スカンク臭がする蔓という意味)。中国では鶏屎藤(けいしとう)と呼ばれ、鶏のふん尿を連想させる名前になっています。
物は試しと、葉と花をちぎって揉んでみました。
強烈な臭いを覚悟していたのですが、意外にも、予想したほど酷くはない独特の青臭さです。

葉は対生します。
釣鐘状の花は長さが1㎝ほどです。花冠の先は浅く5裂して開き、白い花びらの縁は優雅に波打ちます。
この特徴的な花の姿からつけられた別名があります。
その一つはサオトメバナ(早乙女花)。
花を水に浮かべた姿を早乙女のかぶる笠に見立てたというロマンチックな名前です。

もう一つはヤイトバナ(灸花)。
花の真ん中の赤い部分がヤイト(お灸)をすえた痕に似るというのがその由来です。
また、赤紫色の部分には産毛のような白い毛が密生していて、この毛をお灸に使うもぐさに見立てて付けられた名前だとも云われています。
さてこの花に一番似合っているのはどの名でしょうか…。
盛夏の野山ではヘクソカズラ以外にも目立つつる性の花があります。
キンポウゲ科のボタンヅル(牡丹蔓)とヤマノイモ科のオニドコロ(鬼野老)は、土佐町土居辺りを散歩しているとどこにでも咲いています。

ボタンヅル
ボタンヅルは白くて長いオシベが特徴です。
果実になっても花柱が白い羽毛状になります。

オニドコロ
オニドコロはヤマノイモに似ています。
簡単な見分け方は葉のつき方で、ヤマノイモが対生するのに対しオニドコロは互生です。

エゴノキ
暑いさなかに涼しげな白い実を枝いっぱいにぶら下げた木もあります。
落葉樹のエゴノキです。
5~6月に咲く花も、この時期の果実も独特の美しさがあり、庭木としてもよく利用されます。
どういう訳か今年は目にする機会が多いような気がします。
写真は土佐町井尻の県道沿いで撮影したものです。3mほどの樹高で枝を広げ、道路待避所に日陰を作っています。
7月頃の実は緑色ですが、徐々に白くなり、10月ころ茶色くなって熟し、果皮が裂けて種子が落下します。
今の時期、果実としては一番見応えのある灰白色です。