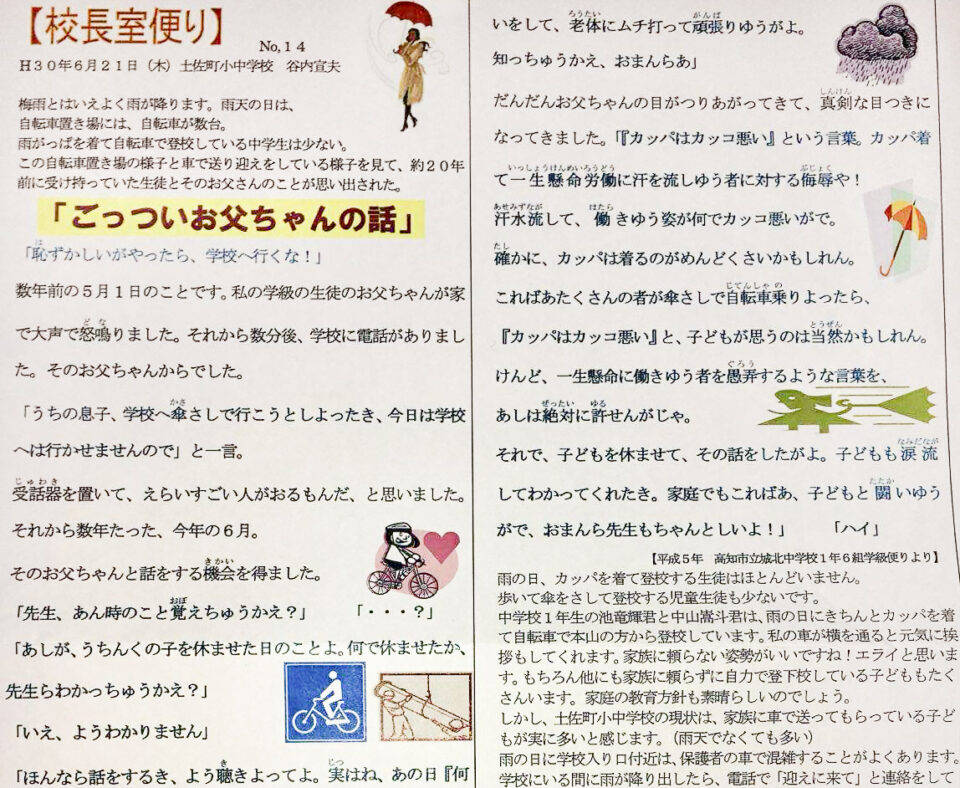
【校長室便り】平成30年6月21日 土佐町小中学校 谷内宣夫
「恥ずかしいがやったら、学校へ行くな!」
私の学級の生徒のお父ちゃんが家で大声で怒鳴りました。それから数分後、学校に電話がありました。そのお父ちゃんからでした。
「うちの息子、学校へ傘さしで行こうとしよったき、今日は学校へは行かせませんので」と一言。
受話器を置いて、えらいすごい人がおるもんだ、と思いました。
それから数年たった、今年の6月。そのお父ちゃんと話をする機会を得ました。
「先生、あん時のこと覚えちゅうかえ?あしが、うちんくの子を休ませた日のことよ。なんで休ませたか、先生らわかっちゅうかえ?」
「いえ、ようわかりません。」
「ほんなら話をするき、よう聴きよってよ。実はね、あの日「何でカッパを着て行かんのか」と、子どもに聞いたがよ。そしたら、うちの子「カッパはカッコ悪い」とひとこと言うたがよ。あしは、その言葉に腹が立って、「恥ずかしいがやったら学校行くな」と怒ったがよ。「カッパが恥ずかしい」という言葉が許せんかったがよ。何で許せんか、わかるかえ?」
「いいえ…」
「先生、そんなこともわからんかえ。先生らあカッパ着て一日中仕事したことあるかえ?梅雨時にカッパ着て仕事しゆう者のしんどさがわかるかえ?朝から晩までカッパ着て仕事しゆう者の思いがわかるかえ?実は、あしんくの息子のカッパは、おばあちゃんが息子のために買ってくれたものよ。おばあちゃんは、雨の日は朝から晩までカッパ着て、しんどい思いをして、老体にムチ打って頑張りゆうがよ。知っちゅうかえ、おまんらぁ」
だんだんお父ちゃんの目がつりあがってきて、真剣な目つきになってきました。
「「カッパはカッコ悪い」という言葉。カッパ着て一生懸命労働に汗を流しゆう者に対する侮辱や!汗水流して、働きゆう姿がなんでカッコ悪いがで。確かに、カッパは着るのがめんどくさいかもしれん。こればぁ(これくらい)たくさんの者が傘さしで自転車乗りよったら、「カッパはカッコ悪い」と、子どもが思うのは当然かもしれん。けんど、一生懸命に働きゆう者を愚弄するような言葉を、あしは絶対に許せんがじゃ。それで、子どもを休ませて、その話をしたがよ。子どもも涙流してわかってくれたき。家庭でもこればぁ、子どもとたたかいゆうがで、おまんら先生もちゃんとしいよ!」
「はい」 ”
いつの時代の話だろう、と思った読者もいるに違いない。実はこの話、今年18年振りに校長として土佐町小中学校に戻っていらした先生が、梅雨のある日の校長室便りで紹介したものだ。雨のなか、自転車登校を許されている中学生のほとんどが車で送り迎えされている姿を見て、約20年前に同じ土佐町中の同僚から聞いたこの話を、思い出さずにはいられなかったのだという。
このエピソードの後には、家で子どもを過保護に育てないように、そして「危険なほどのどしゃ降りでない限り、カッパを着て自転車で登校させるか、歩いて登校させるべき」との校長先生の考えがはっきりと綴られていた。「子どもに不自由な環境をあえてつくったり、与えなければ、自分で考え最善の方法を導き出して実行しようとする態度や意識も育ちにくくなります。家族がやってくれるのが当たり前になれば、感謝する気持ちも育ちにくくなります。」
数日後、僕は校長先生と話す機会があった。家庭が従来の教育機能を失っているのでは、という彼の危機感が伝わってきた。ある親から、学校に1本の電話がかかってきたそうだ。その親は、子どもが家でゲームをしないように、学校の方で指導してくれと息子の学級担任に言った。どうしたら良いものか、とその教員に相談された校長の反応は明快だった。
「次にそんなこと言うて来たら、「そんなことは家でやれ」と一言ゆうて電話を切れ。家庭でやらんといかんことを学校に押し付けてきたら全部断れ!かまん。」
それだけではない。校長先生は、冒頭に紹介したエピソードに添えて、教職員にはこんなメッセージも送っていた。子どもには、一人ひとり異なる背景があるわけで、それを知る努力をすること。自分の指導力のなさを子どものせいにしないこと。「なぜできないのか?」ではなく、「どうしたらできるようになるのか?」を追求する教師であること…。
あの校長室便りを通して僕が感じたのは、校長先生の教育者としてのプライドと「本気」だった。学校は「サービス業」、保護者は「お客様」と化し、些細なリスクも冒すことができず、事なかれ主義に陥りやすいこの時代に、「いかんものはいかん!」と親を叱る管理職の姿はとても新鮮で、同時に懐かしく感じた。
子どもを人として育てるために、どれだけ本気になっているか?
「ごっついお父ちゃん」が放った問いが、一人の教師の中で温められ、20年の月日を経て地域に帰ってきたような、そんな気がした。
(雑誌『教育』2019年2月号より再掲載)









