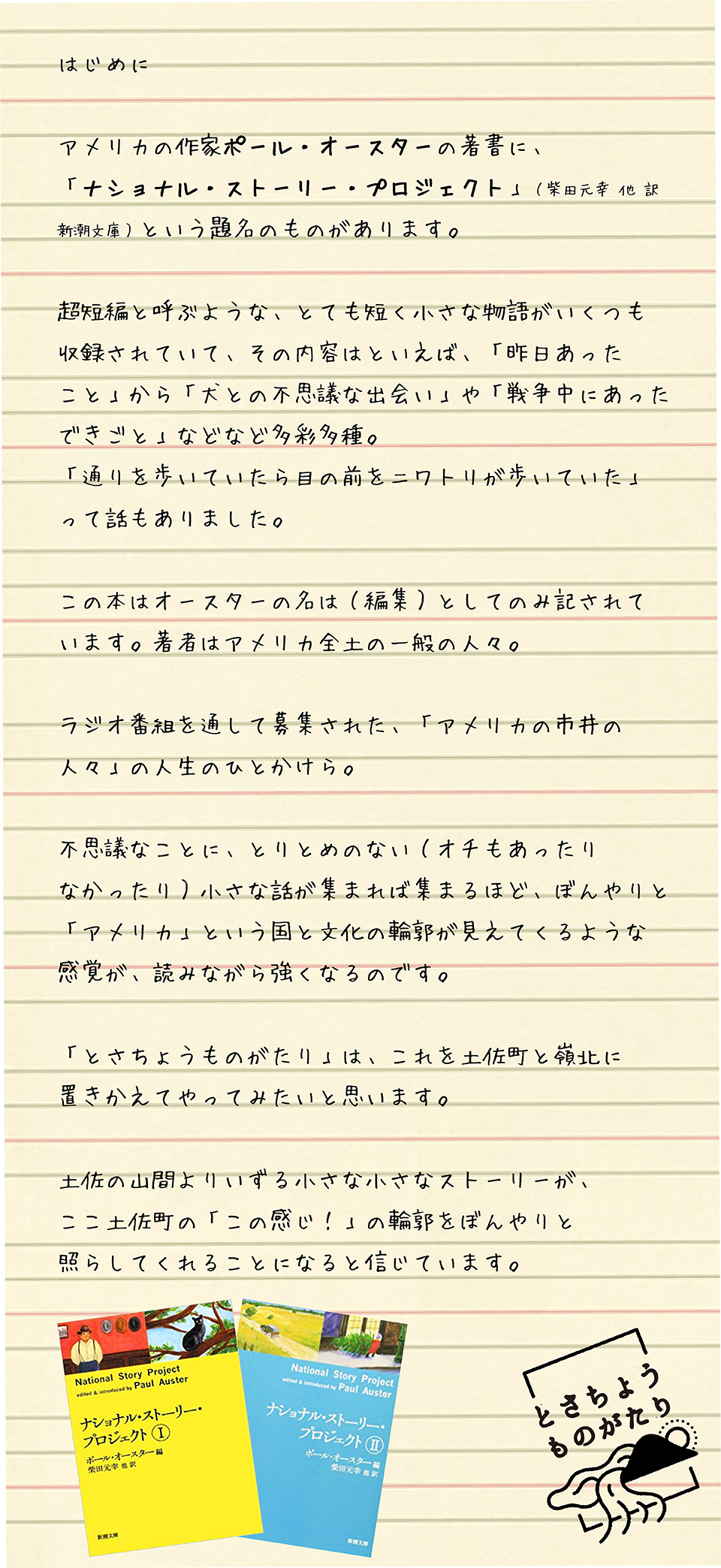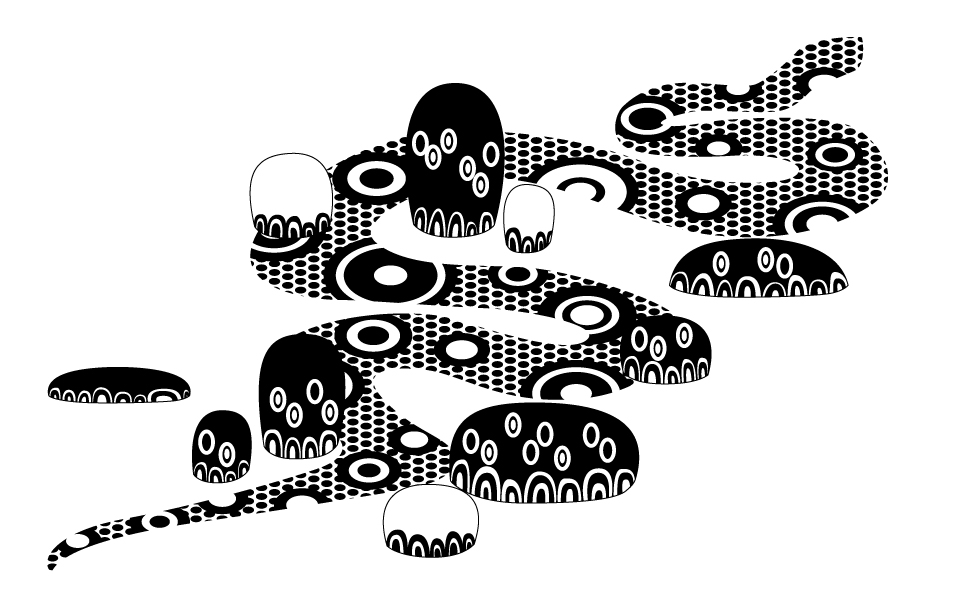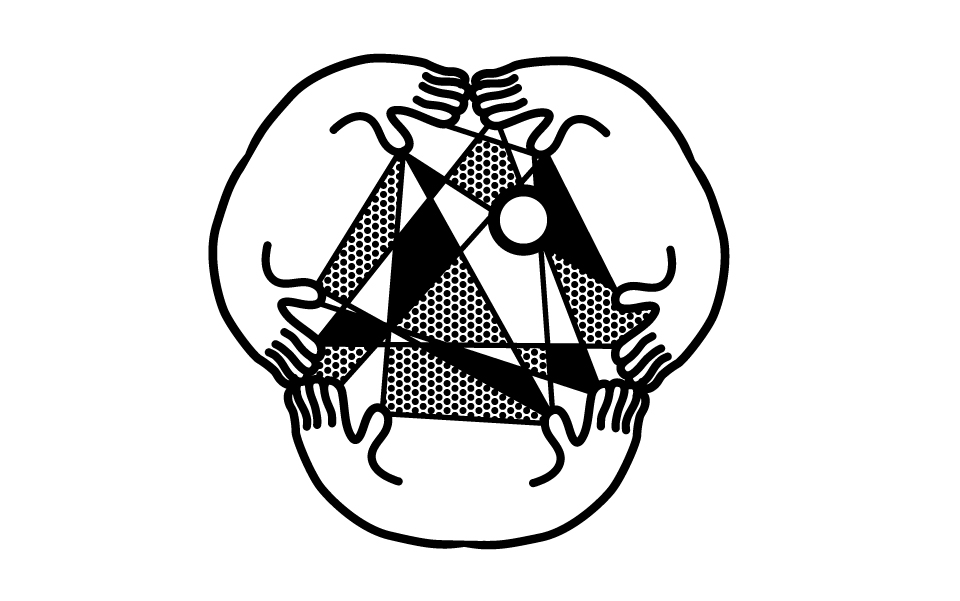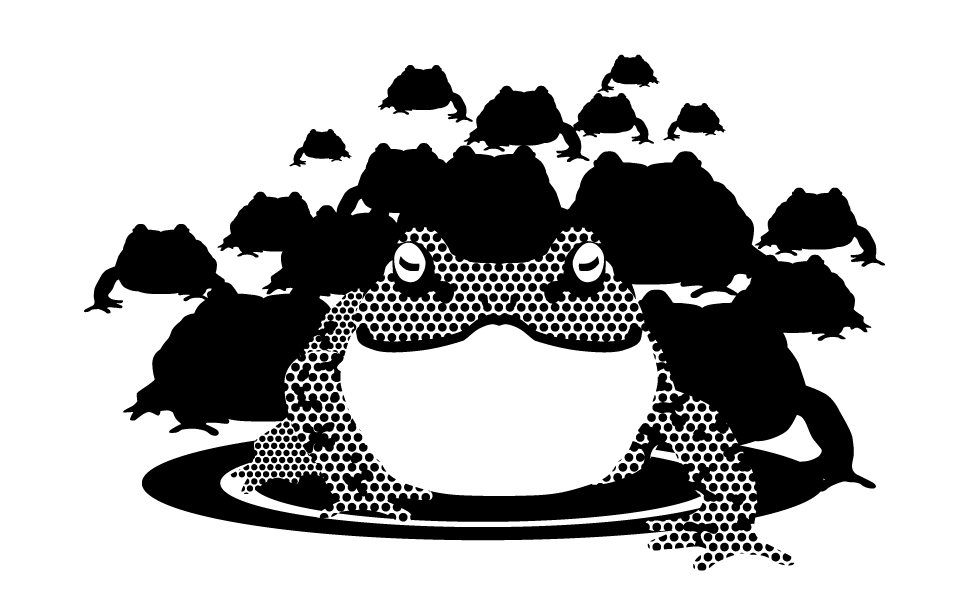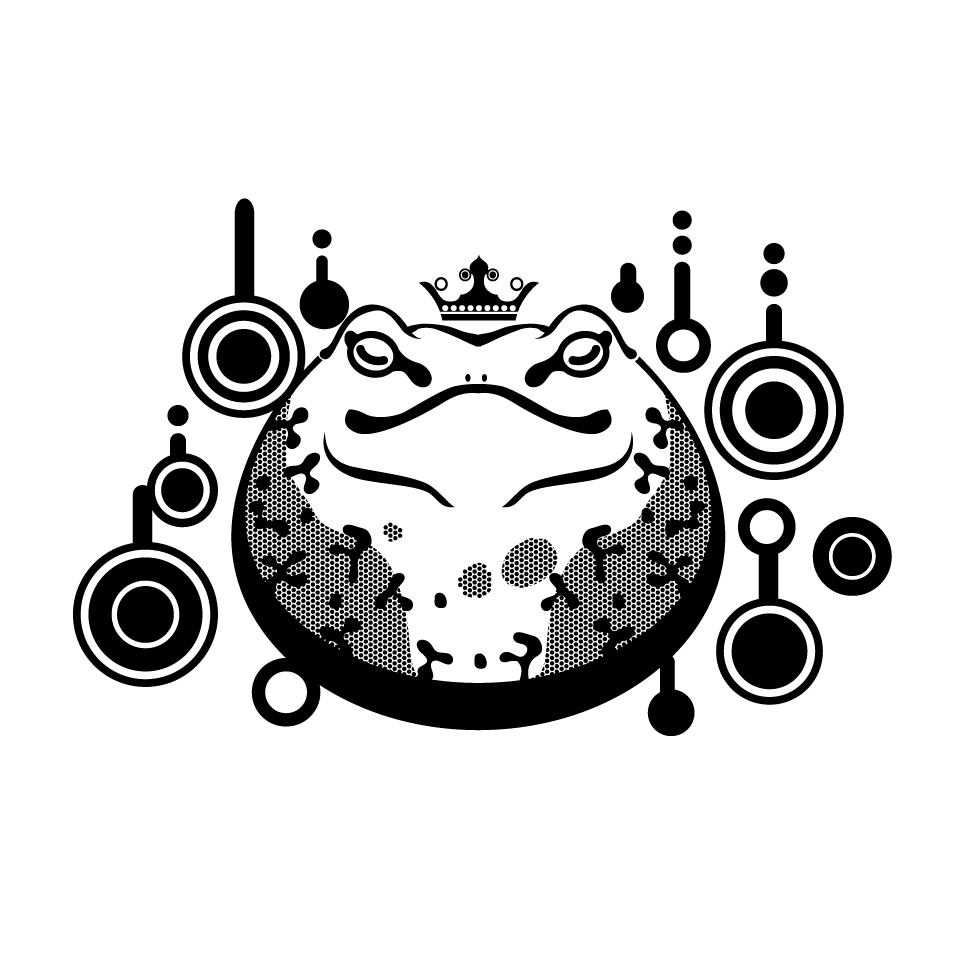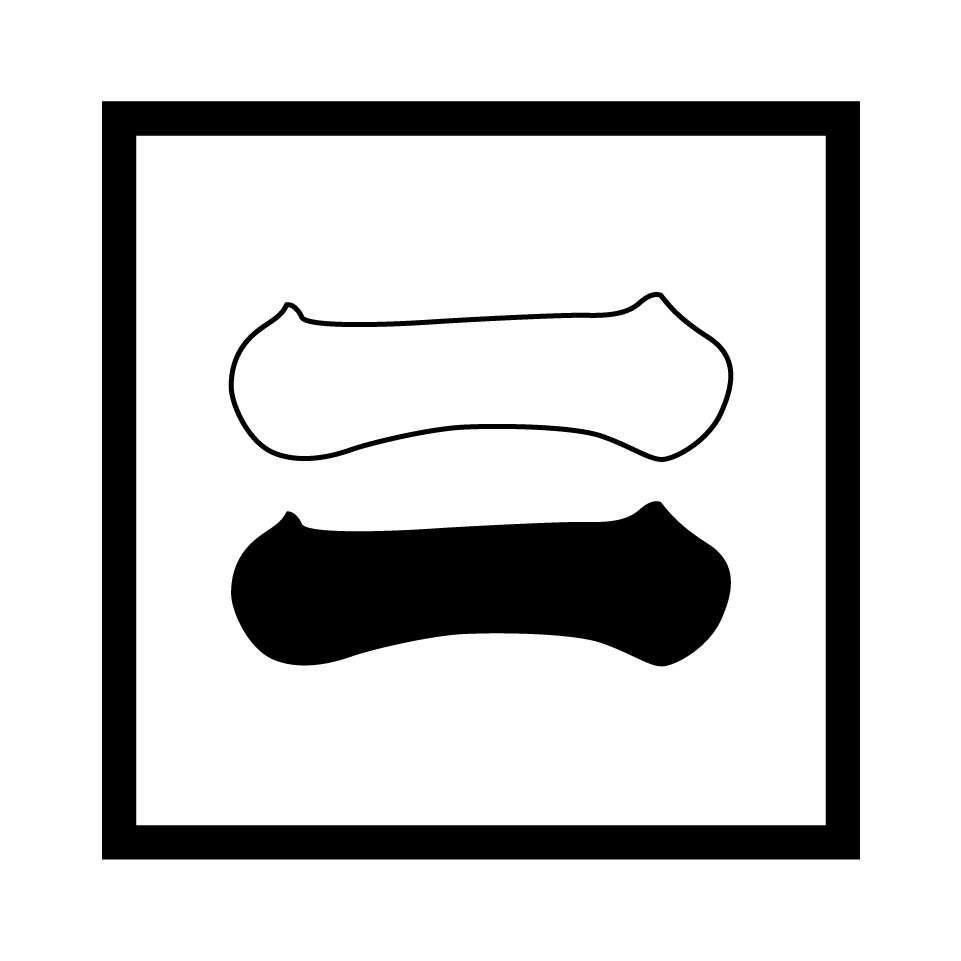土佐町に来て驚いたことがある。それは桃園とりんご園があること。
桃といえば岡山。りんごといえば長野や青森。
単純にそう思っていた私には衝撃的であり、嬉しいことの一つだった。
調べてみると、佐川町にもりんご園があるみたい。それもびっくり。
りんごといえば、初めてのひとり旅に私は長野県を選んだ。
京都の短大を卒業した後、同じ短大の専攻科に進級した1年生の秋に
大阪梅田のバスターミナルから長野行きのバスに乗って、上高地へ行った。
なんで長野県だったのか理由は忘れたけどその旅は学校を辞めようか悩んでいた、いわば傷心(?)の旅だった。
上高地へ向かう私鉄の車窓から目に飛び込んで来たのは、真っ赤なりんごがたくさんなった木。
その電車はりんご畑の中を通っている電車だった。
(はっきりは覚えてないので本当かどうかは今になっては不明・・・)
「りんごが木になっちゅう!!」
当たり前だけど、お店でしかりんごの姿を見たことがなく、
木に果物がなるといえば高知では柑橘類、あとは道々にある柿やびわくらいしか見たことなかったので、
それはそれは嬉しかった。りんごの良心市があるのも驚いた。
土佐町に来た時、りんご園があると知って、私は真っ先にその学生時代の悩んだ時期のこと、
りんごが木になっているのをみて嬉しかったことを思い出した。
りんごのように甘酸っぱい思い出。

りんごの季節になると、土佐町のりんご園のりんごが近くの道の駅や産直市に並ぶ。
その光景も高知では珍しく、薄赤いりんごが並ぶのはほんの一瞬の土佐町の味。
爽やかな秋風と同じように、土佐町のりんごは爽やかな酸味と甘味。
生ではシャキシャキとした食感が気持ちいいけれど、少しの水と一緒に似て煮りんごも甘みが増して美味しい。
うちの3歳の子は離乳食時期、生のりんごは食べなかったけど煮りんごはよく食べた。
じっくり火を通して、焼きりんごもいいな。
同じ時期に採れるサツマイモやジャガイモと合わせてポテトサラダにも。
ホクホクとシャキシャキを一緒に楽しめるおかずの一品にもなります。

ジャガイモとりんごのサラダ
材料:
りんご・ジャガイモ・(あれば)パセリ・塩・こしょう
オリーブオイルまたはマヨネーズ
作り方:
茹でたジャガイモを塊が残るくらい軽くつぶし、いちょう切りにしたりんご、みじん切りにしたパセリと合わせる。
塩こしょうと少しのオリーブオイルで味を整える。マヨネーズの場合はマヨネーズの味が出過ぎないように少なめに。
そうするとりんごとジャガイモの美味しさが際立ちます!
胃腸の虚弱を強くしてくれるジャガイモとりんごの組み合わせ。
夏に冷たいものを取りすぎたりして胃腸を弱くしている人にはオススメです。
特にこれからは乾燥も気になる季節。
今が旬の梨もそうですが、りんごも体の渇きを潤してくれます。
ぜひ普段のポテトサラダに、旬のりんごを入れてみてください。
りんごは体を温めも冷やしもしない「平」という性質。
冷蔵庫で冷やしたりせず常温で食べるのがポイントです。
胃腸の不調を整えたり、消化吸収が良いので便秘を改善。
下痢や吐き下しに良いとされています。
子供の時、熱が出たらりんごを食べさせてもらったりしませんでした?
「一日一個のりんごで医者いらず」よく言ったものでした。
特に皮には胃腸の働きを良くしたり、コレステロール値を下げるペクチンが豊富に含まれているので、
皮も食べると効果的!
イライラした時リラックスしたい時に食べたり、甘酸っぱい香りを楽しむだけでも心を落ち着かせてくれます。
りんご園のりんごを見た時、学生の頃を思い出して心がほっこりした気分になったのも、
りんごの持つ薬効だったのかもしれないですね。