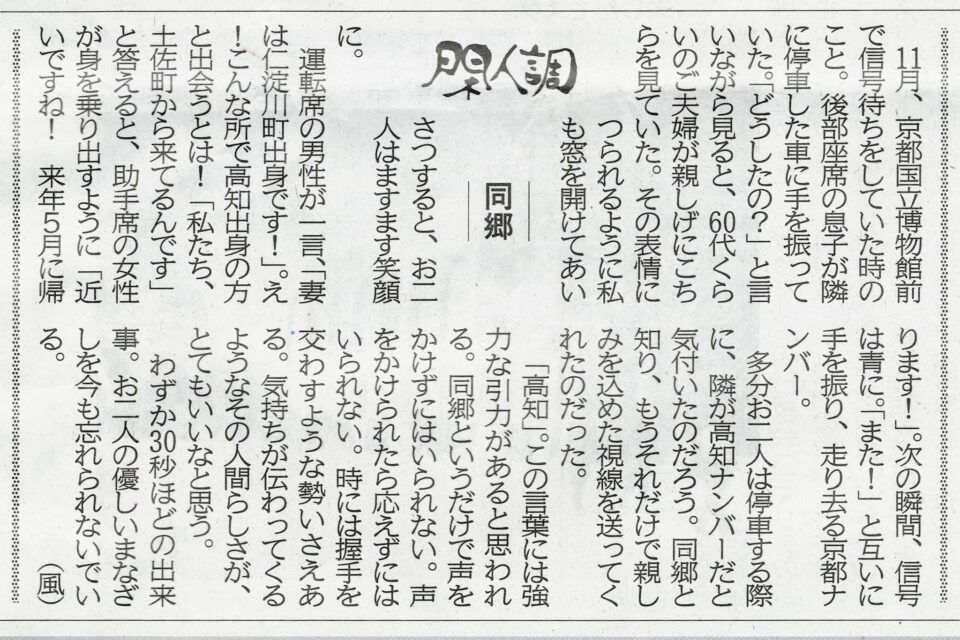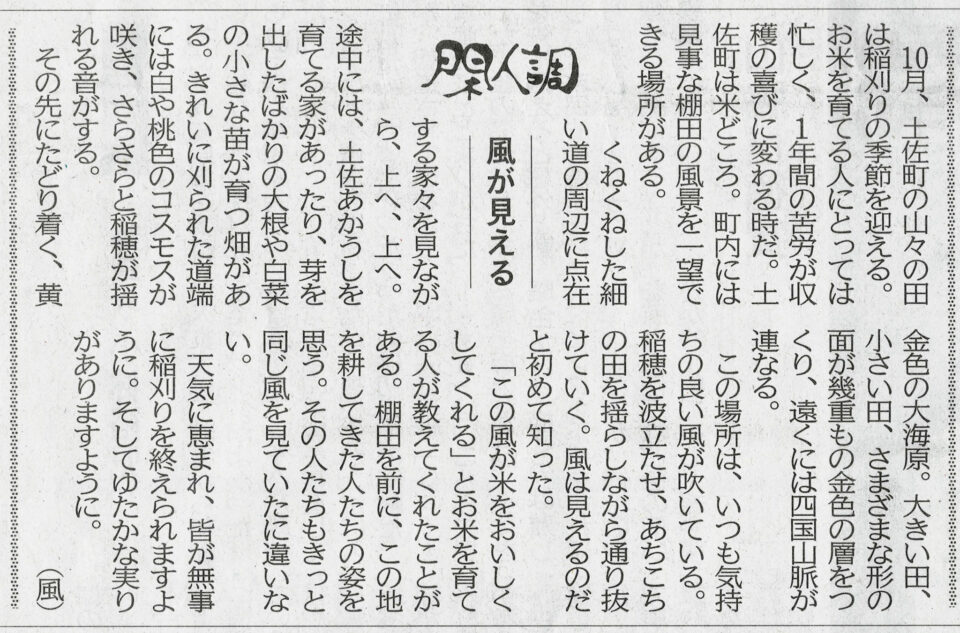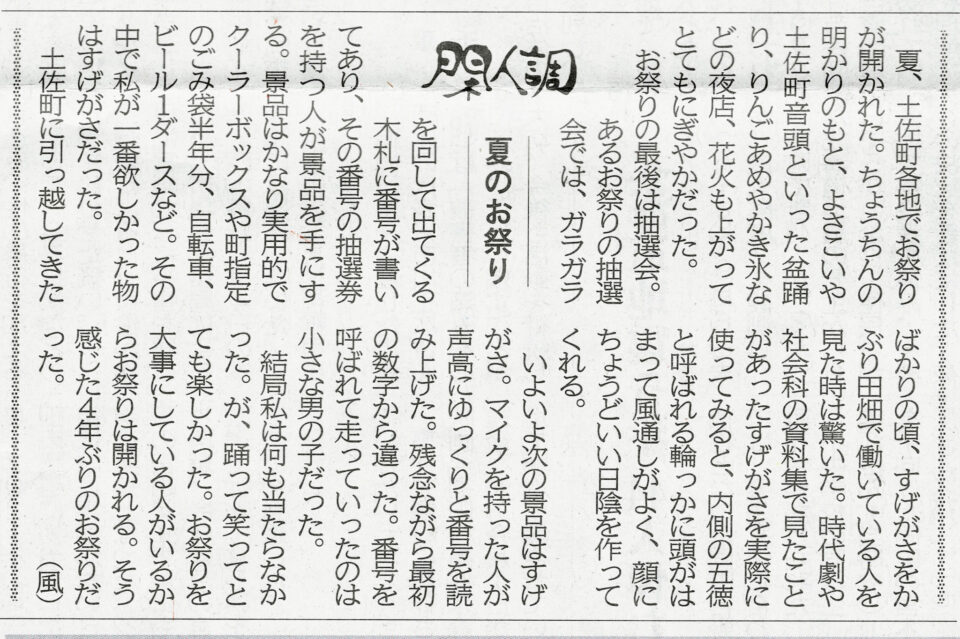賀恒さんはお正月用の飾りを作るところを見せてくれた。
地面にゴザと座布団を敷き、母屋の隣の小屋から藁の束を出して来た。秋にお米を収穫した時に、きれいな藁を取っておいたのだという。その藁でお正月飾りを作ったり、しめ縄を綯ったりする。
藁の束を片手でひょいと持ち、ホースからちょろちょろと流れ出る山水で濡らす。そうすることで藁がしんなりし、手で綯いやすくなるのだ。ぽたぽたと山水の雫を伝う藁を揃え、座って静かに藁を綯い始めた。
夕方の橙色の光に照らされながら「高峯神社の鳥居のしめ縄もこうやって綯っちゅうのよ」と話しながら綯われた飾りは、それはそれは美しいものだった。高峯神社の手洗石や鳥居、本殿に上がる階段につけられていたいくつものしめ縄は、賀恒さんが作ったものだったのだ。

目の前に迫る山を指差しながら「この山の尾根伝いに行ったら高峯神社に着くよ」と教えてくれた。山道をくねくねと行ったり来たりしながらたどり着いたこの場所に立つと、方向感覚なんていうものはなくなってしまう。賀恒さんが指差した方向は、私が思っていた方向と真逆だった。
高峯神社には、拝殿へ向かう階段のところどころにコンクリート製のブロックが置いてある。段差がきつい箇所に置いてあるので石段を上りやすいようにしていることはわかった。でもいつも不思議で仕方なかった。きっと歴史ある特別なこの場所なのになぜ「コンクリート」を使うのだろう、他に方法はなかったのだろうかと残念にさえ思っていた。
ある日突然、その謎はとけた。賀恒さんと一緒に階段を上っている時だった。
「このブロックがあると、先輩たちが上りやすいろう。ホームセンターのブロックを買ってきて置いたんで」
賀恒さんはさらりと言った。地域の先輩に相談してホームセンターで1つ100円のブロックを買い、軽トラックで神社のそばまで載せて来て、賀恒さんが一つずつ運びあげたのだという。
まさか賀恒さんだったとは!
心底驚き、そして爽快だった。
これは、70年間この場所へ通い続けた賀恒さんがした仕事なのだ。
「ブロック」は、この地では日常的に使われているものだ。賀恒さんにとって、きっとこの場所は日常であり、生活の一部でもあるのだ。この場所に毎日のように通い、小さな変化に気づき、その時の自分にできることをしてきたのだ。ブロックを抱え、ひとり階段を上る賀恒さんの姿を思うと「なぜブロック?」と、そんな風に思ってしまった自分が恥ずかしかった。
「大変だったでしょうね」と言うと、賀恒さんは「いやいや、そんなことない。やらしてもろうて」と首を振るのだった。
そして、ぼそっと言った。
「高峯神社の縁の下の力持ちになれたらと思うちょります」

賀恒さんの背中を見ていて思う。
どうしてなのだろう。
誰に言われるでもなく、誰に褒められるわけでも認められるわけでもなく、自らひけらかすこともなく、自分のやるべきことを淡々と積み重ねる。自分のしたことが誰にも気づかれないこともあるかもしれない。
でもきっと、大切なことはそんなことではないのだ。
この地で生きる人たちの一見さりげない仕事の数々が、気持ちの良い風を吹かせる。小さなひとつひとつが目の前の現実を昨日よりもよりよく、より美しくしているのだと思う。その変化は見ようとしないと見えないかもしれないし、ふとした時に初めて気付くのかもしれない。世の中を動かし支えているのは、世界中のこういった市井の人たちなのだとあらためて思う。
高峯神社に初めて一緒に行った日のことだった。賀恒さんを家まで送り、挨拶をしてふと見上げた時に目に入った。賀恒さんの家の2階の窓際に小さな机があって、机の上に土佐町史が置かれていた。
ああ、あの場所で賀恒さんは土佐町史のページを開いているのだ。
あの場所に座り、自分の生まれ故郷や暮らしている土佐町の姿を思い描いてきたのだ。
賀恒さんが自分の知っていることや学んだことをいつも熱心に話してくれるのは、会ったことのない祖先たちから受け取った何かを次の世代に手渡したいという賀恒さんの願いのあらわれなのではないだろうか。
重ねてきた日々の尊さを思う。
今まで通りすぎてきた道のあちらこちらに、いつのまにか手のひらからこぼれ落ちてしまったこの町の輪郭があることを賀恒さんは教えてくれた。毎日通る道の風景や頰に感じる風を、昨日とはまた少し違うものに感じるようになった。
次の世代に手渡すということは、こういうことなのかもしれない。