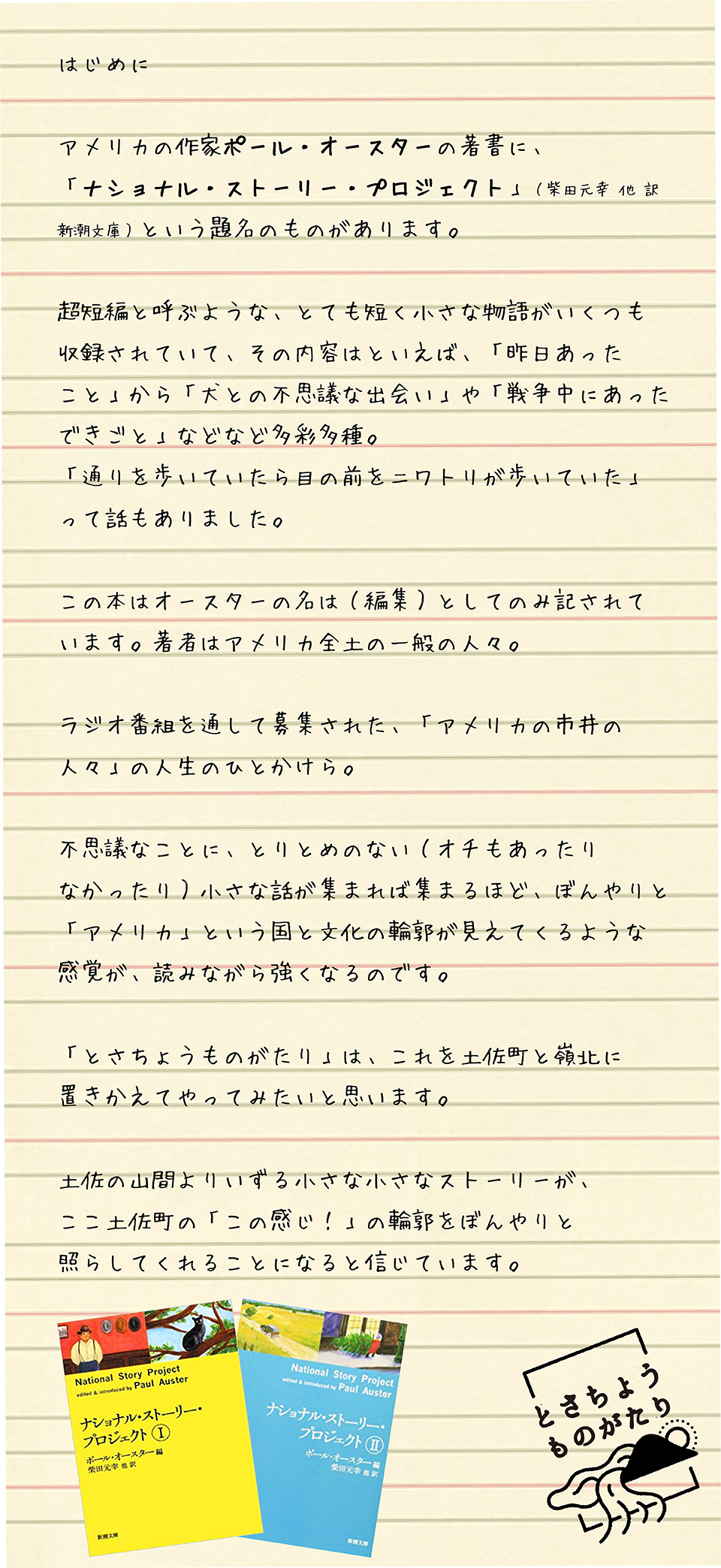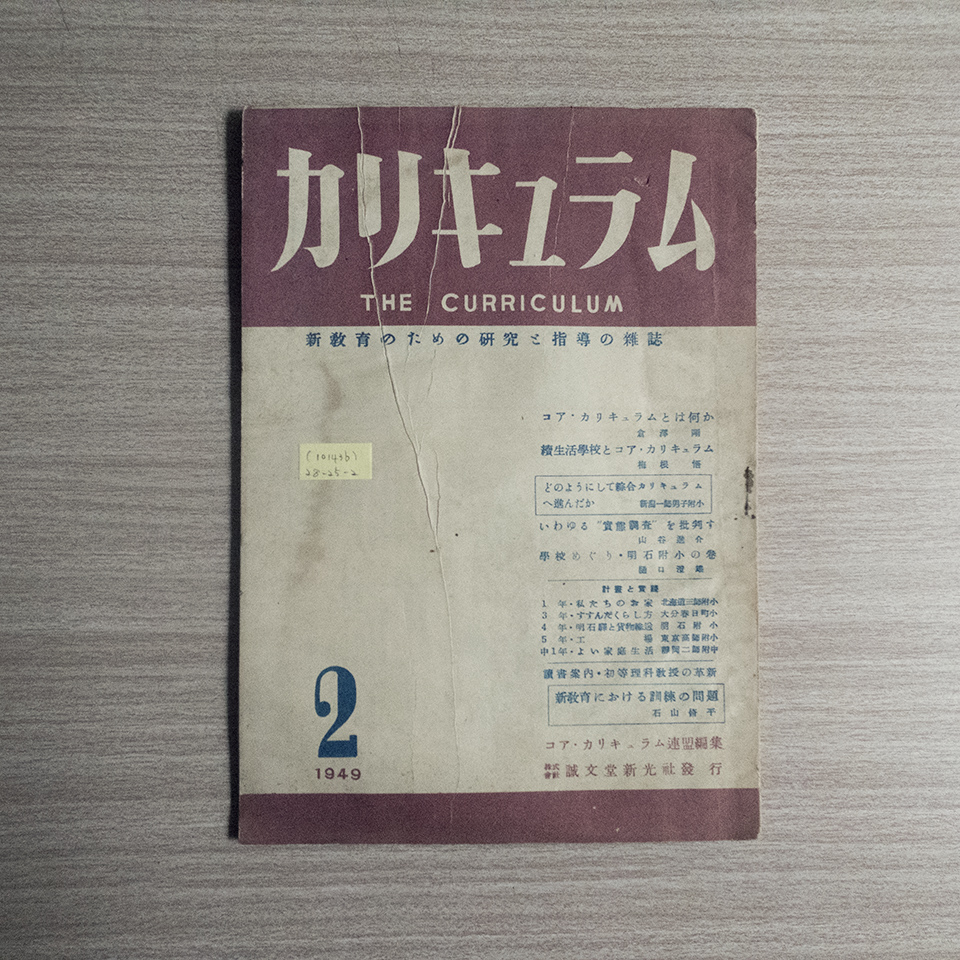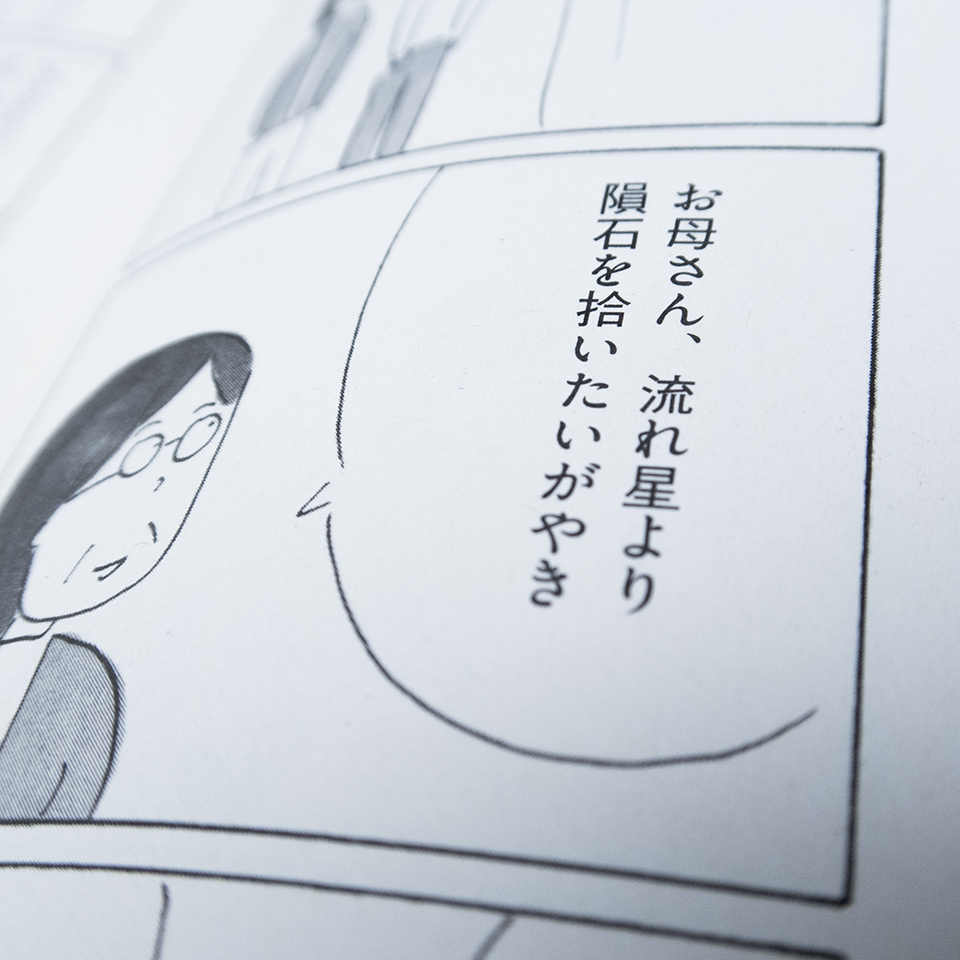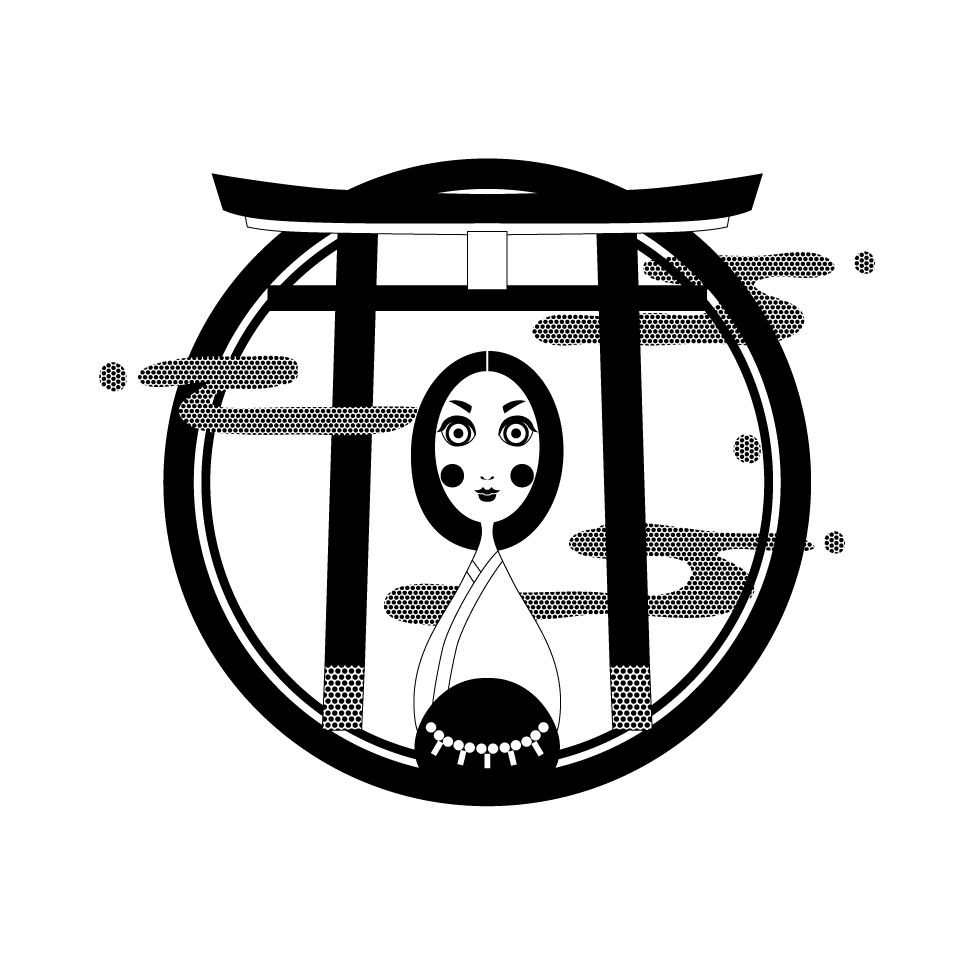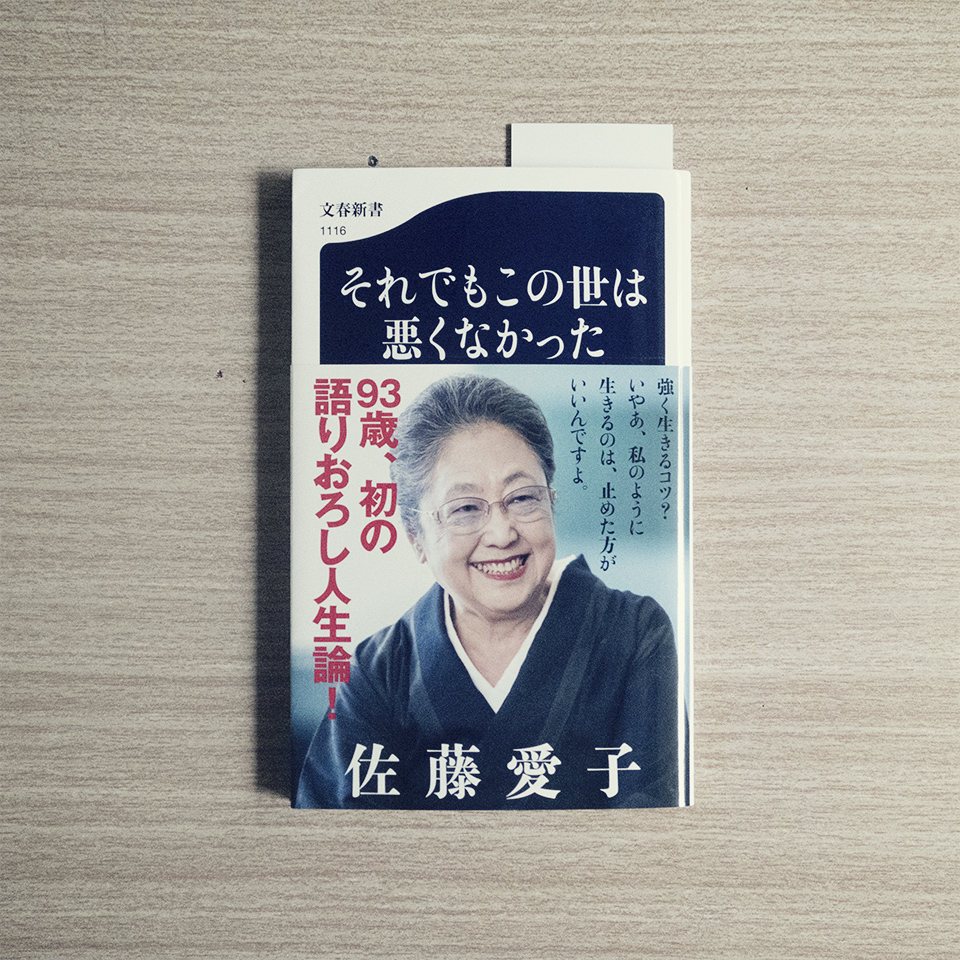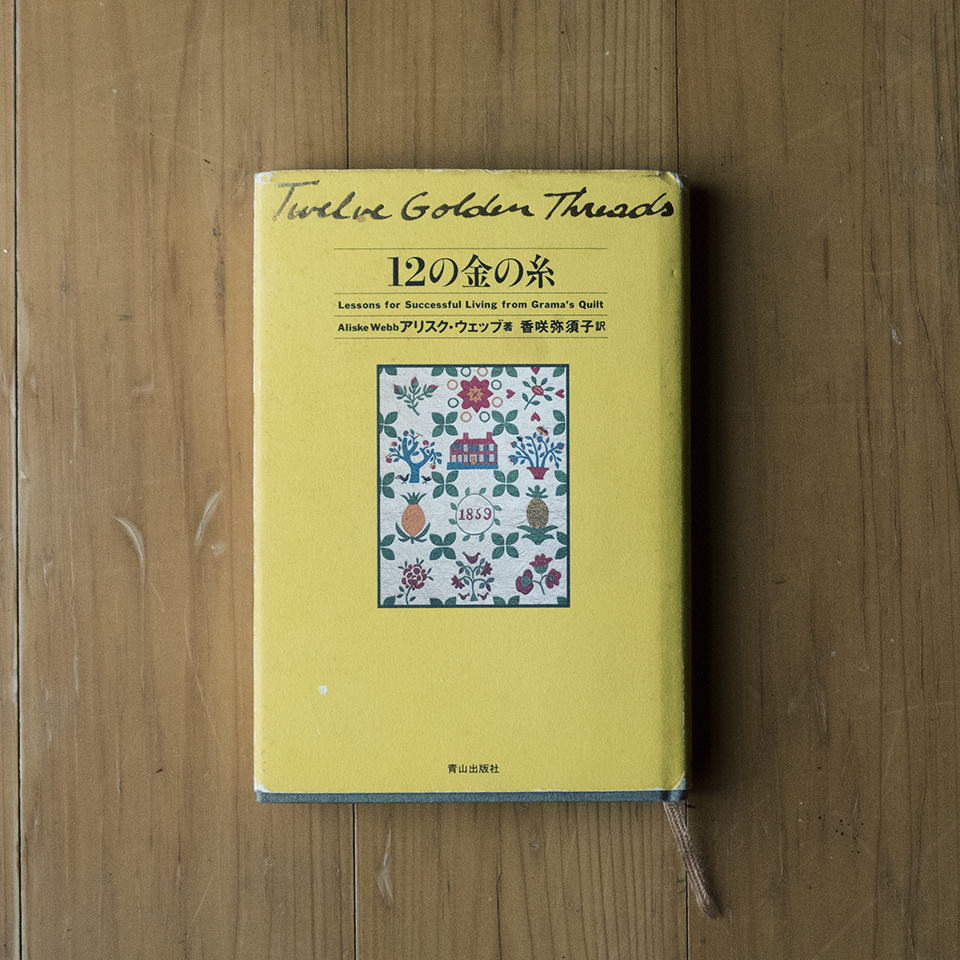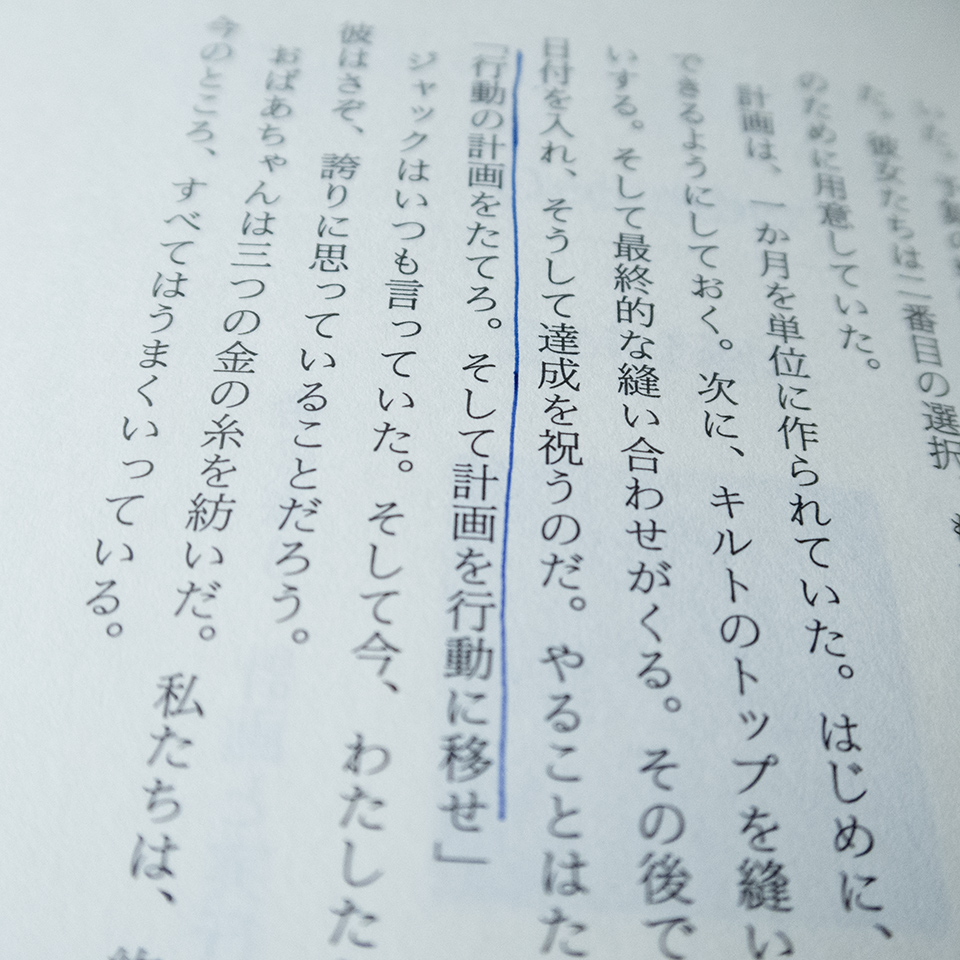2017年7月30日。「一日限りのパクチーフェス」当日。
17年前に閉校になった瀬戸小学校(瀬戸コミュニティーセンター)の台所にミニトマトが届いた。かごいっぱいの真っ赤なつやつやのミニトマトたち。きらきらして本当にきれいだった。
このミニトマトを作っているのは土佐町黒丸地区の森一子さん。この日のために「使って」と用意してくださった。これだけの数を収穫するのにどれだけ時間がかかったのだろう。かごの中にひとつまたひとつと入れ、かごがいっぱいになった時にはどんな気持ちだったのだろう。
目の前でつやつやと光っているトマトを受け取った時、まだお会いしたことがない一子さんの背中が思い浮かんで、なんだか胸の奥の方から込み上げてくるものがあった。

黒丸で何度目かの打ち合わせの時、予算がなかなか厳しいということがわかった。(もしかしたら最初からわかっていたことかもしれないが)。
野菜は土佐町のものを使いたかったから、土佐町の「sanchikara」の釜付さんと上堂園さんにお願いをしていた。でも使いたい野菜を全部頼むと予算は厳しい…。
頭を悩ませていると、黒丸地区の集落支援員の岡林さん(以下みちさん)が口を開いた。
「ミニトマトは森一子さんが作ってる。聞いてみようか…?」
「むかしきゅうりは中町吉香さん。」
「デザートにはスイカがあったらいいね」という話していると、
「スイカか…。森元美さんがもう少し大きくなるまで、と畑においているスイカがあったはずやから…。声をかけてみる。」
「ぜんまいは松子さんのところにあると思う。」
驚いた。
みちさんは黒丸の方たちの畑の様子も知っているのだ。
「〜さんはこれ、〜さんはあれを作っている」と知っていることだけでも驚きなのにそれに加え、育てている野菜の状態まで把握している。
みちさんが一軒一軒の家へ足を運び、どれだけ話を聞き、話をしているのか、みちさんの背中から伝わってきた。
黒丸の人たちが心を寄せてくれたからこそ、7月30日を迎えることができた。
食材を分けてくれたり、大きなクーラーボックスや皿鉢を貸してくれた黒丸地区の人たちにも来てもらいたかったが、みちさん曰く「みなさん恥ずかしがり屋やき、なかなか来れないかもしれない」とのことで、お弁当を届けることにした。
この日作ったパクチー料理の数々をつめた。喜んでくれるといいな、食べてもらえるといいなと思いながら。

【お弁当のなかみ】
・パクチーライス
・炊き込みご飯(パクチーのせ)
・ゼンマイパクチー
・おからとパクチーのひろうす
・パクパクピッグパクポークビッグパクパクパクポークしまんと豚
・厚揚げパクチー
・ミニトマト
・かぼちゃの素揚げ
みちさんが運転するバンに乗り込んで、夕方、お弁当を届けに行った。
一本道のくねくねした急な坂道を登っていく。少し暗い深い緑色の木々が立ち並ぶ苔むした道を進んで行くと、突然空が広がり雲がかかった山々が見える。日中はあんなに暑かったのに、頰で感じる風はいつのまにかどこかひんやりとしていることに気づいた。ひぐらしが鳴く声が遠くからも近くからも聞こえてくる。
黒丸は標高700〜800メートル。
下の方から川の流れる音が聞こえる。向かいの山から風が降りてくる。
緑の木々とむんむんとした草の間にふと現れる、黄色や白やピンクの花たちが目に入るとはっとする。花があるところには人が暮らしているのだ、と思う。
玉切りにした木を積み上げている小屋がある。こうやって乾かし、木を割って薪にし、お風呂を沸かすのに使ったり山菜を茹でたりする時に使うのだろう。薪が道々に積み重なっている風景があるということは、この山には人が暮らしているということなのだ。

一本の道を進んでいくと、家の前に広がる急な斜面に畑がある。トウモロコシ、かぼちゃ、きゅうり、トマト、なす、しそ、ねぎ…。実をつけたトマトが赤くなっていく様子を見つめていたり、きゅうりの花が咲いた後、小さなきゅうりの赤ちゃんがだんだんと育っていく様子を見守る人がいるのだ。
自分の生きている場所で自分の食べるものを育てる人がいる。買い物のできるお店が近くにないから、自分で作るしかないということもあるのだろうが、この畑は、今ここで生きているのだというひとつの証のようなものなのだと思った。

森一子さんの家へ向かう道は急な下り坂だった。むらさき色の紫陽花や、名前はわからないけれど鮮やかな黄色い花が咲いている。
小屋の中には薪がたくさん積み上げられていた。家の軒下ではインコが楽しげにかごの中で飛び回っていた。かわいがられているんだろうな、ということが伝わってきた。
みちさんが「かずちゃーん」呼びかけると、少ししてから家の奥から静かに一子さんが出てきた。
パクチーハウスの佐谷さんがお弁当を手渡す。
「今日作ったものをお弁当にしました。」
「まあまあ…わざわざありがとう」とひかえめに笑いながら受け取る一子さん。
一子さん「行きたかったけど…まあ、ねえ…。」
みちさん「来てほしかったけど、送り迎えができんかったけ…。」
一子さん「なんちゃあないわね、こんな山の中…。」
みちさん「そんなことない。そういうところが素晴らしい、って言ってくれてるんよ。」
佐谷さん「素晴らしい。本当にいいところです。」
一子さん「…また今度。会える時があったら…どうもありがとうございました。」
一子さんの慈しみのある、穏やかなまなざしを本当に美しいと思った。

「なんちゃあない(何にもない)」。
一子さんに限らず、土佐町の人から時々その言葉を聞くことがある。
「なんちゃあない」。
本当に「なんちゃあない」のだろうか。
私は土佐町の外で生まれ育っているからそう思うのかもしれない、と自分に問いかけてみるけれど、でもやっぱり私には「なんちゃあない」とは思えない。

黒丸地区の一番上で暮らしている中町吉香さん。吉香さんはむかしきゅうりを分けてくれた。
むかしきゅうりは太めでずっしりとしていて、土佐町では昔から種を取り継いで育てている人が多い。吉香さんのむかしきゅうりは、スープにした。火を通しても美味しいのだ。
吉香さんの家の前の斜面に広々と広がる畑にはこんにゃくが育っている。きっとこんにゃくも自分で作っているのだろう。家の前では山からの水をホースで引き、おけにためては流している。山ではこんな風景が多くあって、ふと気づくといつもどこかで水の流れる音がする。
大きな町ではこんなことはなかった。水も野菜もお米も遠いところで管理され、運ばれてくる。お金でやりとりされたものを食べたり飲んだり使ったりして生活していた。そのことを何の疑問も持たず当たり前のことように思っていた。
土佐町に来て山での暮らしを知っていくうちに、都会での暮らし方は大切な何かをどこかに置き忘れてしまっているのではないかと、そんな感覚を持つようになった。その「大切な何か」はまだ言葉にできずにぼんやりとしているのだけれど、この地での暮らしを積み重ねていくことでいつかきっとその姿を見せてくれるのではないかな、と思っている。
吉香さんにお弁当を渡すと「まあまあ、すみません」とにこにこと受け取ってくれた。
むかしきゅうりをいただいたお礼を伝えると「今年は去年みたいになってなかってね。去年は上にも下にもいっぱい種をまいちょったけ、じゃがいも植えちょった後へきゅうりをまいたら、いっぱいなってねえ」と話してくれた。
最後「気をつけてね」とサンダルを履いて玄関の外へ出て見送ってくれた。
玄関を出るとひぐらしが鳴く声が聞こえた。一瞬、それまで時がとまっていたかのように思えた。
今まで知らなかった人同士があるひとつの場所で出会い、時を重ねること、積み重ねていくことは、なんてかけがえのないことなのだろう。

森元美さんのお家へ向かう。元美さんはすいかを分けてくれた。
家の前には白い百合が咲いていた。お風呂の煙突からは煙が出ている。お湯を薪で沸かしているのだろう。何の木を燃やしているのかはわからなかったけれど、あたりはとてもいい香りがしていた。もうお風呂を沸かすような時間になっていたということに、この時初めて気がついた。

「もとちゃーん、おるかねえ?」と門のところからみちさんが呼びかけると、遠くから「はーい!」と元気な声がした。
元美さんがこちらに歩いてくる。
佐谷さんが「すいか、ありがとうございました」と言うと「食べれた?美味しかった?」とこちらも思わず笑顔になってしまうような顔で聞いてくれる。
「どう?楽しかった?」
「今晩は泊まり?楽しんでいきなさい」。
美味しかったか?
楽しかったか?
心に響いた。
私はわからなくなっていた。本当は楽しみたいしそのままの思いを伝えたいのに、自分の気持ちのどこかにふたをして勝手に遠慮して、そんなことを続けているうちにどんなことを楽しいと感じるのか、感じていたいのか、そのことさえもわからなくなっていた。でも今は、閉じていたふたが少しずつ開き始めていることが自分でわかる。開いてもいいんだと初めて自分で自分を認められるような、そんな感覚を少しずつ持てるようになった。
元美さんの言葉は、それでいいのよ、と言ってくれているみたいで何だか泣きそうになった。その人の存在そのものから伝わってくる何かは、心の深いところに届いてくる。

7月30日のための準備のために瀬戸小学校へ訪れるたび感じることがあった。かつてたくさんの子どもたちがここで育ったのだ、と。あちらにもこちらにもその気配が残されていた。学校はしっかりと覚えているのだ。
17年ぶりに多くの人のにぎやかな声を聞いた瀬戸小学校は、この日のことをどんな風に感じただろう。
台所の前のぎしぎしとした床も、体育館へと向かう階段を登る時に何度も見上げた窓枠も(外は真っ白い入道雲と夏の青空、緑の山々。まるで一枚の絵のようだった)、土佐町の花農家、みどりさんからいただいたトルコキキョウを飾った三角フラスコも、校長室の黒板にチョークで描かれていた土佐町の地図も、きっと喜んでくれていたのではないかと思う。
パクチーフェスが終わって何日かしてから、しん、と静まりかえった学校に入ると、確かにこの場所に満ちていた、人と人がつながるエネルギーと喜びの余韻があった。
16世帯28人の土佐町黒丸地区。世間ではこの場所のことを「限界集落」というのだろう。
黒丸の道には、黒丸という地で生きる人たちの家がある。ひとりで暮らしている人、ふたり暮らしの人、ご主人が入院しているから今はひとりでお家にいるという人…。それぞれの場所で、こつこつと毎日の暮らしを積み上げている人たちがいる。
地球儀を回したら、日本の、四国の、高知県の、土佐町はほんのほんの小さな一点。その一点一点は日本中、世界中にたくさんあって、小さなその中に確かな暮らしがあるのだということを忘れずにいたい。
それぞれの暮らしをつくっているのはかけがえのないひとりひとりだということも、そのひとりひとりをのせて地球は回っているのだ、ということをいつも心のどこかに置いておきたいと思う。