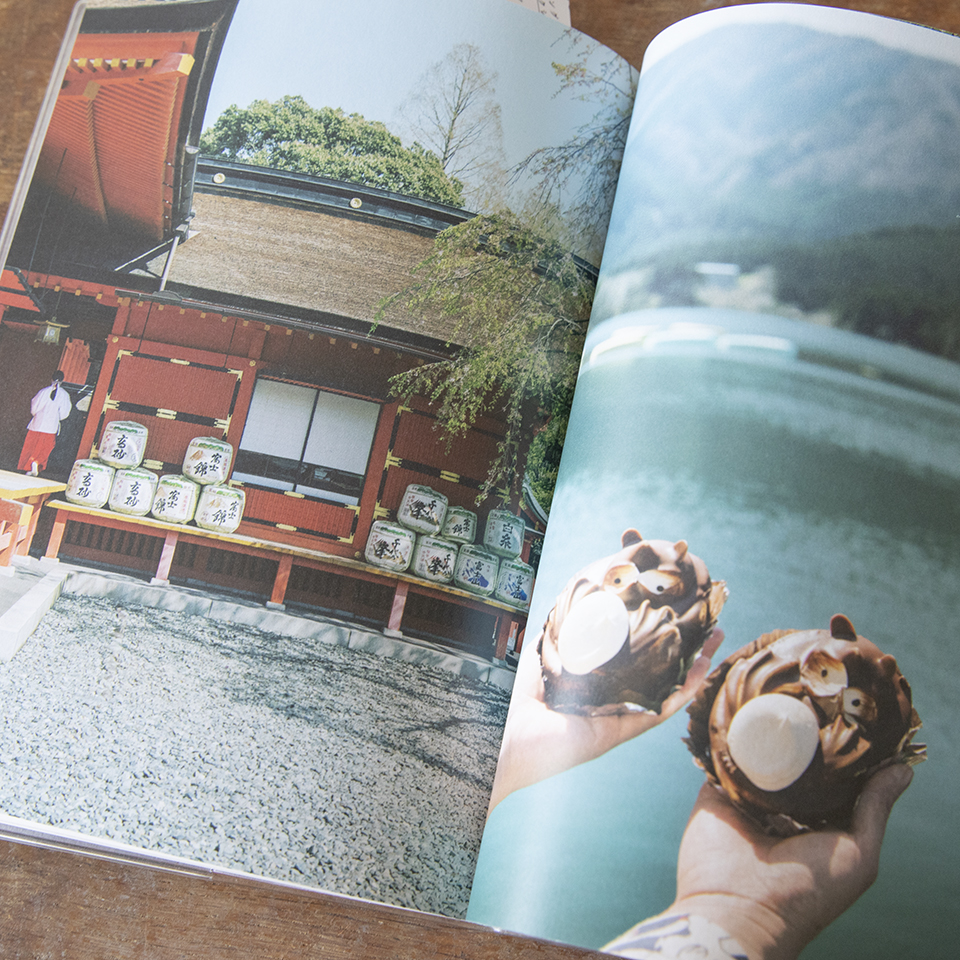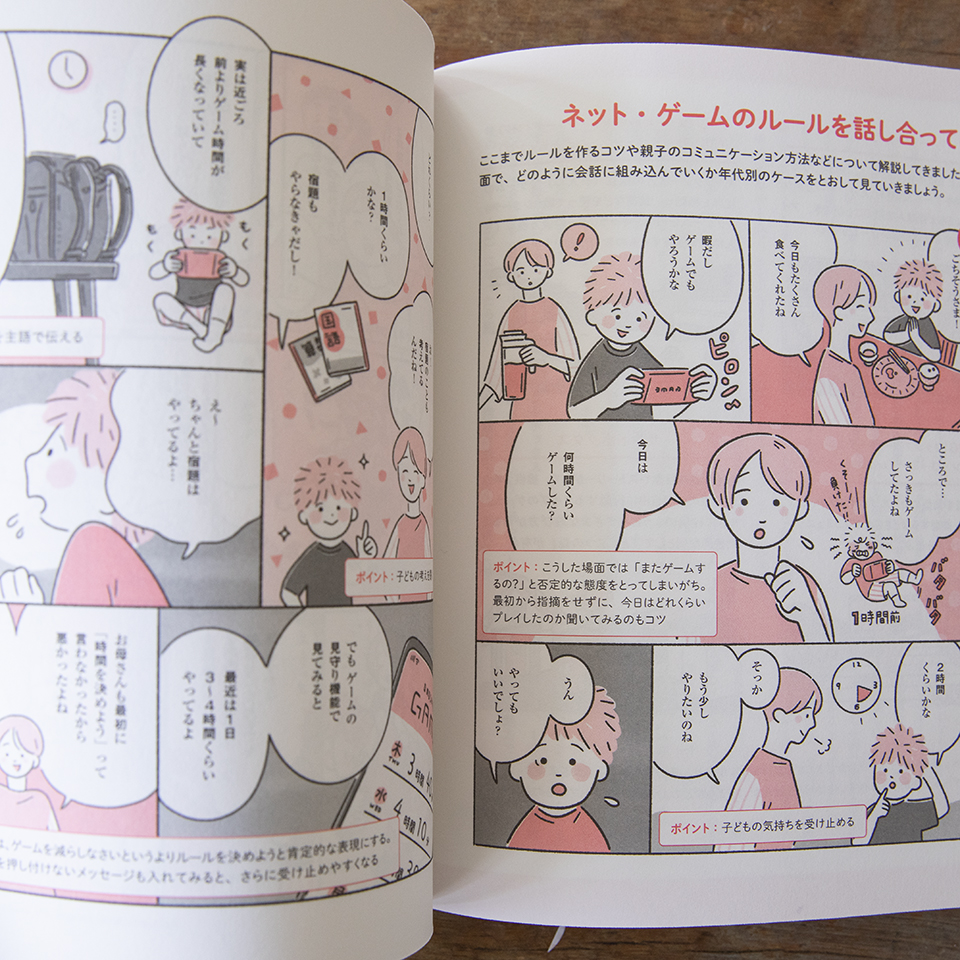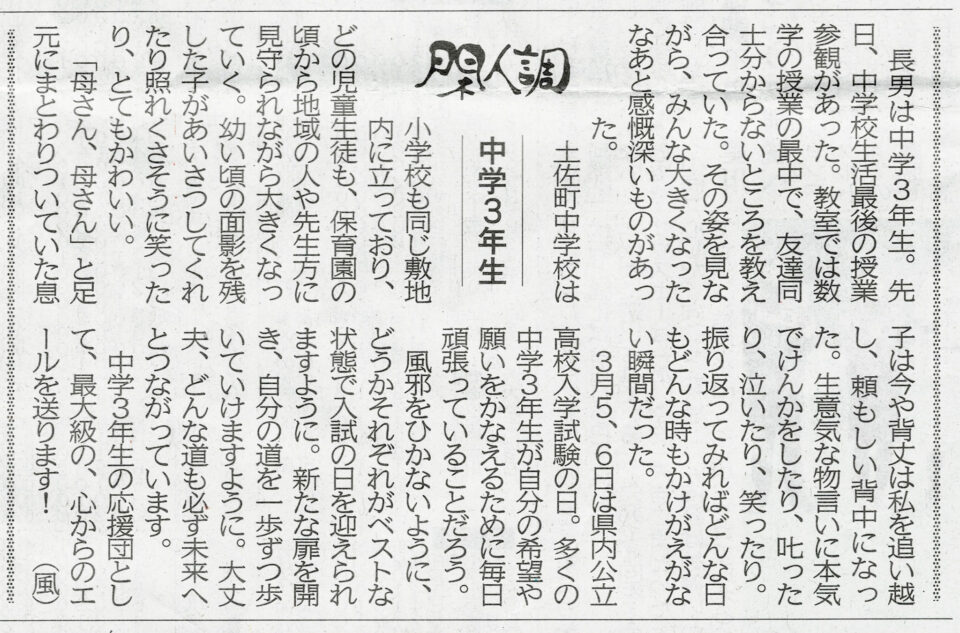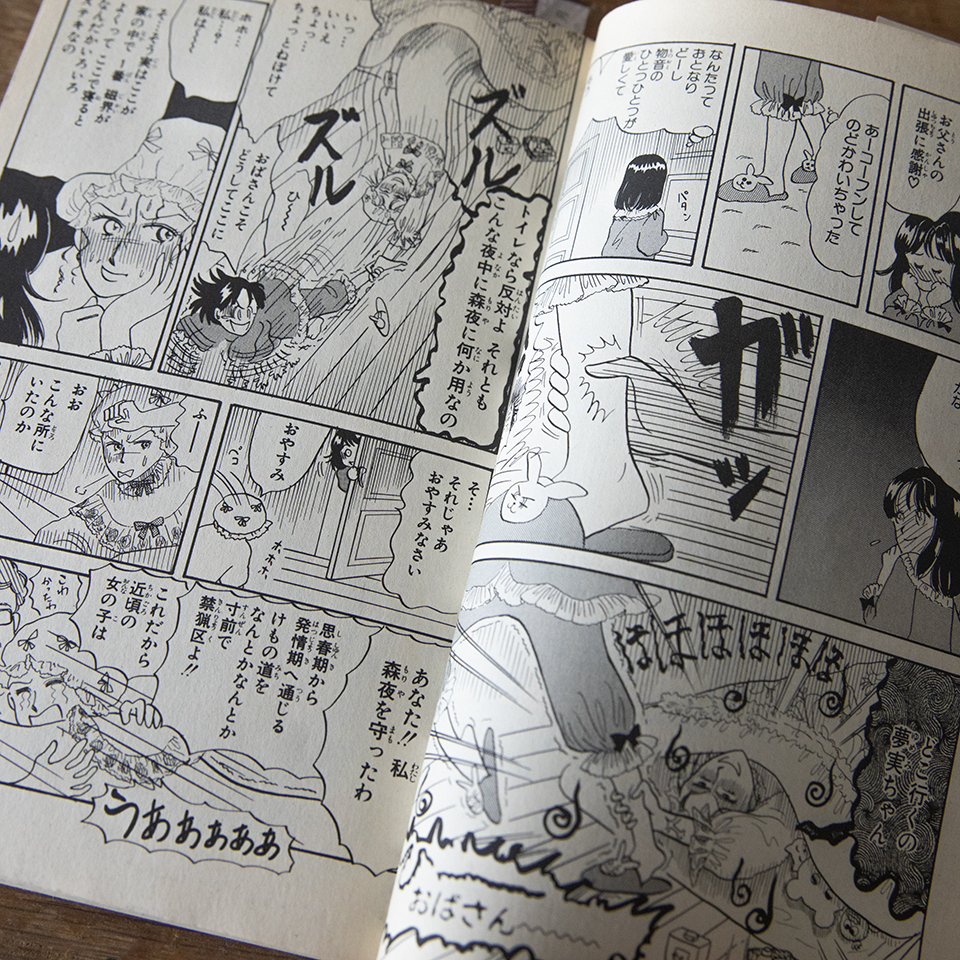セリ科の1属1種の植物です。
草丈10~20㎝ほど、地面に這うように咲いている小さな草本です。
山裾で他の花があまり咲いていない時期に見られるので目立つと言えば目立ちますが、花があまりにも小さくて野の花に興味のある人でないと気がつかない存在なのかも知れません。
長い花茎(※かけい)と根生葉(※こんせいよう)の葉柄(※ようへい)が、紫色を帯びているのがこの花の特徴です。

セントウソウ(仙洞草)という和名の由来については興味深い説がいくつかあります。
「京都の仙洞御所(退位した天皇の邸宅)に咲いていたから」とか
「仙洞というのは人里離れた仙人の庵(住まい)のことで、そのような場所に自生しているから」とか
「春一番に咲く、つまり先頭を切って咲く」「セリ科の中で一番早く咲く」などと解釈して、先頭草と書かせるのもあります。
因みに牧野富太郎博士はセントウソウの語源は不明としているようです。
早春に咲くセリ科の花はこのセントウソウ(仙洞草)だけです。
葉は3枚ワンセットの複葉で、それぞれの小葉に細かな切れ込みがあります。

全体的に繊細な雰囲気があります。
柔らかな緑の葉の上に直径2~3㎜の小さな花がいっぱい広がる光景に出くわす時の感動は、花好きにとって毎年早春の楽しみになっています。
花を拡大してみると真っ白な花弁の先に雄しべが踊っているのが分かります。
葯(※やく)は、鮮やかなピンク色の時がままあります。


セントウソウの葉の形に似た植物は、畑ならニンジン、野に出ればオヤブジラミなど多くあります。キンポウゲ科のセリバオウレン(芹葉黄連)の葉にもよく似ていて、セントウソウにはオウレンダマシ(黄連騙し)という別名がついています。
※花茎(かけい):花だけをつける茎
※根生葉(こんせいよう):植物の根元から出ている葉
※葉柄(ようへい):葉を支える柄
※葯(やく):花粉をつくるところで、雄しべの一部