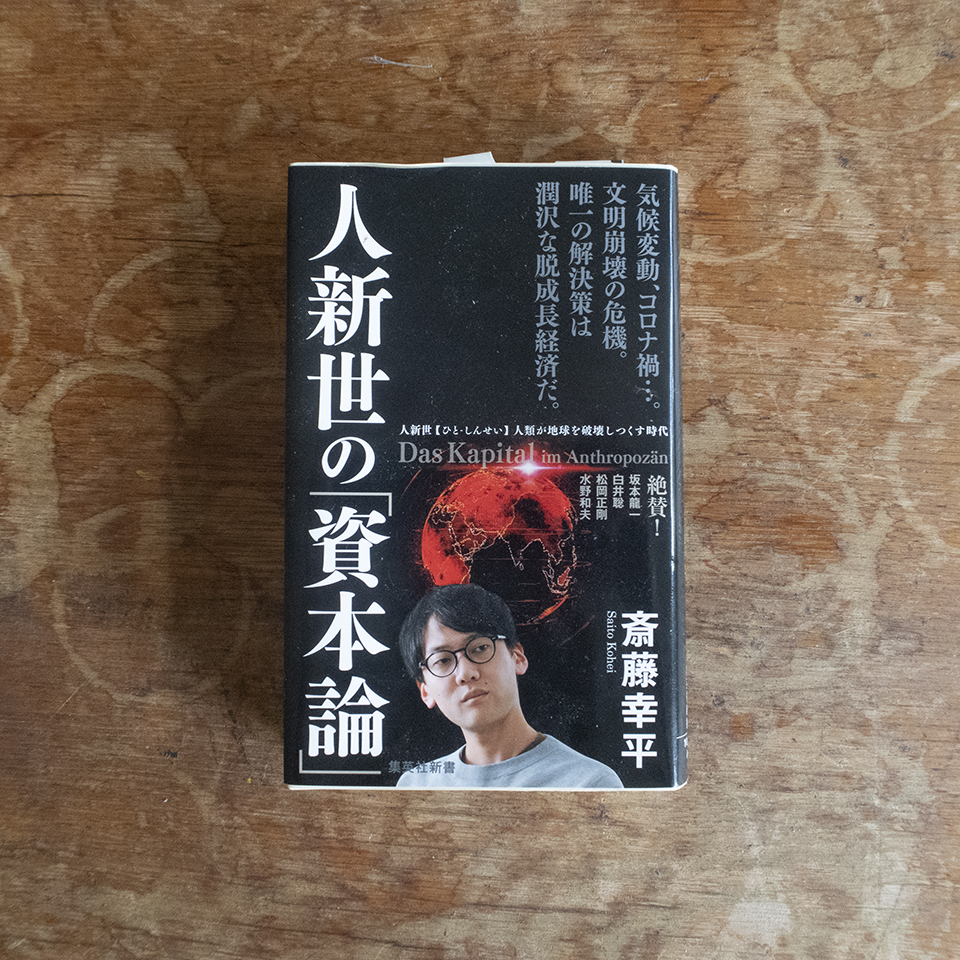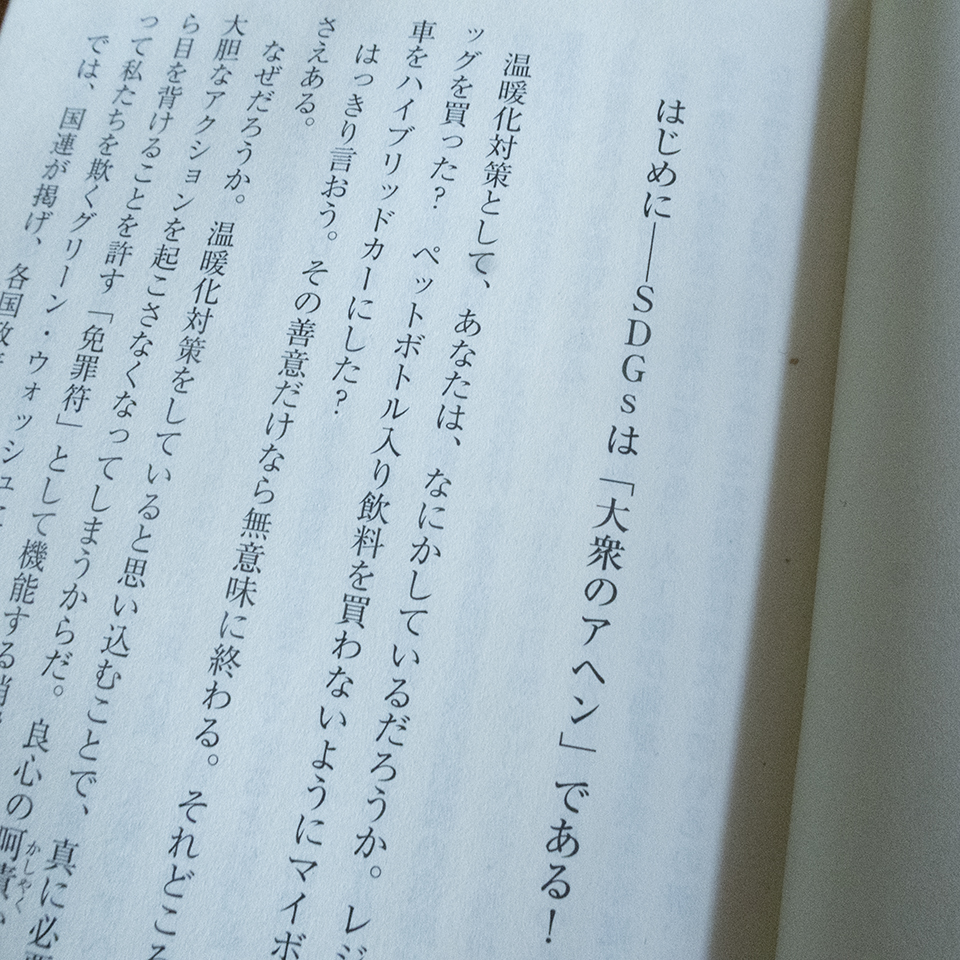笹ヶ峰
笹ヶ峰は、土佐町南部と南国市にまたがる、標高1131mの山です。
「笹ヶ峰」という名前で呼ばれる山は石鎚山系にもうひとつあり、こちらは標高1859m、いの町本川村と西条市にまたがっています。
今回の記事は土佐町の笹ヶ峰のお話。
登山口
登山口までは車で上がれます。いくつかルートはありますが、相川地区から上がるのが最もわかりやすいルート。
通称「台の牧場」と呼ばれる牛舎を右手に、さらに上がると下の写真のような登山口手前につきます。
ここに車を停めて、ここから片道1時間程度の登山です。



天狗岩と小天狗岩
登山口付近に掲げられた道標。とても良い感じで苔むしています。空気もとてもきれいです。
この笹ヶ峰、道標に書かれているように「天狗岩」と「小天狗岩」のふたつの目的地があります。
ふたつともそう離れたところにあるわけではないので、どちらかに寄ってからもうひとつに行く。例えば小天狗岩に行ってしばし眺めを堪能したら天狗岩へというルートになります。

この苔の美しさ!ダイダラボッチが出てきてもおかしくなさそうです。いやおかしいか。

途中にはこんな岩も。子どもだったら絶対にくぐってるヤツですね。

左に行くと小天狗岩、右に行くと山頂+天狗岩という分岐。名前に「小」がつくけれど小天狗岩の方が眺めが良いで〜という地元の方は多いです。

小天狗岩に到着。ちょっとわかりずらいですが、中央に見える白っぽい岩が小天狗岩。ここによじ登ると待っているのは下のような眺望です。

小天狗岩から北側を臨んだ景色。眼下に広がるのは土佐町の風景です。この日はあいにくの曇り空でしたが、晴天の日には四国山脈が彼方まで見通せます。


小天狗岩を降りて再び山頂を目指します。後ろ姿は同行した高知新聞記者・森本さん。
1,131.4Mの山頂へ

山頂までもう一歩。

密とはほど遠い世界で、マスクをとって新鮮な空気を深呼吸できる環境です。


山頂に到着!

山頂に立つ1131.4Mの看板。

山頂には祠が鎮座しています。山神様がお住まいです。

こちらが山頂の天狗岩。

天狗岩に立って臨む土佐町。雲の下の雄大さが伝わるでしょうか?

ここからが帰り道。ちゃんと「帰路」と出ていますので迷いようがありません。

以上、笹ヶ峰往復報告でした!今回は撮影しながらの往復でしたので2時間半ほどかかったのですが、登山口からまっすぐ山頂を目指せば小1時間ほどで踏破できる距離です。
途中危険な箇所は皆無です(天狗岩から踏み外さないように気をつけてください)ので、低山トレイルには最適な山のひとつです。