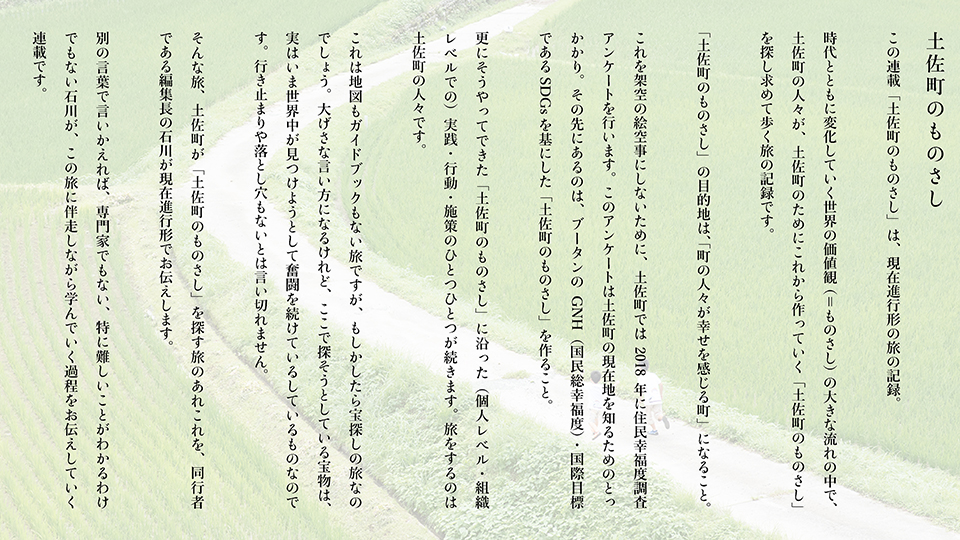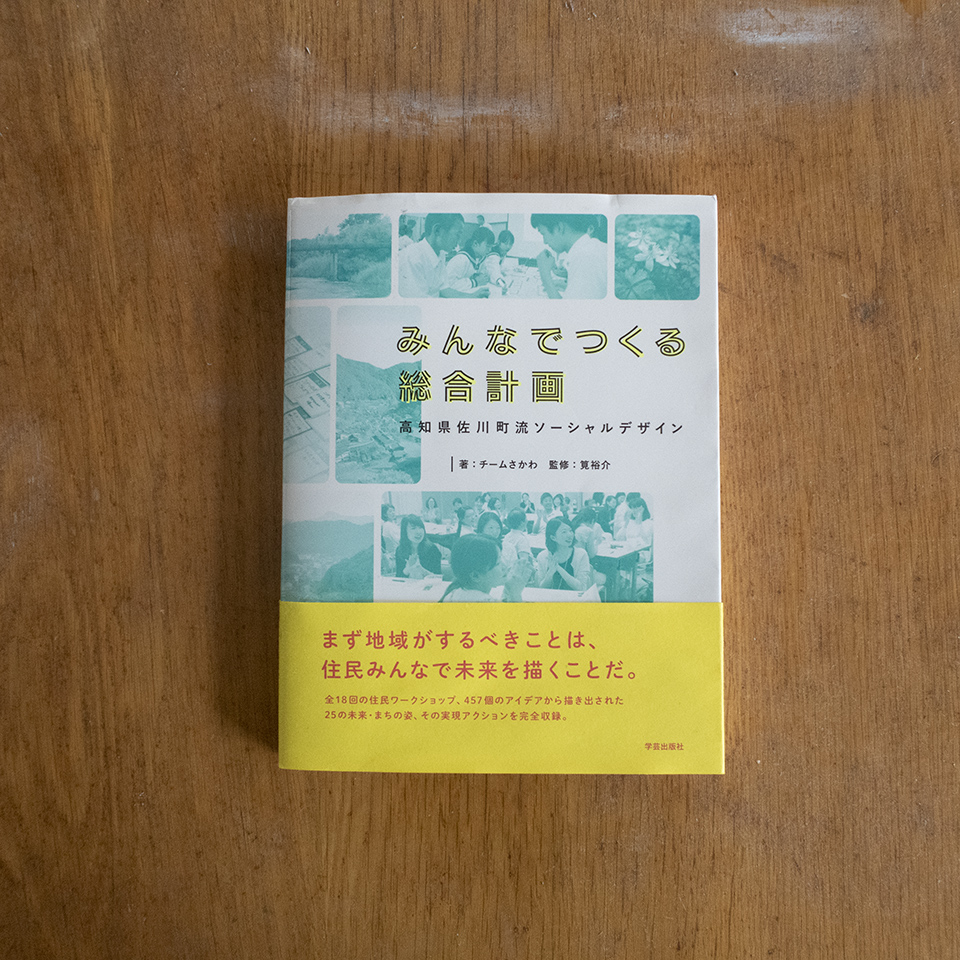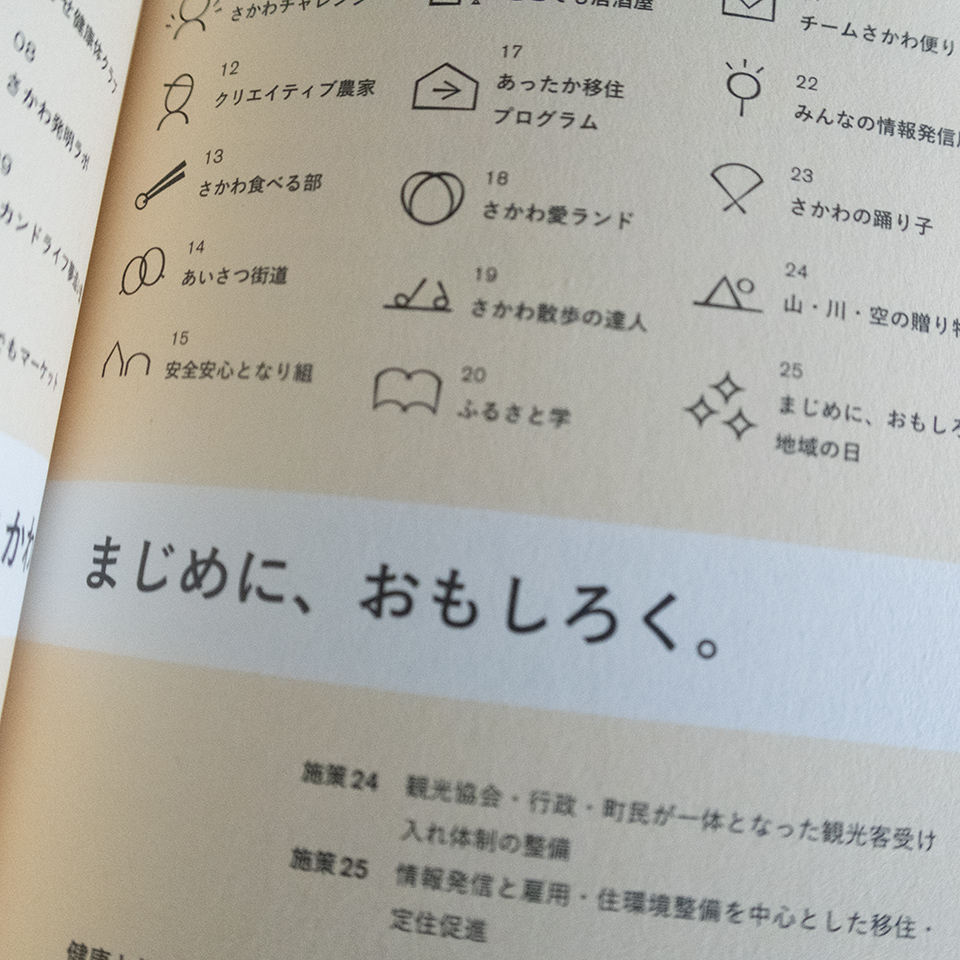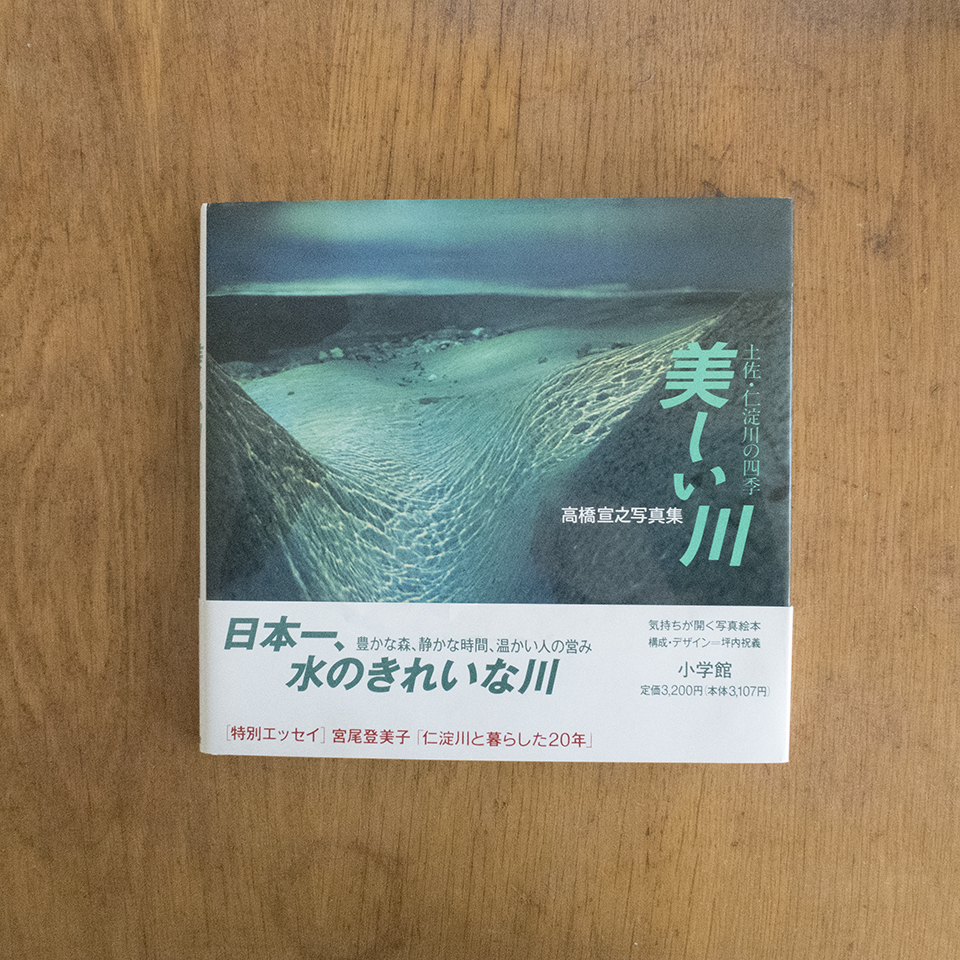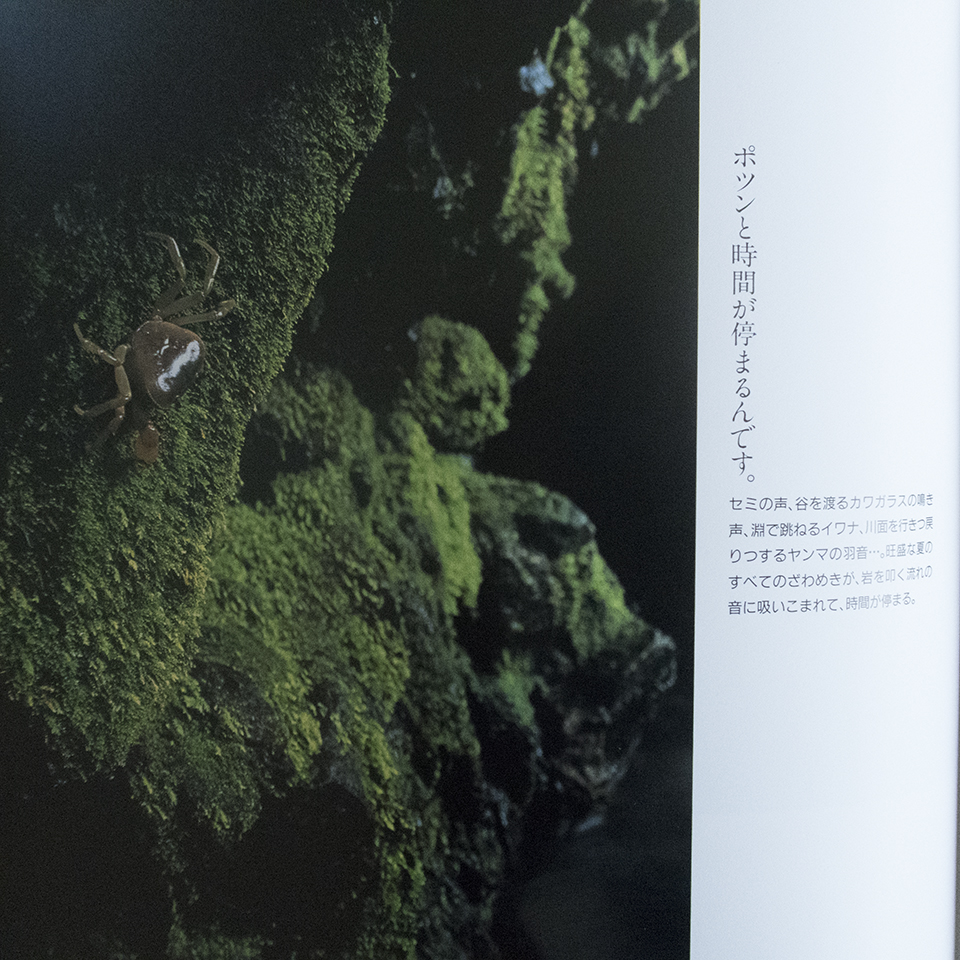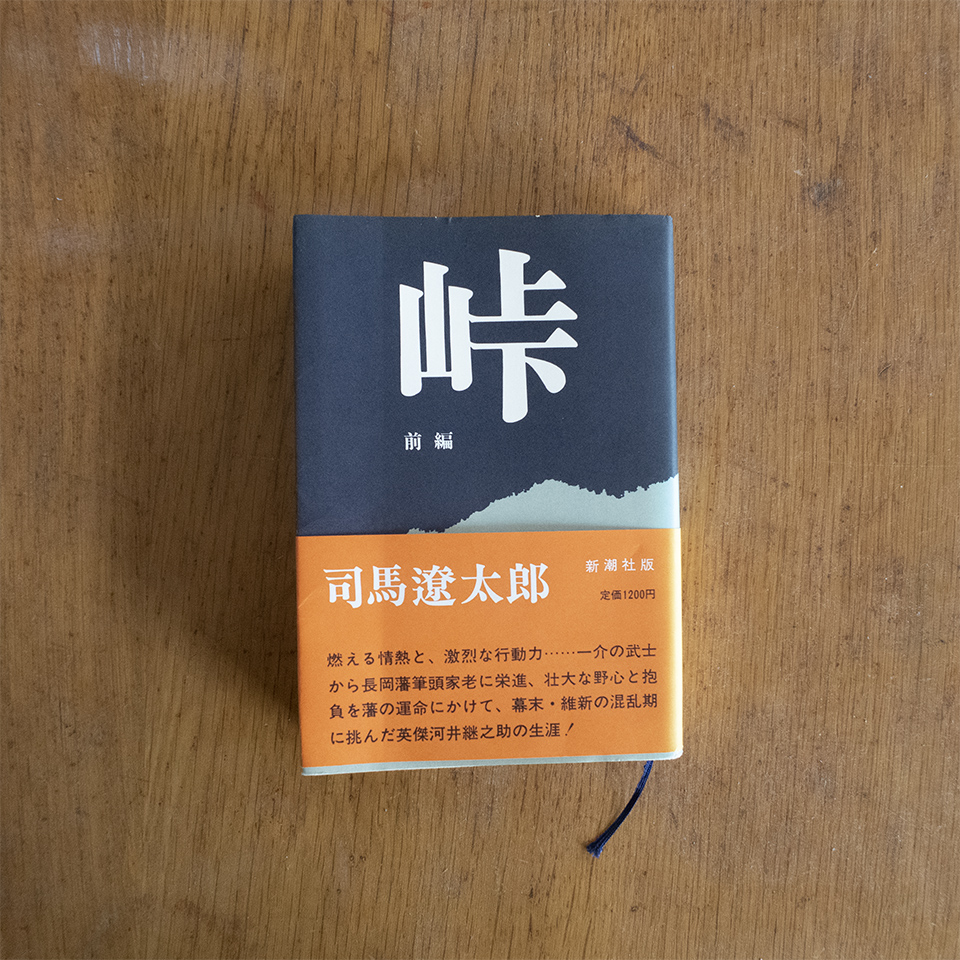以前からお知らせしていたように、現在土佐町では「土佐町が目指すべき幸福」の形を顕にすべく、その第一歩目とも言える住民幸福度アンケートの内容を作成中です。
土佐町役場の各課にも意見を求め、よりバランスの取れた、少しでも本質的な部分に迫れるようなアンケート内容にするための作業が進行中です。
土佐町独自のアンケートが仕上がり、実施を行うタイミングも徐々に近づいて来ています。アンケートというのはたいがい面倒くさいものだということを重々承知のうえで、土佐町の今後10年を作っていく上で大事なステップ、実施の際にはみなさまのご協力をぜひお願いいたします。
この欄では、これまでブータンのGNHを中心に紹介してきましたが、今回はそういった話からさらに一段、階段を下に降りたいと思います。
つまり、
そもそもなんのためにGNHをやるのか?
そもそもなんのために幸福度調査アンケートをやるのか?
この二つはほぼ同じ意味ですね。
当たり前のことですが、土佐町役場は他の自治体と同じく、様々な仕事を行なっています。
自治体として基本的に必要なことから、時代に合わせた新規事業まで、それはもう本当にいろんな種類の業務があるわけです。
根本的なことを敢えて言えば、そういった事業のそれぞれを、人手もかけて税金もかけてやる目的というのはなんでしょう?
表面的な目的のことを言っているのではありません。根本的なところまで降りていって考えれば、おそらく目的はひとつだけ。どんな種類の事業であっても、目的はたったのひとつなのです。
それは
町の住民の幸せのため
ということ。
言葉を変えれば、「より住民が幸せに住める町にすること」が税金を運用している役場の唯一の目的であるとも言えるでしょう。
以下は幸福度による国づくりを進めるブータンに伝わる法典の言葉です。
もし政府が人々の幸福を創造できないとしたら、政府が存在する目的はない
If the government cannot create happiness for its people, then there is no purpose for government to exist.” – Legal code of Bhutan (1729)
政府(役場)は全住民の幸せのためにある。このことに異論のある人は、そうそういないでしょう。(いたらぜひご一報を!)
ただ、ここで問題になるのは「では全住民の幸せってなんなのサ?」という疑問。
そう、住民幸福度アンケートというのは、その疑問の解答を得るための手段なのです。「土佐町にとって、幸せとはこういうことだ」という土台をみんなで確認しましょう、そういう目的のもとやっていることなのです。意外性のないオチで、どうもすいません。

そうやって得た解答。「土佐町はこういうことを幸せだと思う」という解答を、今度は全ての事業や施策や行動に当てはめて考えてみる。
もしかしたら、やることが習慣化して目的を見失っているものがあるかもしれない。もしかしたら、やること自体が目的と化しているものもあるかもしれない。「住民をより幸せにする」という目的から外れて、お金(経済)の問題に終始しているものもあるかもしれない。
いったん表面的な部分から階段を降りて、より根本的な価値観を当てはめてみる。そのためのアンケート調査です。