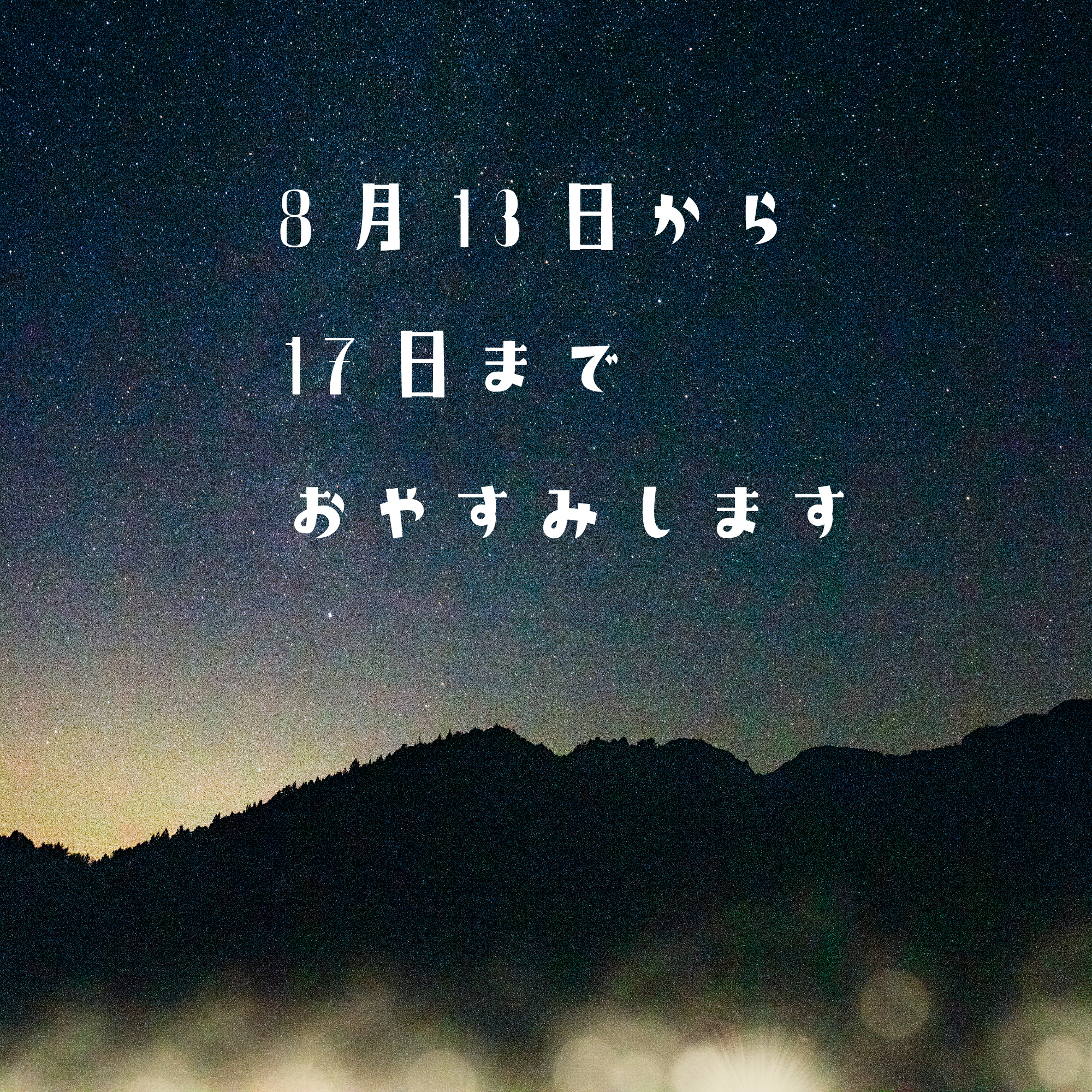がいに
【形容詞】強く
例文:壊れるき、がいに触ったらいかん!
意味:壊れるから、強く触ったらいけないよ!
著者名
記事タイトル
掲載開始日
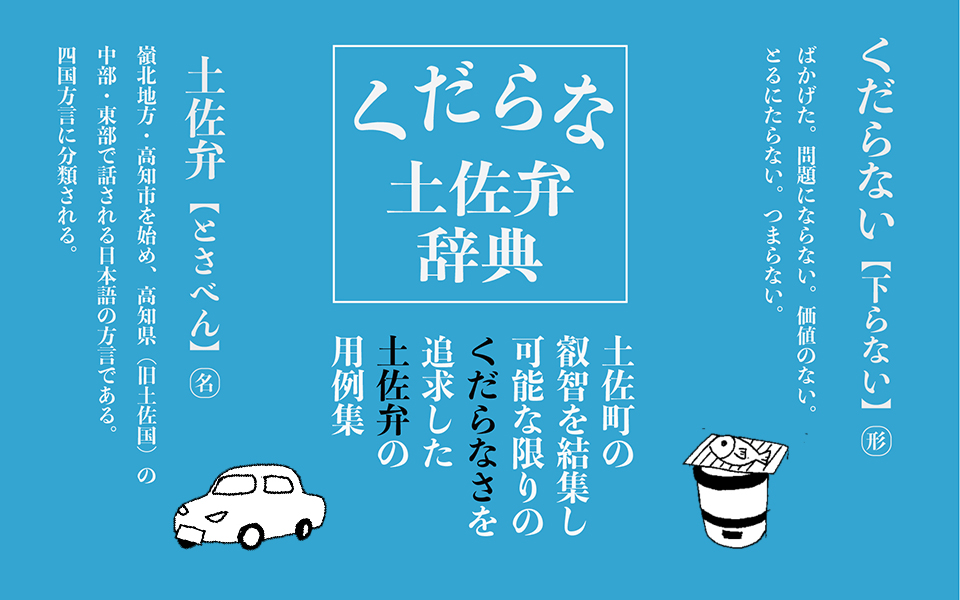
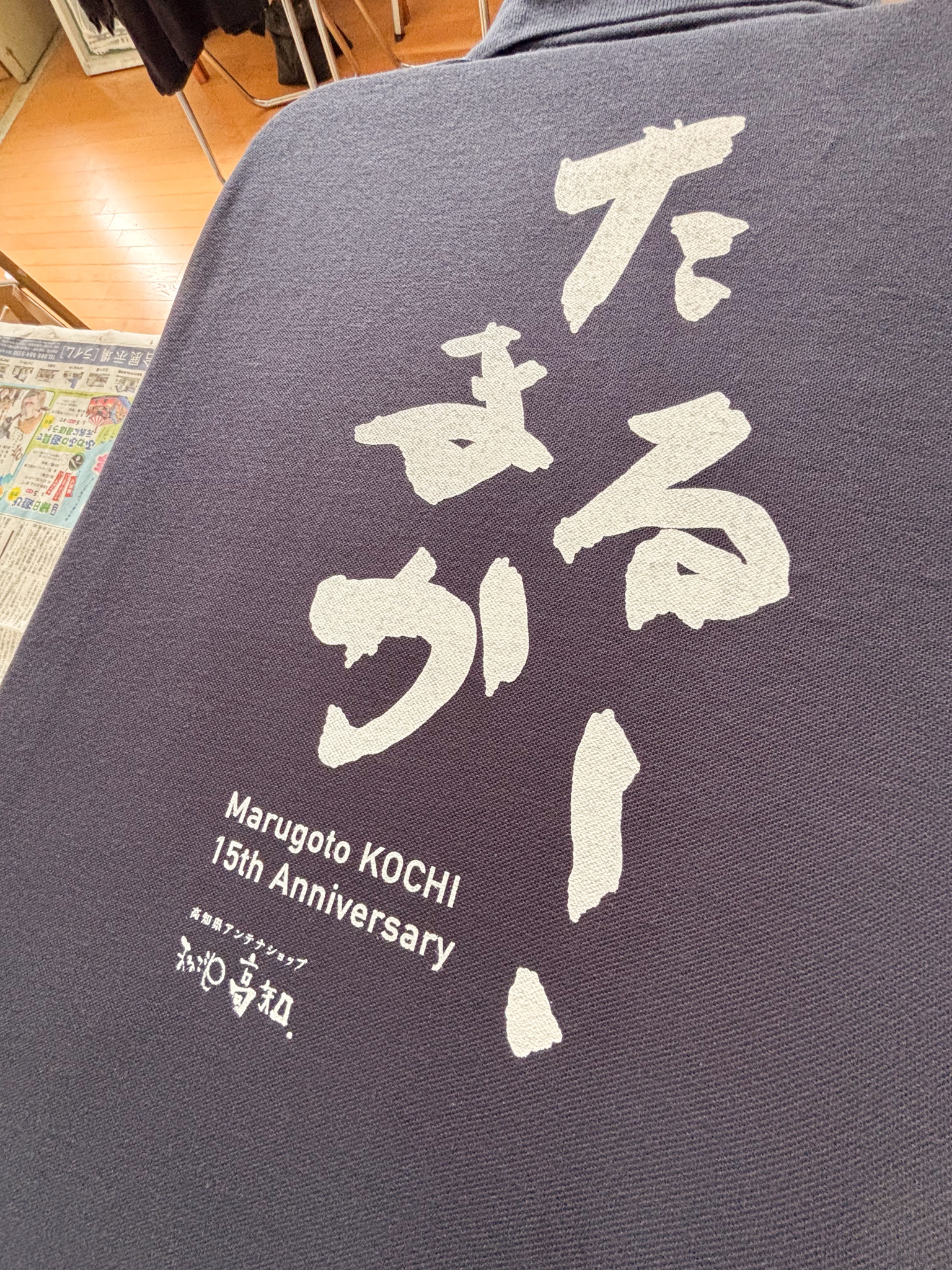
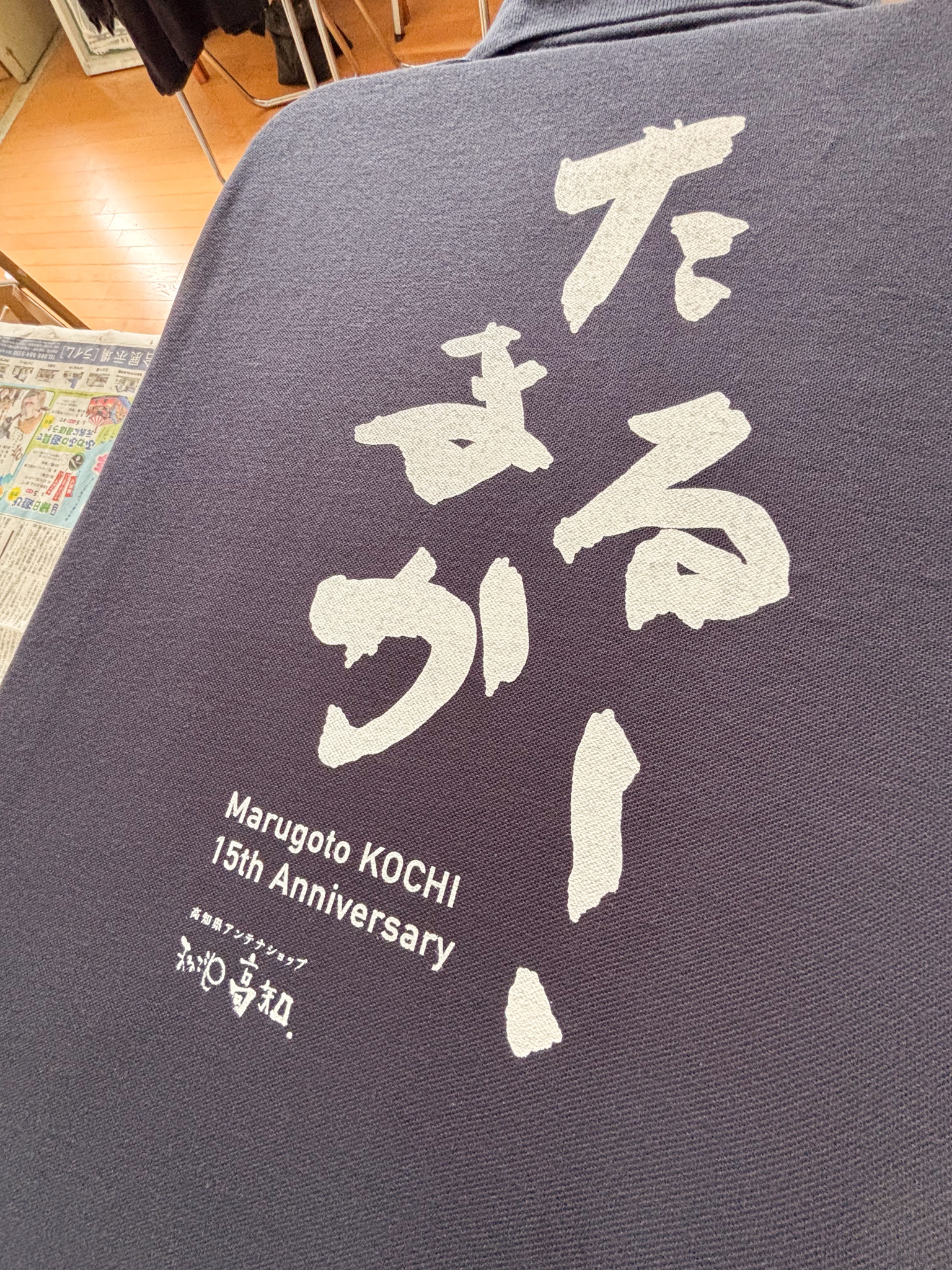
土佐弁「たまるか」。
現在放送中の朝ドラ「あんぱん」でも、たびたび登場する土佐弁です。
たまるか!デザインは3種類です。

上から インディゴ,サンドカーキ,ブラック。サイズはS~Lサイズ。
↑どんぐりの石川寿光さんと川井希保さんが印刷
↑ワークセンターファーストの大尾剛さんが印刷。
胸と背中のデザインを一枚ずつ丁寧に、順番に仕上げていきます。

制作したものが誰に届いているか、誰が喜んでいるのか。作っておしまいではなく、作った先が見えることは、大きなやりがいや喜びにつながります。
土佐町の方からも「たまるか!Tシャツ、欲しいんやけど」というお問合せもありました。
「たまるか!」
土佐弁の深い味わいが、多くの方に届きますように。まるごと高知15周年、誠におめでとうございます。
15年という月日を積み重ねることには並々ならぬご苦労や涙、そしてかけがえのない喜びや笑顔があったことと思います。