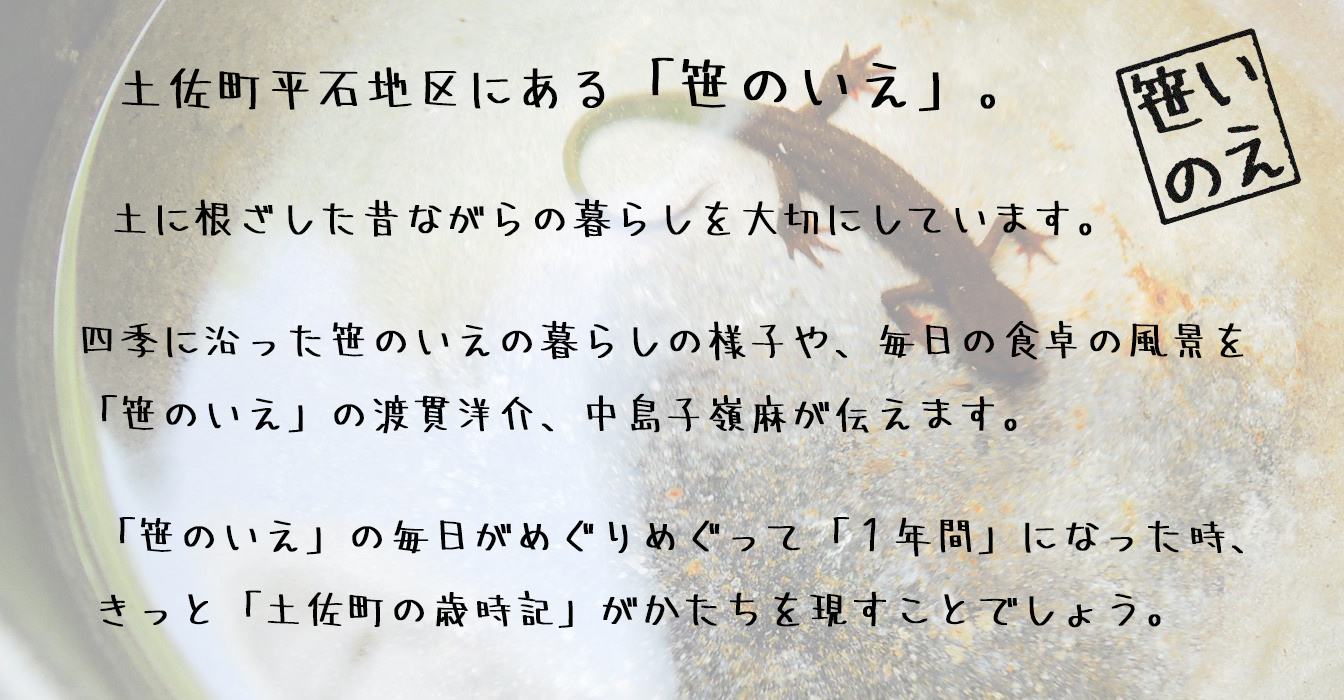母屋から風呂とトイレの小屋を挟んで、二階建ての建屋がある。
かつて、一階を牛小屋、二階を子供部屋として使っていたそうだ。その佇まいから、僕らはなんとなく「蔵」と呼んでいた。
たいそう大きな建物で、使われている材も立派。柱は五寸以上のものもあるし、棟木は一抱えもあるような松の木だ。
正確な築年数は不明だが、50年以上経っているだろう。重機などの機械が現代ほど発達しておらず、人力に頼る部分が多かった時代に、これだけの材木を製材し、運び、家を建てるのはちょっと想像しづらい。
しかし、人が住まなくなってから何年も放置され、僕らが引っ越してきたときにはだいぶ傷みが進んでいた。朽ち落ちた材には錆びた釘が打ってあったり、雨風で瓦が落ちてきたりすることもあり、子どもが近くで遊んでいることを考えると、なるべく早く壊す必要があった。
業者に頼み、機械の力で一気に壊す手もあった。でも、材を取り外して再利用したい、無理なら分別して後処理をちゃんとしたいと思っていた。そして、なぜかこの蔵に対する畏怖の念のようなものを持っていた僕は「自分の手で丁寧に解体したい」とも考えていた。とはいえ、作業には危険を伴うし、解体なんてしたことのない、しかも高いところが大の苦手の僕がひとりで作業するモチベーションもない。どうしようどうしようと思いつつ、4年が経った。
ふと思いついて、知り合いの左官さんに相談してみると、どうにかやってみよう、というありがたい返事が来た。彼に棟梁をお願いしたのは、慎重で無理をしない人柄に安全第一に作業を進めてくれると確信していたからだった。なにより、これまで土壁や釜戸つくりなど一緒に作業して、気心が知れている。
友人二人にも声掛け、はたして作業ははじまった。
まずは屋根から。
足元の悪い瓦の上を踏み抜かないように歩きながら、瓦を落としていく。
状態の良いものは積んで取っておき、割れたのは軽トラに積んで、隣町の処分場へ何往復もして運んだ。
瓦の下に敷かれていた土はそのまま地面に落とし、必要なら後で田畑に入れる。ルーフィングの役目していた大量の杉の皮は焚き付けに使う。建具も外し、ストックする。
そして、いよいよ構造材が露わになった。
年月によって建物自体が歪んでいるし、腐っている箇所もあるため、どういう順番でどの材を外していくか、ひとつひとつ確認しながら作業する。ときにチェーンソーで材を切り、ときにロープで柱を引っ張りしながら、少しずつ建物が細く小さくなっていく。
驚いたのは、木が保つ粘りだ。
ボロボロの建屋だったが、ホゾで組まれた材は、加わった力を四方に逃がすようになっていた。四人以上の大人がロープで引っ張っても捻ってもビクともしない。前述したように、可能なら材を綺麗に取り外したいと思っていたが、材自体が重いこと、がっちりと組まれているため手で外すのは困難なことがわかってきた。結局、安全を一番に、材の再利用は諦め、解体を進めることにした。
五日間の作業の末、どうにか無事に終えることができた。目の前には、たくさんの材が山となった。二三年は焚き物に困らなさそうだ。無事故で解体させてくれた蔵に、皆で感謝した。
在来建築の構造や技術に感心したり、驚いたりすることが多かった。昔の大工さんは、木の性質を理解し、材となった木の上下や微細なねじれさえも考慮し家を建てたそうだ。プレカットが主流の近代建築とはだいぶ異なる。また、験(げん)を担いだり、山や家の神様にお祈りをして作業の安全を願った。蔵に触れながら、当時の空気を吸っているような、タイムスリップしたような不思議な感覚を覚えることがあった。