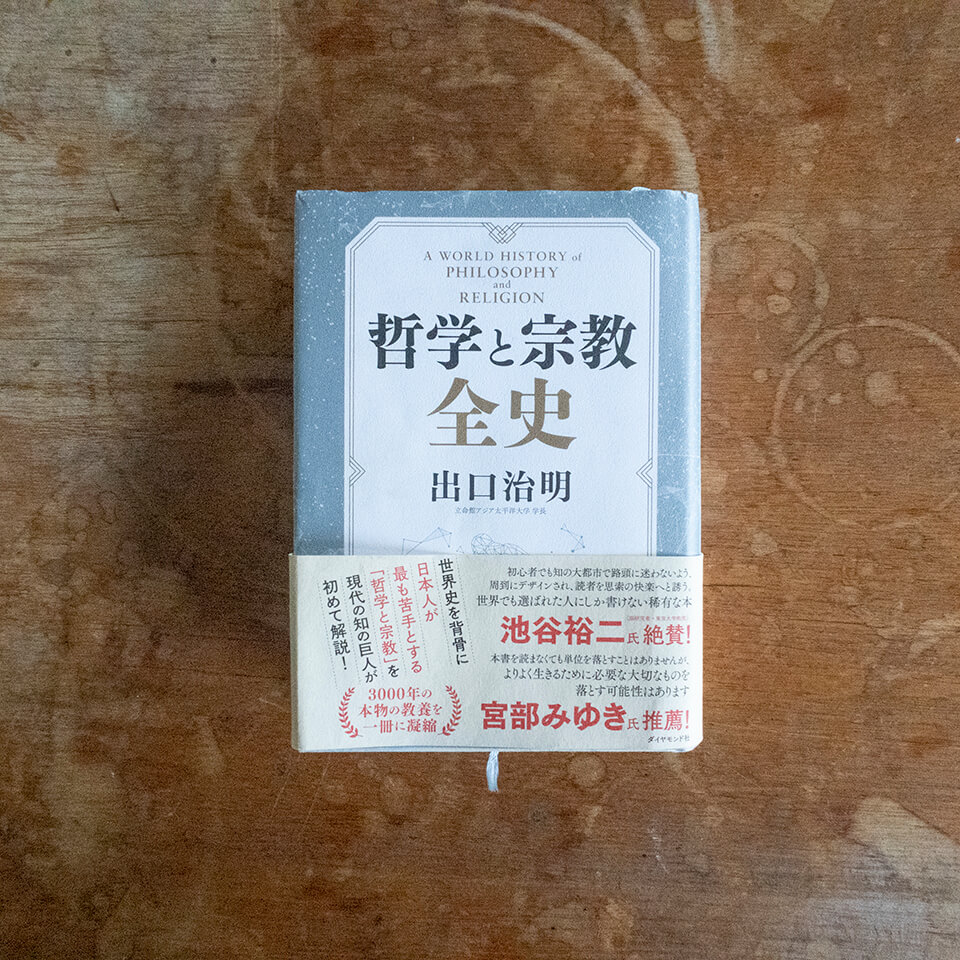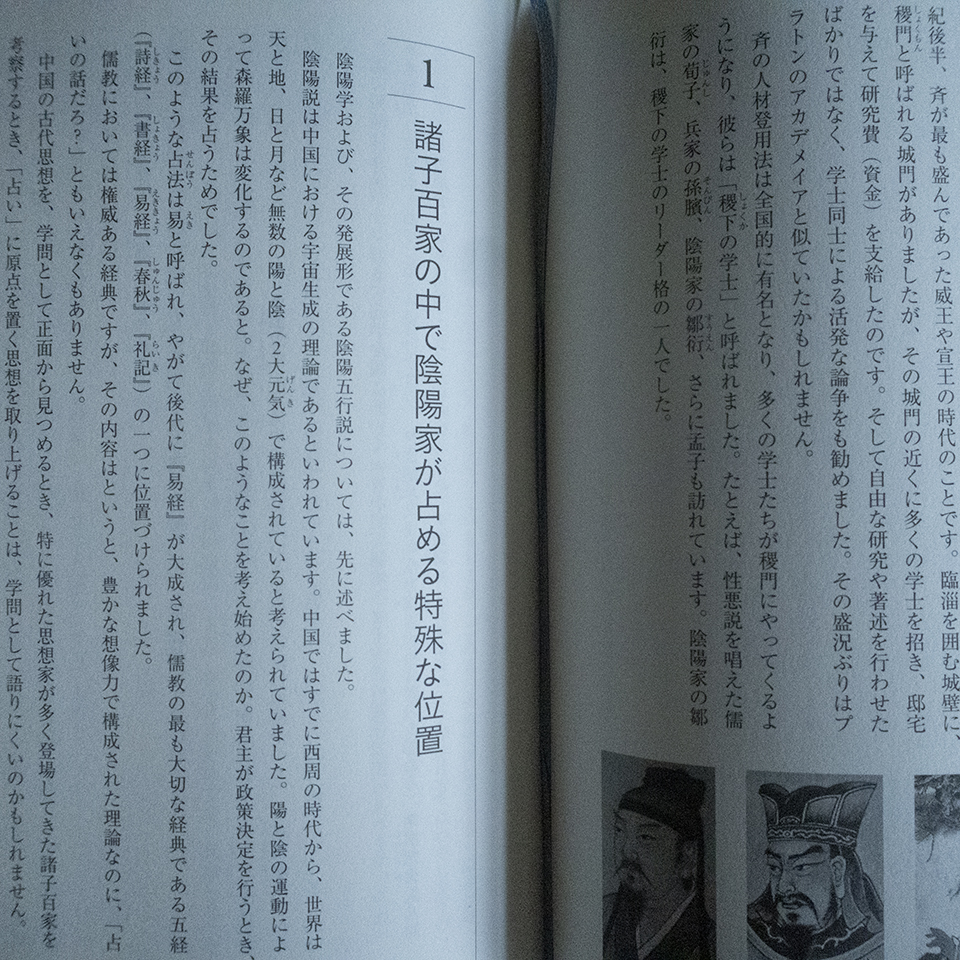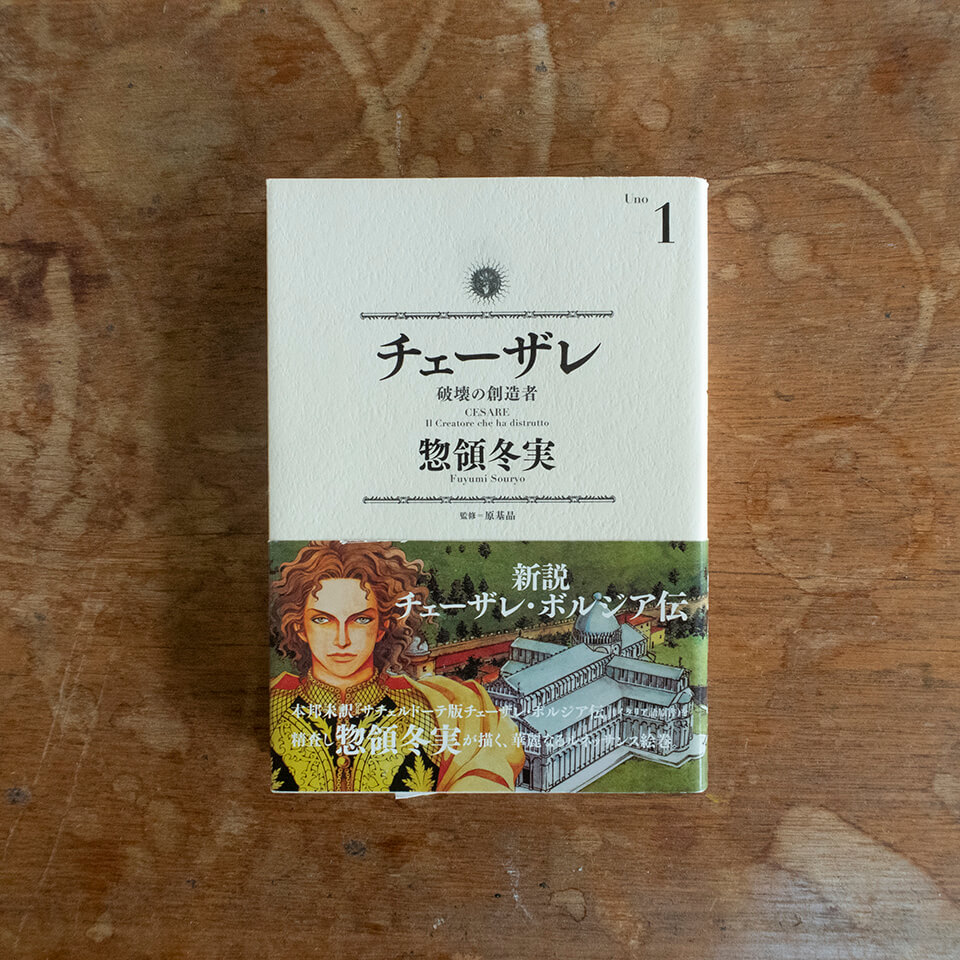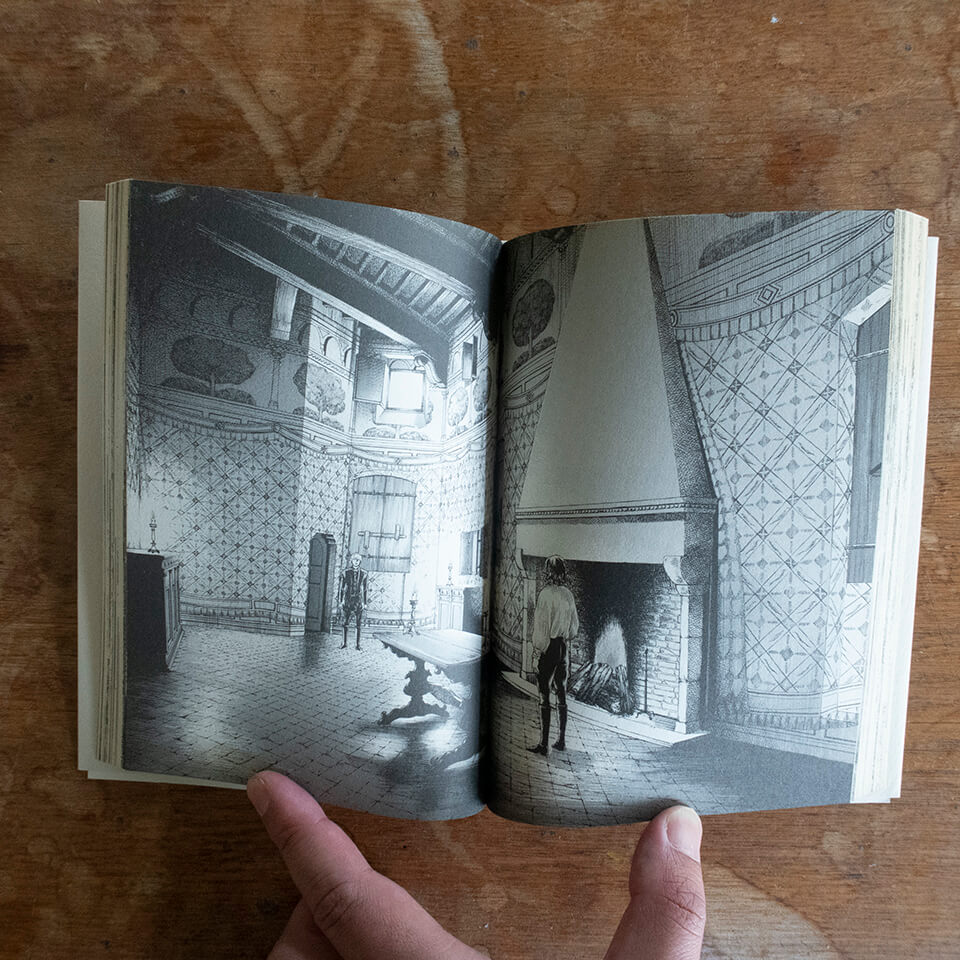7月20日に発行した「とさちょうものがたりzine 06」。おかげさまで多くの方々から反響、感想などいただいております。
06号は「とさちょうものづくり」と題して、これまでの取り組みをご紹介した号になっています。今回の記事は、その06号に掲載した文章です。シルクスクリーン事業の根本的な目的などに触れた「仕事のことお金のこと」(著:石川拓也)です。
縦糸と横糸
とさちょうものがたりには様々な事業が同時進行している中で、全てに共通している根本があります。
それはこれまで土佐町で紡がれてきた「物語」の続きの一部であろうすること。
歴史の中で辿りようもないぐらいはるか以前から、この地で暮らしてきた何世代にも渡る人々の営みが現在の土佐町を作ってきました。
おじいちゃんやおばあちゃんの世代、またその前の世代と、時代は違えどそのときそのときの町の人々の小さな営みのひとつひとつが、現在の土佐町を作ってきたと考えています。
その小さな営みの膨大な積み重ねのほんのわずかな表面に、現在という時間があるということは、土佐町の地面、田んぼや石垣などが与えてくれる実感です。
とさちょうものがたりはその「物語」をできるだけ深く理解した上で、その物語にきちんと接続した小さな「新しい物語」を繋げることを目的のひとつとしています。
深く、さらに深く土佐町の地面につながっていくこと。そこから芽生えてくる物語を大切にすること。
それがとさちょうものがたりの「縦糸」です。
対してとさちょうものがたりの「横糸」は、同時代を生きる人々との繋がり。
特に現在の土佐町に生きる人々ときちんと繋がり、できるだけお互いを理解した上で、力を合わせて共に仕事をしたい。
さらに多くの周りの人々を少し笑顔にするために、地域の人々とお互いに持てる力を出し合って一つの仕事を完遂していく。そのことが自分たちの笑顔も作っていく。それがとさちょうものがたりの横糸です。
縦糸と横糸、この両方がバランスよく揃ってとさちょうものがたりの全体が編まれていく。そんな思いがとさちょうものがたりの活動のひとつひとつの根底に流れています。
商売が商売であること
これもとさちょうものがたりがとても大切にしていることのひとつです。
特にシルクスクリーン事業に関してはこれを可能な限り徹底しようとしています。「商売が商売である」とはどういうことか?
これは町で商売や事業をしている方々にとっては当たり前の単純明快なこと。
①ものを作る。②販売する。③その代金を関わった人たちのお給料にする。④利益を遣って次の材料や機材を仕入れる。⑤さらに良いものを作る。 そして①〜⑤の繰り返し。
自分たちがきちんと稼ぐためには、まずお客さんを喜ばすこと。お客さんがお金を払って「ほしい」と言ってくれるものを作っていること。その単純明快な論理の中に踏みとどまって良い仕事を続けていくこと。
それがとさちょうものがたりが考える「商売が商売である」ということです。
地域で作る。自分たちで作る。
とさちょうものがたりのシルクスクリーン事業のスタートは、「地域の自分たちで作れるものは自分たちで作ろう」という思いからでした。
都会の業者さんにお願いした場合には地域外に流れていくお金を、自分たちで作ることで地域外に逃がさないようにするということ。そうしてできた仕事に、仕事を必要としている地域の人が取り組み実現させていくということ。さらにこういった仕事のひとつひとつを、たとえ不器用でも着実に完遂していくことで、仕事をする人々だけでなく、仕事をお願いしてくれる地域の人々にも、その経験値が蓄積されていくということ。
そうした一方通行ではない、相互に生きた経験を積み上げるほどに、関わってくれる地域の方々との間に理解が深まっていくのを実感します。
お金を稼ぐことの本質
主に地域の方々のおかげで、シルクスクリーン事業は年間約1,000点~1,200点の商品を製作し販売することができています。ざっとした言い方になりますが、これは単純計算で約250~300万円の売上になります。
そこから人件費や材料費・機材費などをまかなっています。シルクスクリーンの作業に必須の乾燥機・プレス機などは売上を少しずつプールした上で購入しています。インクなどの材料代や、Tシャツやポロシャツなどの仕入れ代もこの売上を循環させる形での購入です。 もちろん、どんぐりやファーストのメンバーさんの賃金もこの売上から。年間約80万円前後が賃金として支払われます。
この事業にとって、お金は最終的な目的ではありませんが、目的に到達するためのとても大切な一要素。際限の無い右肩上がりの成長を目標としている訳でもなく、この事業にとっての「適正サイズ」であることが大事と考えています。
目的は目の輝き
全ての仕事、全てのものづくりの目的は、関わるすべての方々の目の輝き。もしくは笑顔、と言い換えてもかまいません。「すべての方々」は共に仕事をする人々、関心を持って応援をしてくれる町の方々、もちろん購入していただくお客さん、文字通り「すべての方々」です。
「商売が商売である」仕事には多少なりとも失敗するリスクが付きものと思いますが、(例えばシルクスクリーンでは仕入れたTシャツをミスしてダメにすることが時にあります)そのリスクを乗り越えて世の役に立つものを作れた時に、本当の意味で仕事の価値や喜びや誇りが培われるのだと思います。
その少しのリスクを自分たちの力で解決して、お客さんが必要とするものを作ることができた時に、本当の意味での目の輝き、本当の意味での笑顔が見れるのだろうと考えています。
とさちょうものがたりの様々な事業で関わってくれている全ての方々が、本当の意味での目の輝きを見せてくれること。それがとさちょうものがたりの仕事をする最終的な目的であると考えています。
その目的のために仕事がある。その目的のためにみんなで力を合わせて、一人では乗り越えられない問題を乗り越えていく。
「商売が商売であること」や「各人がお金をきちんと稼ぐこと」は、その目的に到達するための大事な手段。すべきことをきちんとやって、みんなで気持ちよく笑おうよ。それがとさちょうものがたりの基本的な姿勢です。