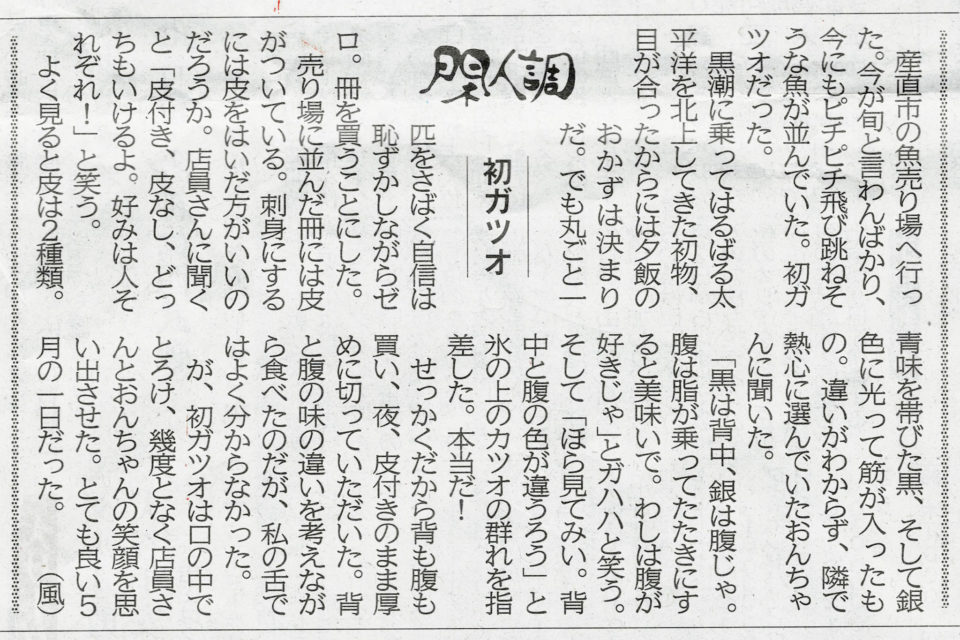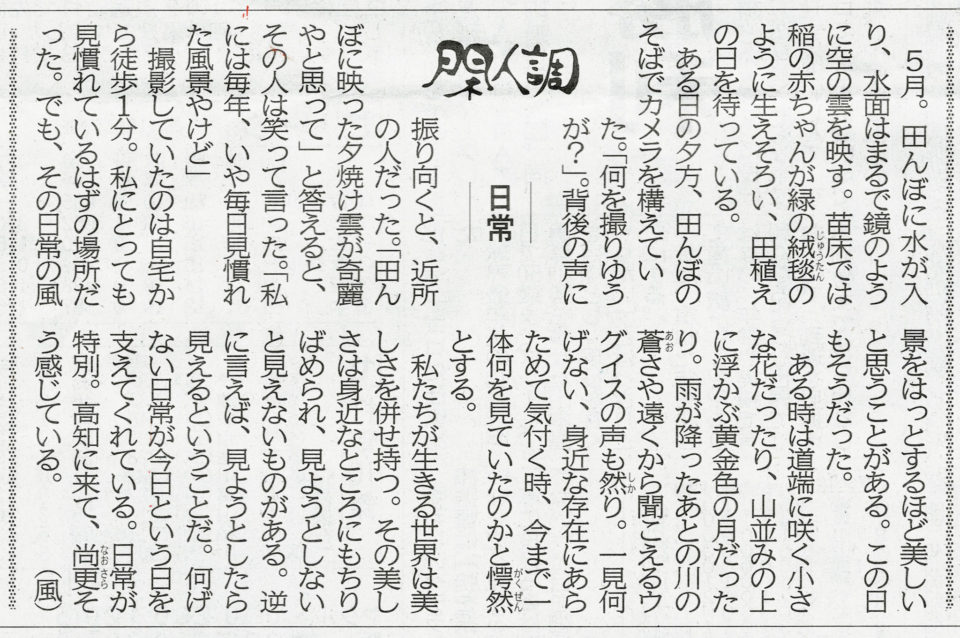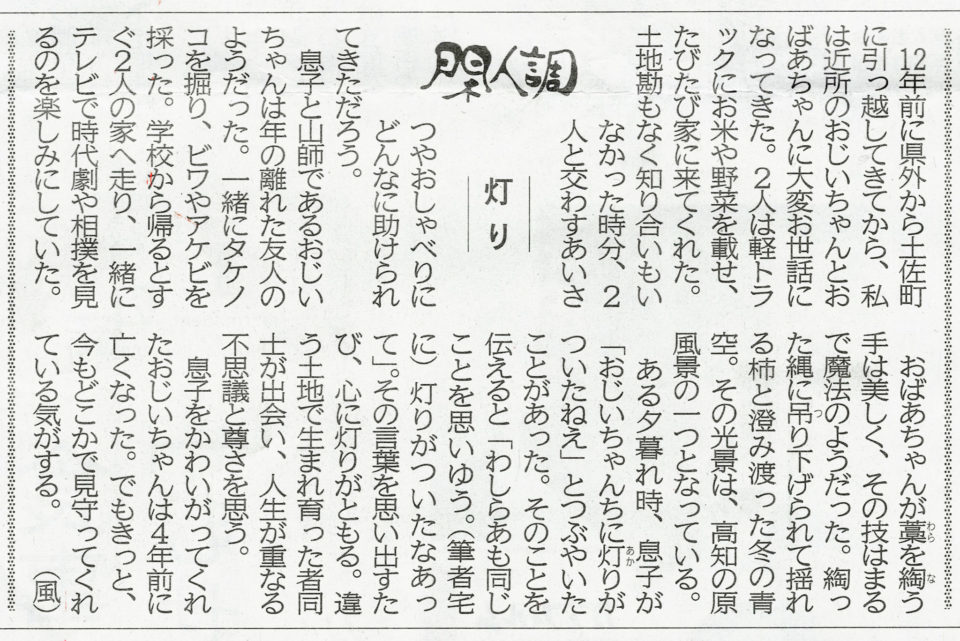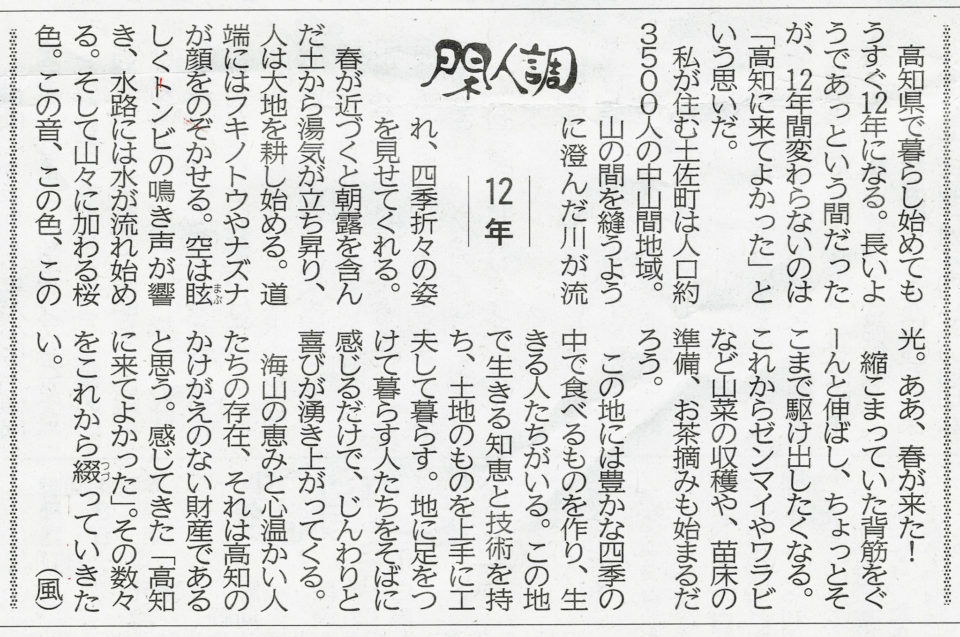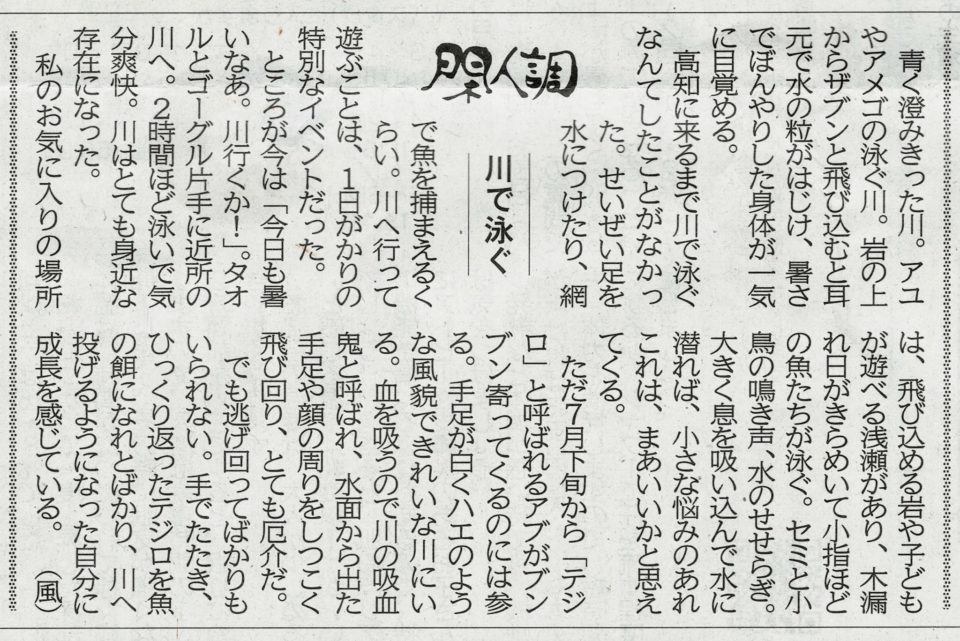
とさちょうものがたり編集部の鳥山が、2023年春より、高知新聞の「閑人調」というコラムに寄稿させていただくことになりました。
このコラムには数人の執筆者がおり、月曜日から土曜日まで毎日掲載。月初めにその月の執筆者の氏名が掲載され、コラム自体には執筆者のペンネームが文章の最後に記されます。
鳥山のペンネームは「風」。月に2回ほど掲載される予定です。
川で泳ぐ
青く澄みきった川。アユやアメゴの泳ぐ川。岩の上からザブンと飛び込むと耳元で水の粒がはじけ、暑さでぼんやりした身体が一気に目覚める。
高知に来るまで川で泳ぐなんてしたことがなかった。せいぜい足を水につけたり、網で魚を捕まえるくらい。川へ行って遊ぶことは、1日がかりの特別なイベントだった。
ところが今は「今日も暑いなあ。川行くか!」。タオルとゴーグル片手に近所の川へ。2時間ほど泳いで気分爽快。川はとても身近な存在になった。
私のお気に入りの場所は、飛び込める岩や子どもが遊べる浅瀬があり、木漏れ日がきらめいて小指ほどの魚たちが泳ぐ。セミと小鳥の鳴き声、水のせせらぎ。大きく息を吸い込んで水に潜れば、小さな悩みのあれこれは、まあいいかと思えてくる。
ただ7月下旬から「テジロ」と呼ばれるアブがブンブン寄ってくるのには参る。手足が白くハエのような風貌できれいな川にいる。血を吸うのでかわの吸血鬼と呼ばれ、水面から出た手足や顔の周りをしつこく飛び回り、とても厄介だ。
でも、逃げ回ってばかりもいられない。手でたたき、ひっくり返ったテジロを魚の餌となれとばかり、川へ投げるようになった自分に成長を感じている。
(風)
2023年8月4日に高知新聞に掲載されたコラム「閑人調」です。タイトルは「川で泳ぐ」。
夏、子どもたちに何度も「川に行きたい!」とせがまれます。そう言われたら「よっしゃ、川行くか!」といそいそと水着に着替え、タオルとゴーグルを持って、近所の川へ。車で10分もしないところに、お気に入りのきれいな川があるなんて、なんて幸せなことでしょう。
岩から飛び込んだり、浮き輪でぷかぷか浮いたり、浅瀬に座ってぼんやりしたり、満足するまで遊んだら、家に帰ってアイスを食べる。これ、最高。
本当は、夏休みの間ずっと川で遊びたいのに7月下旬からはテジロが出現。いつも行く川にテジロが出ると、もっと川の下流で泳ぎますが、やっぱりいつものあの川が最高だなと思うのです。