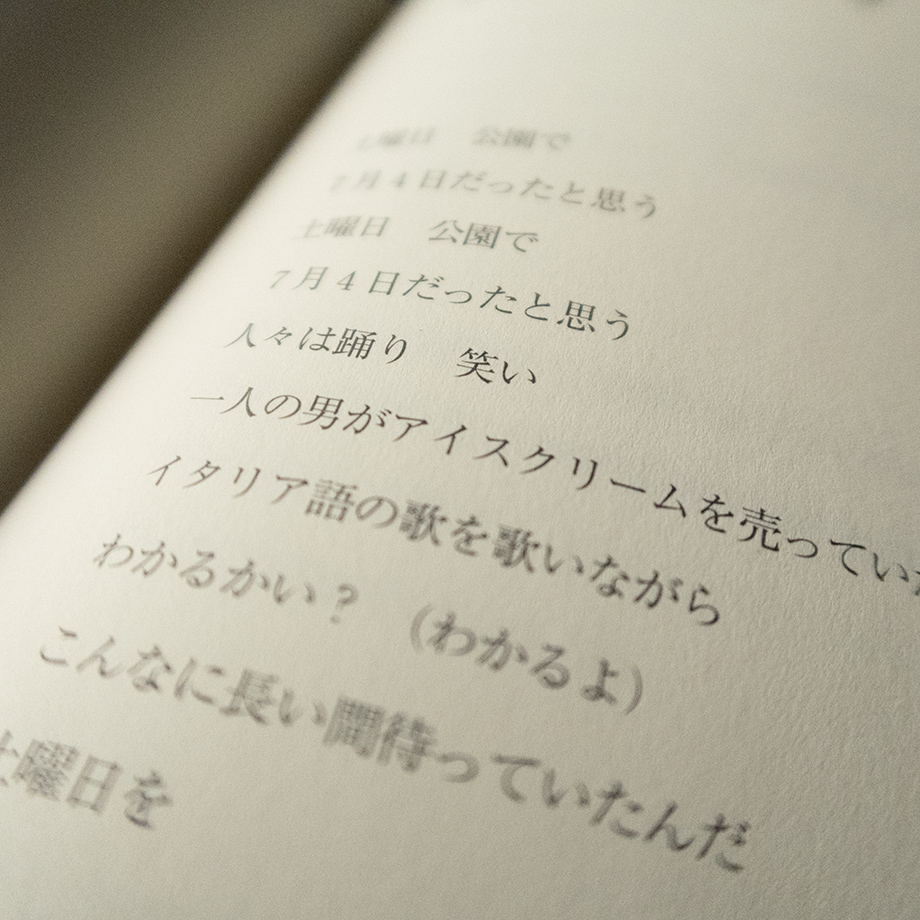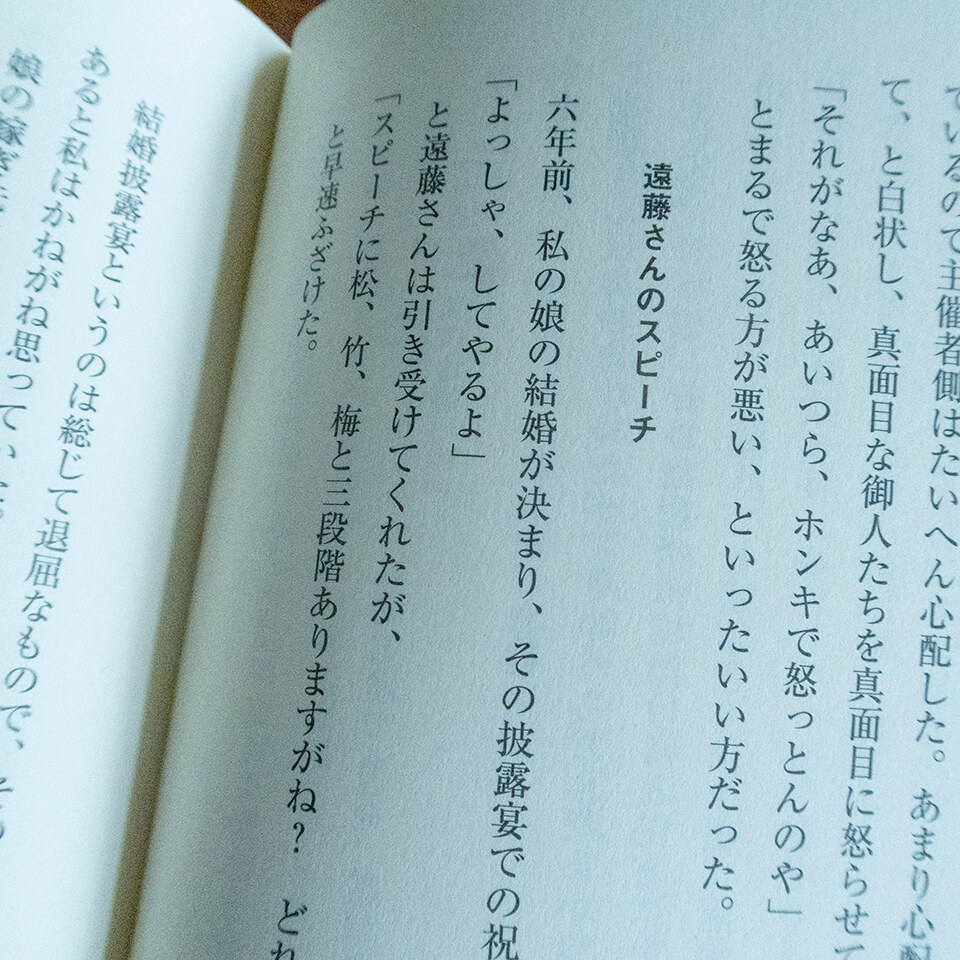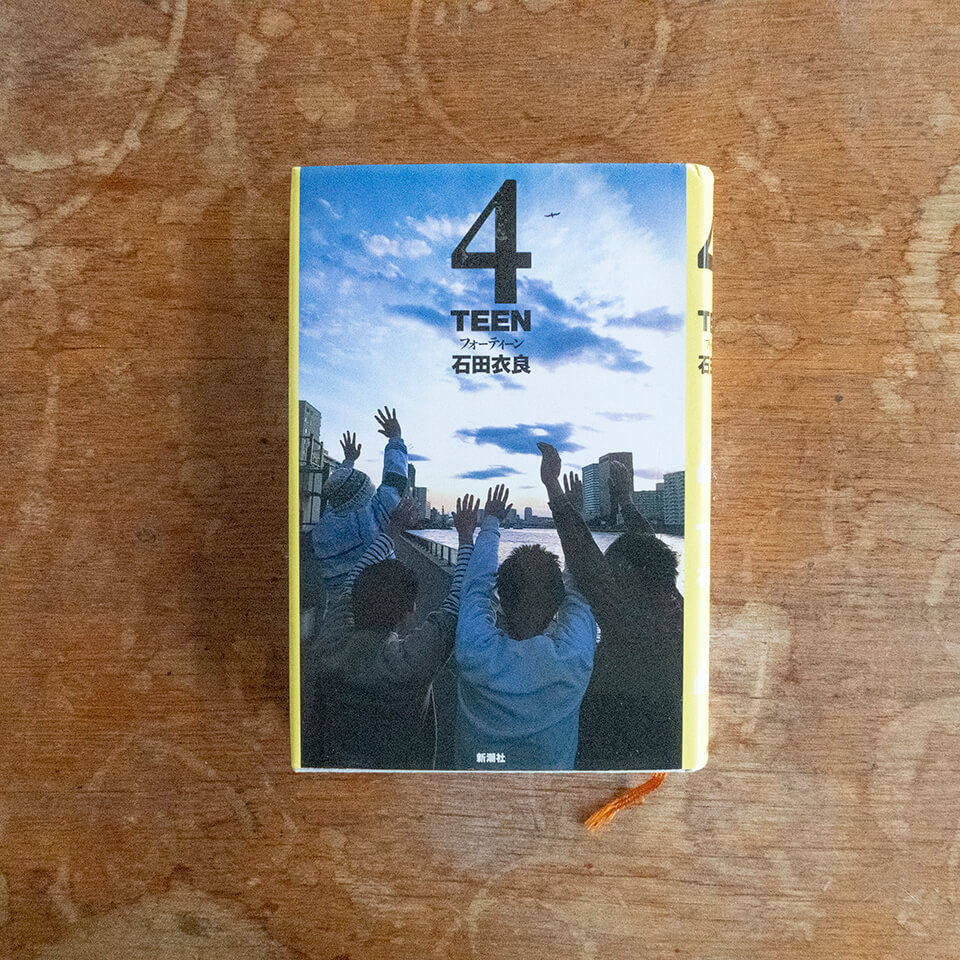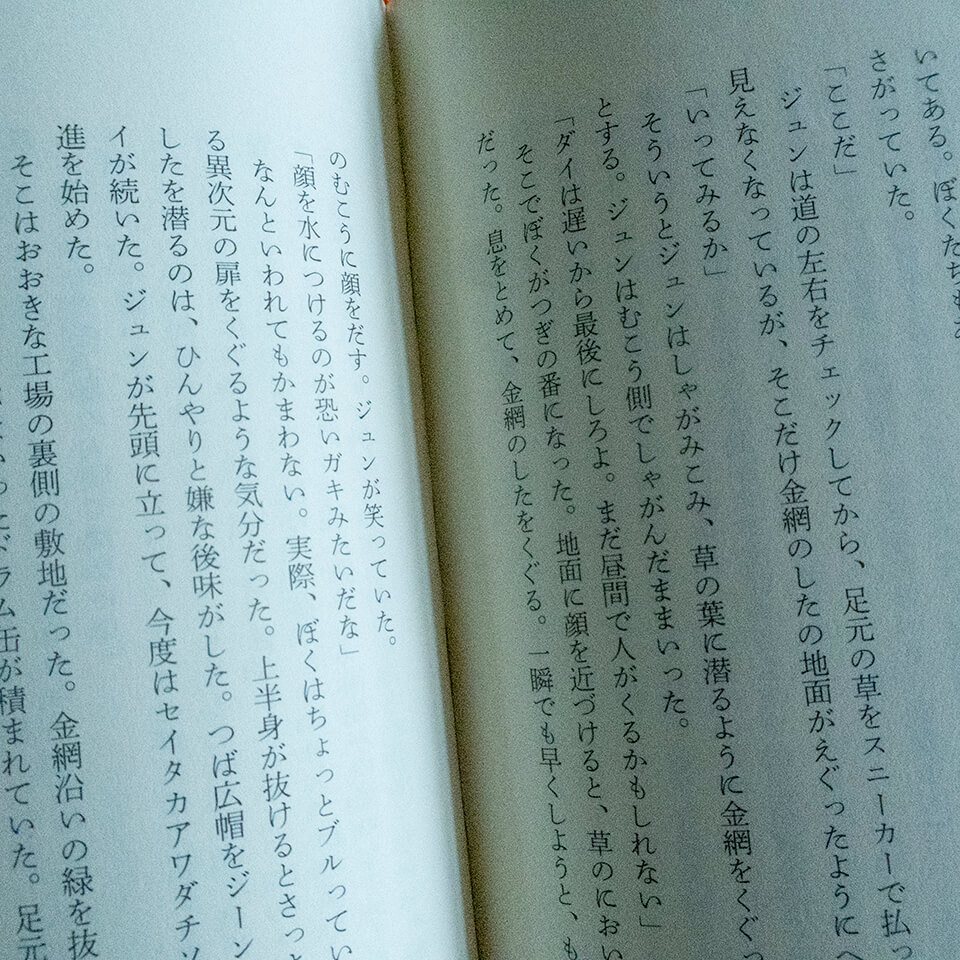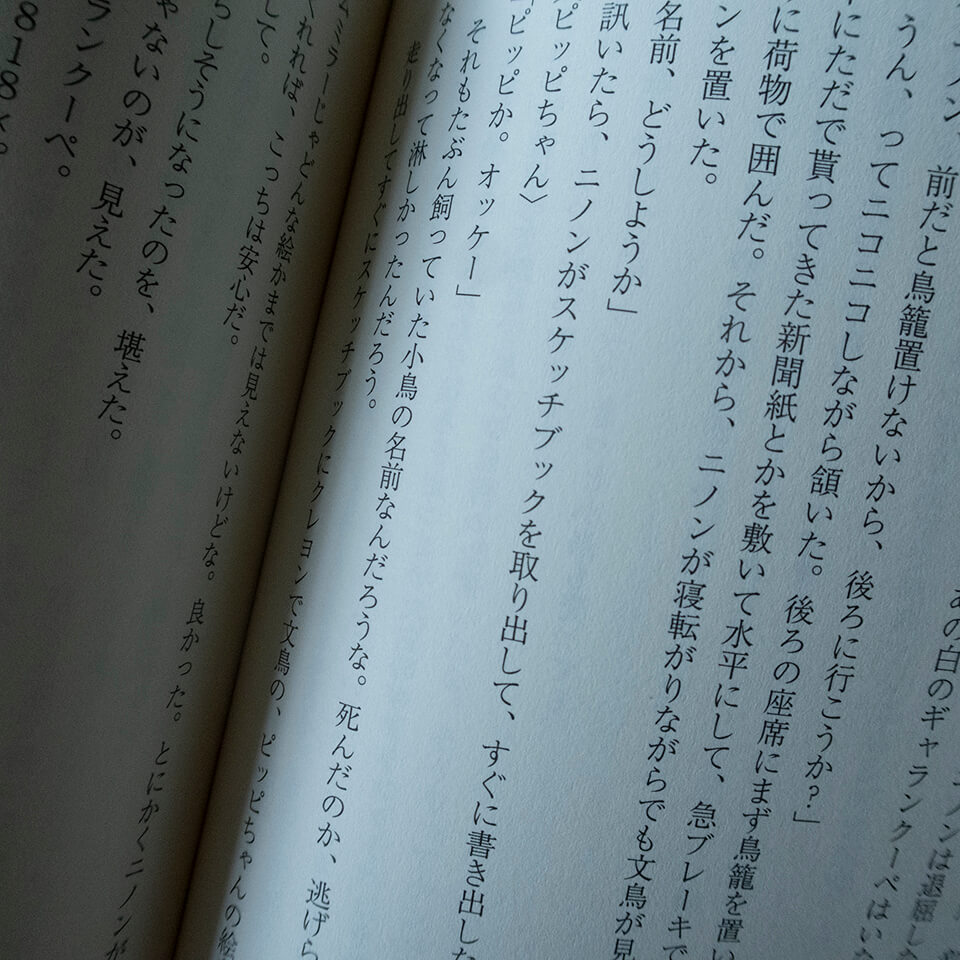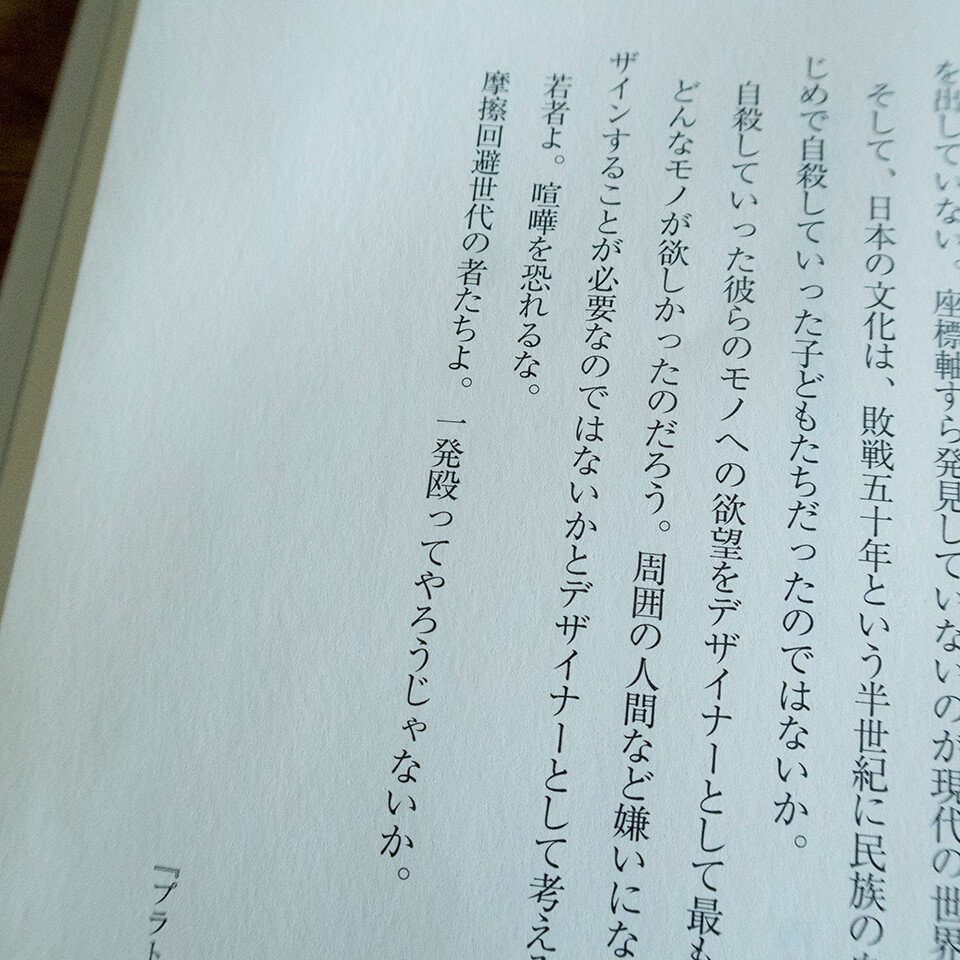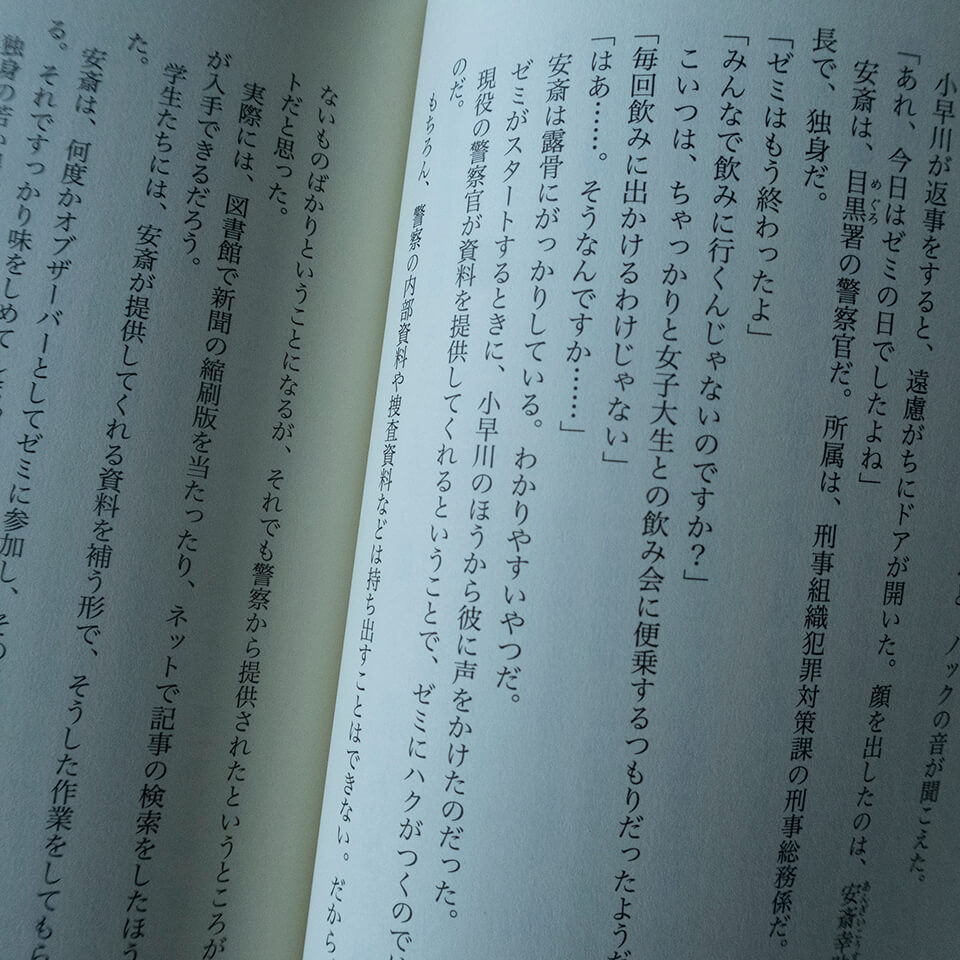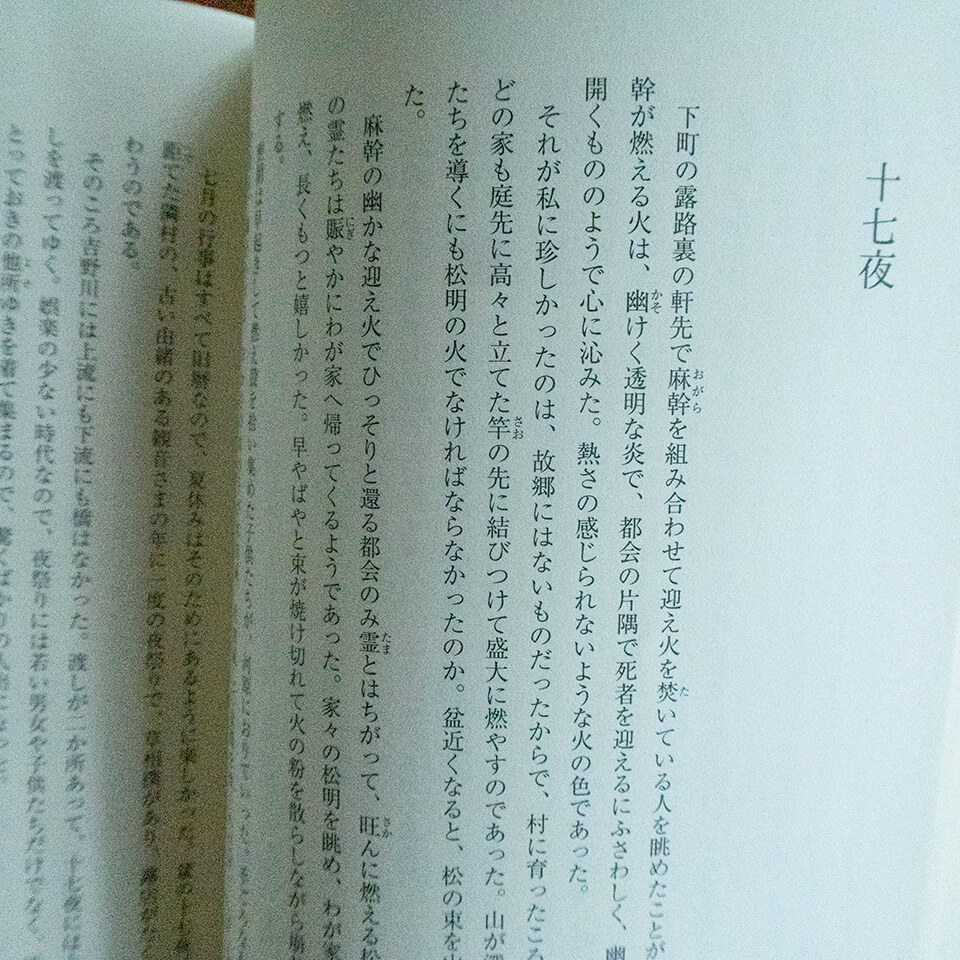
「ふるさとの丘と川」 大原富枝 飛鳥出版室
土佐町の隣町である本山町出身の作家・大原富枝さんが、ふるさとを描いたエッセイと随筆がまとめられている一冊です。
この中に「十七夜」というお話があります。「十七夜」とは、土佐町にある中島観音堂の「中島観音夏の大祭」のこと。昔からそう呼ばれ、親しまれてきたその名を題として、大原さんは次のように書いています。
「盆の十七夜は吉野川を距(へだ)てた隣村の、古い由緒のある観音さまの年に一度の夜祭りで、草相撲があり、露店がたくさん出て賑わうのである。
そのころ吉野川には上流にも下流にも橋はなかった。渡しが二か所あって、十七夜には上流の方の渡しを渡ってゆく。娯楽の少ない時代なので、夜祭りには若い男女や子供たちだけでなく、近村中の者がとっておきの他所ゆきを着て集まるので、驚くばかりの人出になった。
渡し場は足もとが危ないので十七夜はたちまち月の出るのを待って渡る。渡し舟は岸に沿ってずっと上流まで漕ぎのぼってから、流れの早い真中に出て流されながらいっ気に向こう岸につく。幼い私はこわくて身体を固くしていた。
観音さまの境内でみかん箱の上にあがった村の青年が、政談だったか恋愛論だったか演説をぶっているのを、私はびっくりして口をあけて見上げていた。」
この本は、大原富枝文学館にお勤めの大石美香さんが貸してくださいました。
大石さんは、中島観音堂で撮影された土佐町のポストカードの写真を見て、「大原富枝さんの随筆に『十七夜』というのがあって、こちらの観音様のお祭りが出てきます」と連絡をくれました。ひとりずつ、ひとつずつに思えていた人とものごとが、まるで最初からそうなることが決まっていたかのように繋がっていく様はいつも私を驚かせ、この世の不思議さと尊さを教えてくれます。
まだ吉野川にかかる橋がなかった時代、中島観音堂の石階段に揺れる提灯のやわらかな灯りを大原さんも見つめていたことでしょう。昔の風景の一片を知ることは、昔と今がたしかに繋がっているのだということをあらためて思い出させてくれます。