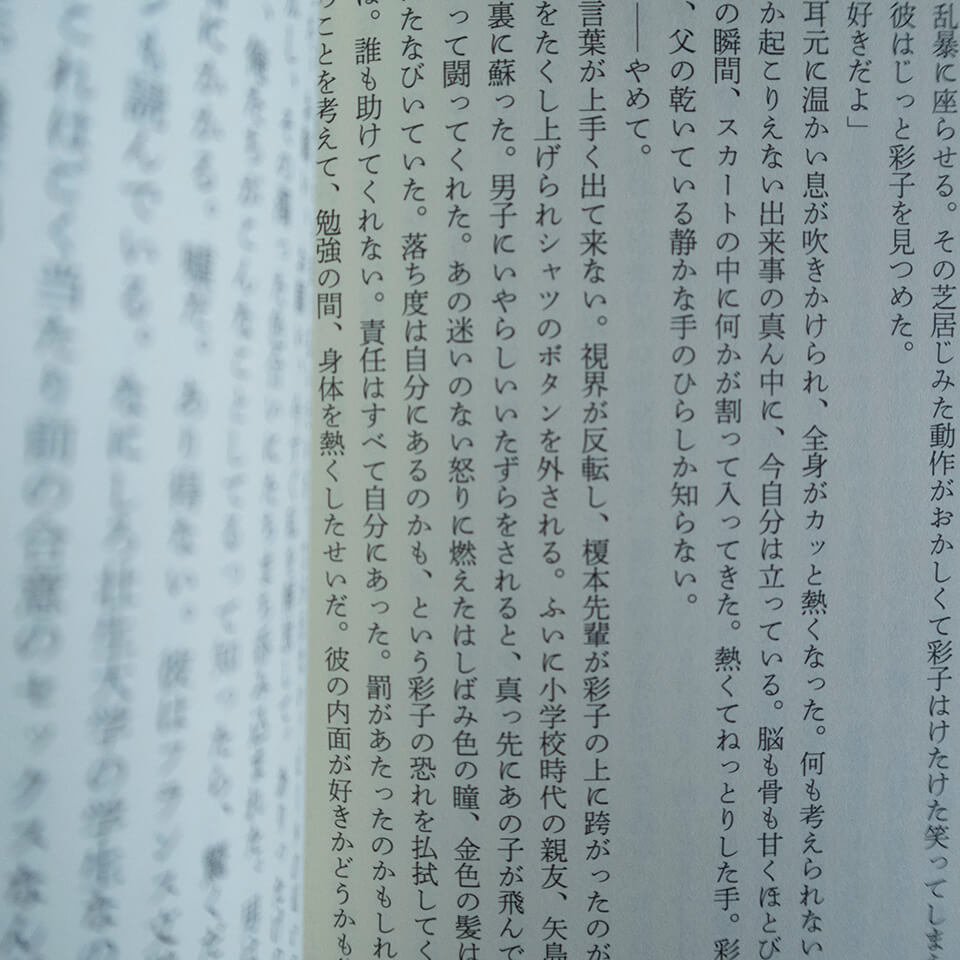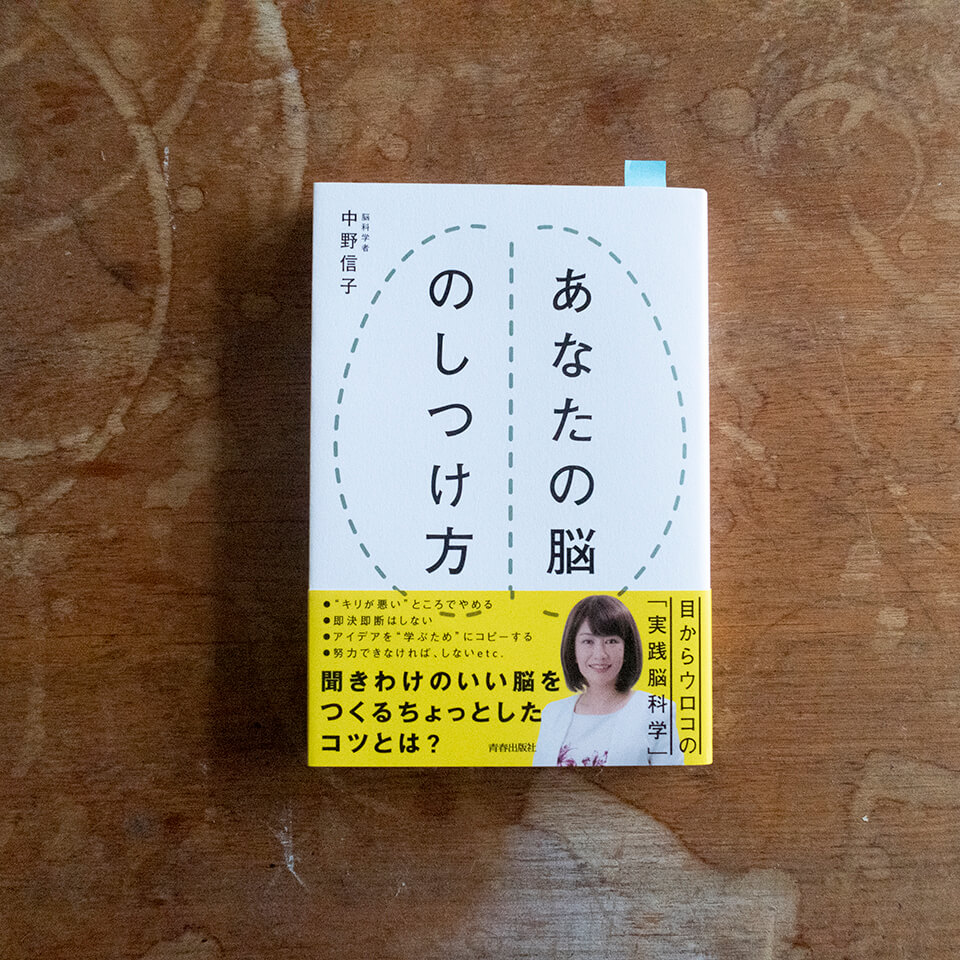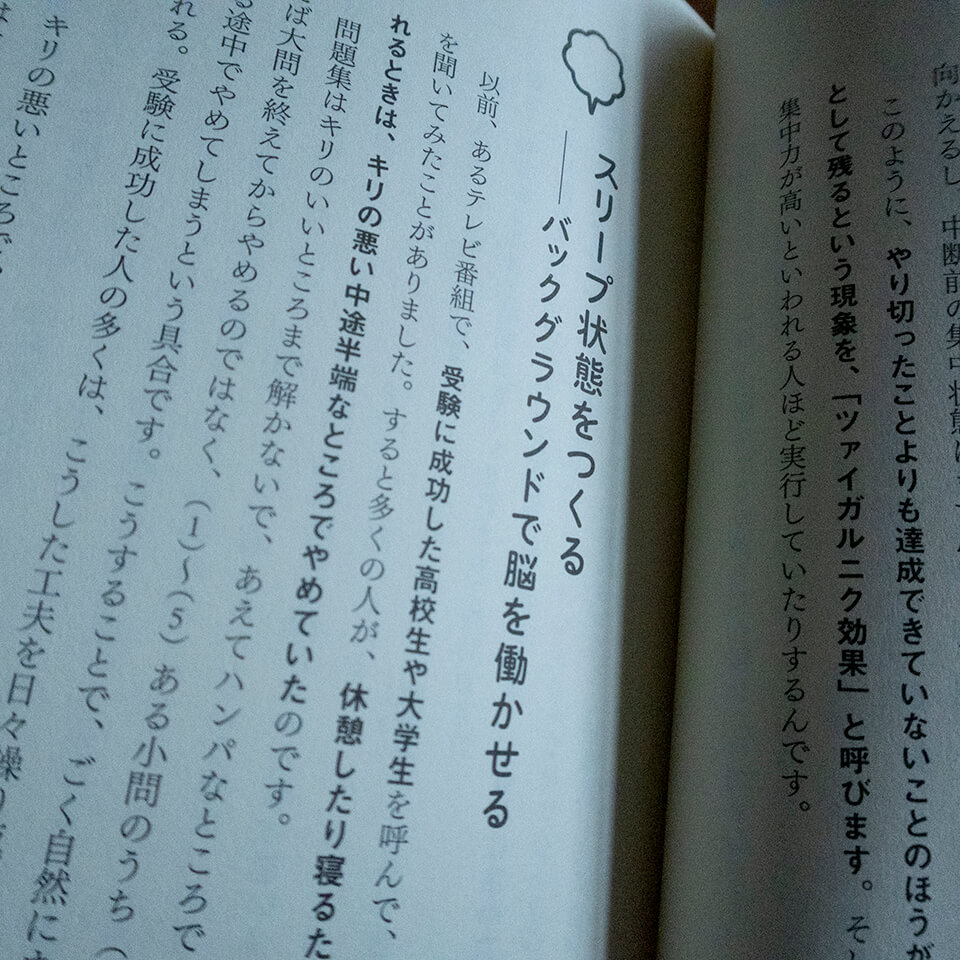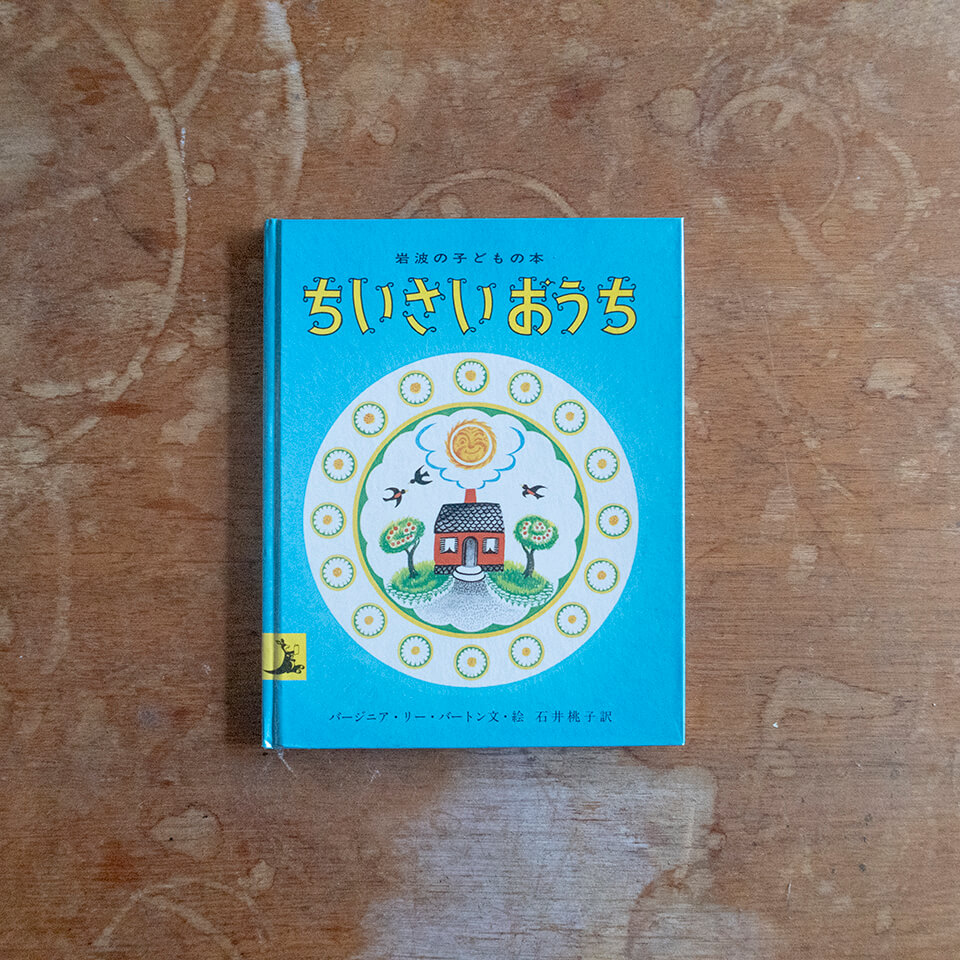一つの傷あとを見るたびに、もう70年以上も前のことが鮮明に浮かんでくる。
小学校6年生だった昭和19年(1944)の夏休みのある日。金突鉄砲を持って、川へアメゴを突きに行った。
走って行く途中の道路で転び、硝子の破片で、左の手の平の、親指の付け根あたりを切った。驚くほど血が出たので、右手でそこを押さえながら、一時は茫然としていた。
少し痛みと出血がおさまって川へ行き、傷を洗ってみると、思ったより深い。そのうちふと思い出し、いつもしているようによもぎの葉を摘んだ。それを右手だけで揉んで、汁を傷につけると、飛び上がるように痛かったが、血が殆ど止まった。
それを見ていて頭をよぎった思いは、家族はもちろん、近所の大人がこの傷を見たら、必ず医者へ連れて行かれ、医者は縫うだろうということであった。
そうなれば、治るまでは川に行くことを間違いなく止められる。それはいやだ。しかし、この傷ではやはり医者だろうか。一生懸命に“打開策”を考えた。その結果、金突鉄砲などの道具をひっ掴んで、家に駈け戻った。
祖父母と母は山仕事に行って、家には居ない。
早速、富山の置き薬の中から消毒薬を取り出して、傷口にかけた。血は出ていなかったが、川に居た時よりも開いていた。
そして縫針に木綿糸を通して、傷口を縫った。それまでにけがをして、村の医者に縫ってもらった時のことを思い出しながらであったが、当然そう簡単にいくものではない。
第一、生身に針を刺すのだから、痛さで涙が出た。それでも右手と口を使って糸を結びながら、5針縫った。縫ったあとは、妙に痛みがやわらいだことを覚えている。
包帯をすればばれるので、富山の貼り薬を傷にかぶせ、家では左手を握って、傷が見えないように細心の注意を払った。川にも時々行った。長時間水につけるのは避けた。
10日か半月ぐらいで、傷は治った。その間、誰にもばれなかった。
しっかりと肉が締め付けている木綿糸を抜く時は痛かった。はさみで糸を切り、それをピンセットで引き抜いた。痛みと共に血が出たが、大したことはなかった。
今、左の手の平の傷あとを見ると、その左右に、虫の足のように短い傷あとが出ている。それが縫ったあとである。70年以上の年数を経て消えそうなものだが、よほど不器用に縫ったのだろう。不器用なのは当然である。
生傷で川に入って、よく化膿しなかったものだと思う。その一方で、当時の川の水は、生傷にばい菌が入らないくらいにきれいだったろうか、とも思う。
その翌年、旧制の中学校に入学したが、同級生の中に
「俺も切り傷を自分で縫うたよ」
と言う友人が2人居た。