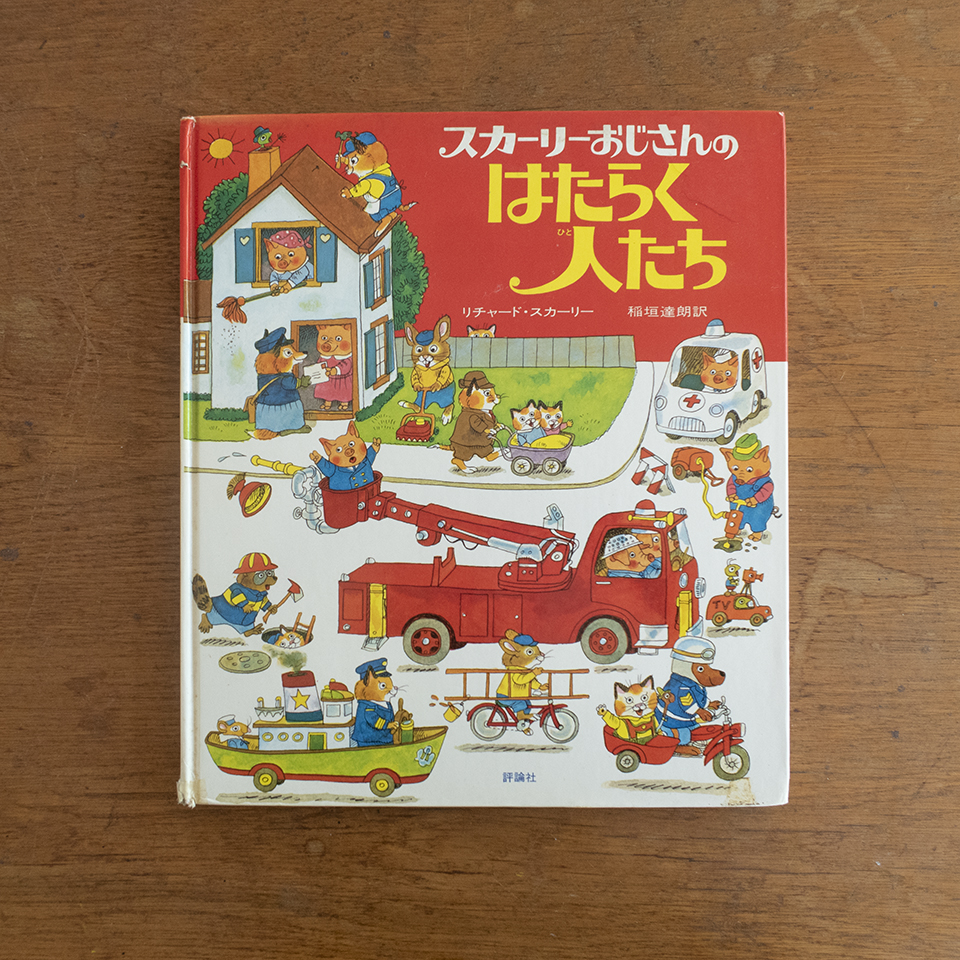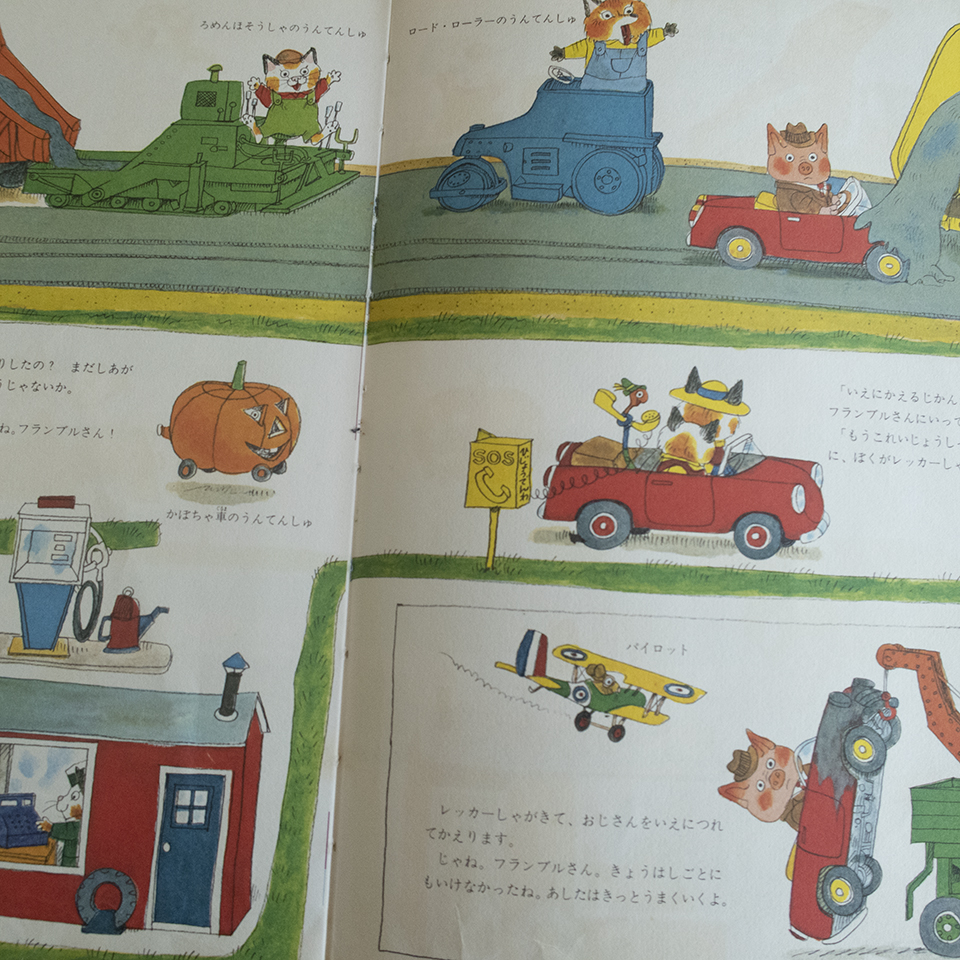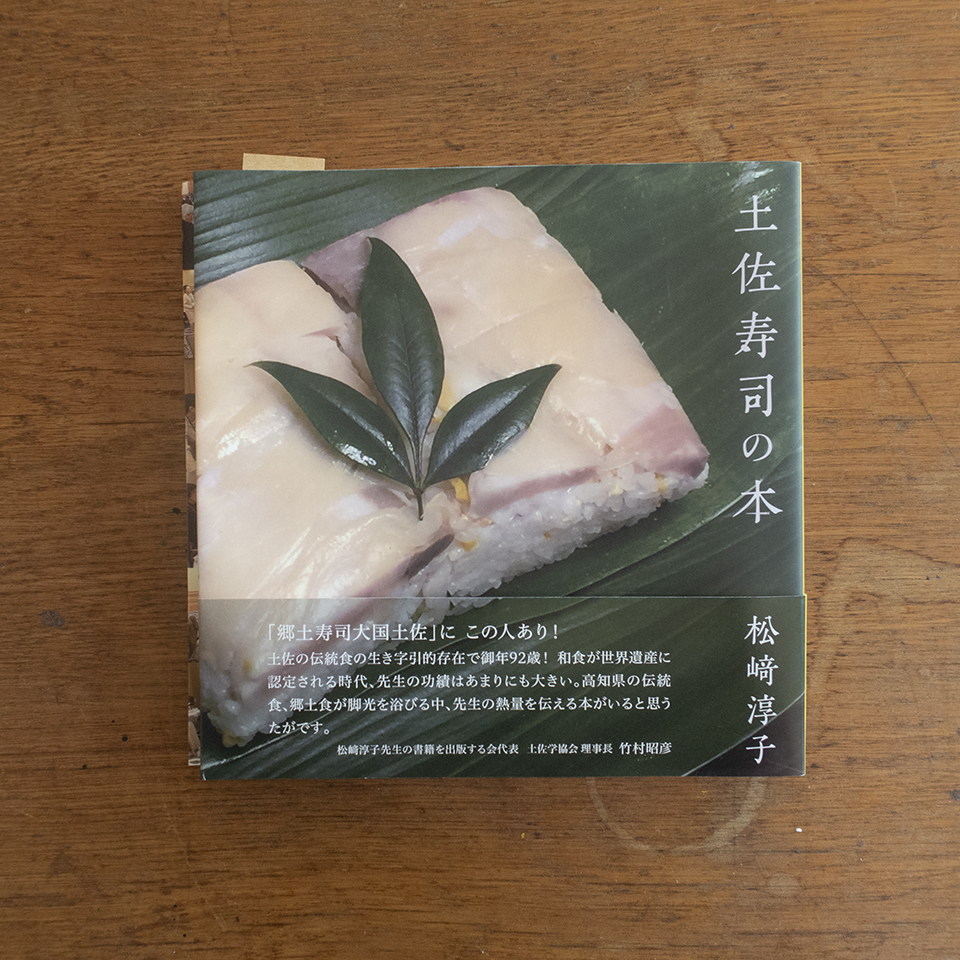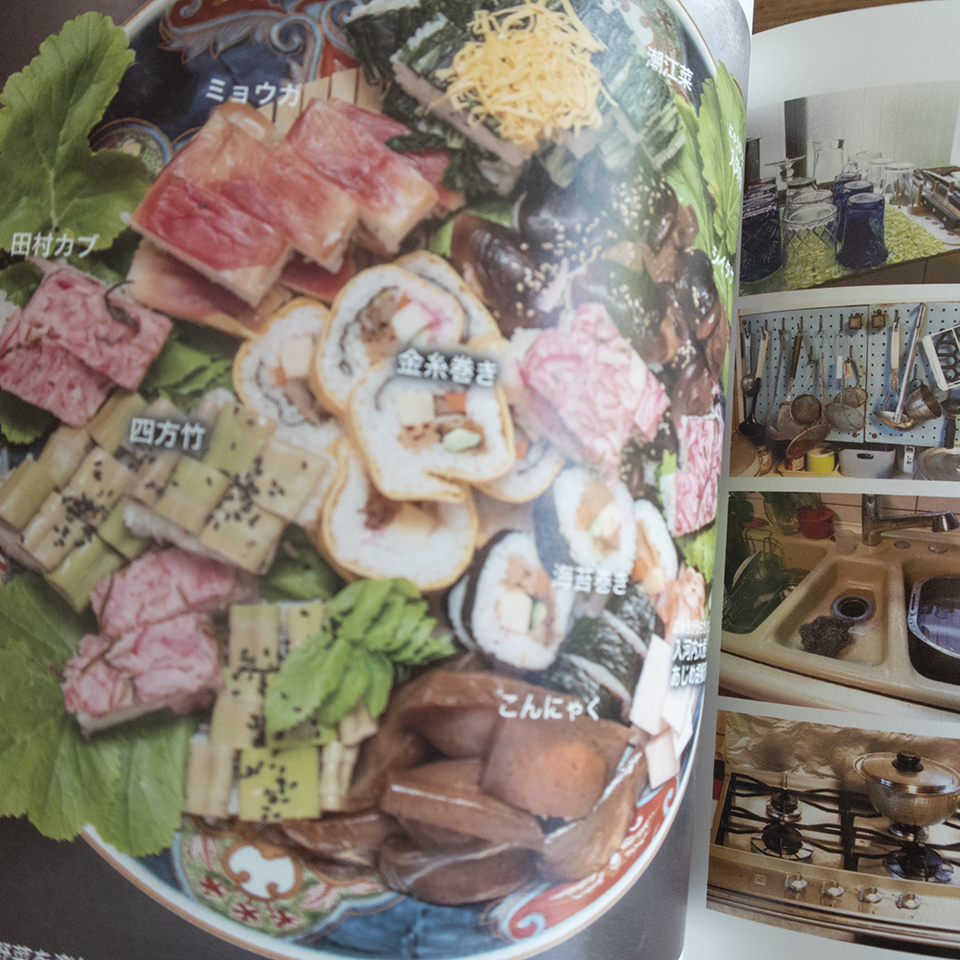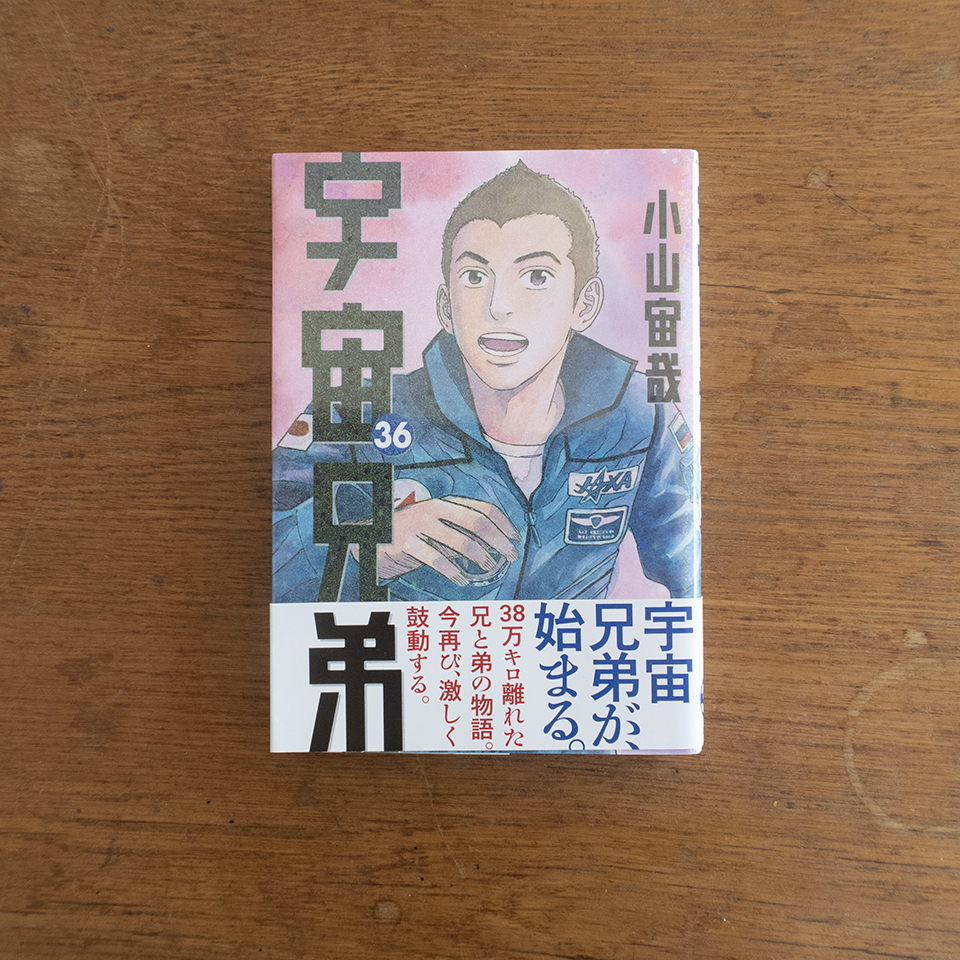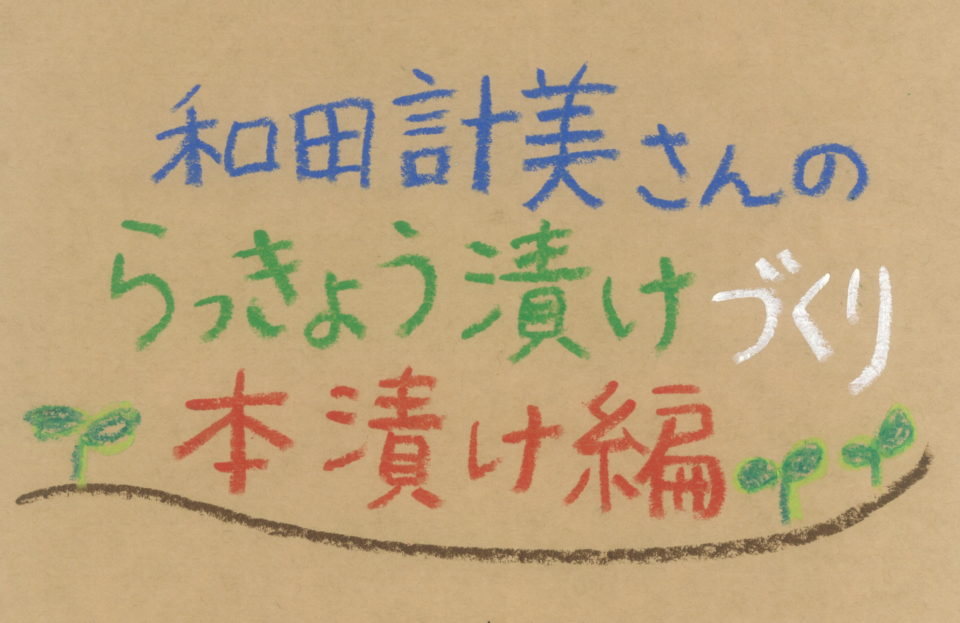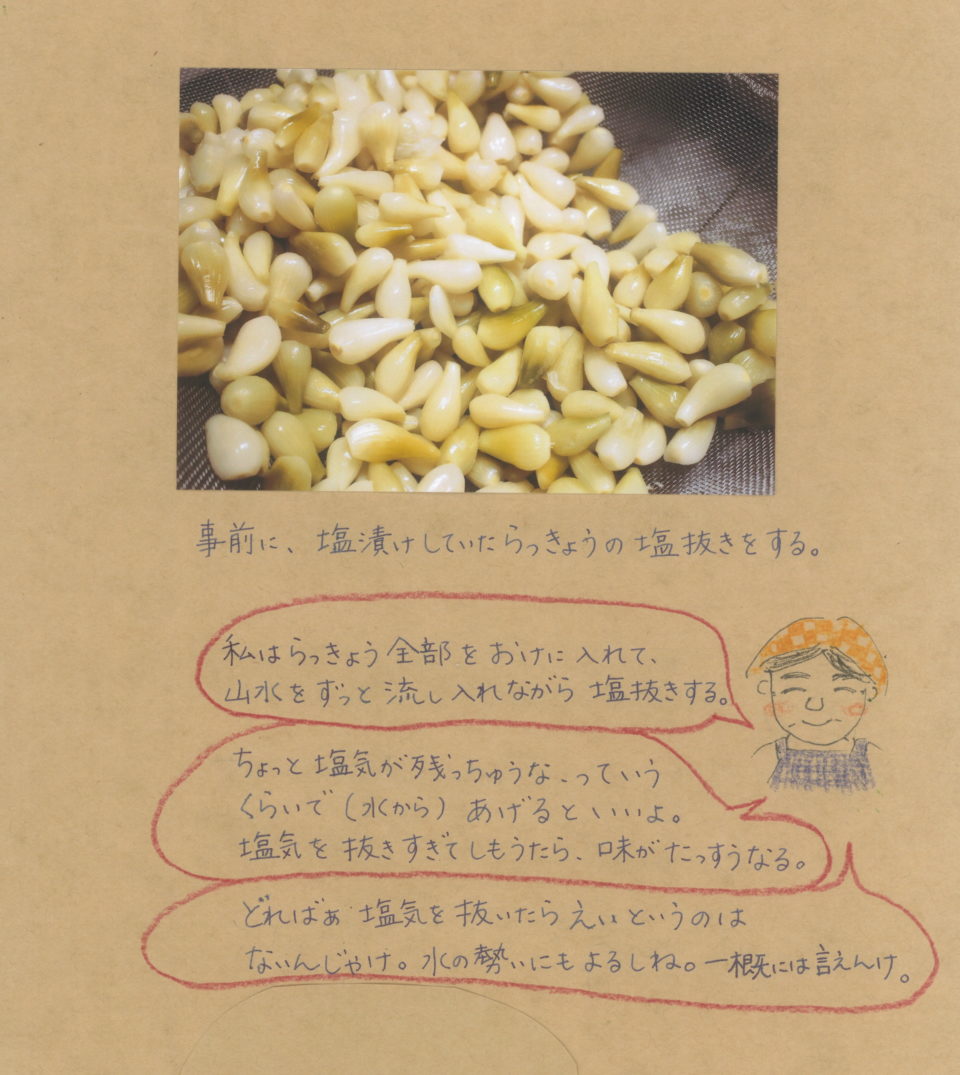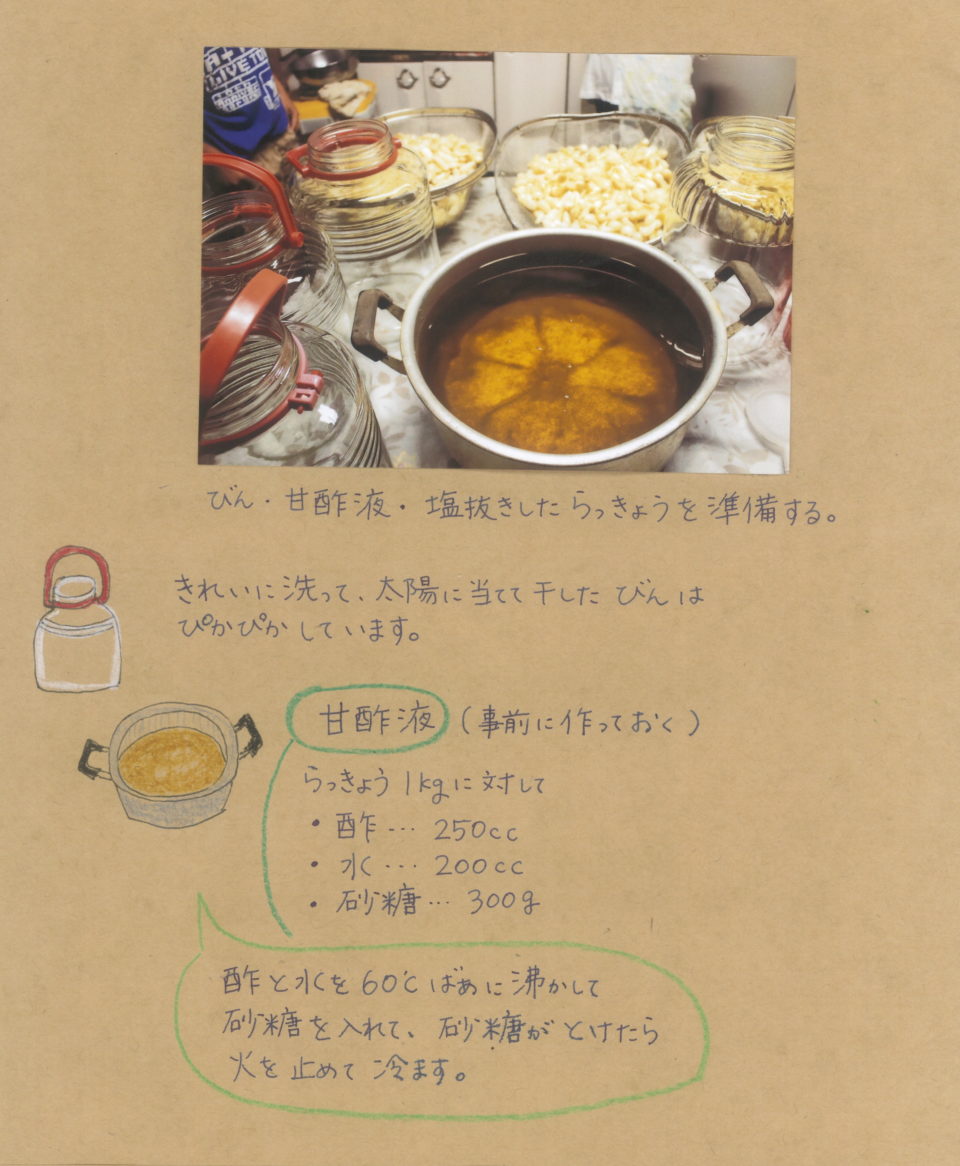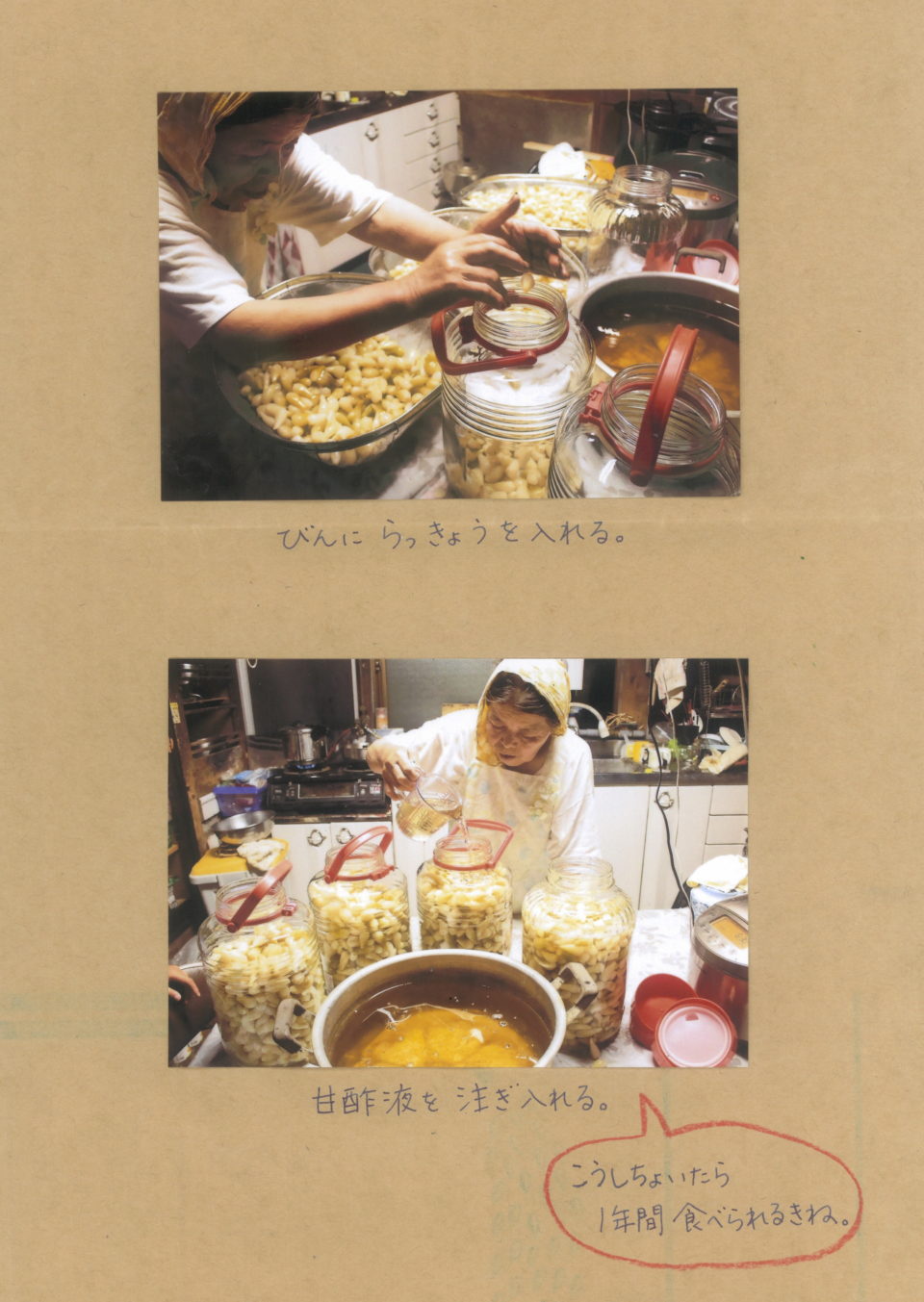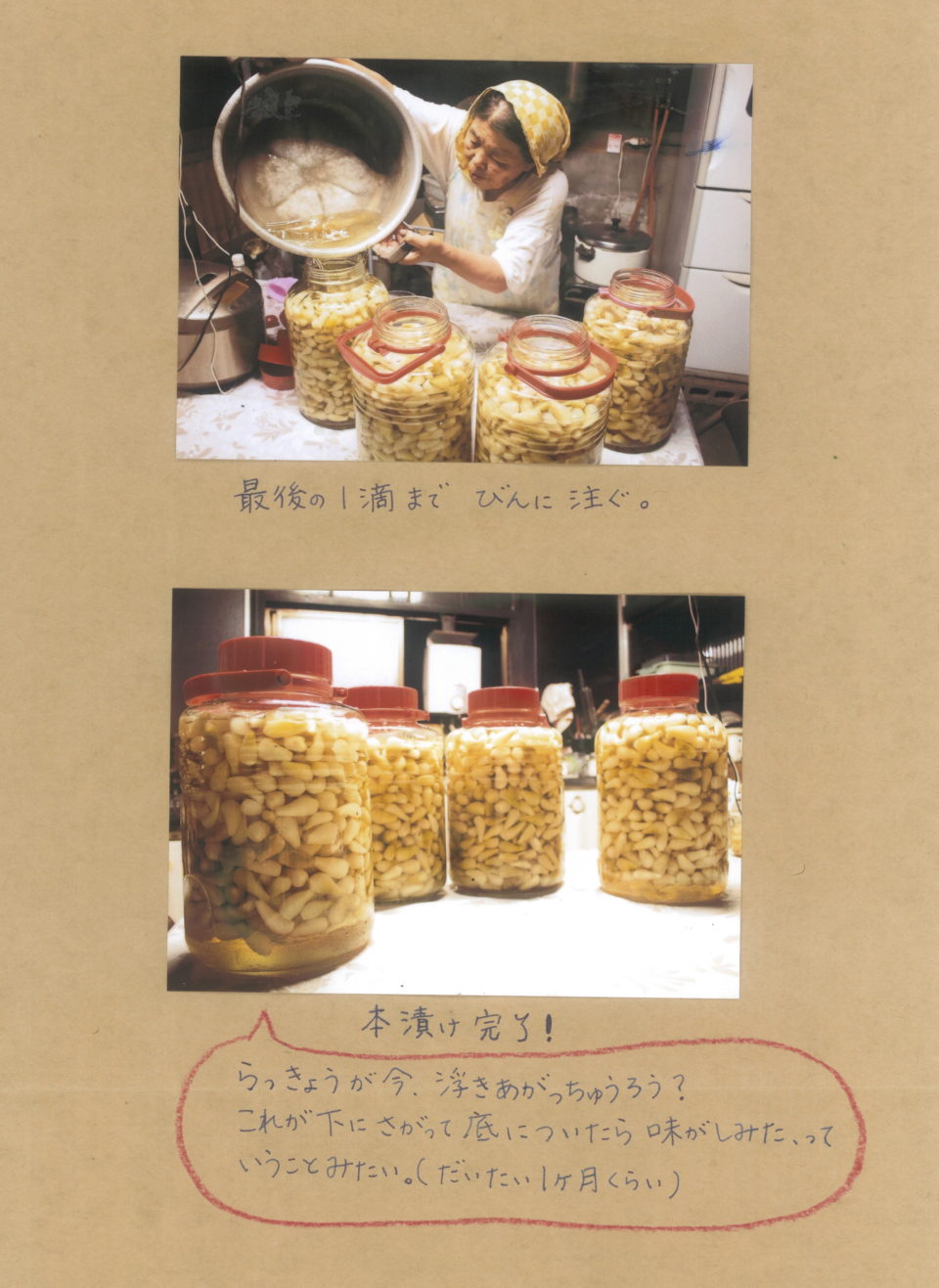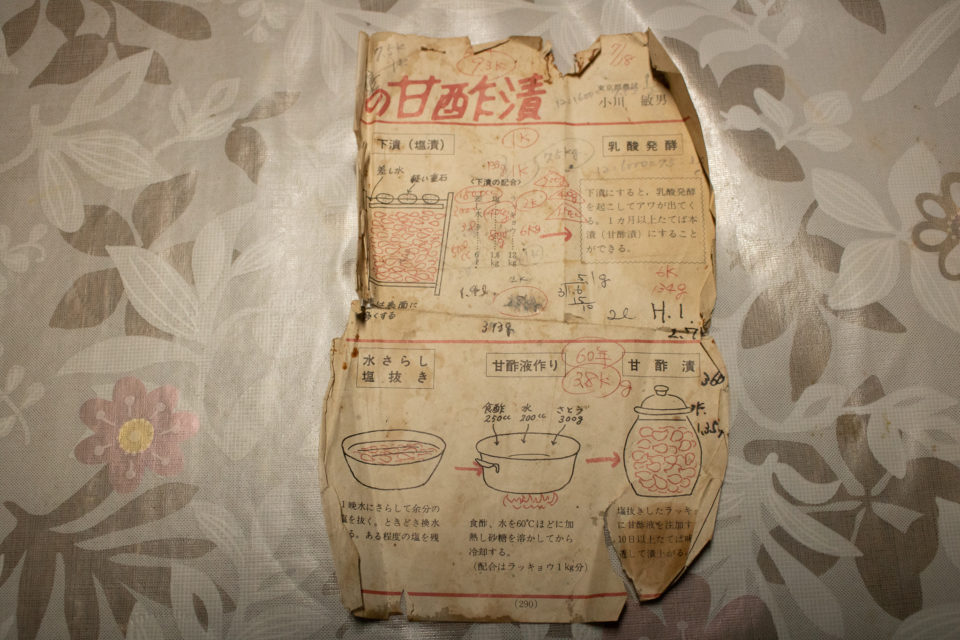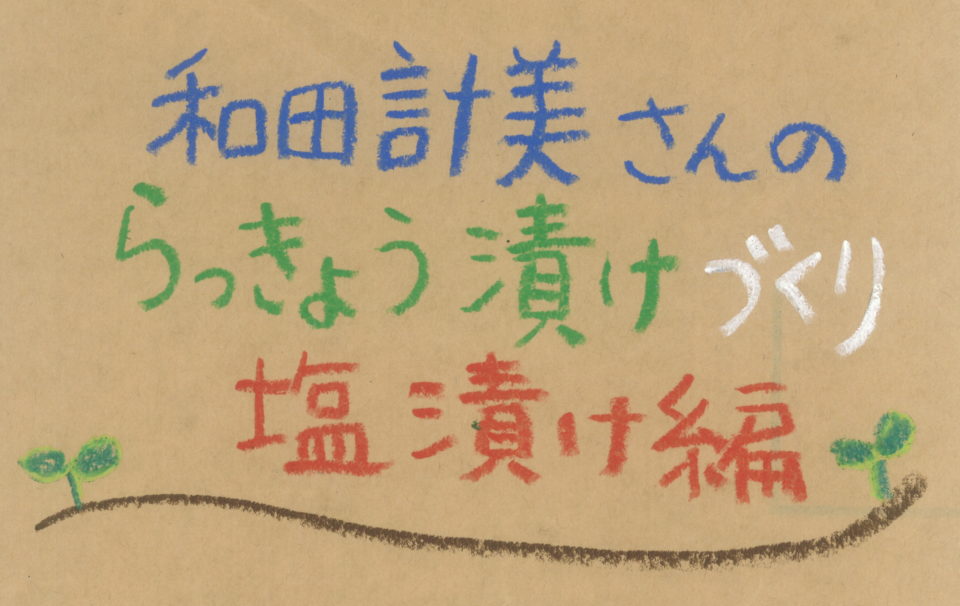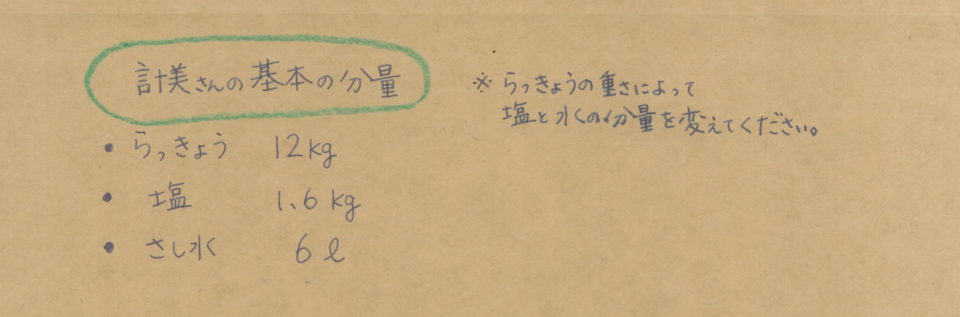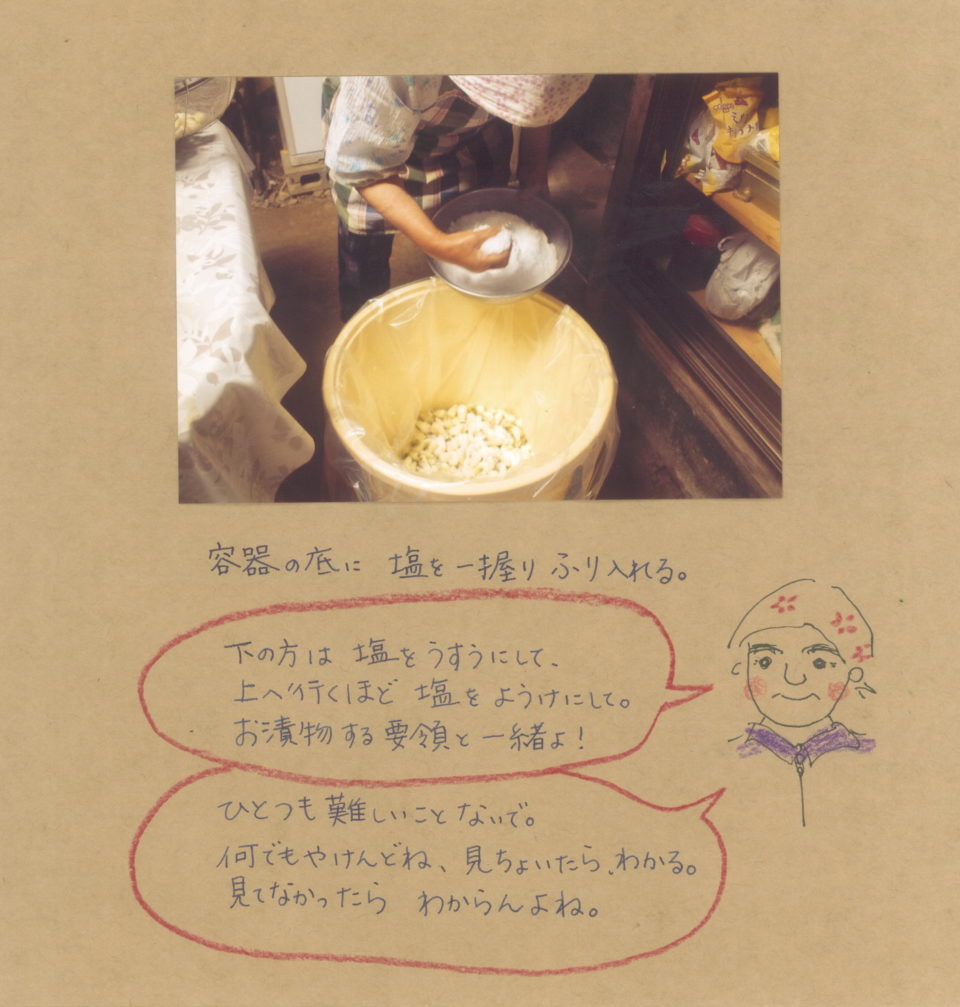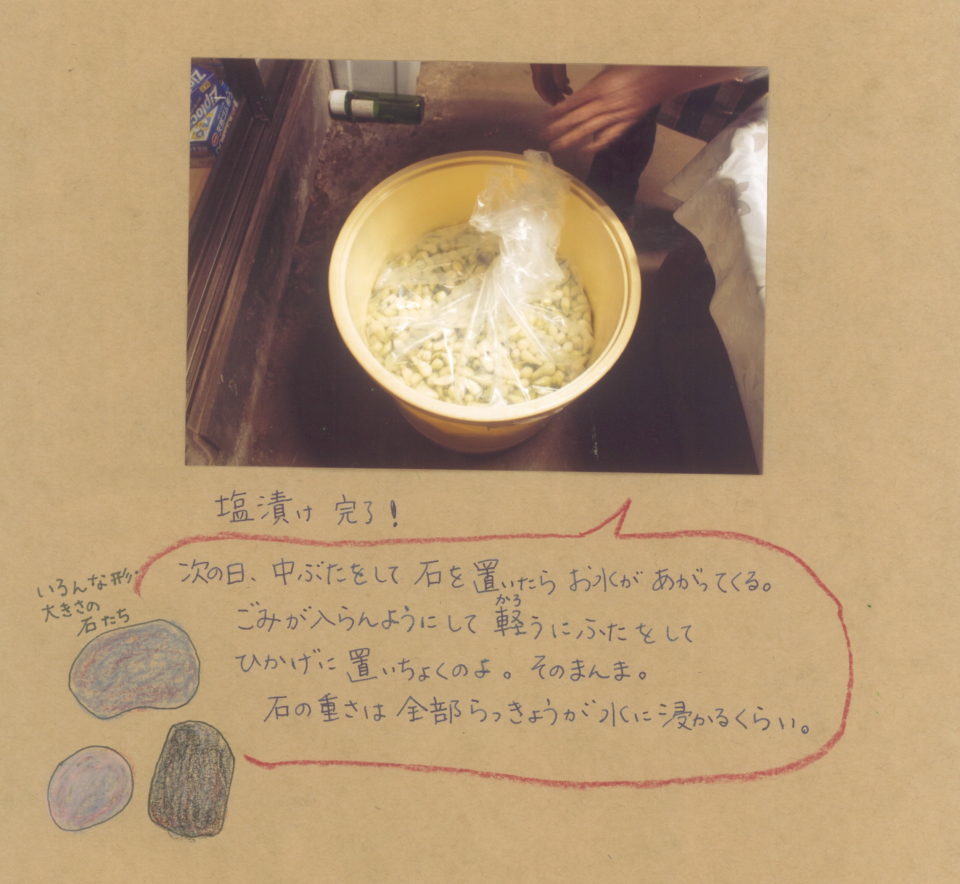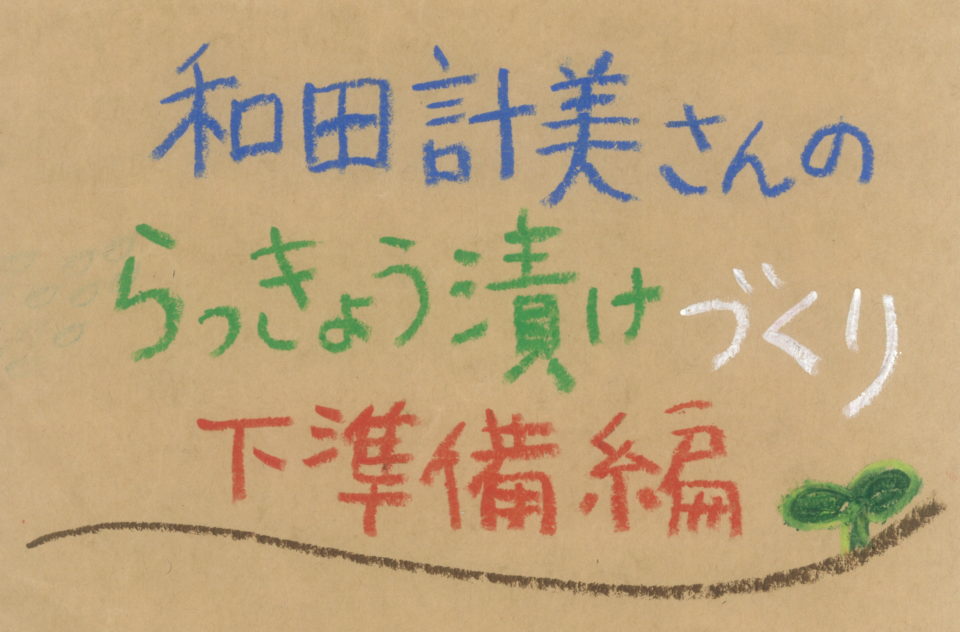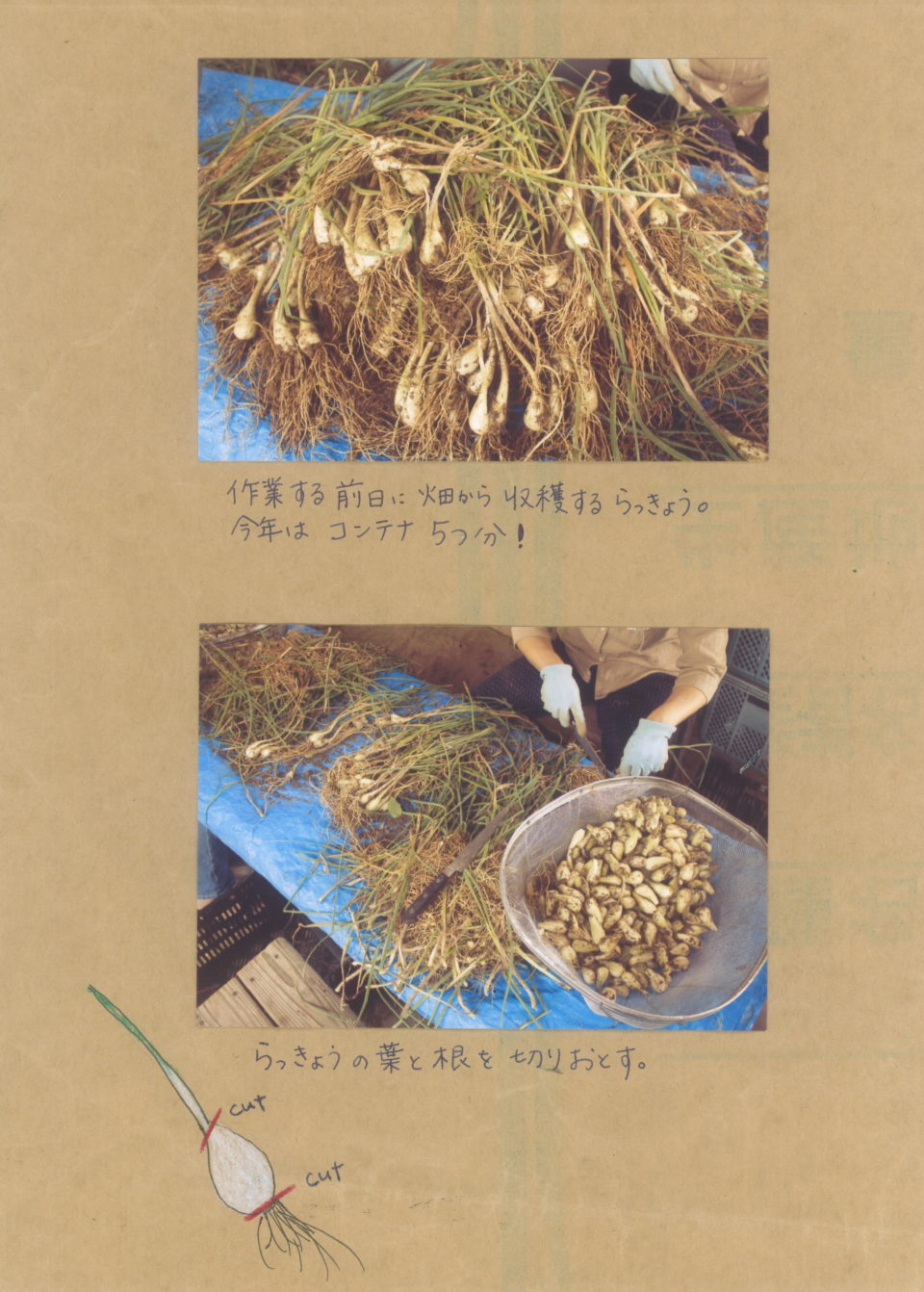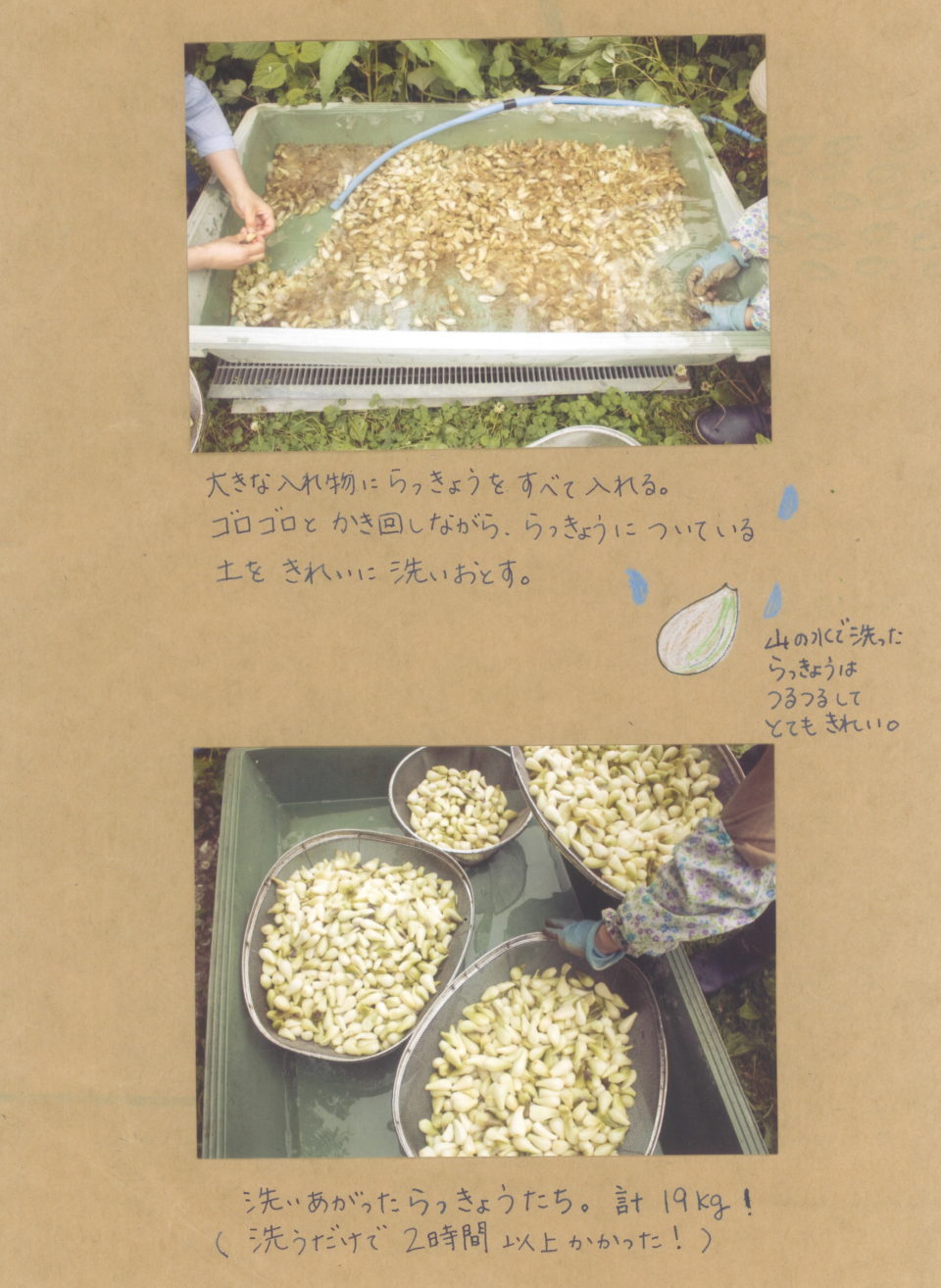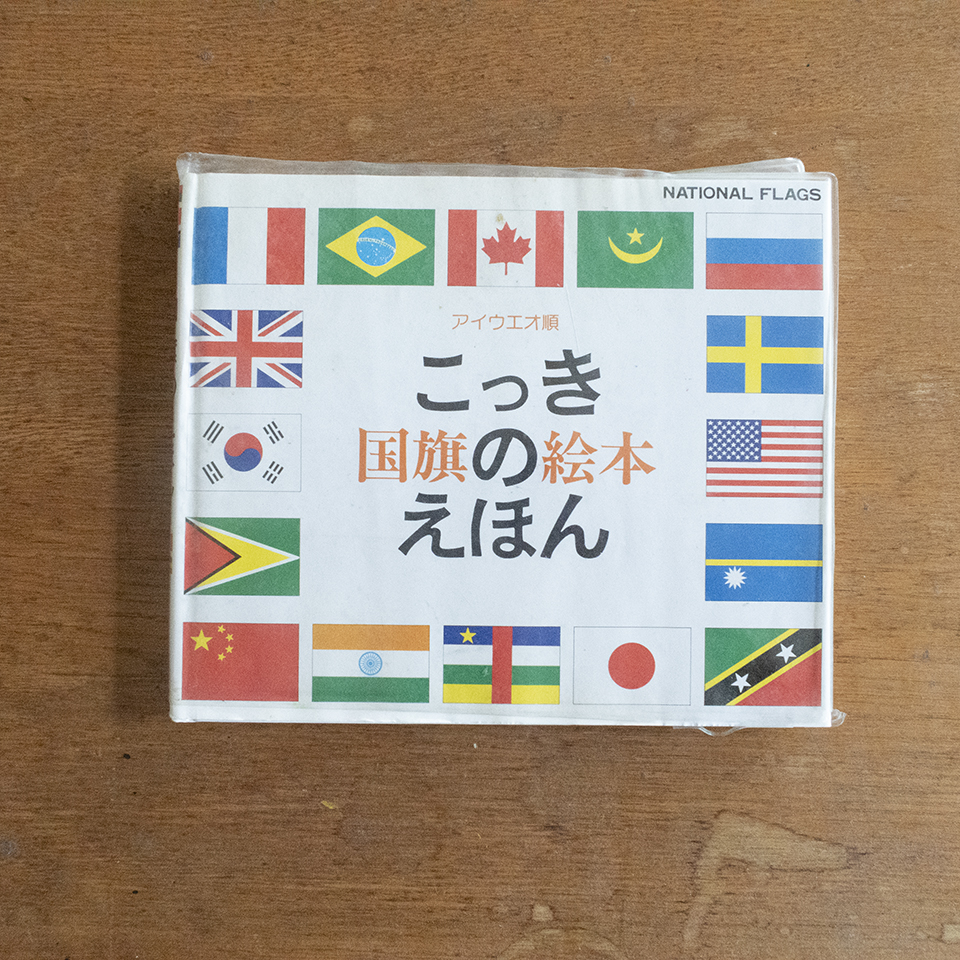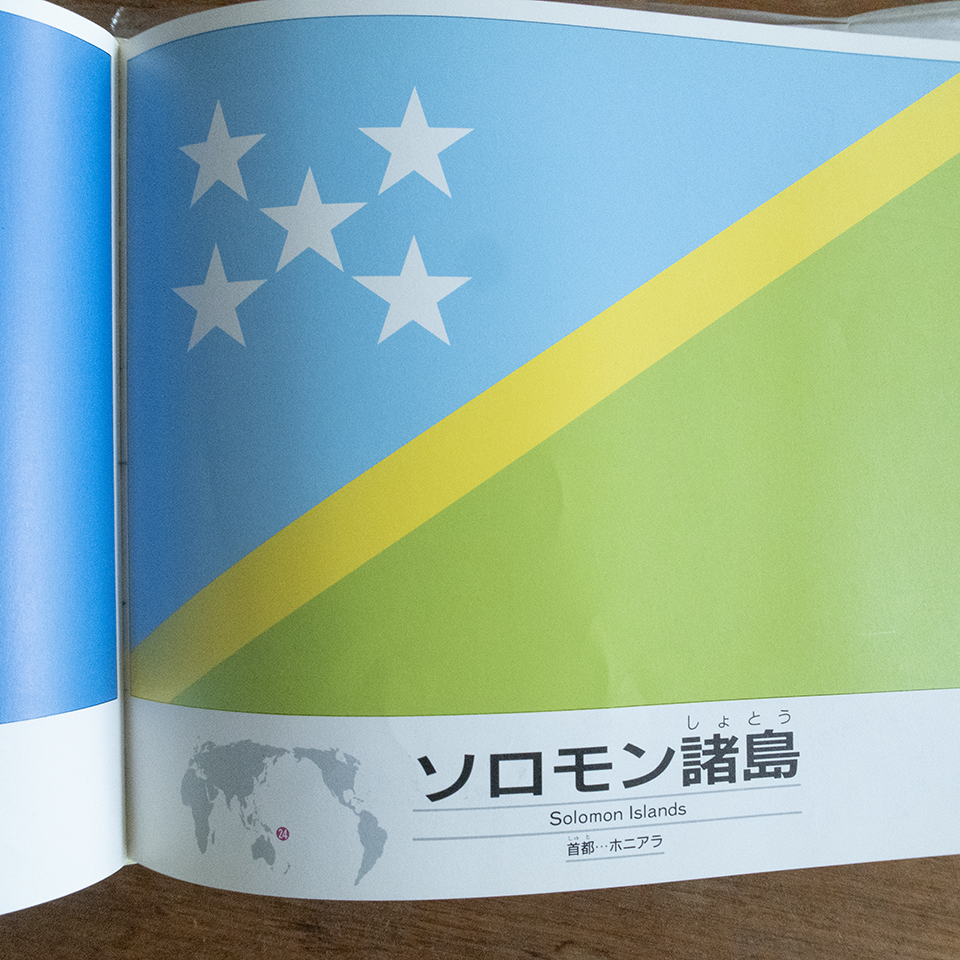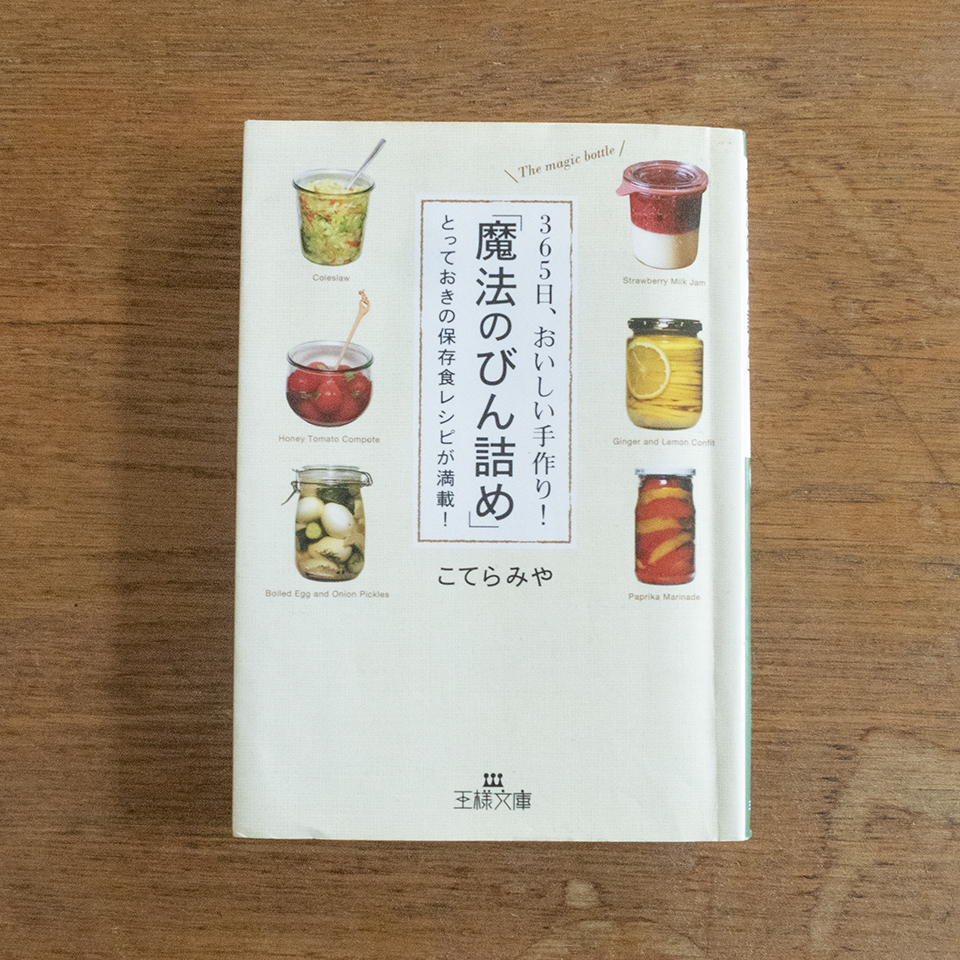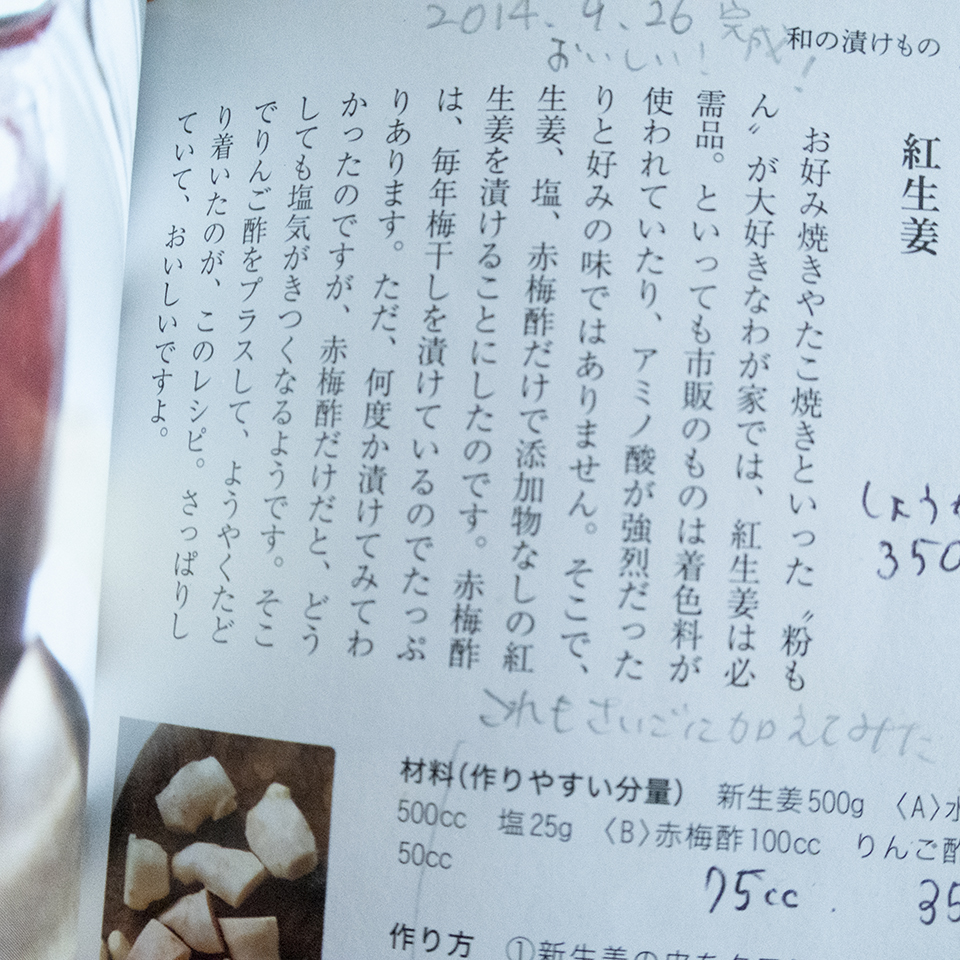土佐町の山沿いの道を見ていて気づくのは、山側の斜面に木箱が置いてあること。その木箱は大抵トタンで屋根がしてあって、箱の下側が少し開いている面が道に向けられ、風通しが良さそうな場所に置いてある。中には箱の表面に大きく墨で名前が書いてあるものもある。
土佐町に来てからしばらくの間、あの箱は何のためにあるのだろうと思っていた。神様が祀ってあると思っていた、と言った友人もいた。
その箱が、はちみつをとる為に置いてあるのだと知った時は本当にびっくりした。ミツバチが花粉を運び込み、その花粉が発酵することではちみつができるのだそうだ。
はちみつの収穫は夏。
8月上旬、上津川地区の高橋通世さんが蜂の巣箱をあけ、はちみつを収穫するところを見せてもらいました。

車一台がやっと通れる細い山道をのぼっていったところに通世さんのミツバチの巣箱はあり、連なる山々に臨むように置かれています。
ミツバチが巣箱の入り口を出たり入ったり、小さな体で忙しく働いています。
ブンブンブンブンブンブン…。
土底から響いてくるようなうなりがひっきりなしに聞こえてきます。
ブンブンブンブンブンブン…。
その音は箱の内側から発せられているのに、すぐ近く、まるで耳元を取り巻くように聞こえるのです。

「これは重い!よう持ち上げるろうか?」
蜂に刺されないように帽子にネットを付け、長袖長ズボン、手袋をした通世さん。蜂を握ったら刺されるので、蜂に触れないように慎重に巣箱を平らな場所へと動かします。
巣箱は大きな杉を製材して板をひき、通世さんが作ったのだそうです。

トタンを取ると、中にはミツバチがびっしり!

蜂が逃げないように、巣箱の口にむしろを巻きつけます。
ブンブンブンブンブンブン…。
ブンブンブンブンブンブン…。
むしろの内側で鳴る羽音が響く中、通世さんは淡々と仕事を進めます。
箱の脇を木片で叩きます。そうすることで中の蜂が驚き、巣箱から上がり、むしろの方へ移動するのだそうです。
トントントントン、トントントントン…。
森から聞こえてくる蝉の声と巣箱を叩く音が、山の中に響きます。
しばらくすると、羽音が静かになってきました。
「音がせんなったら、みんな上がったっていうこと」
むしろをそっと外すと、あんなにびっしりとひしめいていた蜂がいない!
むしろに移動したようです。

金色の規則正しい六角形の組み合わせでできた層が、いくつも連なっていました。ミツバチはどうしてこんなに美しい組み合わせを作ることができるのでしょう。ずっと昔から引き継いできた本能なのだと思いますが、あの小さな体に詰まっている知恵は本当に素晴らしい。
みつの匂いを嗅ぎつけて、スズメバチやウシアブが何匹も飛んできます。スズメバチは隙あらばミツバチをさらおうと勢いよく飛び込んできて体当たりしてくるのですが、作業中、巣箱にいた一匹のミツバチがスズメバチに捕らえられ、あっという間に連れ去られてしまいました。

竹で作ったヘラで箱に付いている巣の縦の部分を切り、持ち手のついた鉄の棒で下の端を切り、上へと持ち上げます。
「巣箱に戻ってきたミツバチはびっくりするろうね、家がない!って」と通世さん。
「夕方、ミツバチがアメ(通世さんは、巣とはちみつのことを“アメ”と言います。ここでは“花粉”の意)を取りに行って、日が暮れるやろ。そしたら山で泊まって、あくる朝に戻ってくる」
泊まり込みで働いて戻ってくるミツバチ…。なんて働き者なんでしょう!

黄金色のはちみつがポタポタと滴り落ちます。
「ちょっと食べてみや」
まさにエネルギーの塊!美味しい!

巣は全部は採らず、いくつか残しておくのだそうです。
「アメを取られて、ミツバチは機嫌悪くして逃げる時がある。ハチにとったら大変よ、全財産取られるんやき。人間だったらおおごと、訴えられる」
いくつか残しておいた巣のミツを食べながら、ミツバチたちはさらにミツを集め、冬までにまた巣箱をいっぱいにするそうです。この時のはちみつは採らず、冬の間のハチたちの食料になります。
「冬の間はミツバチは働かんき、外に出んずく巣箱の中でそれを食べて3月ごろまで暮らさないかん」
「3月頃、ミツが足らんかったら死ぬるき、はちみつのエサをやらないかん。砂糖水でもいいけんど、あんまりやったら、巣へも使うき味が悪くなる。一番いいのは、安いはちみつでもいいから、それをやったら違う。ミツを皿に入れて、その上にすりぬかを入れたりしてハチが溺れんようにしてやるのよ」
ハチたちの仕事を分けて頂いた分、人間もちゃんとお返しをする。そうすることで、ハチと人間のいい関係を長く続けていくことができるのでしょう。

巣箱を元に戻し、下に棒を挟んでミツバチが入りやすいようにしておきます。

むしろを広げておくとミツバチは巣へ戻ります。女王蜂が中へ入ると、皆あっという間に中へ入っていくのだそうです。

巣箱の中へ入ろうと押し合いへし合いしているミツバチたち
写真の真ん中あたりに、お腹の脇に黄色の花粉をつけたハチがいるのがわかるでしょうか?
「山から戻ってきたのが足に花粉をつけちゅう。これが集まって、中で発酵させてミツにするんやから。気が長い話よ」
作業中、ミツの甘い匂いに惹かれてスズメバチが飛び交っていましたが、もしオオスズメバチが巣箱の中へ入ったら、2日ほどでミツバチは全滅、食い殺されてしまうそうです。ミツバチも戦う術を持っていて、入り口付近にスズメバチが現れると、全部のミツバチが羽を一斉に同じ方向へと左右にバタバタと揺らして威嚇します。それでも巣箱のなかに入ってしまった場合、ミツバチたちはスズメバチを一斉に取り巻き、自らの発する熱で蒸し殺すのだそうです。
お互い命がけなのです。

働き、戦い、また働くミツバチたち。
今日も山を飛び、せっせと花粉を集め、自分の仕事をしていることでしょう。
収穫したはちみつは、ひと晩からふた晩、ざるに入れて漉し、はちの巣のカスなどをのけるそうです。通世さんは、さらに網で漉して別の容器に移し替え、純度の高いはちみつともっと細かい不純物を分離させてからビンに詰めるそうです。
その方法も人それぞれ。
自分にとってどの方法がいいのか、はちの巣箱を持つ人と情報を交換しながら色々と試しているそうです。
*一昨年の8月にも、高橋通世さんのお父様である高橋美雄さんにはちみつを収穫するところを見せてもらいました。美雄さんは、今年の収穫風景をきっと空から見守ってくださっていたことと思います。美雄さん、通世さん、本当にありがとうございました。
高橋美雄(上津川)