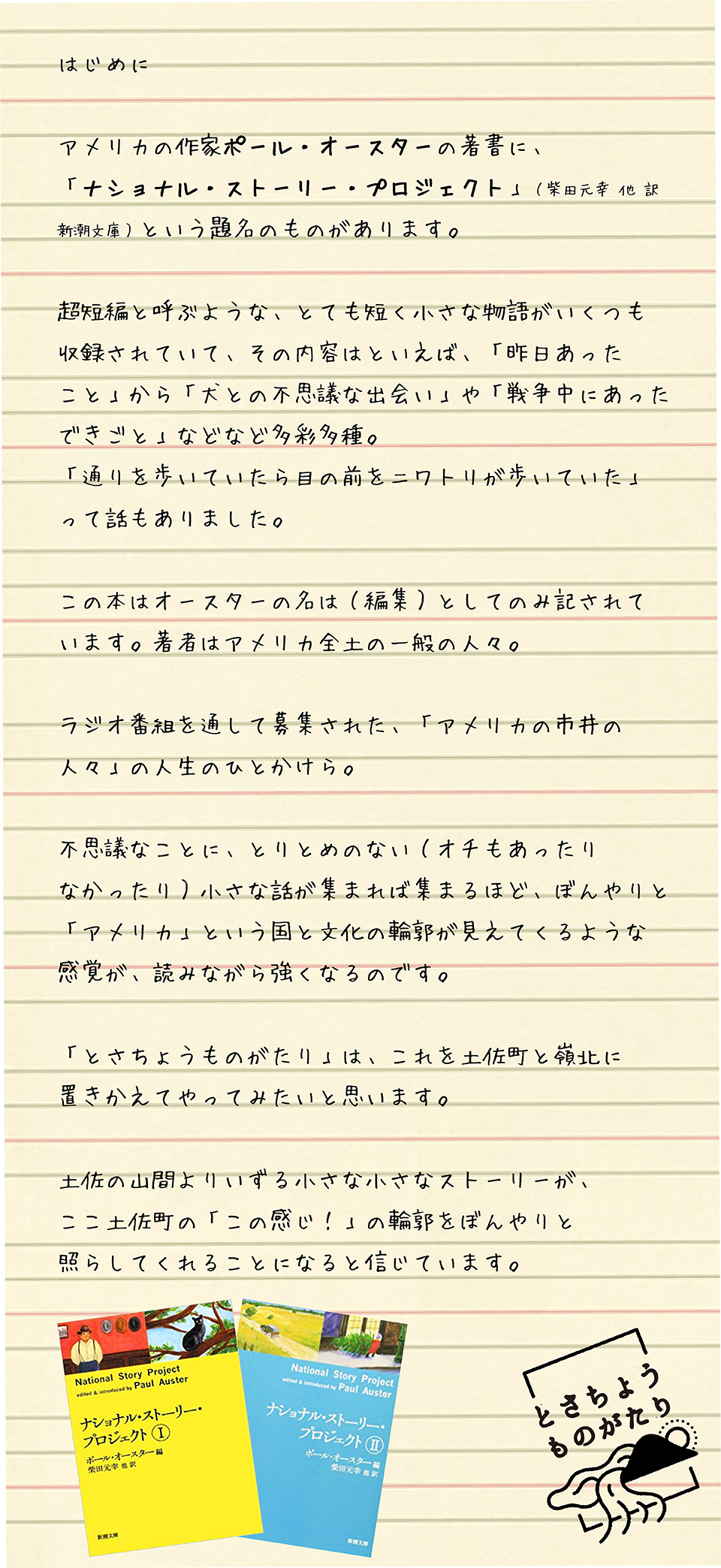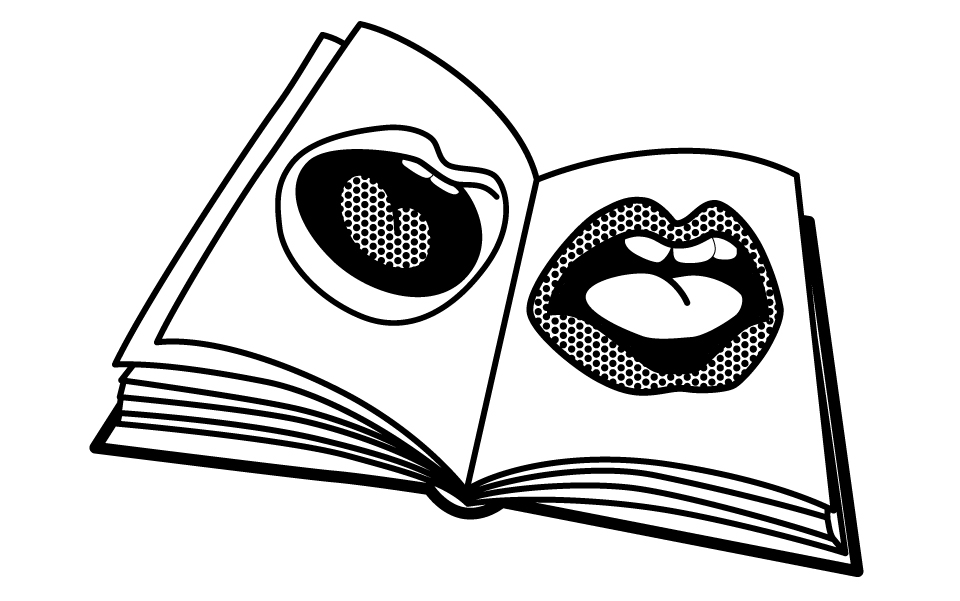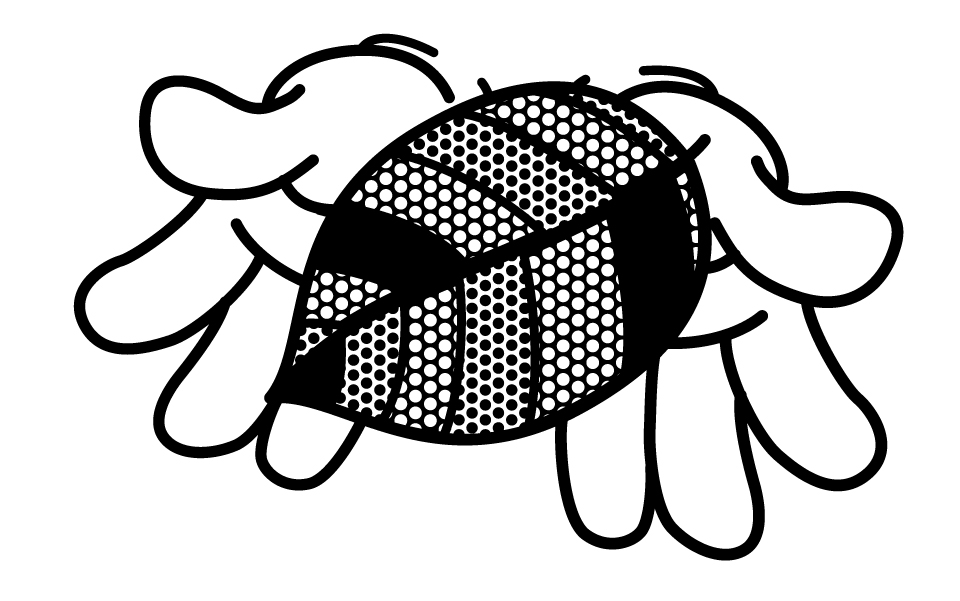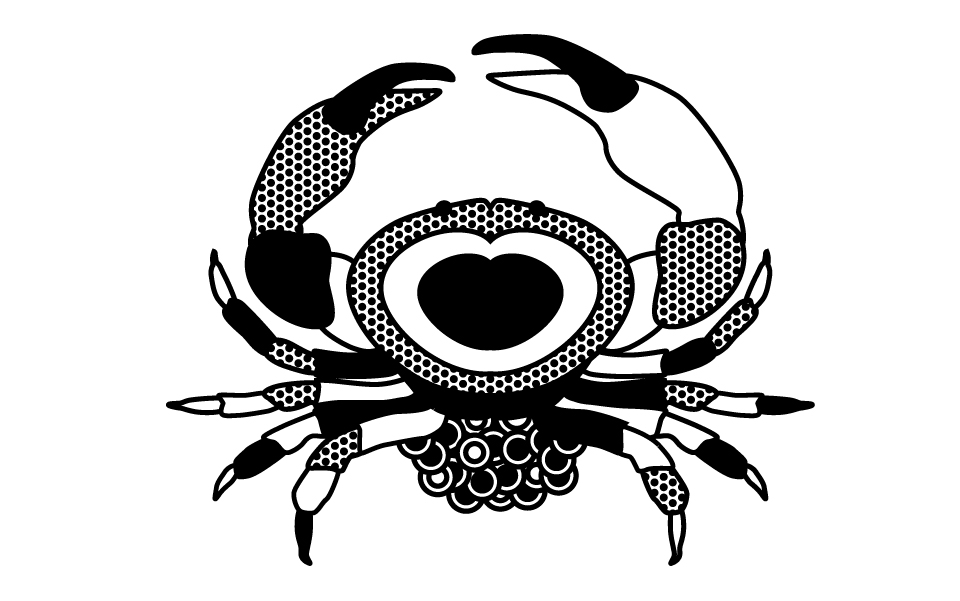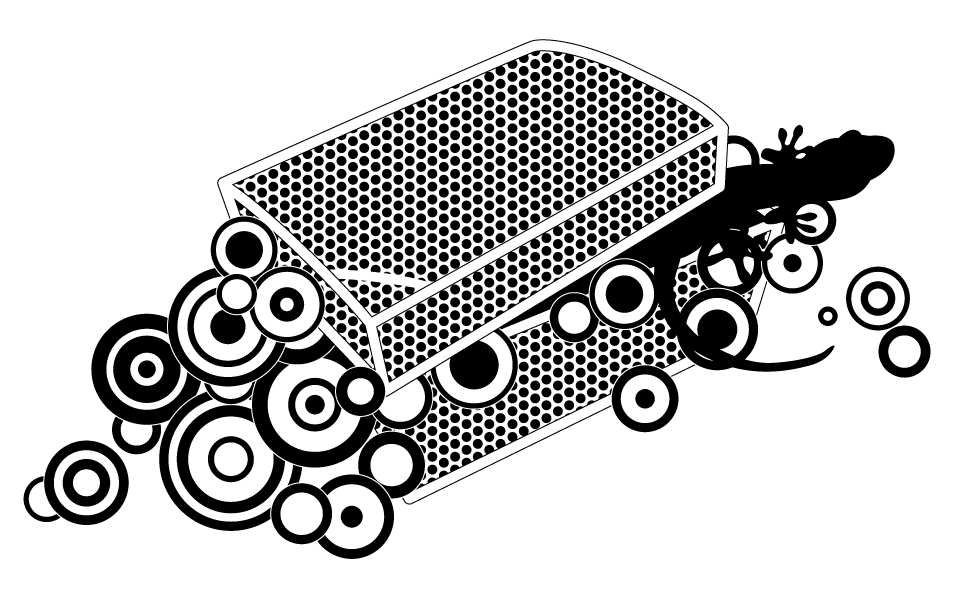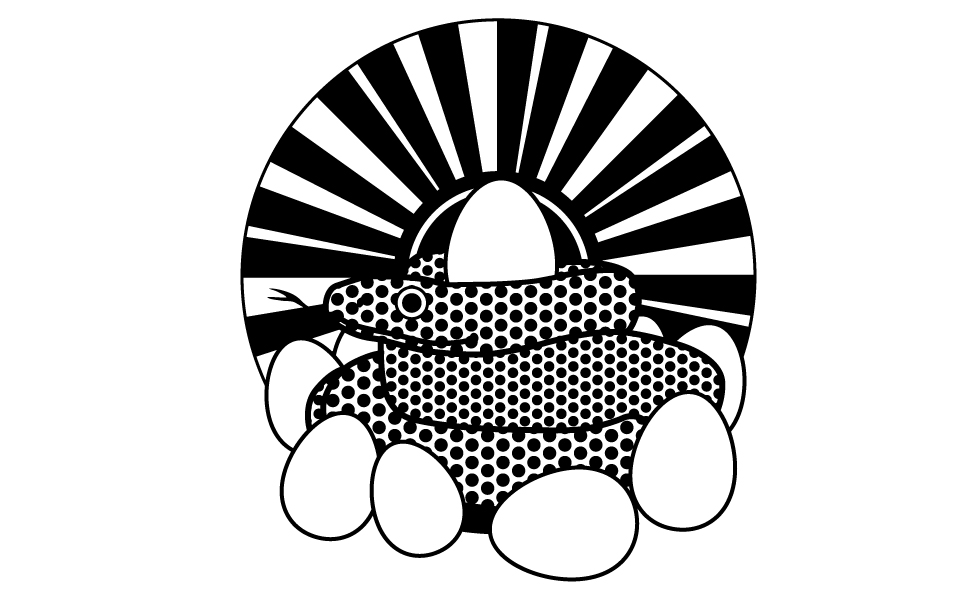土佐町で唯一の産直市「さとのみせ」。
石原という地域の住民グループが毎週日曜日に国道439沿いにオープンしている。

長男を連れてドライブがてら行ってみた。
行ったのがお昼になるギリギリの時間だったのでもうほとんど売り切れてしまっていたけれど、
陳列ケースには美味しそうなサバ寿司やたけのこ寿司が並んでいた。
薄緑かかったツヤツヤの綺麗な黄色のたけのこ寿司と、
味付きご飯が好きな長男が選んだ山菜おこわを手にとって野菜コーナーを見ると、
唯一残っていた存在感のある大きな「しいたけ」。
肉厚で子供の手のひらよりも大きいカサは、プリッとしていてみずみずしい。
これこれ!と思いながらもちろん買う。
高知は意外ときのこ類の生産が盛んなのか、
山間地に住んでいる人はしいたけを自分の家用に作っている人が多い。
高知市内の産直市にもたくさんしいたけが出ているし、中にはエリンギやえのき茸もある。
四万十ではしめじも栽培している。
冷蔵庫にいろんな種類のきのこが揃ったので、夕食は迷わずきのこ鍋にしよう。
ホカホカの湯気が出る鍋料理は秋や冬の季節にぴったりの調理法。乾燥する季節に
立ち上がる湯気。体を中から外から潤してくれるそれも薬膳の食養生なのです。

いろいろきのこ鍋
【材料】
しいたけ・えのき茸・しめじ・エリンギ・黒きくらげ・白菜・豆腐・春菊・昆布・ポン酢
(その他、お好きな具材を入れて、味噌味やキムチ味にしても。)
【作り方】
①土鍋に水と昆布を入れて火にかける。
②石づきを取って食べやすい大きさにしたきのこ類を加える。
(私の場合はきのこエキスをしっかり出したいので早めに入れて煮てしまいます。)
③適当な大きさに切った白菜・豆腐・春菊を加えて一煮立ちさせて出来上がり。
秋冬はこってり味噌や豆乳スープが合うけれど、あえてポン酢でさっぱりと。
我が家は頂き物の今が旬のすだちをたっぷり絞っていただきました
ちなみにきのこによって薬効が変わってきます。
しいたけ・・・ 食欲のない時、胃もたれする時。高血圧や高脂血症に。免疫力アップ
えのき茸・・・ お通じをよくしたり、美肌効果あり!
エリンギ・・・ から咳が出る時や手足が火照っている時に。
しめじ・・・ 貧血や高血圧に。ガン予防にも。
黒きくらげ・・・血液さらさら効果。から咳、乾燥肌にも。
鍋をしたら残りの出汁は絶対捨てず、シメや翌朝の朝食に雑炊を!
きのこや野菜、いろんな食材から出る最高の薬効出汁になっていますよ!
土鍋に残った栄養たっぷりの出汁にご飯を入れて一煮立ちさせたら溶き卵を回し入れ、蓋をして火を止める。
30秒くらい待ったら蓋を取ってふわっと立ち上る湯気の向こうに
ふんわりとろりとした卵のかかった雑炊が!
あ〜、美味しいに決まってる!
部屋中の窓を湯気で曇らせながら、こたつでホカホカ。
また今晩もお鍋だな。