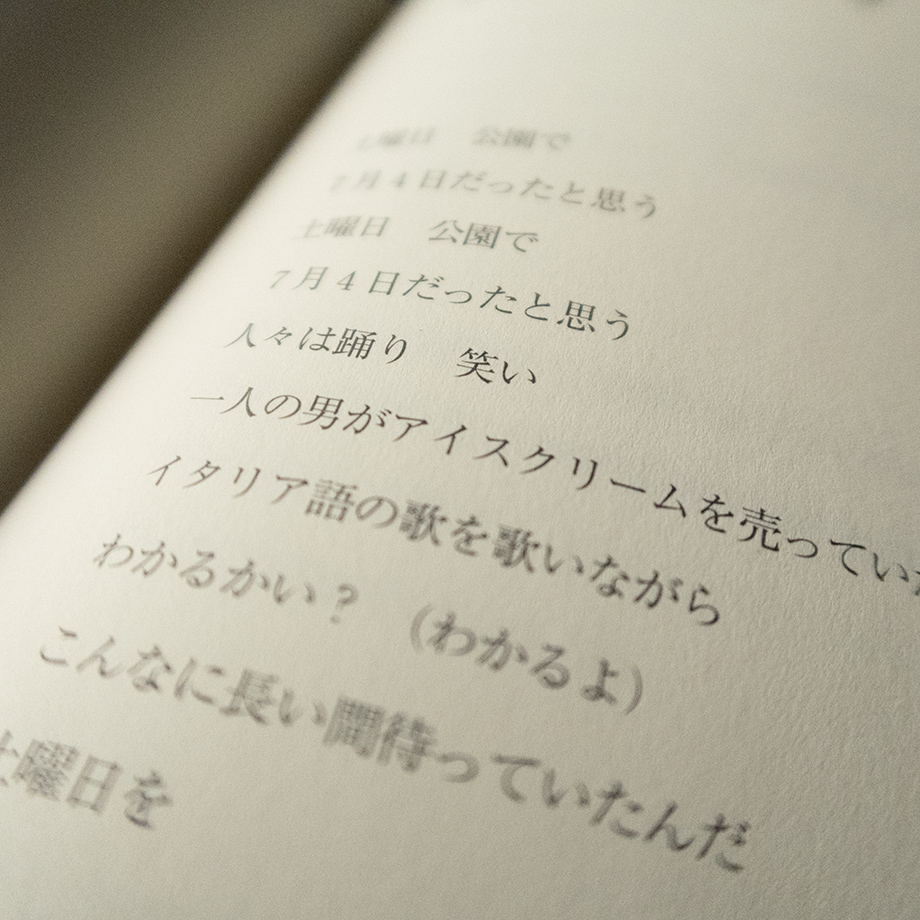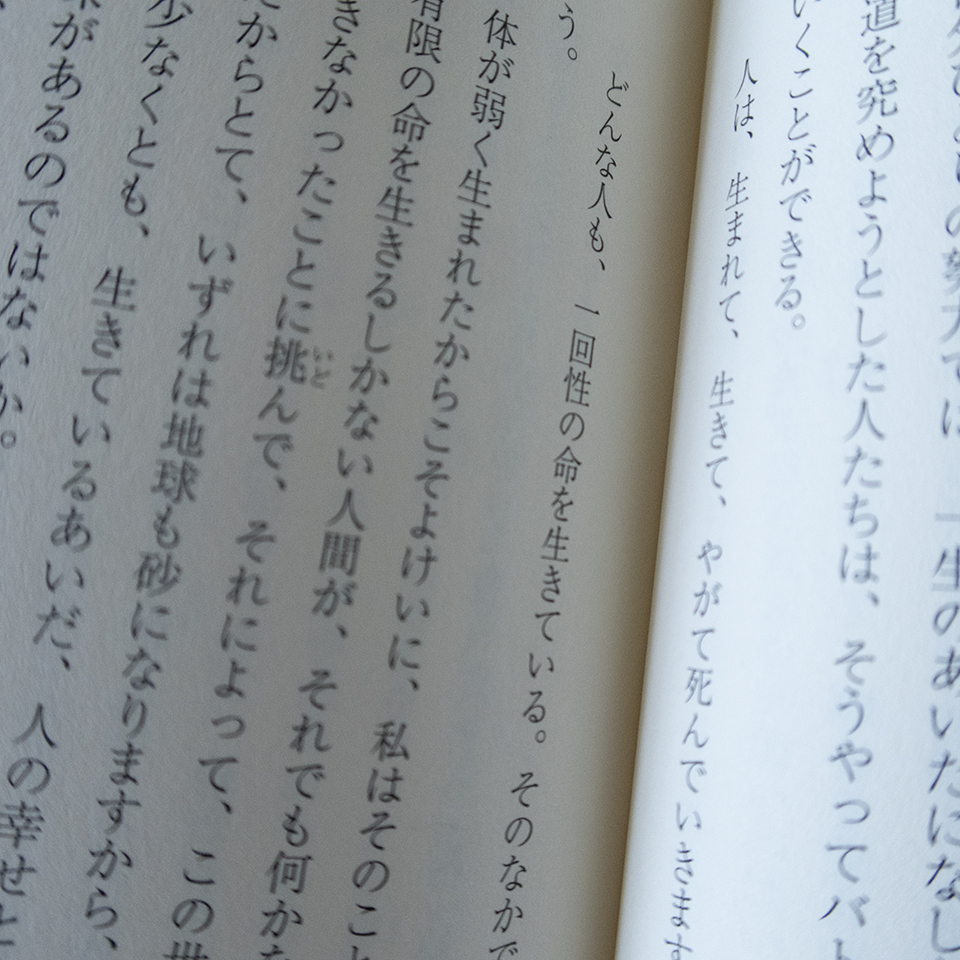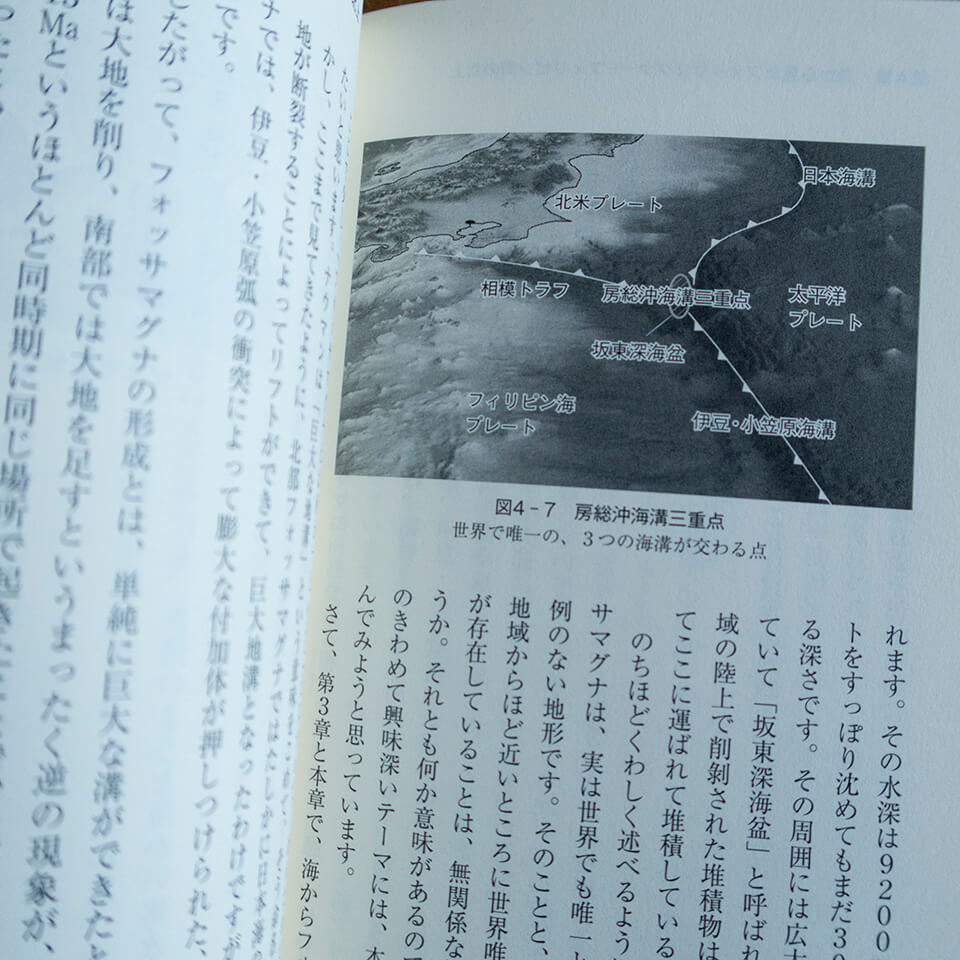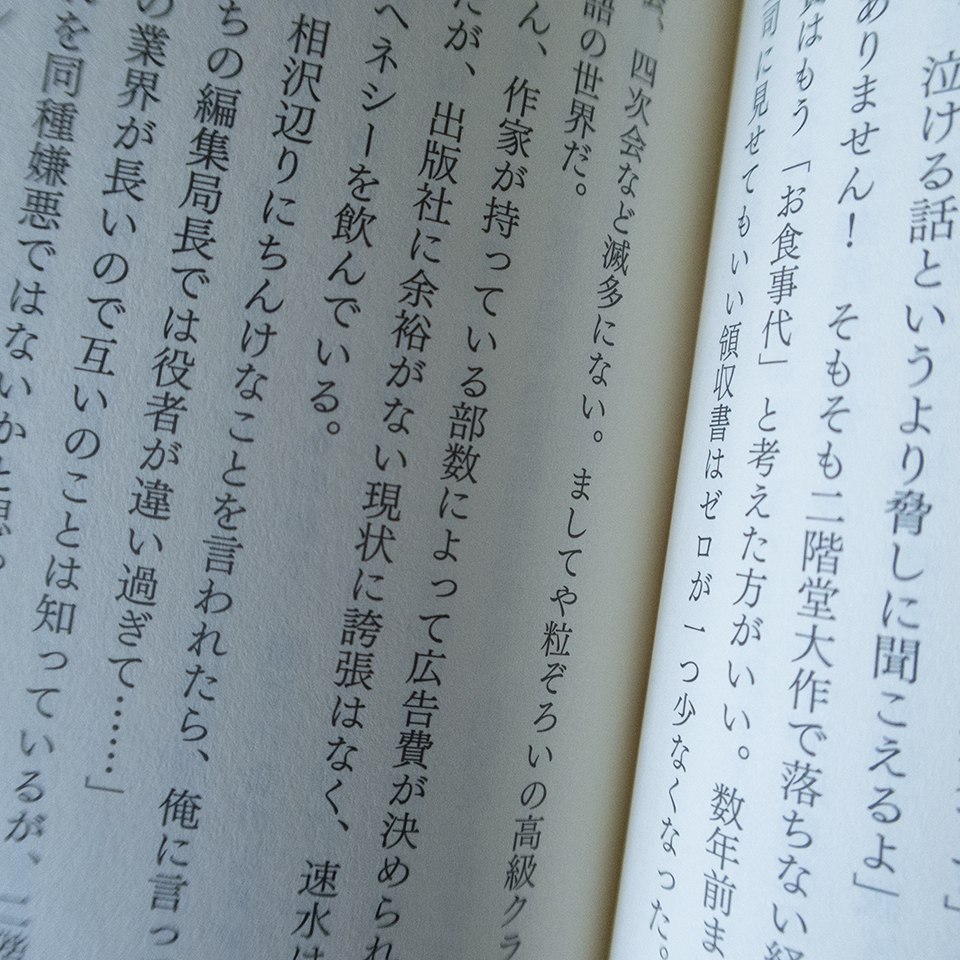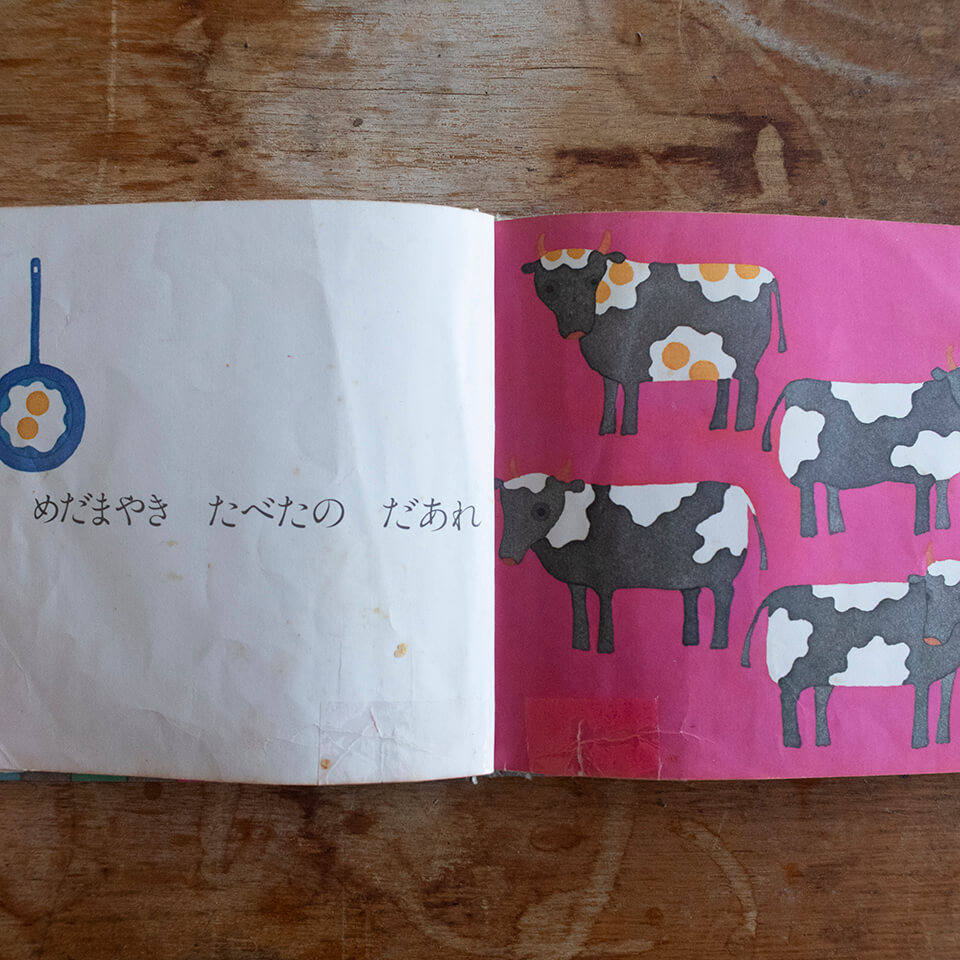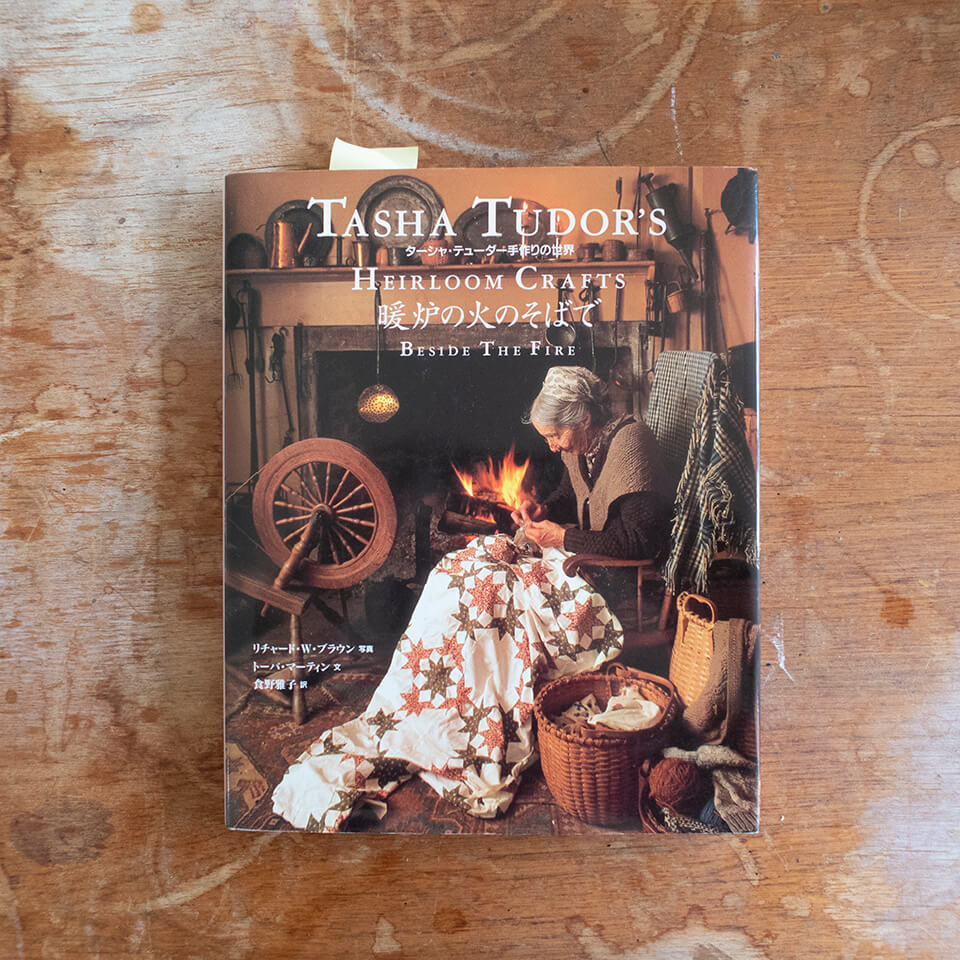師走真っ只中。私は、家族3人でクリスマスイブのケーキを食べています。
叔母のつてで、昔からイブのイブからケーキがありました。小さい頃はたまらなく嬉しく、プレゼントの気配にもつられて、楽しみに、きそきそしていたものでした。
今となっては、クリスマス前の苦行のひとつです。イブのイブからケーキがあるものですから、本番で歌う讃美歌「聖しこの夜」まで2曲ほど工面しなくてはなりません。
大体毎年、父と私でクリスマス・キャロル矢野家アレンジが即興で歌われます。今日は「ジングルベル、フフフハミングversion」でした。あと、その蝋燭の消しかたといったら!。今日は咳風邪で右肋軟骨(前回は左)を損傷し、鼻水ずるずるの母をからかってやろうと、吉本の芸人よろしく鼻息で蝋燭を消そうと父と企んでいました。
「絶対どつかれるね!笑」と言いあったのに、母はノリよく鼻息で蝋燭を消そうとしてくれたのでした。(名誉のために弁明しますが、本当に鼻水飛ばして鼻息で消したわけではありませんので、悪しからず!)
さて、前座はこの辺で。
私の書く一冊はどれも胃もたれすると思われるのもしゃくなので(笑)、今回は「守り人シリーズ」の著者である上橋菜穂子氏のエッセイ『物語ること、生きること』、構成・文は瀧晴巳氏です。
彼女は冒頭で自分がどのように物語を描くか触れています。 “物語を書いているときは、馬車を走らせているような気がすることがあります。私の周りに、たくさんの荒馬がいて、懸命にたずなを操って走らせているような気がするのです。~中略~それが、あるとき、まるで違うメロディが合わさって、ひとつの合唱になるみたいに、ものすごいスピードで一勢に走りだします。その瞬間、「ああ、書ける……」と、思う。“
彼女からすると、物語は生まれるもの、不意に降ってくるもの、急に見える風景なのかもしれません。
そして、「どうすれば作家になれるか?」という作家であれば一番多く聞かれるであろう質問に、彼女なりに答えてくれます。ただ彼女が “とても一言では言えそうにないんですよ。“ と述べている通り、このエッセイまるまる一冊かけて、答えてくれる訳ですが。
『第一章 生きとし生けるものたちと』の「おばあちゃんとわたし」の中に、昔話の話がでてきます。昔話と言えば私の場合、父が話してくれたことを覚えています。
「昔むかーしあるところに…」というお決まりのフレーズで始まりますが、大抵父が語る桃太郎は桃の時点でおばあさんに真っ二つ!かぐや姫は竹の時点で、お爺さんが鉈で一刀両断してしまいます。
大胆なアレンジから始まる昔話は、声音も表情も芸人コロッケもかくやと言うほどで、今夜のように底冷えするに日も楽しく眠ることができました。
そういえば、上橋氏のおばあさんは怖い話が十八番と述べられていましたが、私も小さい頃震え上がった怖い話があります。「耳なし芳一」です。
夏の夜に、妙に上手な琵琶の音真似で語られる芳一と平家の落ち人の話は、土佐のとめ言葉「昔まっこう猿まっこう」で終えられても、なかなか寝付けませんでした。
そもそも矢野家は、早明浦ダムが出来るまで平家の落ち人伝説の残る大川村にいたのです。なんだか他人事ではない気がして、夏布団から体を出さないようにして扇風機の音を聞いていたように思います。
実はこの話には後日談があります。それも十数年後のことです。大学4年生の夏、小学生の剣道強化合宿の手伝いをしていたときのことでした。
大学生には夜の重大任務が課せられました。自分の担当する部屋のガキンチョもとい、悪ことしな児童を定刻の時間に寝かしつけること(静かにさせて、別の部屋等へいかないように見張る)でした。なんというmission inpossible!!無茶ぶりにもほどがあるぜ!と感じた私は、ここで一計を案じました。
そう題して、「寝てもらえなくても、恐怖で静かにさせる作戦」。私秘蔵の怪談セレクションを、「まぁむかーしのことなんやけどねぇ…」と父譲りの演技力で語って聞かせました。
もちろん〆は、耳なし芳一から平家蟹のメドレーで「昔まっこう猿まっこう。お仕舞いおしまい」。私の部屋の担当は、わりと、おませな女の子ばかりだったので “昔話は効かないかも…” と思っていたものの、効果はてきめんでした。もはや泣き出す子もいる始末。
お陰で「はやく寝ようよぉ」とみんなすぐに寝てくれました。その後、一つしたの階を見回ったとき、どうやら担当の大学生が誰よりも早く寝たらしく、夜更かしを楽しんでいた悪ことし二人組を震え上がらせ、私の作戦はみごと成功したのでした。
さてさて話は変わりますが、この本を読んでいると思い出します。 “私も小説家になりたい、と一瞬でも思った事があったなぁ“ と。
でも私は、次から次に見つける面白い本を読むのが楽しく “ちまちま書くのは性に合わんにゃあ~“ と思い、小説を書いてみたいと思ったことさえ忘れていました。
しかし、今『私の一冊』というところで、何やらかんやら書かしてもらっているのは、奇遇なことだなぁと思います。 “あの物語は本当にすごいよ“ と少しでも伝えたくて、ちまちま書いています。それに誰かが伝えてくれた物語は、伝え得ずにはいられません。私は上橋氏のようにハイ・ファンタジーを描くことはできないけれど、物語ることはできる、受け継ぐことはできる。そう思えたのがこの本でした。
そして、小説家になりたい人、文を書くのが苦手な人はこの本を読むと、気が楽になるかも知れませんね。
尻切れトンボですけれど、それではまた。