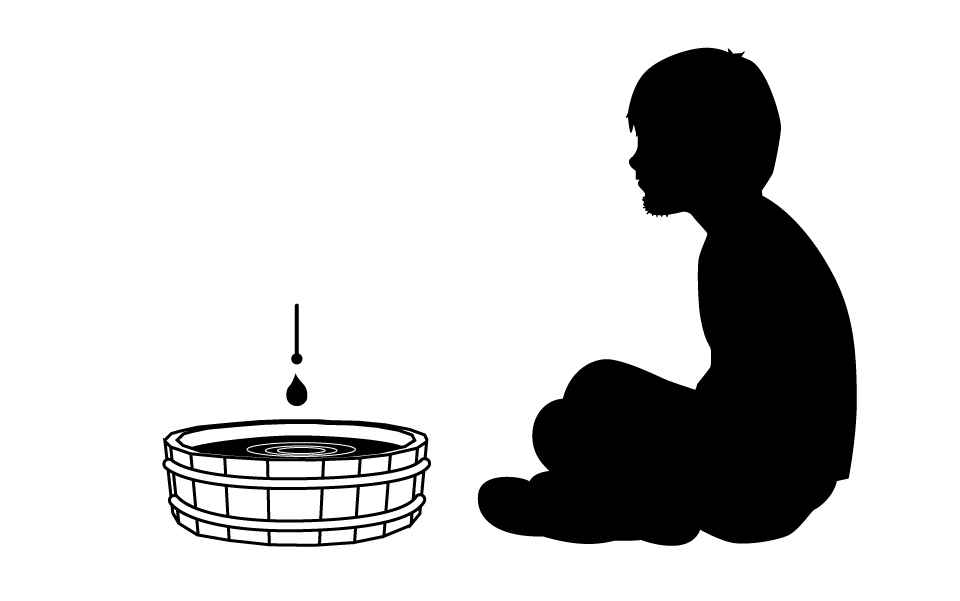
黒丸にカキチさん言うて家伝の薬をこしらえていた。
破傷風、梅毒、ハメ(蛇)にかまれた時に、その薬を湯にとかして、たらいの中に座らすときれいに毒を吸うた。
医者で治らんのがすぐによくなった。
九州や青森の方からも欲しい言うて来とった。
カキチさんはまたその人の生年月日と歳を聞くと、大きな古い暦をめくって、
あんたはどこそこの病気じゃ
言うて当てていた。
それがまた当たってよく見てもらいに来よったと言う。
町史
著者名
記事タイトル
掲載開始日
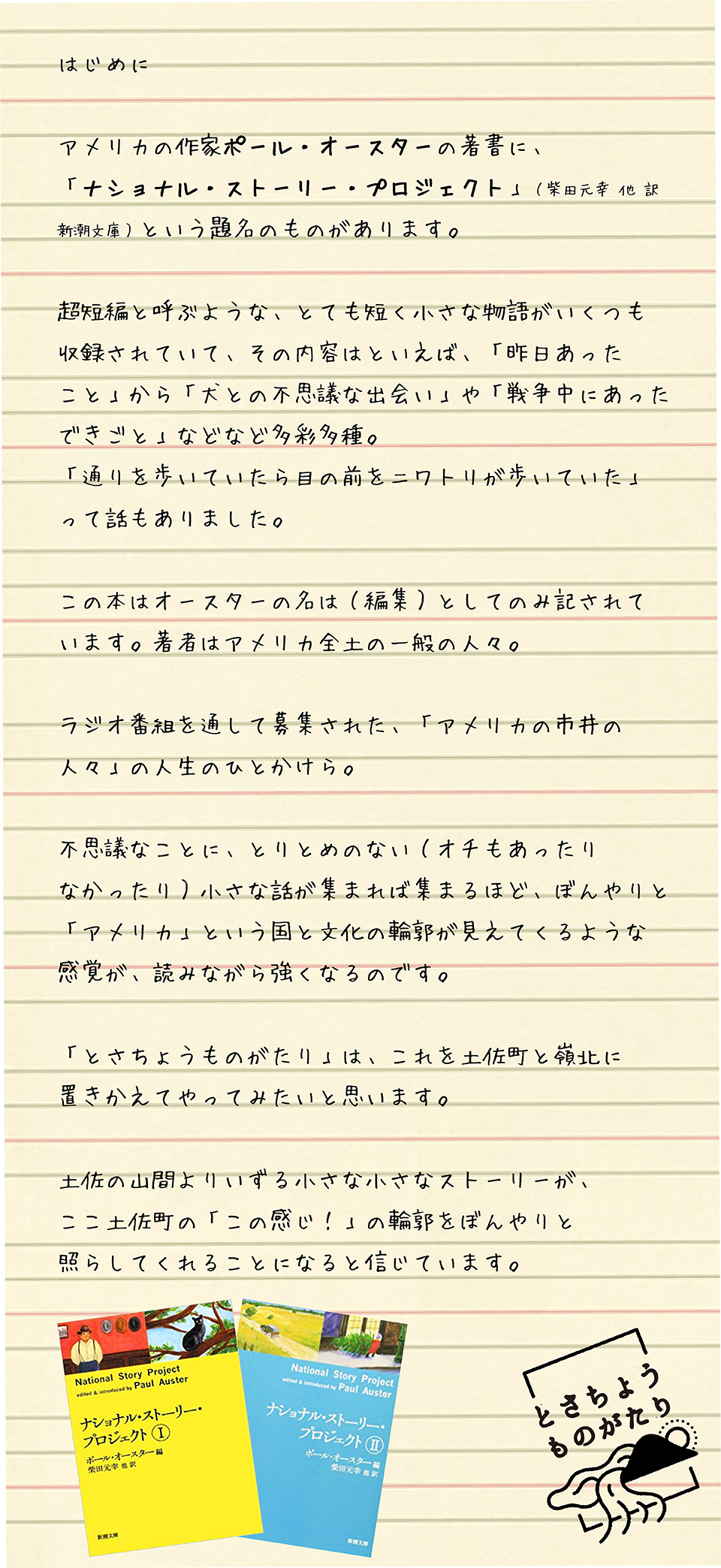
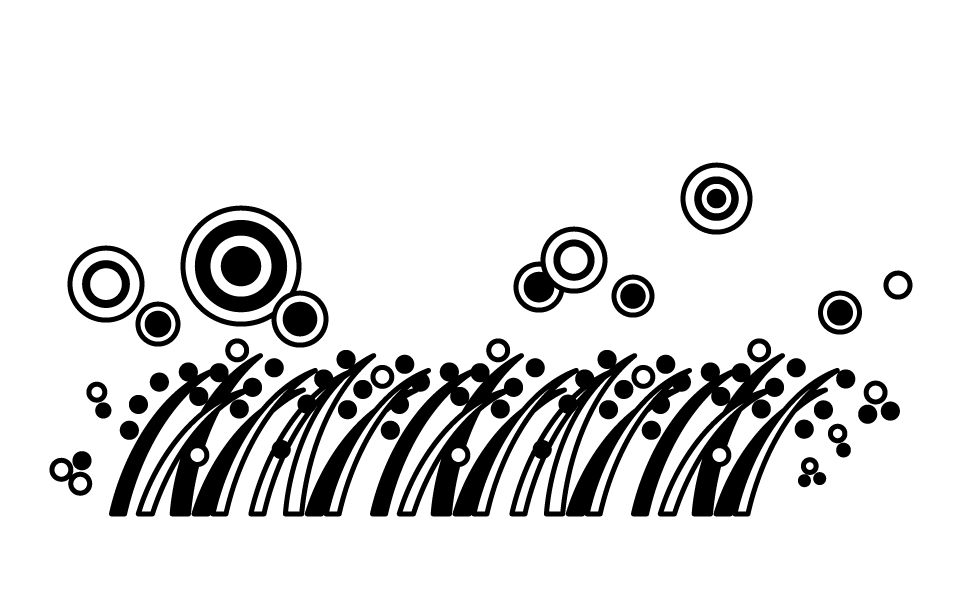
ムクムクした入道雲、セミの鳴き声。
山の神さまが洗濯したての緑のじゅうたんを大地の上に思いっきり広げたみたいな夏の田んぼ。
その田んぼに稲穂がつき花が咲き始め、表面がうっすらと黄金色になってきた。
じゅうたんの上を太陽の光を浴びて羽をキラキラさせながら、とんぼたちが飛んでいる。
この季節、土佐町には気持ちの良い風が吹く。
頰に感じるのはからりとした、顔を洗ったあとのような気持ち良さ。
この風は一体どこから生まれているのかなといつも思う。
山からか、谷からか、川からか。
並んだじゅうたんの上を風が通り抜ける。
まるで誰かと追いかけっこをしているみたいに稲穂を揺らしながら、重なるように、もつれるように、ぶつかりあいながら、あっちからもこっちからも走り抜けていく。
稲の波。きみどり色の海。
「風が見える!」
棚田が広がる風景を目の前にそう言った人がいた。
風は自分の足跡を残しては消え、残しては消え、また現れる。
この地の先人たちもこの風を感じていただろうか。
田んぼの畦に座り風の足跡を見つめながら、そろそろ収穫の準備を始めようか、と思いを巡らせていたのかもしれない。
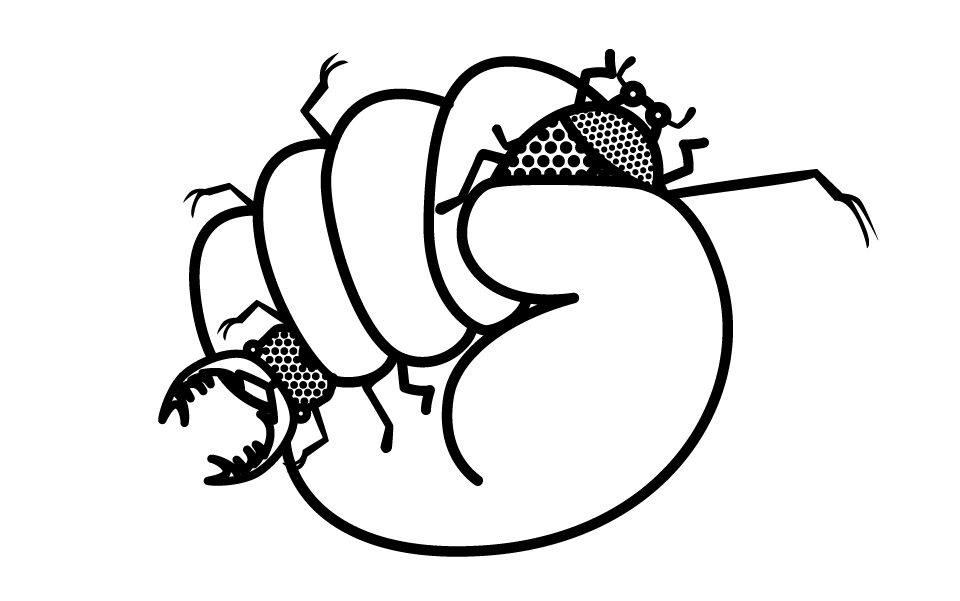
夜、暑いので網戸にして寝ていると、虫が入り込んでくる。
眠っているのに、太ももを何かが這う気配を感じると不思議なものでサッと覚醒する。
とっさに手で虫をつかむ。
何故つかむかというと、逃がして子ども達が刺されたり噛まれたりしてはたまらないから。
ある時はカミキリムシ。
ある時はカナブン。
とりあえず、勝手口からそっと逃がす。
今朝もまた太ももにモゾモゾとした気配を感じたので、とっさに握りこむ。
硬くてギザギザしたものが右手に収まってビクッとする。
ヒエッ。
これ何!?
暗闇で目をこらすと、ゲジゲジだった。
足が4~5本落ちて、布団の上で「ギギ・・・ギギ・・・」という音をたてながら動いている。
うへぇ。
何か、つぶしても動きそうだったので、ビニール袋に入れてゴミ箱に投入する。
もっとえいもん入ってこんかな。
クワガタとかカブトムシとか。
昆虫採集できそうやん。

私が住んでいる相川地区には、「二本杉子ども会」という子ども会があり、毎年夏休みに入ってすぐにキャンプをする。
釜でご飯を炊いて、カレーを作って、花火をして、子ども達は校庭にテントを張って寝る。
大人はその辺で寝る。
夕食後、子ども達はそれぞれに遊びはじめ、大人たちは慰労会へと突入する。
辺りが暗くなってきた頃、運動場の隅で子ども達が騒ぎ出した。
「セミの幼虫や!」
「脱皮しゆ!」
それは羽化というのだよ。
いそいそと見に行った私は、テンションが上がって写真を撮りまくる。
また大人の輪に戻り話をしていると、また遠くから子ども達が
「亜美ちゃん亜美ちゃん亜美ちゃん!!!!」と呼ぶ。
「セミが完全に出てきた!!」
「写真撮りや!」
さかさまに出てきていたセミがいつの間にかぶら下がり、しわしわだった羽が美しく伸びている。
「こっちにも幼虫いっぱいおるで!」
そう言いながらプラコップに3~4匹入った幼虫を見せてくれる。
「写真撮りや!」
「セミになったやつもおるで!」
「写真撮りや!」
いや、セミはいつでも撮れるきえいわ!と言いながらも撮る。
どうやら、すごいセミ好きのおばちゃんと認識されてしまったようだ。
今年は川原でキャンプファイヤーもした。
本格的に木を組んで火を点けると、結構な勢いで炎が燃え上がる。
暗闇の中で炎が幻想的に揺らめく。
何かあった時は、消防団の保護者もいっぱいおるき大丈夫大丈夫、と言いながら。
「まぁホース持ってきてないけど」
しかもみんな酔っ払ってるし・・・。
キャンプの最後はみんなで花火。
広々とした運動場で、みんなが思い思いに花火に火を点ける。
小さい子達にお姉さんが「やる?」と花火をわけてくれる。
「打ち上げ花火やるで」と大人が順番に火を点けると、子ども達が歓声を上げる。
並んだみんなの後ろ姿が可愛かった。
夏休みのはじまりだ。
夏本番!
我が子が通う保育園では7月からプールが始まりました。
土佐町には子供達が遊べる川スポットが近くにたくさんあるので、夏の間、国道からは川岸から元気な子供達の声が聞こえます。
夏場は、川やプールに入ったり、冷たいものを飲んだり、ツルッとしたものを食べたくなったり、体の中からも外からも、水分を欲しがち。
長時間水に浸かれば体はふやけてくるし、温かい体(内蔵)の中に冷たいものを一気にたくさん入れてしまうと、体に湿気が溜まり、体がだるくなったり、むくんだり、食欲がなくなったりします。
ビシャビシャに濡れたタオルをギュッと絞って水を絞るように出来たらいいけれど、私たちの体はそうもいかないので、尿で排出したり、汗をいっぱいかくことも大切になってきます。
そんな時にオススメは、とうもろこし。
土佐町ではいろんなところで、とうもろこしを植えている風景が見られます。
とうもろこしはヒゲ一本に実が一粒。ヒゲがふさふさのものを選ぶと、身が詰まっている証拠ですよ。
「とうもろこしご飯」

材料:
とうもろこし・米・昆布・塩
作り方:
とうもろこしを炊飯器に入る大きさに切って、実をこそぎ取る。ヒゲはみじん切りにする。
米を普通に研いで、通常よりほんの少し多めの水加減にして、トウモロコシの実、芯、ヒゲ、昆布、塩を入れて炊く。昆布もむくみを取る効果があるので一緒に炊き込みます。

芯を入れるとだしが出ていい旨味に。ヒゲは中国では乾燥させたものを「南蛮毛」といって、生薬として使われているほど薬効が高いのでぜひ入れてください。
とうもろこしは利水効果があるので、体の水分を排出する働きがあります。一粒一粒を包む皮は硬いので、たくさん食べると消化不良になりますが、皮のおかげで便通が良くなり、中の柔らかい甘いところは、疲労回復に効果がありますよ!
たっぷり水場で遊んだ子供達のおやつにもぴったり。元気に夏を乗り切りましょう!
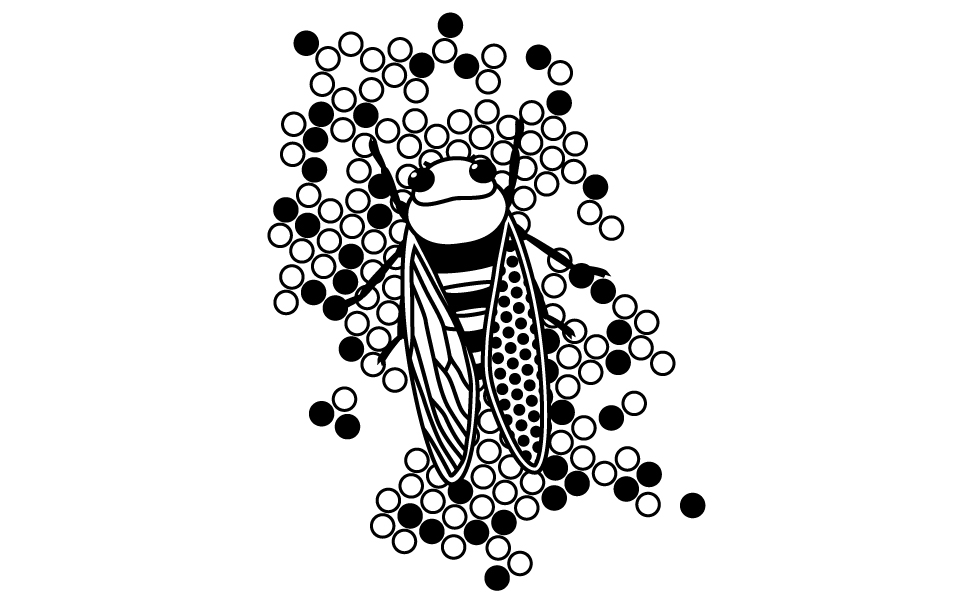
7月に入ったあるとき、朝4時をすぎた頃からひぐらしが鳴き出す。
森の奥の方からこちらの方へだんだんと近づいてくるような、銀色の鈴を響かせているようなこの声が目覚まし時計がわりになって、いつも寝坊助な私も早起きになる。
この声を聞くと「夏がやってきたんだ」と思う。
枕の向こうの山から、あちらこちらから、まるで輪唱しているように途切れることがない。
カナカナカナカナ・・・
セミたちは朝がやってきたことをどうやって知るのだろう。
セミは6〜7年間、土の中で過ごしてから地上に出てくるそうだから、この鳴いているひぐらしたちは今1年生の子どもたちが生まれた頃に土の中で誕生したんやなあ、とまだぼんやりした頭で考える。
しばらく布団の中でごろごろしていると、障子の向こうがほんのりと白く明るくなってくる。
小鳥たちが鳴き始める。
大地が目を覚まし、生きているものが順番に起きてくる。
いつのまにかひぐらしの鳴き声は遠ざかり、ジージージーという鳴き声にバトンタッチ。
鶏も鳴いている。
いろんないのちの音で満ちる朝。
今日も夏の1日が始まる。
もう1週間以上雨が降っているのではないだろうか。
早明浦ダムも全部のゲートが開いて、ゴオゴオという音を立てて放流している。
こんな時、停電になったら・・・土砂崩れがおきたら・・・と色々考えてしまう。
何にも防災対策をしていないけれど、唯一頼りにしているのが、アウトドアグッズ。
停電の時はランタン。ガスや電気が使えない時は、簡易のカセットガスで使えるガスバーナーが大活躍をしてくれる。
私が通っていた薬膳の学校では、「災害時に、薬膳師として私たちができること」というテーマの授業があった。
その授業以降、私も普段から常に常備しているものがある。
それは乾物。ひじきや、わかめ、切干大根。栄養満点のご馳走たち。
それを缶詰の水分で戻して、おかずの一品にするのです。

「切干大根とわかめの和え物」
材料:
切干大根・わかめ・コーン缶・シーチキン
作り方:
切干大根とわかめをビニール袋に入れる。
コーン缶とシーチキンを汁ごと加え、缶詰の水分を乾物に馴染ませるように揉み込む。

馴染んだら出来上がり。
そのままでも旨味が十分ですが、これに普段から使っているポン酢やドレッシングを加えて味をつけてもいいですね。
今回はちゃんと使いこなせるか練習に、ガスバーナーでご飯を炊いている間に、この乾物サラダを作って夕食にしました。

ちなみにガスバーナーはこんなやつです。10分炊いて、10分蒸らし。
合計20分でできました。わかりにくいですが、艶々に炊けてます!

防災グッズの中の食料だと、カップラーメンや缶詰が主流だけれど、栄養も偏ってきて体力的にも精神的にも参ってくるのではないでしょうか。
今はスーパーでも人参やいろんな野菜が入った干し野菜も売っているので、それを常備して普段から使い回し、いざという時にはカップラーメンに入れたりするのもいいかもしれません。
干し大根にはカルシウムや食物繊維もたっぷり。胃腸を整えたり、ストレスを軽減したりする働きがあります。
ひじきやわかめは、貧血予防やむくみ、血圧を上げる予防にも効果があるので、お年寄りにもとてもいい食材です。
カットした干し椎茸や干したけのこなどもいいかもしれませんね。
嶺北にはたくさんの乾物があります。普段食べ慣れてるものも使いまわしながら、防災食にしてみませんか。

「いや~、百合子さん。そろそろだよ。」
これは、笹のいえの洋介さんとのある日の会話。
そうそう、洋介さん、私もそう思っていた。
6月、私たちはそわそわし始める。国道439号線を走りながら「あの木」のある去年の風景を思い出し、確かあの木がそうやったと見定める。
そこから毎日の観察が始まる。
あの木、緑の葉をあんなに茂らせている。
そろそろかもしれない…。
そんなことを思いながら同じ道を通る日々が何日が続く。
ある日、はっとする。
咲いてる!
今年も咲いた。小さな線香花火のような、桃色と白のふわっとした軽やかな花。
それは、ねむの花。
「ねむの花が咲いたら、大豆の蒔きどきだよ。」
土佐町で暮らし始めたばかりの頃、近所のおばあちゃんが教えてくれた。
ああ、大豆を蒔かなくては!大豆で味噌や麹を作るのだ。
その言葉を知ってから、この花の咲く頃はそわそわして仕方がない。
そして咲いている間、ずっと私は落ち着かない。(早く種をまけばいい話だが。)
この季節にそわそわしているのはきっと私や洋介さんだけではないはずで、私にその言葉を教えてくれたおばあちゃんも、あの人も、あの人も、きっとねむの木を見上げ、独り言をいっているに違いない。
「大豆を撒かなくては!」
カレンダーや手帳に書かれた予定ではなく、この地に育つ花や木が「この季節がやってきましたよ」とそっと耳元で内緒話をするように教えてくれる。
それはコンクリートの上からは聞こえてこない声。気づこうとしないと気づけない声。
それは大地からの手紙のようなものなのかもしれない。
この地で繰り返されてきた営みを支えるその声に耳を澄まし、心に置き直す。
さあ、大豆の種をまこう!
*大豆だけではなく、小豆など豆類の種はこの時期に蒔くと良いそうです。

どんぐりさんとの打ち合わせが終わって外へ出ると、ワイワイとなにやら人だかりができている。
「あ!ちょっとこっち来や!よかったら持っていきや~。」
こちらを振り向いた笑顔のその人が指差した先にあったのは、かごいっぱいのすもも!
なんて美しい色なんやろう!
さっき採ってきたばかりというだけあって、つやつや、ピカピカ紅色に光っている。
「うちで採れたもんやき、好きなだけ持っていきや!」
カゴの前にしゃがんですももを袋に詰め、立ち上がると「え?それだけでいいが?もっと持っていきや!」と、次々と何本もの手が袋にころころと入れてくれる。
すももの入った袋をそれぞれの人が手にしながらにこにこと笑い、みんなはまたおしゃべりを始めた。
土佐町の人たちはもしかしたら気づいていないかもしれない。
すももをカゴにいっぱい採って好きなだけ持っていきやと言えること、季節の食べ物が手の届くところにあるということ、この風景が日常であることが、どんなにゆたかであるか。
こういったやりとりに、私がどんなに励まされているか。
私たちの毎日の中には当たり前のようでいて実は当たり前ではないことが、あちらこちらにちりばめられている。

出張中の車内、昭和生まれの職員が3人集まるとこんな話になりました。
「そういえばたぬきの油とかあったよね」
「何にでも効くゆーてね」
「うち、今でも冷蔵庫に入ってますよ」
「ホンマに効くがやろうかねぇ」
「でもたぬきの油、刺さったトゲを抜くのにはえいで!ちょこっと塗って一晩置いちょったら、トゲが抜けちゅうがって」
「ええー!何の成分なんやろう?」
「火傷にはよくアロエ塗りましたよね」
「フキとかも使いよった気がする」
「え?フキの葉?茎??」
「茎。消毒になるとかゆーて」
「ぼく、小さい頃、車酔い予防にゆーて、車に乗る前にセンブリ飲まされよったがよ。でもあれ苦いやん?そんなもん飲んで乗ったら余計酔うわね」
「センブリって腹痛用なんじゃ・・・」
「腹痛といえば、梅肉エキスとか、昔作りよった気がします」
「梅肉エキスって何?」
「梅の実を、黒うなるまで煮詰めたやつです」
「ええー、そんなん見たことない!」
「(インターネットで検索して)青い梅の実をすりおろして、汁をしぼったやつをアクをとりながら煮詰めるがやと」
「昔は薬とかなかったき、そんなんやったんでしょうかねー」
「いや、うちらぁ、薬箱に置き薬あったがで!それやのに・・・」
他にも、ヨモギの葉は止血ができる、とか色々ありますね。
私は小さい頃、よく蕁麻疹が出る子だったのですが、蕁麻疹には山椒がえい!と言われて蕁麻疹が出るたび庭に生えている山椒の葉っぱをかじらされていました。
良薬口に苦し?