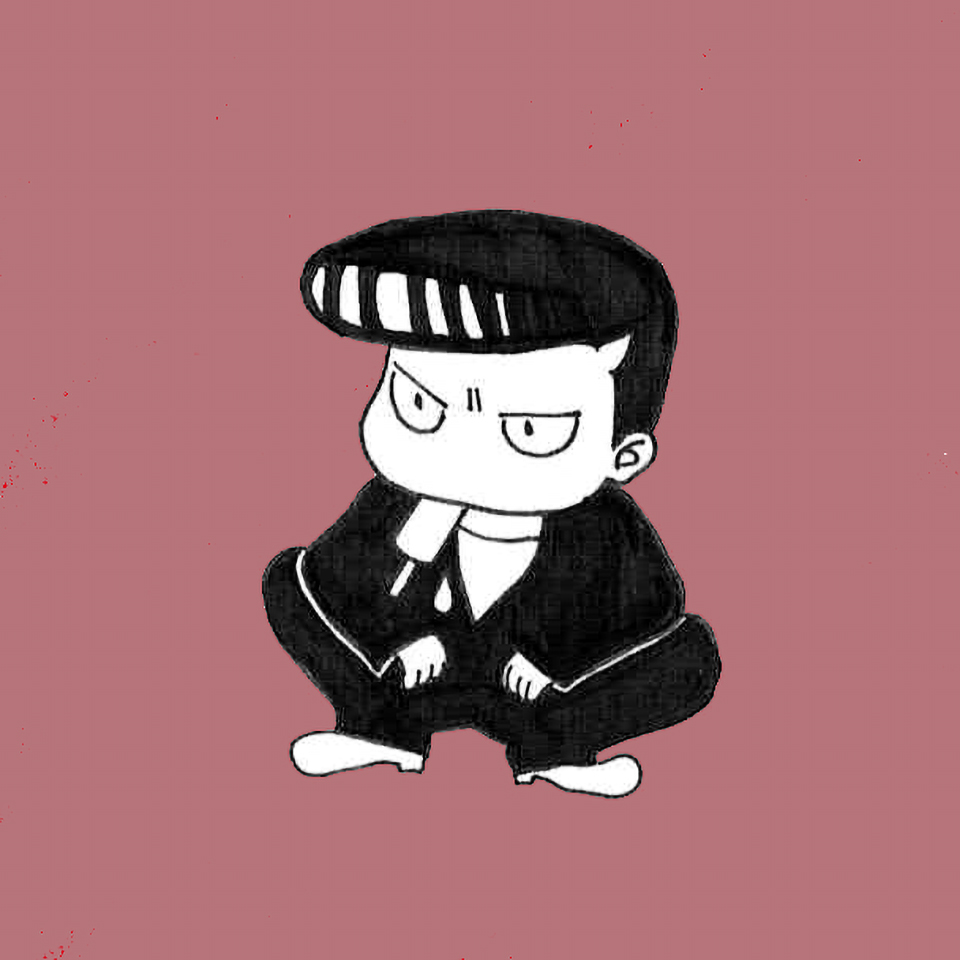
ケーキ
【名】アイス
*高知ではアイスのことを「ケーキ」と呼びます。
著者名
記事タイトル
掲載開始日



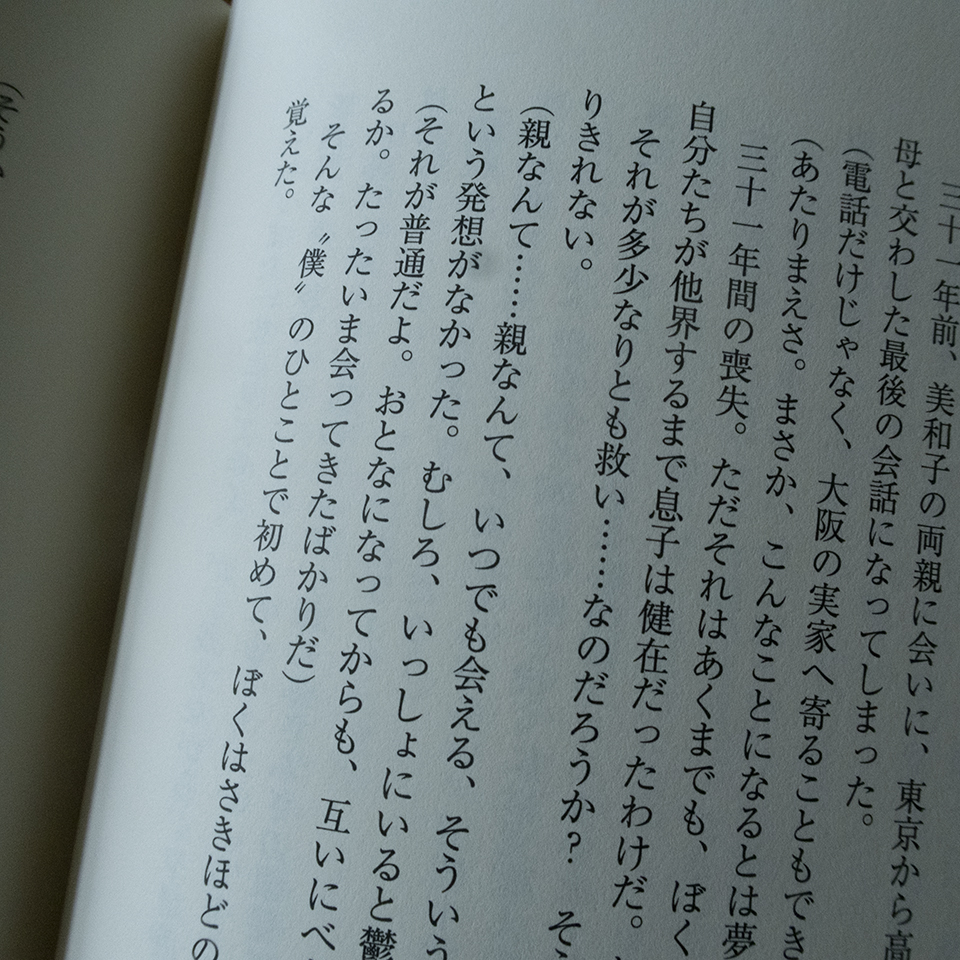
「スイッチ」 西澤保彦 光文社
梅雨時、すっきりしないお天気が続きます。
この作品の舞台は高知で安芸や春野、はりまや橋と、身近な場所がでてくると頭の中の地図に再現されます。
時は昭和52年、婚約者に会いに高知を訪れた22歳の菜路充生。彼女の都合で、一人でホテルに泊まることになったその夜、銀色の奇妙な雨にうたれ意識を失ってしまう。目覚めた時、ボクの体は別の人格に乗っ取られていた。
体の中には二人の存在があり、22歳のボクと53歳になった僕。体を自由にできるのは53歳の僕。ボクには記憶のない31年。妻とは離婚したという。人生の輝く時期をうばわれ、喪失感に苦しむボクを、今度は連続殺人事件が襲う。
ミステリアスな作品でした。作家のあとがきも楽しんで読みました。


未だかつてこんな立派なレタスを手にしたことはなかった。正真正銘、私が種をまき、次から次へと周りに生えてくる雑草を引き抜きながら育てたレタスだが、今まで大抵の苗や植木を枯らしてきた私には、自分で育て上げたということがいまいち信じられない。
今年の春、草茫々だった畑の草を鎌で刈って、耕して、畝を立てた。5月頃、レタスの種をまいた。しばらくすると小さな芽を出し、隣り合った芽同士で切磋琢磨するように大きくなっていった。それはちょっとした感動を覚えるほど、新鮮な体験だった。
毎日、畑に行くのが楽しみになった。毎日足を運ぶようになると、わずかな変化にも気づくようになる。
ある日、大きくなりつつあるレタスのそばに、昨日はなかった何かの小さな芽がいくつもあることに気づいた。いつもならすぐさま引き抜くだろうに、なぜかこの時はそうしなかった。次の日も、その次の日も、その小さな芽は増えていった。
小さな芽が成長し、葉となって初めてわかった。それは青紫蘇だった。種子をまいた覚えはないのに、あっちにもこっちにも、畝を無視した紫蘇たちが生えてくる。
多分、土の中にまぎれていた種が、掘り起こされて光を浴び、眠りから目覚めたのだろう。
青紫蘇は好きなのでうれしかった。すりおろしたニンニクとごま、醤油を和えたタレに青紫蘇を漬け、ごはんのお供をせっせと作った。が、最近手がつけられないほど勢力を増し、利用が追いつかなくなってきた。正式に畝に種子をまいたレタスや、オクラやスイカ、イチゴの苗を脅かすほどの勢いである。
季節柄、他の雑草も負けてはおらず、畝に何が植わっているのかわからないほど、青紫蘇は緑々としてきた。そろそろ仕分けをしないとと思っているのだが、せっかく芽を出したのにね、と思うと何だか気の毒で、その日をあと伸ばしにしてきた。
今現在、あと伸ばしにし過ぎて手がつけられなくなり、一体どうしたらいいかと頭を悩ませている。
レタスと青紫蘇、欲しい方はお伝えください。



「(昔の)ku:nel」 マガジンハウス
「昔の」ku:nelが面白い。 ku:nel(クウネル)は2002年にアン・アンの増刊号として創刊された。 2015年の11月号を最後に突如リニューアルされ、現行のku:nelはまったく雰囲気の異なる雑誌になってしまった。 なんとも不思議な歴史をもつ雑誌。 2015年11月号までの「昔の」ku:nelは、むしろ「今の」時代に合っている感じがする。
内容を読んでいて、何度も表紙を見て発行された年を確認。 あまりにナウすぎて驚く。 昔のku:nel、最先端をいってたのか…!
今流行りのキャンプもDIYも自然との共生、なんならマスキングテープのよさまでとっくに伝えていた。預言書の如し。
味のある写真と、物語を読んでいるかのような文章でやさしく語りかけるように。 『ほんとうにこころゆたかになれる生活とは?』 その答えのヒントとなるであろうアイデアが、そこかしこに散りばめられている。
いきなり終了してしまった悲しき「昔の」ku:nel。 最終号には、太陽光で料理をするおばあちゃま。当時御年84歳。 やっぱり最先端いってる!


谷種子さん。稲叢山の山麓に、20年以上もの長い年月、桜の木を植え続けている方です。
種子さんが植えたその桜の木が満開を迎える時に、どうしてもその前で写真を撮らせていただきたくて、急な話になってしまったのですが一緒に山まで行っていただきました。
撮影中も、おそらく遠方からやってきた家族が車を止め、しばしの間桜を見つめ、その前で写真を撮っていました。
長い時間をかけた種子さんの仕事が、こうしてたくさんの方々の目を楽しませています。
種子さんがここまで来た道のりをお聞きしましたが、種子さんの口から出てくる言葉は「楽しかった」「私がやりたかった」というものばかりで、そこには義務感や悲壮感はかけらもありません。
「自分がやりたいこと」がそのまま「周りが喜ぶこと」となっているところに、種子さんの膨大なエネルギーの源があるような気がしています。



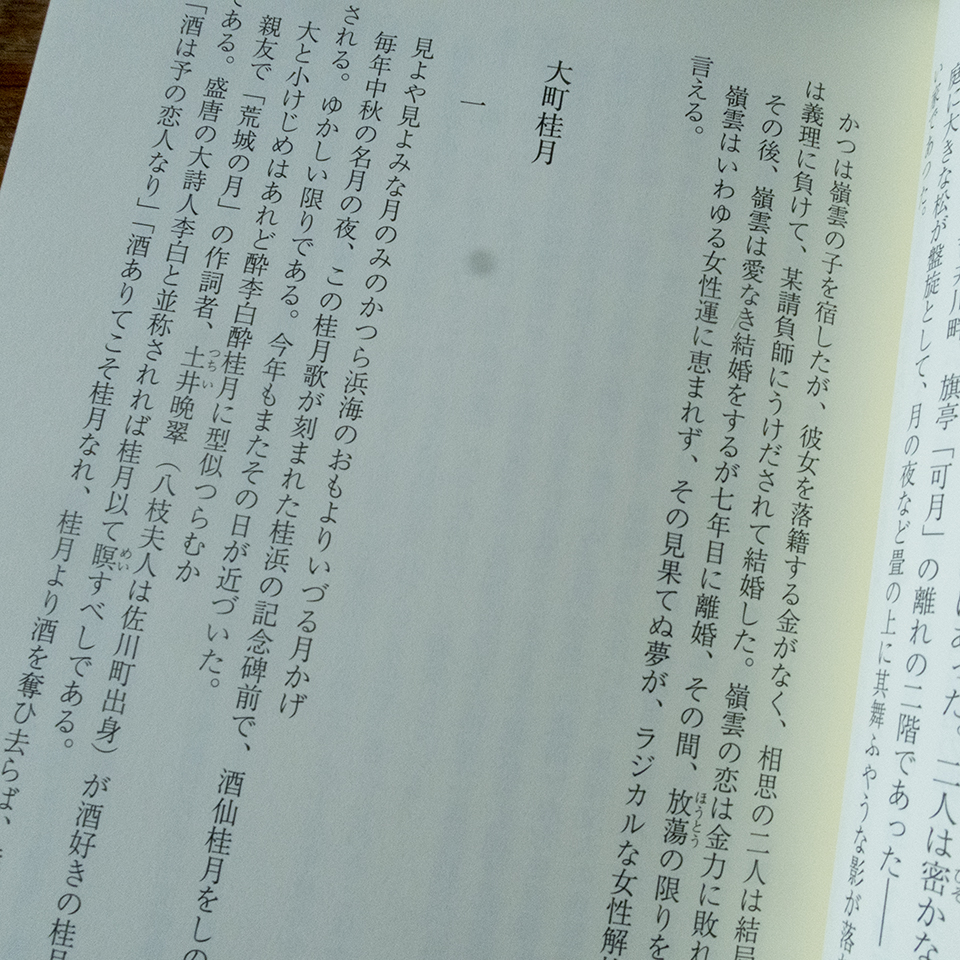
「高知の近代文学さんぽ 照射と影」 高橋正 高知新聞総合印刷
自分の想いとは裏腹でも、人生で一つの区切りが出来た時、人は、次のステップへ行く方法を模索するものなのですね。
私も、次をどう生きて行こうかともがいていた時、その道のひとつに、高知市で開かれている文学学校への参加がありました。
夕方、仕事を終え、すぐさま友人二人と車に乗り込み、一年位通いましたが、思いのほか、ハードルの高い勉強会という事もあり、昼間の仕事の疲れもあり、私はほとんど居眠りばかりしていたように思います。
でも、その時出会った先生が、友人を通して著書を送ってくださいました。
それが、この「高知の近代文学さんぽ」。今年、卒寿を迎えられた高橋正先生のひたむきな文学研究に触れ、今一度、自分を振り返った書です。


山村の子にとって、竹は遊び道具作りに欠かせない材料であった。突き鉄砲、竹とんぼ、竹馬、釣竿など、人それぞれの思い出の中に残るものである。
私もそうであった。まず作ったのは多くの子と同じように、突き鉄砲だった。
銃身となる竹筒に、紙を濡らして丸めたものや、草の実を弾丸として詰め、それを小さな竹で押して、空気の圧力で飛ばす。
的となる目標物を置き、それをめがけて射って、命中率を競ったりしたことだった。
広辞苑では「紙鉄砲」とあるが、自分たちは「突き鉄砲」だった。大抵の子がこれを作っていた。
そのあと私がのめり込んだのは、釣竿作りであった。小学校に入る前から渓流釣りを始め、まずモツゴ釣り、ついでアメゴ釣りとなっていったことは、これまでも別の機会に何度か記した。その釣竿は自分で作った。
今のように強化プラスチック製の釣竿などはもちろん無く、釣具店で売っている竿もすべて竹製であった。村には釣竿を売る店がないので、自分で作るしかなかった。
渓流釣りの入門編とも言えるモツゴ釣りには、ニガタケで竿を作った。この竹は子供がよく利用する笹竹で、広辞苑にはメダケ、カワタケ、オナゴタケ、アキタケ、シノダケ、シノベダケなどの異名があるが、村ではみんな「ニガタケ」と呼んでいた。
この竹を何本か切り、自分の手に合う太さと、力に合う長さ、重さのものを選んで釣竿にした。
木の枝が水面上に伸びたりしている所では、それに引っ掛ってテグスが切れることがあるので、広い所を選んでモツゴを釣った。
モツゴ釣りを卒業してアメゴを釣り始めると、竿に気を使わねばならなくなった。
アメゴの場合は、木の枝などの障害物がある瀬などで釣ることが多い。そんな場合にはモツゴ釣りの1本竿では長すぎる。
川だけではなく、川へ行く途中でも、長い竿は不適当と思うようになった。
モツゴの場合は、道路から川へ下りる道を通って行き、広い楽な場所で釣る。
しかしアメゴは、よいポイントに早く行きたいため、道がなくても道路から薮をくぐって、そのポイントに行くこともある。そんな時には長い竿が邪魔になって歩きにくい。
ポイントでは前述のように、障害物があると、長い竿では使いにくい。
そこで考えたのが、大人たちが使っている継ぎ竿であった。これなら邪魔な障害物があっても、竿を短かく縮めて釣れる。薮をくぐる時もそうすれば楽である。
そう思ってまず、2本継ぎの竿を作った。これは割合楽に出来た。
ニガタケを適当な長さに何本か切り、太い方を元にする。それにはまる竹を選んで穂先にした。場所によってはそれをはずして、半分の長さにして釣ればいい。薮をくぐる時も楽になった。
そのうちに同じやり方で、3本継ぎを作った。元になる竹はシチクを使うこともあったが、思考錯誤しながら作るのは、苦労というよりも楽しみが大きかった。
竹は真っ直ぐのように見えるが、意外に曲った部分がある。曲ったままでは釣竿として使いにくいので、そこを矯め直して作った。曲りを直すのは、余り難しくはなかった。
これは釣りをする大人から、
「青竹のうちに、火であぶって直せ。竹が枯れてからやったら、焼けてしまうきに」
と言われ、実地に習った。
青竹を炎であぶると、簡単に曲りが直せる。思うように矯め直して、そこに水をかけて冷やすと、元に戻らず、真っ直ぐになる。楽に出来た。
今は強化プラスチックの釣竿を使っているが、“あの頃”の思い出は消えることがない。


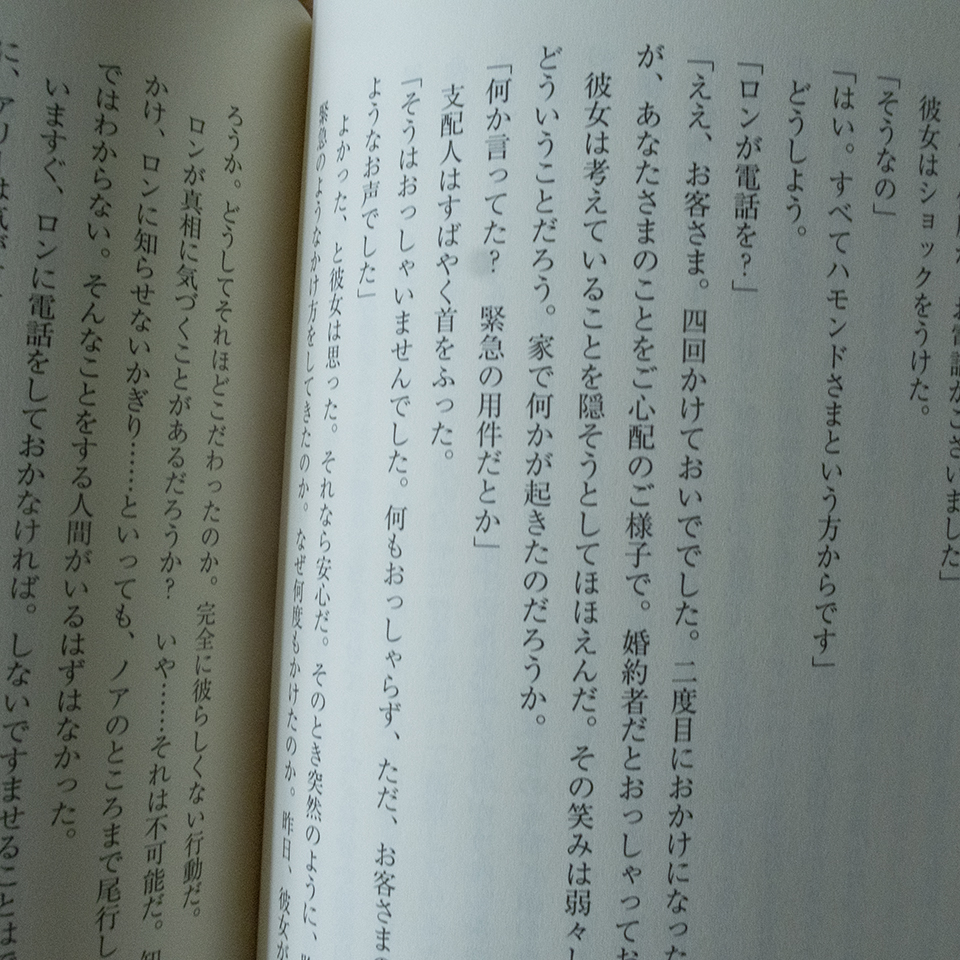
「きみに読む物語」 ニコラス・スパークス アーティストハウス
10代の夏に巡り会ったブルーカラー育ちの若者とエリート階級の娘。理不尽な別れがあっても、若者は一途に愛を貫いた。離れて暮らした苦しい年月。そして偶然の導きによる再会。その後の平凡で幸せな日々。
数十年後、妻は病にかかり、日々の記憶を忘れてしまう。記憶をなくした妻に、毎日読み聞かせるのは、二人が出会い、別れ、そしてまた恋に落ちた現実のラブストーリー。
文中に「わたしはありふれた人間だ。ごくふつうの考え方で、ごくふつうの生活を送ってきた。記念碑などないし、名前もすぐに忘れられるだろう。でも、わたしには全身全霊をかたむけて愛する人がいる。いつでも、それだけで十分だった。」と…。
優しい純愛小説。著者の妻の63年間連れ添った祖父母の実話に基づいた作品で、2005年海外小説第1位に選ばれました。


2021年1月から2月にかけて高知県内9市町村の郷土料理を撮影し、製作した動画をご紹介しています。
第7回目は、安芸市入河内地区で作られている郷土料理「かしきり」です!
かしきりは、かしの実で作られた豆腐のこと。干したかしの殻をはぎ、実をミキサーにかけ、三日三晩水をかえながらアクを抜きます。そして、それを煮詰めて、固めるという手間隙がかかる郷土料理です。
昔、朝鮮半島から伝わったといわれ、韓国では「トトリムッ」という名で今もよく食べられているとのこと。かしの実を粉にしたものも販売されていて、各家庭でよく作られているそうです。
撮影のために、高知県安芸市入河内地区でかしきりを作ってくれた有澤淑江さんは、現在87歳。子どもの時はミキサーなどはなかったので、かしの実を石臼で挽いていたとのこと。「昔、若い人たちが仕事に出ている間、家で留守番しているおばあちゃんがよく作っていた」と教えてくれました。
当時は、石臼で挽いた粉を布袋に入れ、山水に晒してあくを抜いていたそう。食料が少なかった時代、身の回りにあるもので何とかやっていこうと知恵を絞った人たちの苦労が偲ばれます。
かしきりは、そのままだとほぼ味がないので、「葉にんにくのぬた」をかけて食べます。畑で収穫したばかりの葉にんにくをすり鉢ですりすり…。辺りには、にんにくの香りが広がります。続いて、味噌やごま、砂糖、柚子酢などを加え、かしきりにかけて食べます。
想像していた以上に美味しくて、ぬたの風味を味わいながらいくつも食べました。
かしきりの風貌がくず餅のようにも見え、家で黒蜜をかけて食べてみましたが、こちらも美味しかったです!
動画のタイトル文字を描いてくれたのは、土佐町の隣町、本山町の障がい者支援施設「りんどう」のメンバーさんたちです。とても楽しんで描いたり作ってくださったと聞いて、とてもうれしかったです。ありがとうございます!

毎年10月頃、有澤さんはたくさんのかしの実を拾います。「天気の良い日に拾ってきたかしの実を干すと、『ぱちっ、ぱちっ』と殻が割れるんよ」と話してくれました。その割れ目がにっこりと笑っているように見えることから、殻が割れることを「かしの実が笑う」というそうです。
こういった言い方ひとつとっても、自然とともにある生活の中に、ちょっとした楽しさを見つけようとしていた人たちの心意気を感じます。
有澤さんは、現在87歳。安芸市入河内地区でかしきりを作ることができるのは、有澤さんだけだと聞いています。郷土料理を作ることができる人が高齢化し、後継者がなかなか見つからないという現状は、安芸市だけではなく高知県全体、日本中が抱えている問題でもあるのだと思います。
今回、高知県各地で動画を製作したのは、その地の郷土料理の作り方や、作り続けてきた人の姿を残したいという高知県庁の思いがあってのことでした。
各地で引き継がれてきた郷土料理はかけがえのない文化です。その文化を引き継ぎ、次の世代へバトンタッチする。
そういったことが少しでもできたらいいなと思っています。